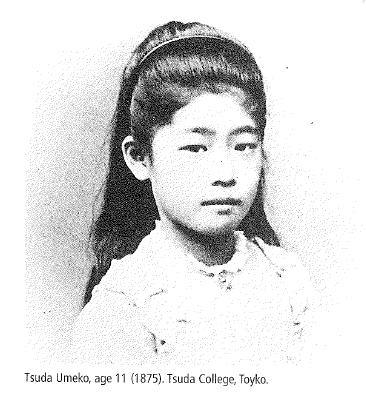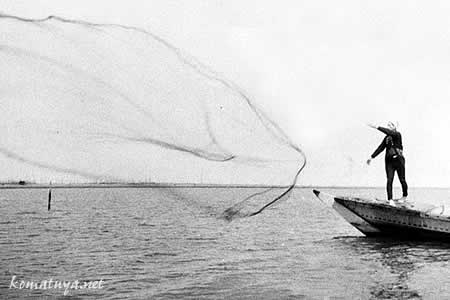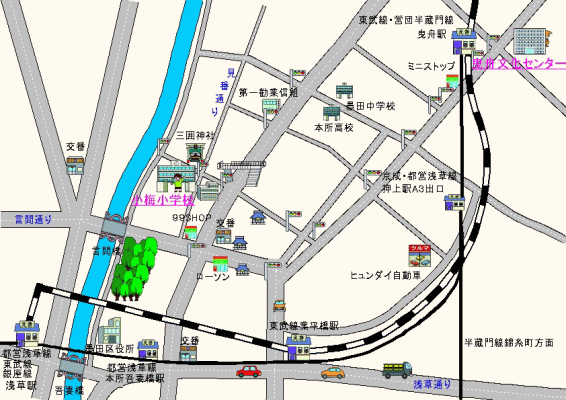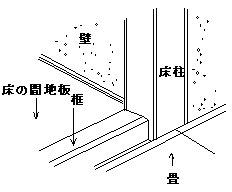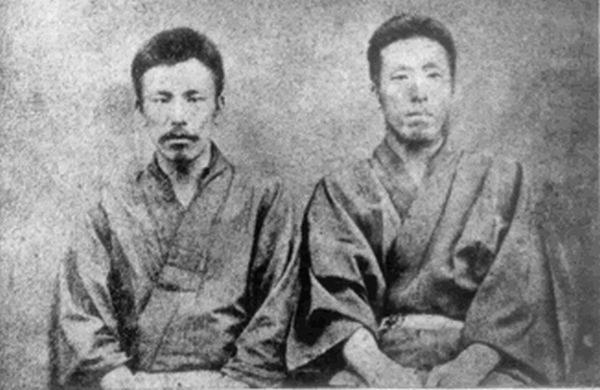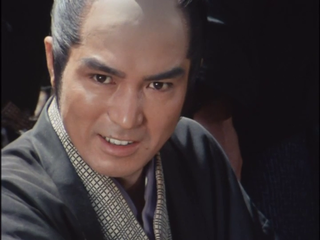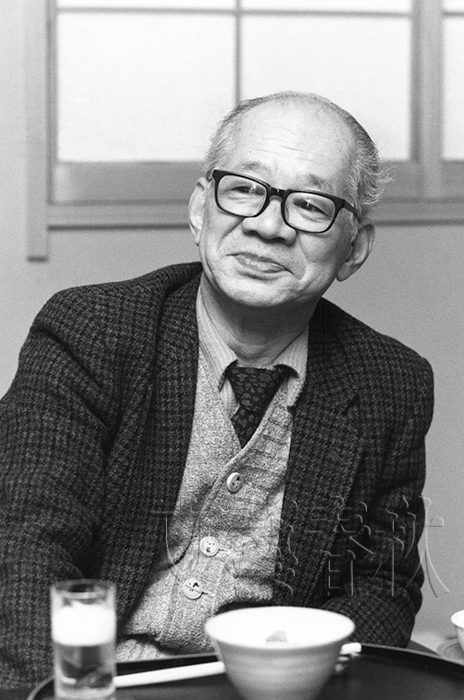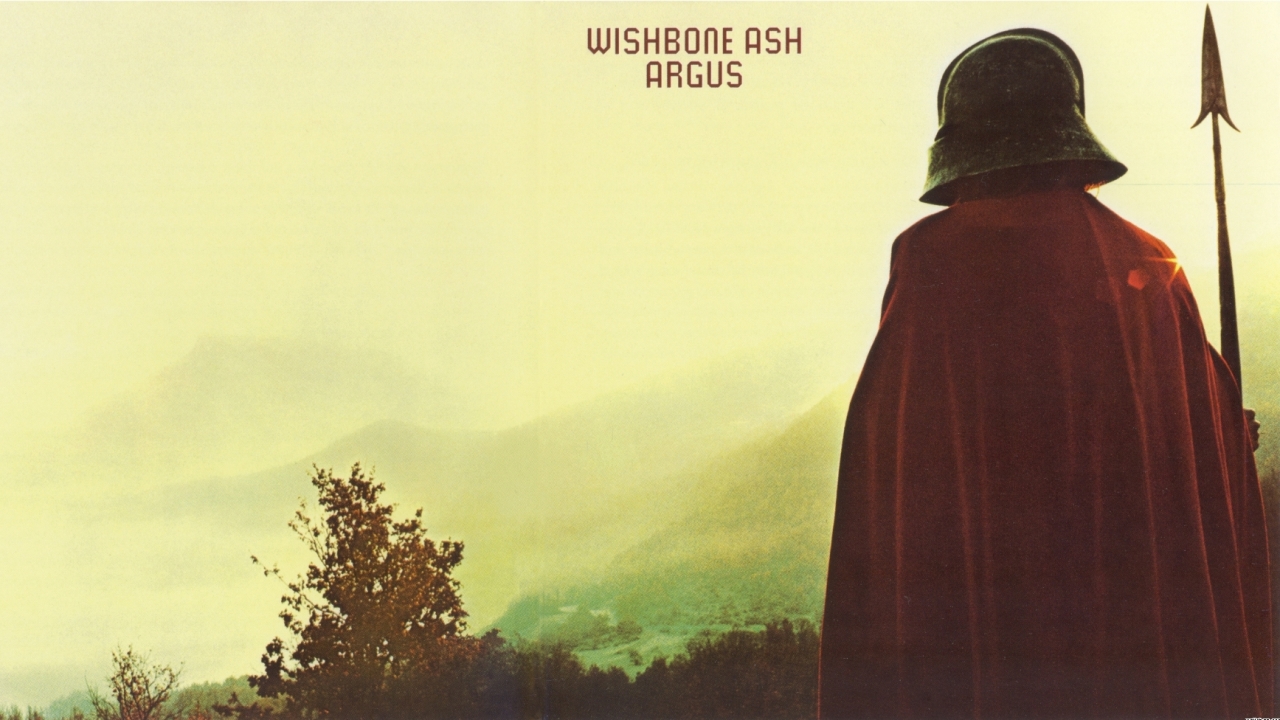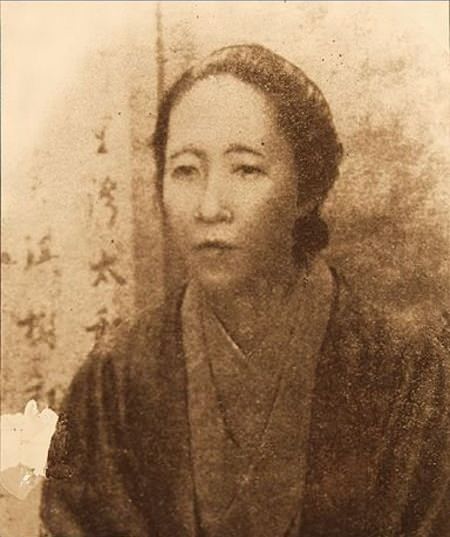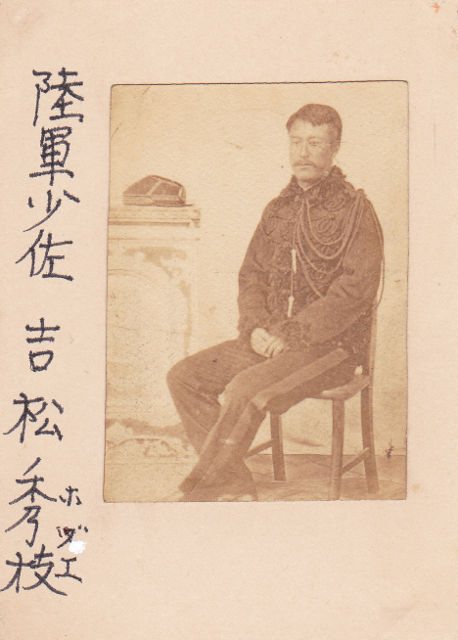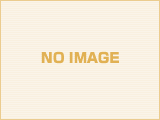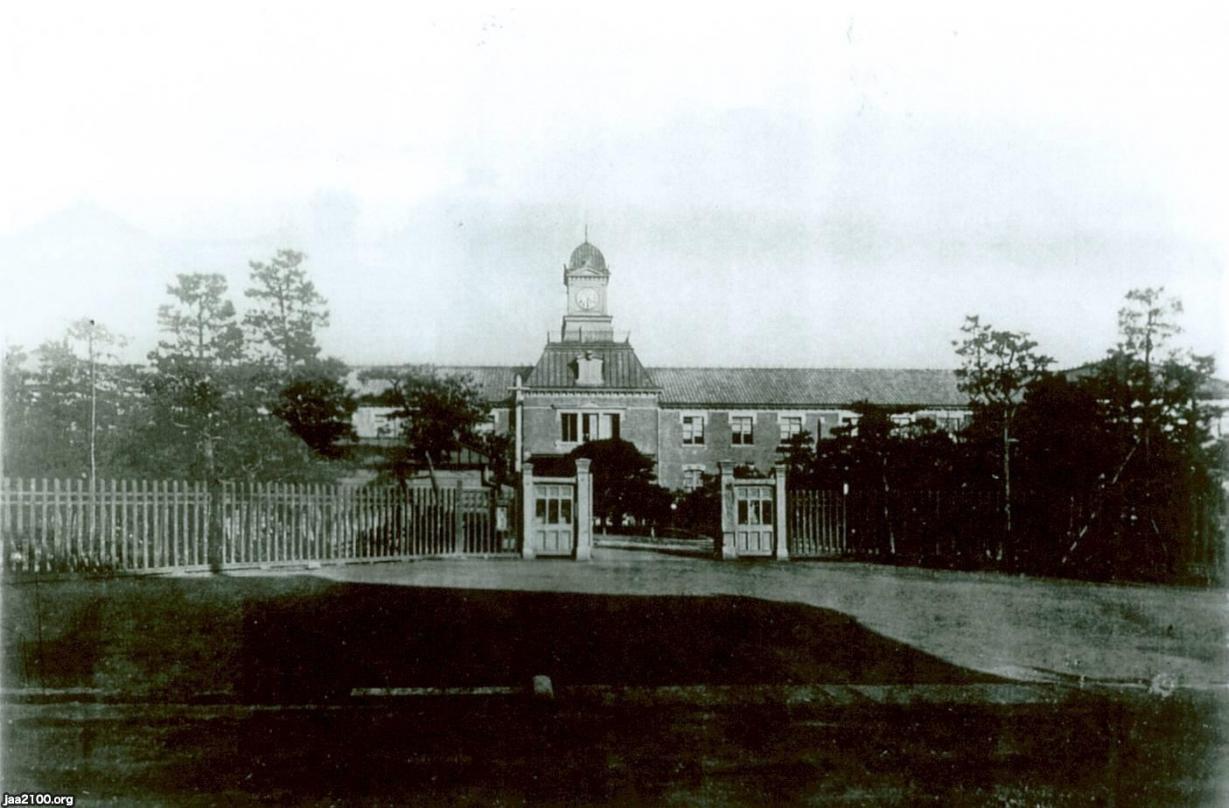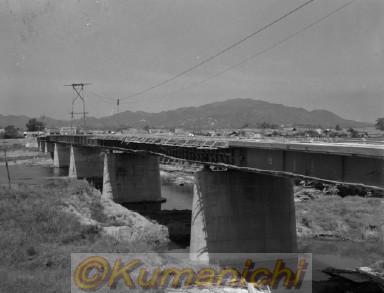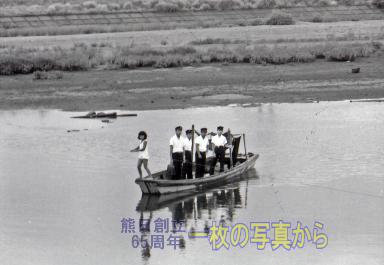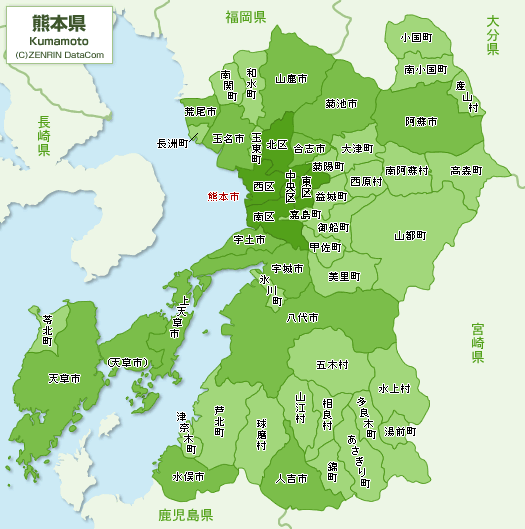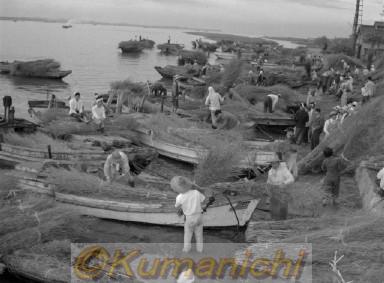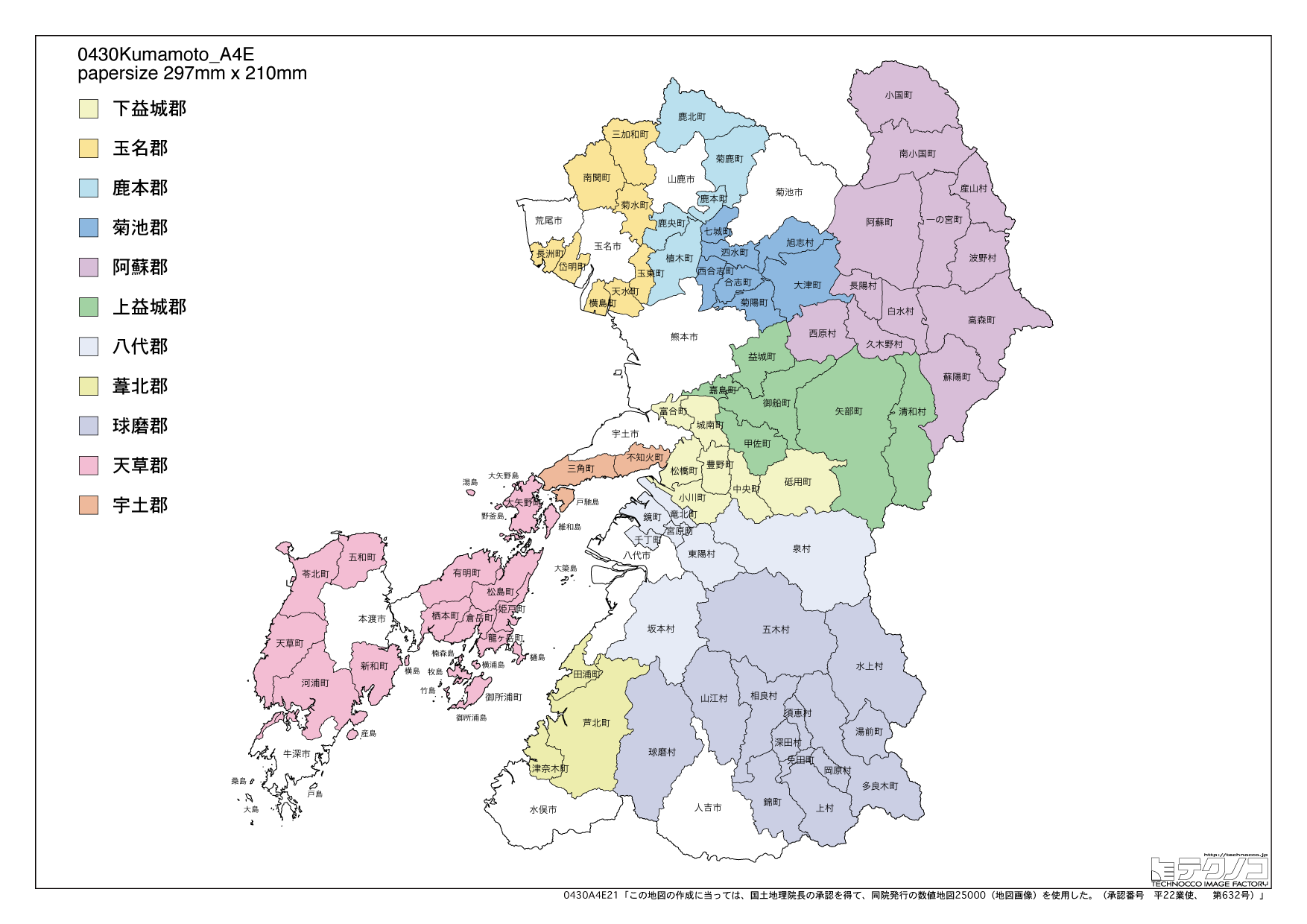�������ȗ��R�ɂ�鏑�����݂̍폜�ɂ��āF �����p�V �Ƃ݂������:�i�n�ɑ��Y�@Part13 YouTube����>6�{ ->�摜>303��
����A�摜���o �b�b
���̌f����
�ގ��X��
�f���ꗗ �l�C�X�� ����l�C��
���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/history/1521275224/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B
�i�n�ɑ��Y�S�W���d���̋������Ȃ���ǂݐi�߂Ă܂���܂��B
���݁u�ĂԂ��@���v���i�s���ł��B
�O�X��
�i�n�ɑ��Y�@Part12
http://2chb.net/r/history/1516287702/ �y�}��z
�������E�I�s�ł͕���̏ꏊ�������͗��̏ꏊ�������i�]�k�̂Ƃ��́A���ڂ������j�B�]�_���ł́A���ڂ������B
����i�ɏo�Ă�����E����
����i�ɂ͏o�Ă��Ȃ����A�w�i�𗝉����邽�߂ɕK�v���Ǝv������
�y���Ӂz
���̃X���b�h�ł́A�i�n��i�𒉎������A���ɉ摜�����Ă��邽�߁A�G���O���摜���܂܂�Ă��܂��B
18�˖����̕����邢�͂����ɂȂ肽���Ȃ����́A�q�G���O���r��NG���[�h�ɓo�^�Ȃ��邱�Ƃ𐄏��������܂��B
�܂��A�G���O���摜�����X�������́A�K���q�G���O���r�̕�����Y�t���Ă�������悤�A���肢�\���グ�܂��B
�y���Ӂz
�����̃��[�U�[�̕��X���A���ݐi�s���̎i�n��i���ɏW�����āA���߂���������A�c�_���Ȃ����Ă����܂��B
���̎i�n��i�Ɋւ��ċc�_�Ȃ���������ׂ���Ȃ��肽�����͈ȉ��̃X���b�h�ւ����z�������肢�\���グ�܂��B
�����i�n�ɑ��Y�nj�Q�ɂ��Č��vol.3
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/history/1365866256/ �i�n�ɑ��Y�̉ƍN�ߏ��]���ُ͈�
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/history/1331922006/ �����y�[�X���グ�Ȃ��ƁA�M�҂����ʂ܂łɏI�����Ȃ��B
�Ō�̍�i�́A�w�X�����䂭�x�́u�F��E�Í��X���v�ɂȂ�\��B
��19�́@�ދ��i�Â��j
�ǂ������H���ƂȂ����Ȃ����ȁB�،˂������̂��H
�����{�����Ԓ�
���c���^��
���c�̔����ؘ_�́A�O���ɂ���Ėk�C���J��̗\�Z������邱�Ƃ��뜜���Ă̂��Ƃł������B
������
�����ېV�̌��J�ҁE�����������A�V���{�̉��B�ǐ��p���ɕs���������A�����U�N�ɗ��R�叫�̐g�ʼn��삵���Ƃ��A
>>15 �̎����������B
�ނ͂Ђ����Ɋx��̐S���������炵���B
���`�w�@�q1090-1155�r
�`�w�v�w�́A�����ĂЂ��܂������𒆍��E�Y�B�ɂ���x���_�̒��ɍ���A�_�ʼn���ꂽ��A��ɂ�f����������̂ŁA�����Ԃ��Ȃ������B
�����́A
>>15 �̎��ŁA��v�ۂ�`�w�ɉ������Ă���B
���x��@�q1103-1142�r
������v�̕����B���͖Q���B���쓒�A�i�͓�ȓ��A���j�o�g�B��v���U��������ɑ��Ċ��x�ƂȂ����������߂����A�x���̐��͂��g�傷�邱�Ƃ����ꂽ�ɑ��E�`�w�ɖd�E���ꂽ�B
�x��͌��A�~���̉p�Y�Ƃ��ď̂���ꂽ�B����ł������̗��j��̉p�Y�Ƃ����A�܂��x��̖��O��������قǂł���B
���F�g
���z�㉮�̏���
���Ȃ̘V��
�g�`�m�L�B�i�n����́u�Ɂv�Ə�����邱�Ƃ������B�t�����X�ꖼ�u�}���j�G�Fmarronnier�v�Ƃ��Ēm���Ă���B
�T���g���́u�q�f�v�ŁA��l���A���g���[�k�E���J���^���́A�����̃x���`�ɍ����Ėڂ̑O�̃}���j�G�̖̍����������A�������f���C�ɏP���A���ꂪ�g���̂������ɂ���Ƃ������Ɓh���N�������̂��ƋC�Â��B�܂�A���̓f���C�́g�����ɑ��锽���h�������̂��B
�����M
�����̌����i�̂Ȃ��ɂ����M�̏�i���������Ă݂����A�v���悤�Ȃ��̂��Ȃ��B
��M���䂭���H�̗��݂̓R���N���[�g��݂������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���z�̐�M������Ɨ����ł�����x�̐앝�ŁA���͂͂��ׂēc�ނƂ����̂��]�܂����B����˂����тɁA�݂̊^�����킽���������֗������ށB
>>13 ����Ő����s���Ȃ̂́A�s�������ɂȂ����ȁB
���Óc�~�q
�������N�i1864�N�j- ���a4�N�i1929�N�j
�Óc��i�����b�E�����{�m���j�̎����Ƃ��āA�]�˂̋������k���i���݂̓����s�V�h��쒬�j�ɐ��܂ꂽ�B
����4�N�i1871�N�j�A��͖������{�̎��Ƃł���k�C���J��g�̏����ƂȂ�A�Óc�Ƃ͖��z�ֈڂ�B
�J��g�����̍��c�����͏��q����ɂ��S�������Ă����l���ŁA��͍��c����悵�����q���w���ɔ~�q�����傳���A���N�A��q�g�ߒc�ɐ��s���ēn�āB5�l�̂����ŔN���̖�6�ł������B11���ɉ��l���o�`���A�T���t�����V�X�R���o�āA���N12���Ƀ��V���g���֓����B
�A�����J�ł̓W���[�W�^�E���œ��{�ٖ��ُ��L�ʼn�Ƃ̃`���[���Y�E�����}���v�Ȃ̉Ƃɗa������B
���Óc�m��w
���{�̉p�ꋳ��E���q����̐��҂ł���Óc�~�q���ݗ��������q�p�w�m��O�g�Ƃ���B�����s�����s�Óc��2-1-1�ɖ{����u�����{�̎�����w�ł���B1948�N�ɐݒu���ꂽ�B
���q���ʓP�p����y�A�j���ٗp�@��ϓ��@�̐ݗ����A�Óc�m��w���Ɛ��̊��߂��܂����A�ꗬ���Ƃ̏d���A�������̏����E���̏o�g�Z����т��ĒÓc�m��w�ł���u�Óc�}�t�B�A�v�Ƃ������t�ŌĂꂽ�B
�w���Ɂu�L���X�g�����_�Ɋ�Â�����v���s�����Ƃ��L�ڂ���Ă��褗�q�����T�s��꤃L���X�g���֘A�̉Ȗڂ��J�u�����Ȃǂ̏@���F��������L���X�g����`�w�Z�ł��邪��Q���͊w���̈ӎv�ɂ܂�����Ă���
�������ӎO
����2�N�i1861�N�j- ���a5�N�B�O�X���k80�l�ŏq�ׂ��B
������`�M�Ǝ����Љ�ᔻ�Ɋ�Â����{�Ǝ��̂����閳�����`���������B
�{�͂ł́A���c�����̒Ǔ��������������Ƃ��q�ׂ��Ă���B
���싙
�u�����������v
�������A����ɂ������č��c�ɂ��������t�Ƃ����̂́A���ꂾ���ł���B
���c�͂��������{�����Ԓ��̐����@�������˂�������ł������̂Ŏ��@�֏o�������B���������̗]�n���Ȃ����q�����O�߂����Ă���A���k���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�������N9��27���ɁA�k�z�o���R�̑��w�����Ƃ��āA�������肵�����������́A�A�����������˂���̏��̂��̍��c�����ɔC�����B�Ė≮�̉z�㉮�������B�����A���c�A�z�㉮�̂Ȃ���́A���̂Ƃ��ɂł����������̂�������Ȃ��B
��19�́@�ދ�
�]�������c�����Ɠ��l��10��21���̔������̑�v�۔h�̍���c�ɌĂꂽ�Ƃ������q�����邾���ŁA���ۂɐ��ؘ_�Ԃ��̂��߂ɂ����Ȃ铭���������̂����A�w�ĂԂ��@���x�ɂ͏�����Ă��Ȃ��B
����q�@
������
�����~��
�O�X���k666�l�Ɍ��݂͂Ȃ����~���ɂ��ď����Ă��������A�m�F�̂��߂ɂ�����x�����B
�������茾���ƁA�n�c�������Ő̓��݂̂����肾�B
�������̊O���_
�����@���q1812�N - 1885�N�r
�m��v�̉ƌn�ŁA�\�c���E�c���E���͒n���̋��t�������B���@���͓���12�N�i1832�N�j�ɉȋ��ŋ��l�̎��i�����A�i�m�ɂ͍��i�o����3������悵�����߁A�����ւ̓�����߂ČΓ�ʼnƏm�̎t�ƂȂ�A���j��n���̌����ɖv�����Ă����B
����𐴖��̏������Ə̂��Ă������߁A���͕ϐl��������Ă����B�����V���̗��̒����Ɋ��A�m���h�����Ƃ��Ă��L���B�����ł́u����Ō�̑单���v�Ɣ��ɍ����]�����Ă���B
���\���ˁq1811�N - 1872�N�r
1851�N�ɑ����V���̗����u�������̐��K�R�ł��锪���������ɂ����������A��A�s�ł������B���N�����ɔ����͋M��������̉����Ă����̂ł���B���̂��ߐ������{�͊e�n�̋��a�����ɋ��E�ƌĂ��Վ��̌R���̒���𖽂����B
�������]���˂͕����̒c���i�n���L�͎҂�����I�ɑg�D�������q�̂��߂̖����g�D�j���܂Ƃߋ��E��g�D�������B���ꂪ��̏ÌR�ł���A�ÌR���ŏI�I�ɑ����V���R��j�����B
�����E
���m���^��
�����@���̕��B�D����
�m���^���̗��O�́A�����̓`���I�ȕ�����x��{�̂Ƃ��A���m�̋@�B�����̋Z�p������������悤�Ƃ����u���̐��p�v�ł������̂ŁA���{�I�ȉ��v�ɂ͎��炸�A�������ێ����邽�߂����̂���ׂ̉��v�ɏI������B
�܂��A�m���^�����s���Ă���1870�`80�N��́A���������ӏ����ɗL���Ă����@�匠���A���X�ƕ������Ă����������ł������B
����ł������͖�����ۂ��Ă���A���[���b�p�e���͐������u����鎂�q�v�ƌ��āA�m���^���̐��ʂ�������Ă����B�������A���N��肩��u������1894�N�̓����푈�́A�����̈���I�Ȕs�k�ɏI������B����ɂ���ė͐����̍��͂�������A98�`99�N�Ɉ�ĂɘI���ȕ���������W�J����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Q�Q�Q�Q�Q
���C������
�C���i��ಁj�͌��݂̒����̐V�d�E�C�O��������ɔJ�s�B���̒n�̃C�X���[�����k���������N�����ƁA���V�A��������o���A������̐�̉��ɒu�����B���V�A�͒����A�W�A�̓�����琨�͂�L���Ă����C�M���X���V�d���ʂɐN�o���邱�ƂɑR���悤�Ƃ��Ă����B
�����̓��V�A�ɍR�c���P�ނ�v�����������V�A�͓����Ȃ��������߁A1875�N���獶�@�����w�����č���W�J��78�N�܂łɐ��̂������B1881�N�ɃC��������A�C���n���͐����̂Ƃ��Ċm�肵���B
�C�������́A1870�`80�N��̐��̂̕Ӌ��ɂ�����̐N�o�̈�ł���B���Ƀ`�x�b�g��_��n���ɂ̓C�M���X������A�������@�匠�������Ă����x�g�i���ɂ̓t�����X���A���N�ɂ͓��{�����ꂼ�ꔗ���Ă����B
���ΘI�����j�̒���
�i�n����̏��q���ƁA�C�������͑��݂����A���@���ɂ��V�d�̐��̉��Ȃ������悤�ɓǂ߂�̂ŁA���ӂ��Ă��������B
�����ł����u�ΘI�����j�v�Ƃ́A�C�������̑O�N�i1874�N�j�ɂ������C�h�E�ǖh�_���ɂ����闛���͂̍l���̂��Ƃł��B
���N�u�E�x�N�̗��k
>>47 �̃C�X���[�����k�̔����̂��Ɓl���_�@�ɓ쉺�������V�A�ɑ��āA���@���͒����ɐV�d�����̏����Ɏ��|����܂����B�����������͂�����ɔ����A����13�N�i1874�N�j�ɊC�h�E�ǖh�_�����N����܂����B
���@���̓��V�A�ɑ��闤��̔����̏d�v�����咣����ǖh�h�̑�\�i�ł���A�C�M���X�ɑ��邽�߂ɊC�R���d������C�h�h�̑�\�i�ł��闛���͂Ƃ͐����I�ɑΗ��W�ɂ���܂����B
�V�d�Ɋւ��Ă��A��̉������x�z�𗧂ĂȂ������Ƃ��鍶�@���ƁA�C�R�ɏW�����邽�߂ɖh�q�̓���V�d�����V�A�Ɋ������悤�Ƃ��闛���͂Ƃ̊Ԃł͈ӌ��̑��Ⴊ�������̂ł��B
�_���͗��������N�i1875�N�j�A�R�@��b���˂��^���������ߊC�h�E�ǖh�ǂ�����s�����j�Ō��肳��A�ԍ���b�ɔC�����ꂽ���@���̓��N�u�E�x�N�̗��ɂ�萴�̎x�z�͂���̉������V�d�̌R����S�����A�V�d�����ɂ����鐴�̐����Ȃ����_�n�~�œԓc���v����̂�A�o���𐮂��܂����B���̌�̓W�J�́A
>>47 �ɏ����Ă���Ƃ���ł��B
�k�������`�ł́A�{�̗{�����̎O�l�̈�҂̂ЂƂ�ɂ����Ȃ��������˂��A�����̌R�@��b�ɂ܂ŏo�������̂��B
�i�n�ɑ��Y�ɂ́u�C���\���L�v�Ƃ����I�s�����邪�A���̂Ƃ��܂łɂ̓C�������̕��͂����낤�ȁB
���@���𒆐S�ɁA�m���^�����ぁ�̐N�����I���ɂȂ�������i1870�`80�N��j�̐����ɂ��Ē��X�Ə����Ă���܂����A��ڂ́A���@���������������̎^���錾�t���q�ׂ��Ƃ����Ƃ���ł��B
���~���Ɍ����������ŁA�]�����l�������Ƃ�������A�܂�������̂ɂȁB
�u�X�����䂭�v�������n�߂Ă���̎i�n����́A����z����Z���o�����B
�������A�g�l�Ԕ��d���h�u���[�m�E�T���}���`�m�̋Z�ɂ͏��ĂȂ��B
����ȃu���[�m�E�T���}���`�m���A�d�C�E�i�M�ɂ͏��ĂȂ��B
�u���[�m�E�}�[�Y�́g�u���[�m�h�́A�u���[�m�E�T���}���`�m�Ɏ��Ă������Ƃ���c������ɕt����ꂽ���������ƌ����Ă��邪�A
>>49 �����������@���́u�V�d�Ȃ���肵���v�Ƃ͏����Ă����B
���̒���ɁA�u���͉������咣����������ɗe����Ȃ������v�Ə�����Ă��邩��A�킯���킩��Ȃ��Ȃ�킯�ŁB
>>49 �����͂��ΘI�����j�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�l����̌R�Ɉ͂܂�āA���V�A��D�悷�邩�A�Ήp����D�悷�邩�̑�������ˁB
�t��A�h�A�m�u�ɐG���ƁA�d�C�����Ŏw�悪�ɂ��B
����A������������c(`��ցL� c)���߂� ��������
���r��l�Y
�������������ˎm���䌺�ׁk�O�X��934�l�Ɍ�����Ƃ������e���Љ��B
�����́A�č����g���W�F���h������A���V�A�Ɖp���̐푈���߂��ƒm�炳��Ă����B�����W�N�̃C�������̂��Ƃł���k
>>47 �l�B
�u�p�E�D�̍ۂɋ߂����N����\���ׂ��ƁA���̍������i�A�����J�j���g�̋ɓ��̐S�t��������ɂ���v
�����́A�p���ƃ��V�A�̑Η��𗘗p���āA���V�A�Ɛ푈���邱�Ƃ��l���Ă����̂ł���B�p���Ɠ������邽�߂ɂ́A�p���ɖk�C����݂��^���邭�炢�̍����������Ă����B�����̗���ŁA���N�Ƃ̐푈���l���Ă����߂�����B
���̏͂ł́A���@���̒k�b�����p���āA������������o�҂ł������悤�ɏ�����Ă���B
�������Ԃ�
���y�q���܂��r
���̒[�ɓn�����B
�����̏��~���̉B��Ƃ�K�˂Ă��������ЂƂ�̐l���A�����۔V���̂��Ƃ��֑��I�ɏq�ׂ��Ă���B
�������۔V��
�����͑�v�ۂ̖��ŁA�]�������~����K�˂������A�����̓��Â�T��ɂ����B
��19�́@�ދ�
����Ə��ې��o���@�@�䂪�Ƃ̏��ېo�����
�����̉Ƃ̏����̉����o�̕����̉������@
���V���̊K�i�̏�̂��ǂɉ˂�����|�͐��������̂��̂ł���B
���̊��|�͖���6�N����47�̂Ƃ��A���ؘ_�ɔj��10��28���A���̓r�ɂ��A11��10���������ɒ������B�܂��ɂ��̓��ɍ��ꂽ�c��������r�̑�ꐺ�ł���B
�������̓k
�M�҂��c�����Ɋ��P�����h���}�����߂��������ŁA�����Ɠ����ł��B
�u��̐����v
�����{�����Ԓ�
��10��24���t����������
��10��28����
����q�c���
�i�n�ɑ��Y�̖{�������c���Ȃ̂ŁA�I���L�����������ȁB
��19�́@�ދ�
�ނ����̔C���f�悪�Njy���Ă����j�̔��w���ȁB
�������ߓc�_��⍂�q�����˖엘�H�������邱�Ƃ͐�ɂ��肦�Ȃ��B
�u�ĂԂ��@���v�Ŏi�n������D�u�Ƃ����˖�̈�ʂ���������邪�A���͋˖삪�o�ꂷ�邽�тɑ���������Ǝv���Ă��܂��B
>>85 ���u������A������v
�u������v�̖��O���x�Ă�ł���̂��A�Q�Ă�����������N�����Ă���̂��A�O�ɓǂƂ����Y�B
���L�n����
����q�Ȃ�ār
�P�D�c�̒��̍ד��B�������B
�Q�D�܂������Ȓ������B
���̎l���̓X��ŗL�n�̌��܂𒆑������Y�����Ă����Ƃ����̂ł��邩��A�����ł͂Q�̈Ӗ��ł���B
����ۓ�Ð��Ձi�{�͂Ƃ͖��W�ł��邪�A��̃C���[�W�ɂ҂�����Ȃ̂Ōf�����j
�L�n�����Ƌߓ��E�̊W�ɂ��ẮA�Z�ҏW�w�]�b�Ƃ��āx�́u�L�n�����̂��Ɓv�ŏڂ������B
�L�n���Y�i�����j�͎i�@�ȏo�d�̎��ɁA�����̎��E�ɑ��������B
�L�n�����E���������A�낤�Ƃ������A�����̈ӌ������蓌���Ɏc���đ㌾�l�ƂȂ����k
>>90 �l�B
�����̎��E���_�@�Ƃ��āA�߉q�R�m�����̑�ʂ̎��E�҂���������B���ʓI�ɁA�����̐��{��]�ł���Q�c�̔����ƌR�l�E������600�l���E���������B
�������ؒʍ�
���ؒʍ�
�˖�͓����ؒʍ�ɂ��������喼���~�ɏZ��ł����B���̑喼�Ƃ͉ƍN�̎l�V���̈�l�匴�N���̍匴�Ƃł���B�����ېV�ŋ˖엘�H�̏��L�ƂȂ�A��ɐ��������ƂƂ��ɗ��H���������ɋA��Ƃ��A���푾�Y�̏��L�ƂȂ����B
���A�ō��ٔ����̎i�@���C���ƂȂ����i���a46�N�j�B���������݂̎i�@���C���͍�ʌ��a���s�ɂ���B
���匴��
���������L��A�x�M�V�ɍ݂�B
�������H�嗘
�����ɂ͎K�т������e���Ȃ炠�������B�ǂ����݂炾�낤���B
�����������@
�����v�Q�N
���n��ŏ����ꂽ������h���}�ł���A�������̐����𒆉������̓����ɂ���܂���̂͗����ł��Ȃ��͂Ȃ��B
�������̋˖��
�����͌��ؑ�g�Ƃ��Ċؓs�Ŏ��ʂ���ł������B
�����͋˖�ЂƂ�ɑ��āA���ؘ_���s���Έꏏ�ɋ����ɋA�낤�ƌ������Ƃ����B
�o���~���S�̋����l���̍l���Ă������Ƃ́A�㐢�̉�X�ɗ������₷���B
�܂��ȁB�Y�݂͐l�Ԃ̓����ɂ�����̂ŁA���͂⌾�t�ɂ��ĕ\�ɏo���Ƃ��́A�Y�݂̕����͕������邩��ȁB
�������˖�������]�����Ă����Ƃ����̂��A���͕\�ɏo�������B
�����c����
���ʝ�
�˖�Ɛ����̎v�z�̋��ʓ_�́A���̐����̌��t�ɑ�\�����B
�����^
������u���ؘ_�̓^���v
�|���ېV�̒B���ɂ́A�˖�̂悤�Ȓj�̗͂��K�v�ł��������A�V�����𐬗������邽�߂ɂ́A�˖�͖��v�Ȃ��肩�L�Q�ł��炠�����B
�V���{�̗v�l����`�̋L�ڎ����̕��ނɂ��Ƃ���ƁA
�˖�̓`�����o�������̐l�ł����āA���_�̐l����Ȃ�����ȁB
�o�J�͎v��������o�J����Ȃ��Ɛl�C�҂ɂȂ�Ȃ��B
>>117 ���܂��A�����Y�Ɉ��𓐂܂ꂽ������āA����͌����߂��B
�����Ƃ͂قlj���������C���[�W�������ꂽ�s�҂͑����B�˖엘�H�Ȃǂ́A���̓T�^���낤�B
��������l�ɂ��˖�]
�������۔V���k
>>71 �l
�u�|���������悤�Ȑ����Ŕ����o���Ȑ����v�u�j�炵�������ō����v�u�����ς肵����艂Ȓj�v
�����y���˂̕x�c�ʐM�i�݂��̂ԁj
�u���ɚ��炸�����Ȃ�l�v�u�����ėE�҂ɂ��ēG�Ȃ�S�����������ł���Ȃ���A�܂������Ĉ���[���l�v
���̕t���s
>>116 �y���ΎO���q�[���[�ɂȂ����̂́A�i�n�́w�R���挕�x���炾��B
����ȑO�̉f��A���邢�́A����Ȍ�������A�q�[���[�͋ߓ��E�ŁA�y���͗⌌���̈����������B
�ߓ����q�[���[�ɂ��邽�߂ɁA�V��g�̓s���̈����Ƃ���́A���ׂēy�������ł�����������Ă������Ƃɂ���Ă����B
�����̖��ꐫ���������邽�߂ɁA�˖�͓y���ΎO�Ɠ����悤�ɁA�D�����Ԃ��Ă���킯���ȁB
���ꐫ�Ƃ������t������ƁA�Y�i�̈�@���W�؋��r���@�����v���o���ȁB
���ؘ_��������̖����A�u�����ߑ㍑�Ƃ����Ă��܂����V�A���g�ƁA������������Ƃ̂Ȃ��h���X�e�B�b�N�Ȑl�X�̑����v�̈�s�ŕЕt�����ǂȁB����Ȓ��������������Ȃ��Ă��B
���ʕ{�W��
����2�N�A�����������������ꂽ�Ƃ��A����̏������ƂȂ����B����4�N�A�����������p�˒u���ɔ����ĕ��𗦂��ď㋞�����Ƃ��A�����𗦂��ď]���A��e���ɕғ�����A�����ŋ߉q���R��тɔC����ꂽ�B
����5�N�A���ؘ_�Ɋ֘A���Đ��������F�E���N��@�𖽂����ۂɂ́A�k�������q�E�͑��m�^�ƂƂ��ɊO�����E�Ԗ[�`���̐����Ƃ����`�Ŋ��R�ɕ����A�ؕ��𒅂ĊؖX��Ղ��A�ϑ�����2�����߂����N���n���@�����B
���W��͍��B�E�͋˖�B
���w�c����x�ł͐������B
�W��͓V�����~�Ȃ����ɕ����v�z�������A���Ƃ��Ε����ɑ��A����������ɂ����B����͕����̎m���≺�m���̕�������̕�ƃR�~�ɂ��ĕ����ɕ��z����̂ł���B
�W��͐���푈�̂Ƃ��Ɋ��R�����Ƃ��e������̂��݂āA
�����}�̐��i�́A�O������̈�ۂƂ��ẮA�u�����͕����������悤�Ƃ��Ă���v�Ƃ������̂ł������B
���剖�����Y
�V�ۂ̑�Q�[�́A�S���I�ɂ͓V��4�N�i1833�N�j�H���瓯5�N�Ăɂ����ĂƓV��7�N�i1836�N�j�H���瓯8�N�Ăɂ����Ă����ɂЂǂ������B
�Օ��ǕJ�ɑ��錣�p�����ꂽ��A�V��8�N�i1837�N�j2���ɓ����āA��������������Ȃǂ��Ď������Ȃ��������~�ϊ������s�����A���͂═���I�N�ɂ���ĕ�s����A�������Ă��������ċ���������ȊO�ɍ��{�I�����͖]�߂Ȃ��ƍl�����B
�V��8�N2��19���i1837�N�j�ɑ剖�͖�l�A���O�Ƌ��ɖI�N����i�剖�����Y�̗��j�B�������A���S�̖�l���l�̖����ɂ���Ď��O�ɑ�⒬��s���̒m��Ƃ���ƂȂ������Ƃ������āA�I�N�����ɒ������ꂽ�B
�剖�����Y�́A�������������h����l���Ƃ��āA���̖����������Ă���B
���|�����c
���߉q���i�ߕ�
�����U�N�����͋߉q�����A���ł���A�߉q�t�c�Ɖ��̂��ꂽ�͖̂���24�N�ł���B�Ȃ��A����24�N�ɂ͒�����t�c�Ɖ��̂���Ă���B
�n���S�u��i���w�v�u�|���w�v����k��10���A�k�̊ی������ɂ��铌�������ߑ���p�ٍH�|�ق́A���Ƃ��Ƌ߉q�t�c�̎i�ߕ����ɂƂ��Ďg���Ă��������ł���B
���������������̂́A����43�N�i1910�j�B�֓���k�Ђ�����������ʂ��A�قڊ��S�Ȏp���Ƃǂ߂Ă���B
����11�N�����̋߉q�i�ߕ��̎ʐ^���������B
�����������V�N�����̋ъG�̌����Ƃ͈Ⴄ�B
�ʕ{�W��������i�ߕ��́A���̋ъG�̕���������Ȃ��B
���̐w�̑����̘S�l�ɂ͐e�ߊ������Ă�̂����A�������s�R�̏��Ŕ�Ƃ̍Ŋ��𐋂�������̖��̋˖��ʕ{�ɂ͐e���݂��N���Ȃ���ȁB
�����ЂƂ̗��R�́A���̐w�̘S�l�͗c�����ɒm�����B�M�҂͗��앶�ɂ̎���̐l�Ԃł͂Ȃ����A�M�҂��c�����ɓǂ���⏬���̍�҂��q���̍��ɗ��앶�ɂ̈��ǎ҂����ł������i�i�n�ɑ��Y�����̂����̂ЂƂ�j�B
>>139 ���ʐ^�܂Ŏc���Ă��閾���̐l�ɂ͘Q�������ʂ���������Ă���B
�����B�ʐ^�����Ȃ���A�˖��ʕ{���D���ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B
���̓�l�A�l���������B
>>140 �c����͂�����Ȃ���l�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����邪�A�c�����ɒm�����q�[���[�́A���ł��q�[���[������ȁB
>>139 ���ؘ_���̎Q�c�����́A���Z���{�j�ŎU�X�o��������ꂽ����݂̂��閼�O�Ƃ����̂�����ȁB
�ނ炪�ꋓ�ɑޏꂵ�āA�F�R�̂Ȃ��݂̂Ȃ����Z�����̖��O����ʂɏo�Ă���ƁA�e���Z�̌��̍��ʉ����ł��Ȃ��āA�܂�Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ����̂�����B
���O��n��
���N�̓암�n��ł���c�����E�S�����E�������̎O���̂��Ƃ��w�������t�ł���B �Â����璩�N�������\���鍒�q�n�тƂ��Ēm���Ă���B�ʕ{�W��͖����T�N�A�k�������q�����ƂƂ��ɁA���N�̎������Ƃ��ĎO��n���𒆐S�Ɏ��n���������B
��������`
�������Ƃł͌R�����i��v�E�̂قƂ�ǂ������ɂ���Đ�߂��Ă���A�����ɂ͎����㐭�{�v�l�ւ̓���������Ă����B�����ĎI�ȕ�����`�̗��ꂩ��A�O���Ƃ̊Ԃɐ����鏔���̉����́A�\�Ȍ��萭���I�ȊO���ɂ���ď������邱�Ƃ��悵�Ƃ���A���y�̖h�q�͏@�卑�ł��钆���ɗ�������ōl����X�������߂��B
���������ɒ[�ȕ����ƍق̕�����`�����ɂ���ČR�����y�����ꑱ�������ʁA���c�Ȃ���̌R����̉������������Ă��܂����̂ł���B
Part11�k657�l�ɏ������悤�ɁA�W��͋A���̌�A�˖엘�H�@��K����A��O���u�{�є��������W����́A���O�Ӓ����ɂ��đ����v�Ƌ��Ɖ]����B���̌�A�����ɏ��i�����B
�������ؒʍ�
���K�g
�˖�̓@�������ؒʍ�ɂ��鋌�匴�Ƃł��邱�Ƃ́A���q�����k
>>95 �l�B
�K�g�͋˖�̉��l�ŁA�F�����g�쑺�̕S���̎��j�V�ł���B
�K�g�͐���푈�ŋ˖�Ǝ�����ɂ���B
�����g
�u�����A������v
�e�ɐH�킹�Ă�����Ă���w���Ȃ�A���̎F���l�̃_���f�B�Y���������������Ǝv����������Ȃ��ȁB
�˖�͑��ېV��10�N��ɂ��A�Ƃ��������Ԃ����ېV�����]�������Ɋ��҂���ƌ����Ă���B
��������
�ɓ��s�V�̕��͂Ɂu���̋��t���ʋ˖엘�H�v������B�����ł̋˖�̏��́A���H�ɂȂ��Ă���B
�����Y���˖엘�H�ɂȂ�A�g�������R�����ƂȂ��āA�����ɂ��������{�̉Ƃ�����ďZ��ł������A���q�����ɑ������߁A��������Ď�H�̐��b�������Ă����B
�˖삪�펀������A���H���˖�̔閧��������̂ŁA�����������Ȃ��������R�����炩�ɂȂ����B
�������p�q�Ȃ݂��r
����7�N�i1824�N�j - ����27�N�i1894�N�j
�����ېV�̂Ƃ�44�ł��邪�A�i�n����͏����Ƃ��Ă���B�����Ԃ�V���������ł����Ƃ�
�L�O���F�����i���啪���F���s�j�̓��g���ɐ��܂�A�F���_�{�����������̉����̗{�k�q�Ȃ�B
���v3�N�i1863�N�j�A�G�R���ċ��s�ɏo�V���ėJ���̎u�m�ƌ����A���������̐������n�܂�B���傤�ǎO����������̎��������ƂȂ�A�Ή����Γ}���A����݂�╮�S���A�����ɉF���ɋA��A�L�O���E�L�㍑�̎u�m��ƌ�炢�Ή��|���̐�ڂ�����Ƃ��ĂȂ炸�A��E���}�d���Ƌ��ɓ��c�̍��ɂɓ������A3�N���o�đ��ʂ̑�͂ɂ��o�������B
����3�N�A�_�_���j�ɔC���A�_�_����j�ɑJ��A���R�ȁi����̗��A��p�o���ɏ]�R�j�A�����{�A�J��g�����i�ԓc���̒��Ƃ��Đ���푈�ɎQ���A�J��g�p�~�܂ŊJ�Ɛ��i�ɏ]���j�A�呠�ȁi�J���v�c�������ψ��j�A�C�j�ǎl���ҏC���i�k�C���j�y�уA�C�k�����̒������܂Ƃ߂�j���C���A�����ʂɏ������A����19�N�Ɋ�����E�ނ���B
���̉����p���˖삪�������������q���ȂƂ����Ǝi�n����͏q�ׂ���B�����p�̔N��炷��ƁA�E�\�������b�ł���B
�܂��A���̍Ȃ����q�ł��邱�Ƃ́k
>>155 �l�ŏq�ׂ��B
�i�n����́A�u������v���邢�́u������v�Ə����Ă����B
���O�����Y�̖��E���}�����w�P�N�̍��ɁA�����q�Ƃ������������k����������Ǝi�n����͏�����Ă��邪�A��������₵���B
�����O�����Y�q�������낤�r
����21�N - ���a26�N�F������w���_�����B���O�ʌM�ꓙ����́B�����Ώۂ́A���@�A�J���@�A�@�Љ�w�B
���O�́A�h�C�c���@�w�S���̎���̓��{�̖��@�w�����T�O�@�w�ł���Ƃ��ēO��I�ɔᔻ���A���@�w�̓]��������炵���v�����ł���B
�������A�i�n�ɑ��Y�̕��͂ɂ��ƁA�˖엘�H�ɘM�ꉜ���p�ɕ���������ꂽ���̑��Ƃ������ƂɂȂ�B
�Ȃ��A���O�����Y�̍ȁE�~�q�́A�e�r��[�̎O���ŁA���R�G�v�i���R��Y�̒�A��ȉh�̉��t�j�̍ȁE���q�̎o�ł���B
�b����₱�������Đ\����Ȃ������A���R�G�v�̍Ȃ��u������v�Ȃȁk
>>161 �l�B
���앪�q�̂킫�r
��19�́@�ދ�
��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@||�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P||
�@�@�@�@�@ �l
�����m��
�F���ˑ攪��ˎ�E���Ïd���͈��i2�N�i1773�N�j�A���������m�ی��O�ɖ�3,400�̕~�n���m�ۂ��A�̐����ł���u�鐬�a�v�A�u���E�w���E���ɂȂǂ����݂����B���ꂪ�u���m�فv�̎n�܂�ł���B
����ْ��ɂ͏d���C�ɓ���̊w�҂ł������R�{���b���C�����ꂽ�B���f���ɂȂ����͍̂]�˖��{�̓��������i������w�⏊�j�ł���B�אڂ���4,139�̕~�n�ɂ͋|����E������_�p�Ȃǂ̓��ꂪ�݂����A������͏��߁u�m�Ï��v�A���N�u�����فv�Ɩ������ꂽ�B
�������掵�����w�Z���m��
��������̐킢
�c��4�N�i1868�N�j5��15���A�������͏��̏��`���Ƃ̐킢�ł͍������S�������B���������͓P�ޖ��߂����������A�����S���������ɍU�ߊׂƂ����E�����������B
���͋ɒ[�ɖ����ŁA���ؘ_�ɂ��Ă��ǂ̂悤�ȍl���������Ă���̂��A�N���m��Ȃ������B
����c����
�����ؔh�̎�c�����́A�u�˖�ȂǁA�ނ��닎�����ق����悢�B����������Ε����͒��Â���v�Ɗy�ς��Ă����B
���Z�n���]�ʉ����@�@�n���@���]�ɟZ�i�݂Â��Ӂj�́@�ʂ͂����ĉ���̓���
�̋��ɋA�����������́A���ӂƓ��{�̏�����J���A���X��X�Ƃ��Ă������A���̎��͂��̍��ɉr���̂ł���B
���͑�v�ۂ�������������邱�Ƃ��l����ƁA������邱�Ƃ��ς킵���A�i���̂����A�p���B�����Ȃ��j�ƁA�ӂ��������B
���|�����c
�����c����
���ԍ≼�䏊
��10��25���[��
���q�����Ƃ���ł��邪�A����6�N5��5���̋{��Ђ���A����21�N�̖����{�a�����܂ł�15�N�ԁA�ԍ�̌��I�B�ˉ��~�Ղɖ����V�c�̉��䏊���u����Ă����B
��v�ۂ͂��̐ԍ≼�䏊�ɑ�ʎ��E�������Ă����߉q���Z�c�����W���A�V�c�̌��Ђ𗘗p���Ď��E���v���Ƃǂ߂����悤�Ƃ����B
�����厛�����q���˂ˁr
�V��10�N�i1840�N�j- �吳8�N
���c���Δh�̌����Ƃ��Ċ��A1862�N�i���v2�N�j������p�|�A���N�c�t�ƂȂ������A1863�N�i���v3�N�j�ɋN�����������\�����̐��ςɊ֗^���ސT�ƂȂ����B
1871�N�{���Ȃɓ���A���]���E�{�����ƌ��C�Ɏ������B1891�N����b�����]���ƂȂ�A�����V�c�̑��߂Ƃ��ēV�c�����䂷��܂ŕ⍲�����B�����V�c�̐����֗^�ɂ͋��������A���c�i�t�炪����x���߂ēV�c�e���^�����s�����܂ɂ͂��̑j�~�ɓ������B
�̐S�̎��͖Ԃɂ������Ă��Ȃ������B
���R�l���@
��10��29��
��20�́@���R��
�����̂��Ƃ�ǂ��Ď��߂Ă䂭�F���n�̋߉q���Z�����́A�R�鉮�����̂Ƃ��ɎR����l��A
��������
�������A�R���̍\�z�������䐧���A�O���ړI�̌R���ł͂Ȃ������B
���F�{
�u���B������݂�v
�u��C�̂Ƃ��A���k���˂̕��m�͊���Ɛ키�̂��������������ł��ȁv
������
��ኁq������r
�Ԍ��I�ɔ��M���A������k������a�C�B��Ƀ}�����A�̈��A�O���M���������B
�u���܂������I�Ɂu�N����v���ꌹ�ł���B
���}�����A�̓n�}�_����ɂ���Ċ�������B
������
�������x�m����
���R���@
�O�X���k258�l�ɏ������B
���݂͎O�Ԓ����p��c���ɂȂ��Ă��鋌�R�p�L���@�́A����18�N�Ɍ��z���ꂽ�B
���u���̗��R�v
�Ƃ��낪�A���c�����A��㑀�Z�A�厛���������������Ő����A���̂��Ƃɂ͖�Ó��т����ЁA�����۔V���͎��r���Đ����@�ɑ����Ƌ��ɗ��R���S�R���̑��݂�Y��炽�B�F�̗��R�̐��͍͂Ƌ��ɐ��ނ��A�R���̑���t��藤�R�̎����͂��ׂĒ��ɋA���ĎF�l�͒��l�ɋ��悤�ɂȂ����B
�F�̗��R�Ɏ���čł���Ȃ�Ō��͍��c�A��ÁA����������㑀�Z�̎��ł������B�Q�d�{���̐ݒu�Ɋւ��Ă͎R���̗͂��傫�����A����������̔@�����S�Ȃ���v���̕{�ɂ����̂͐��ŁA�����푈�̍��{�v��͖w��ǔނ̓��]���o�ł����̂������B
�i�n����͂��������w��̏�̉_�x��ǂق��������B
���O�Y��O
�O�X���k775�l�ŏq�ׂ��B�O��̓o��ł́A�R�鉮�a�������ւ̊֗^���^���Ă����B
�O��3�N�i1847�N�j- �吳15�N
����7�N�ɂ͗��R�ȑ�3�ǒ��Ƃ��đ�p�o���ɔ��B����9�N�A���̗��̒���ɕ����A���N�̐���푈�ł͑�O���c���Ƃ��Ċe�n��]��A��R���ח��������B����11�N�ɗ��R�����ƂȂ�A�����ČR�����B
���B�o�g�Ȃ���˔������ɔ����闧����Ƃ�A�܂��R�p�L���Ƃ͊�����ォ��s���ł��������Ƃ�����A�J����E�������푾�E�\��S����ƂƂ��ɔ��嗬�h���`�����A���j��̒��S�l���Ƃ��ĎR�p�L���E��R�ނ�ƑΗ������B
�{�͂̎O�Y��O�́A�A�������R���@�ɏW�܂�����l�Ƃ��ēo�ꂵ�Ă���B�܂����͂悩�����悤���B
���،ˍF��
�����@
�����@
���E�@
���ߑ���{�̊���
�����̏��F�c��4�N�[4��21�� - ����2�N7��8��
���Z�Ȑ��F�ŐЕ�҂���p�˒u���܂�
���O�@���F�p�˒u���������c�܂Łk
>>206-208 �l
�������W�N�����F����8�N4��14�� - ����18�N12��22��
���R���L��
���呺�v���Y
�����������]
�������́A�呺�v���Y�����i���Ă��āA�呺���ÎE���ꂽ���ɁA�呺�Ɖ���Ă������A���ŗF�l�Ƃ����肠���āA���̂܂܋_���ɗV�тɍs���A�呺�̂Ƃ���ɍs���Ȃ������B����œ�ꂽ���������A�^�̂����j���Ǝv���B
�u���������̂��Ƃ��҂����]�ɏ悶�ċ�B�ŗ����N�����v�Ƃ����呺�̌��t�����̂����������]�ł��B
���F�����
�呺���͐����ł̎m���̔������x�����A���ɑ�㑢���i�i��̑��C���H���j�A���{���i��̗��R�m���{�Z�j��ݒu����ȂNjߑ�R�����݂��w�����܂��B
8��13���A�呺���͌R���{�݁A�y�ь��ݗ\��n�̎��@�̂��ߋ�����ʂɏo���A����������̌��{�A�F���̉Ζ�ɗ\��n���������A20���A������̎{�݁A�V�ێR�̊C�R��n�������A9��5���A���s�ɖ߂����ہA�����B�ˎm���ɏP������d�����A11��5���A���ɂ����Ď������Ă��܂��܂��B
����㗤�C�R������
�k
>>216 �l�Ō��ݗ\��ł������u������̎{�݁A�V�ێR�̊C�R��n�v�̂��ƁB
�呺�ݐ������̗�����́A�܂������ɂ������B������[����T�J�����~���B
���D�z�q
�V��11�N�i1840�N�j- �吳2�N�i1913�N�j
���͍L���˂̍��������Ƃ��Ė����������D�z�����B�L���ˍZ�w�⏊�i���C�����w�Z�E�C�������w�Z�j�Ŋw�ь�ɋ����ƂȂ�B
�呺�v���Y�̎���͎R�p�L���ƌ���ŕ������v�ɂ�����i��ɑD�z�̒��j�E���V��͎R�p�̖����ƂȂ�j�A����3�N�ɕ������ƂȂ邪�A�����ȉ��g�ɂ�藤�R�ȂɈڐЂ���B
�Ƃ��낪�A���R��匓��v�ǒ��̎��ɎR�鉮�����ɘA�����đފ��ɒǂ����܂�ČR�l�����͏I����������B���̌�A����7�N�ɌːЌ����߁A�����Ȑ�����͓��������Ƃ��Ă̓�����B
�D�z�͑呺����l�ҎR�C�������������đ��ɒ����Ă����Ɩ�����ꂽ���A����������O�ɎR�鉮�����ɘA�����ČR�l�������I����Ă����B
�R���͂���͂���̐��U�̓��������A���悻���l���]������A���̐��͂ɂ��Ĕ��܂������Ƃ����ɂ������Ƃ��Ȃ��B
��v�ۂ���{�����O���猩��o�����������҂����͐��E�ɂ�������{�����������̂悤�ɏ������Ǝv���Ă��邪�A�����ɂ����A���͂��܂Ȃ��퍑���̍��������Ɠ��l�A���{�Z�\�]�B�����V���Ƃ������o���甲�����炸�ɂ���B
��������
�H�q�̉ʎ����n���ƐA���͎̂͌����A�n�����ʎ��̓V���Ɍ��������A�a 0.5mm �ɖ����Ȃ����ׂȎ�q����яo���B���ɍׂ��������u�P�V���̂悤�ȁ`�v�ƕ\������̂́A���ꂪ�R���ł���B
������p���̏�ɏ悹��ꂽ�c�u�c�u���H�q���ł���B
�H�q�́u�����v�Ƃ��ǂނ��u���炵�v�Ƃ��ǂށB
�J���V�i�̎�q�͂��炵�i�a���炵�j�̌����ƂȂ�I���G���^���}�X�^�[�h�Ƃ��Ă��B
�u�N�͗��R���Ƃ��Ă܂����R�����Ƃ��āA���������܂ł����݂Ƃǂ܂点�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��v
>>191 �i�n����̂悤�ɎR���L�����匙���Ȑl�́A�R�����������瓦���Ă����ƍl����̂��낤�ȁB
�������A�߉q���ꂪ�N����悤�ȏɂȂ�A�n���̒���╪�c�ł����l�̎��E�������N���邩������Ȃ����A���ɑ����Ȃ��s���m���̗����n������T�����グ��\��������B���ɗ��N�ɂ͍���̗����N����킯���B
�����ɔ����ďo��������̒���̎��@�𗤌R�����s���͓̂��R�Ƃ��������ˁB
�F�{���䂪�P��ꂽ�ƌ����Ă��A���ۂɌF�{������������Ƃ��Ȃ���A��̓I�ȃC���[�W���킩�Ȃ��B
���Z���̍��Ɏi�n��i��ǂƂ��́A�R���L���̈����������Ă���Ƃ���͒ɉ����������ǂȁB
�������w�c����x�̗L�씎�͎R�p�L���Ɍ����Ȃ������ȁB
�����ƃu�T�C�N���j�̓��̍킰���������҂����Ȃ��ƃ_�����B
>>225 ��v�ۂ��V�c�̌��Ђ��g���A�،˂ƎR�����z�������悤�ɂ��Ď����ԗ�������藧�Ă��l���Ă���V�[����ǂ�ŁA���������Ăǂ�قǂ̐l���Ȃ낤�Ɗ��҂�����ȁB
���炭����ƁA�i�n����ɂ���ă{���N�\�Ɍ����o���܂��B
>>219 �A�����E���ԂɎR���L�����������߂ɁA�D�z�ƎR���͐e�ʂɂȂ��āA�ŏI�I�ɂ͑D�z�q�͏����g�ɂȂ�����(�E�́E)����
>>222 �ނ�������s�v�c�Ɏv���Ă����̂����A�A���p���̏�̃c�u�c�u�͊H�q�̌����Ȃ̂ɁA�����Ƃ��h���Ȃ���ˁB
�h�݂����邽�߂ɃP�V�̎����ڂ��Ă��邶��Ȃ��āA�u��������v�Ɓu�Ԃ���v���������邽�߂ɍڂ��Ă���B
�u��������v�̏�ɍڂ��Ă���̂��A�P�V�̎��B
�u�Ԃ���v�̏�ɂ̓S�}���ڂ��Ă���B
�N���A���p���ɐh�݂�����Ƃ͌����Ă��Ȃ��B
>>168 �u��S�\���v�Ɓu�앪�v�́A���ɂň���ɂ܂Ƃ߂�Ă���ȁB
�u��S�\���v�͉�b�����łĂ��Ȃ��ςȏ������������ǁA�u�앪�v�͗ǂ������ȁB
���e�͂܂������o���Ă��Ȃ����A�����ǂ��Ԃ��v���o���ƋC������������A�����Ɩʔ���������������B
��20�́@���R��
����������
�����{�����@66���Q��
���������푾
���������푾
�O��4�N�i1848�N�j- ����38�N�BPart12�k259-260�l�ɏ������B
���������R�����ɔC�����ꂽ�̂�24�̂Ƃ��B����26�B
�������푾�͕�C�푈��ɘa�̎R�˂ɏ��ق���A���˂̌R�����v�ɕ�c���s���ȂƂ��ĎQ�^���Ă���B
���̌o������b�ƂȂ��āA�F���ˏo�g�̎��͎҂������p�˒u���ɐT�d�Ȏp���������Ă����ɑ����@���ɋ���A�쑺���ƂƂ��ɎR�p�ɑ��Ĕp�˒u���̑����f�s���c�����B
����14�N���ς́A�J��g���L���������������_�@�ɁA��������e������G�d�M�����r���������Ƃ��ėL���ł��邪�A���r�����̂́A��G�d�M����ł͂Ȃ��B
�������F�E�q��h�`
��������
����20�N�ȍ~�̒����́A�����m���Ɣ�������`�������č��Ǝ�`�E������`�̋����ɓw�߂��B
���T�؊�T
�T�؊�T�́A���̎���̎m�����A�m���̐����𒅂����߂����o���ΒN�ł��m���ɂȂꂽ��Ƃ��ċ������Ă���B
�߉q�̑O�g�͌�e���ł��邽�߁A�F���y��ȊO�̎l�ˈȊO�̕��͂��Ȃ��B
���߉q�s��
���،˓@
�߉q�s�́A���f�肵�܂�
�R�l�̓|���`�b�N�Ɋ֗^���Ă͂Ȃ�Ȃ��k
>>237 �l�B
����͎Q�c�̌��C�����߂Ă���R���ɂƂ��Ă͓s���̈����_�ł������B
������t�ł́A�]���V�����i�@���ƎQ�c�����C���A��G�d�M���呠���قƎQ�c�����C���Ă����B
�����U�N���ό�A�ɓ��������H�����ƎQ�c�����C���Ă���k
>>213 �l�B
���������̌�����،˂������o���˂A�R�����R�����Q�c�����C���Ă������������Ƃł͂Ȃ������B
�������Z�N����
�u�����A���߂܂��v
�J��i��w�l�Ԑ����ے����鐭���̗͊w�x�i�S�W��35���j
�������V���q�������r
����34�N - ���a31�N�B�}���N�X��`���j�w�E���j�N�w�E����j�B
�������߉�S�����i���E�l�c�s�j�o�g�B
��y�@���@���ɐ����B�����l�c���w�A��O�����w�Z���ƁB1925�N�A�����鍑��w���w���Љ�w�ȑ��ƁB��w�݊w���Ɏu��`�Y�A���s���Ɠ���V�l��Ŋ���B
���a�R�N�A�O�E������̋��Y�}�e���̍ہA��������邪�ߕ�����A�B���j�ς̗���ňېV��_�����u�����ېV�j�v�����s�B���a7�N���s�J�n�́u���{���{��`���B�j�u���v�ɂ����ču���h�̑�\�I�_�q�ƂȂ�B
�i�n�ɑ��Y�͈�т��ĊT�O�̂��Ă����тɁA���������̋������������Ȃ��B���j�̐^���ɋ߂Â����́A���̎����ɐ��������܂��܂Ȑl���̌ʂȎ����ɂ���������z���͂ł���B
�����Ղȑ��i�̍\�����Ƃ��āA�����ېV�͊v���ł͂Ȃ������̈ڍs�ł������ƍ��݂��猩���낵�Ē�`����ƁA���̓r�[�ɑ�v�ۗ��ʂ������������A�P���Ȃ����l�`�ɉ����Ă��܂��B
���j�̔g���ɂ����悤��l�ЂƂ�̐l���̌���ꂽ�ӎ��ɂ́A�ߋ��ƌ��݂����^�����Ă��Ȃ��B�����͖������瓖���̎�����U��Ԃ茩������������Ȃ��B
���w�m
���̐��ł��ώ@�҂ł���Ȃ�A���_���Ђ˂�o���Ă͎��Ȗ������y���߂悤�B�������Q���̓����҂ɂ����ẮA�T�ώғI�Ȍ��_�͕s�v�ł���݂̂Ȃ炸�A���ɑłׂ�����l����ɂ́A�L�Q�Ȏ肩���������ƂȂ�B
�{�e�̖،ˍF�A�ώ@�҂̗���ŁA�i���I�Ȏv�z�������邠����́A�w�m�Ɏ������̂�����ȁB
>>232 �A���p���̏�̃c�u�c�u�̓J���V�̎��ł͂Ȃ��ăP�V�̎�������A�h���Ȃ��̂ł͂���܂��H
>>233 ������A
>>232 �ɒނ��Ă��܂��H
>>247 �������C�̌�͋߉q�s�͂��炭��ȂɂȂ��Ă������A���ǁA���R���̎R�����߉q�s�����C���邱�ƂɂȂ�B
�{�͂ɂ�������Ă���ʂ�A�����̑O�̋߉q�s���R���������B
�w��̉~��UFO�x���ςĎv�����̂����AUFO�Ɛ키���߂ɂ́A�G�����[�̂˂�����ɃG�����R�X�`���[���𒅂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H
�y��z�v���ł͂Ȃ��������
���u�v���v�̓�`
�����̏����́A�v���Ƃ́u�Ր��v���v�̈Ӌ`�ɗp������̂���ʂł������B����ɂ��ƁA�����ېV�͐����̌��Ƃ����F���ɂȂ�B
���u�N�w���b�v�q�����r
�����ېV�͓��쐭����]�������ɂƂǂ܂�i�������j�A�V���ɍ��������Ƃ�������̉ۑ�ɂ����Ȃ������B
�O�������ɓx��䅓�ɂ݂��Ă����v���Ƃ́A���낤���Ċv�����ꉞ�̐��A���݂�ƁA�l�Ԃ��ς�����悢���Ɍ����~�̂����܂�ƂȂ�B
�v���Ƃ̂����ЂƂތ^�́A�������Ȃ�ێ����A�i�v�v����ڎw���ē��O�ɎS�Ђ��Ђ��������^�C�v�ł���B
�����S���Y���qrigorism�r
�������ŗ����郊�S���Y���́A���ʂƂ��Ă͖����ĐX��������̕��ɂ�������B
�������T�g
�S�W50���́w�ЂƂтƂ��퉹�x�̒J��i��ɂ�����u���w�ʼn��_�Ȋ���ړ��̋ɒv�v�ɂ��o�ꂵ���BPart8�k959�l�Q�ƁB
����24�N - ���a52�N�B�o�ϕ]�_�ƁE�o�ώj�����ҁB
���X�R�ƕ��ԓ��{�̖��ԃG�R�m�~�X�g�̑������I���݂ł���B�R�������R���i���E����s�j�ɁA�D��H�̒��j�Ƃ��Đ��܂��B
�ƋƂ̐��ނ��獂�����w�Z���ƌ�ɑ��̑ܕ��≮�ɒ��t����֏o�邪�A1�N�Ŏ��߂Ē��N�֓n�q�B
���{�l����������̉c�Ƃ�̔��A�f�Վ����E�d�M�ǂ̐����Ȃǂɏ]�������B
�����T�g�́A���{���ߑ�o�ς̖{�i�I���B�̊�b��z�������̂́A����18�N���ł���w���{�ߑ�o�ς̈琬�x�ŏq�ׂĂ���B
�y�O�z�v���̌��ʂ������炷����
�E�m���F��������D����
�����А푈
�Ȃ��A�V�ۂ̐d�����^�߁i1842�N�j�̑O�ɁA�����̐d�����^�߁i1806�N�j�Ƃ����̂�����B
�Ȃ��A�呺�v���Y�������̗��ɂ��Ȃ��āu�l�ҎR�C�������������đ��ɒ����Ă����v�Ɩ����������́A�w�ĂԂ��@���x�ł͑D�z�q�ɂȂ��Ă��邪�k
>>219 �l�A�w�Ԑ_�x�ł͎R�c���`�������B
�i�n����́A���������w�Ԑ_�x��ǂق�������(��ͥ)
�y�l�z�O���Ɠ����̗Z���ƍ���
�����ؑ�g
�v���𐬌��������w���҂́A�t�����X�v���ɂ����Ă����V�A�v���ɂ����Ă���O�Ȃ��A�v���𑼍��ɗA�o��������B����͔e���̊g�����Ӗ����A�����ɂ�鑮�����������炷���Ƃ���O���Ȃ��B
�������A�����̏ꍇ�A���z��`�I�ȁu�v���̗A�o�v�ł͂Ȃ��k
>>271 �l�B�����̔��z�́A�������̌������f����b�ɂ����O��_�ł������B
�y�܁z���������œ���������
����������œ������Ƃ̗�Ƃ��āA�]���V���Ƒ�v�ۗ��ʂ����݂ɑ����������Ă������Ƃ��q�ׂ��Ă���B
�����͂��̍˗���@�N���A�ݏd�ȓ����̊O��ŕ�݂���ŘI���Ȃ����Ƃ�S�|���Ă����B�����͍˗������l�i�ł���Ƃ����l�������Ƃ����̂ł���B
�i�n�ɑ��Y�w�����Ɩ،��Ɖ��́x
���J���w�ҏW�҂Ƃ��Ă̏t�ƏH�Ɂx
�����J���q���a�T�N - ����26�N�r
���{�̕]�_�ƁA�ҏW�ҁA�o�Ŏ��ƉƁB�ێ�h�̕ҏW�҂Ƃ��đ����̏�����𑗂�o���A�����{�̘_�d�ɕێ��`�A������`�̒�����z�����B
�����G�i���J�ɐ��܂��B�����{����ܒ��w�Z�A�ꍂ���o�āA������w�@�w���𑲋ƁB���a30�N�A�������_�Ђɓ��ЁB
���{�e�r�O�q������r
�吳15�N - ����15�N�B���{�̕ҏW�ҁA�I�s��ƁB���������_�Џ햱������B
�S���ł̗��𒆐S�Ƃ�����i�𐔑������\�����B���͗��R�卲�ŁA��ɏO�c�@�c���ƂȂ����{�e���g�B���ɍ�Ƃ̋{�e���q������B
��ʌ���z�s��7�l�Z��̖��q�i�O�j�j�Ƃ��Đ��܂��B�����{�R�t�͊w�Z�������w�Z�A�������������w�Z���ƌ�̏��a20�N�A�����鍑��w���w���n���w�Ȃɓ��w�B���a26�N�A�������_�Ђɓ��ЁB
���j������
���J�菁��Y�q����19�N - ���a40�N�r
�����͒^����`�̈�h�Ƃ���A�ߏ�Ȃقǂ̏�������}�]�q�Y���Ȃǂ̃X�L�����_���X�ȕ����Ō���邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����A���̍앗���ށA���́E�\���͐��U�ɂ킽���ėl�X�ɕϑJ�����B
������ꂩ�瑭�������܂ł��g�����Ȃ��[��ȕ��͂ƁA��i���Ƃɂ����ƕς��I�݂Ȍ����������B�w�s�l�̈��x�w�t�Տ��x�w�א�x�ȂǁA��s�⎞�㕗���Ȃǂ̃e�[�}�������ʑ����ƁA���̂�`���ɂ�����|�p�����������x���ŗZ�a�����������w�̏G��ɂ���Đ��]�����A�u�����v�Ə̂��ꂽ�B
���J�菁��Y�S�W
������m�Y�q����31�N - ���a39�N�r
�����ɉE�X���A�R����`�ې��̏����⒘��𑽂����������߁A�����E�Ǖ��ƂȂ邪�A�Ȍ�͕��d���狗����u���A���ƉƂȂǂƂ̂����������������B��[�N���Ƃ͊֓���k�Ђ̗��N�i�吳12�N�j�ɏo����Ĉȗ�����̕ς��ʐe�F�ł������B
��[�N����ʂ��Ĉɓ�����������Œm�荇���������Y�Ƃ́A�n�����m���ɂ����āA�Ȃ̉F����������ĊW�������ƂȂ�A���̌����Ɛ��͗��������B
�v�w�̒��͂��łɂ������Ⴍ���Ă������A�F��ɍD�ӂ��銁��Ƃ�����炸�v���F��Ƃ̐e�����W�ɑ��Ă킾���܂�������Ă�������́A�F�l��ŊJ���ꂽ�p�[�e�B�ŋ��R�����킹������̑ԓx���C�ɓ��炸�A����̊�ɉ̂���������@������Ƃ����������N�����Ă��܂����̂ł���B
���F����q����30�N - ����8�N�r
�����ƁA���M�ƁB���˂Œm���A�ҏW�ҁA�����f�U�C�i�[�A���ƉƂ̊���������B��Ƃ̔���m�Y�A�����Y�A��Ƃ̓������A�k�����v�ȂǁA�����̒����l�Ƃ̗����E�������������A���̔g���ɕx���U�͂��܂��܂ȍ�i�̒��ŕ`����Ă���B
�R������όS�i���E�⍑�s�j�o�g�B���Ƃ͎Ƃ��c�ޗT���ȉƂ����A���e�͐��U���ƂɏA�������Ƃ͂Ȃ��A���ōD���������B��オ�c������ɕ�e���Ȃ��Ȃ�A���e�͐���12�������Ȃ��Ⴂ���ƍč��B���͎���Ǝv���Ĉ炿�A��ϕ���Ă����B���̌p�ꂪ�u���͂�v�̃��f���Ƃ����B
���m�̉����g�Ƃ�����( *�L䇁M)�����
�����R�`�G�q�����イ�r
����33�N - ���a44�N�B���{�̏����ƁB���a13�N�A�w������x�ő�7��H���܁B
�����������͌S�剮���i�����͎s�j���܂�B�������ϒ��w�i�������������ύ����w�Z�j�A����c��w���w���p���ȑ��ƁB
���́w�V�����`�x�w�M�v�̑�x�Ȃǂ̎��㏬���������A���a39�N�A���q���G��`�����w����x�Ŗ�ԕ��|�܂���܂����B
�݂�������Ă���ԑ܂ɐΌ������Đ����̎��ɒ݂邵�Ă����B
���Ƃ��A�������A�������悭�āA���ꂪ�������B
>>300 �݂͒邵�������������B
�����h�́A���ꂾ�B
���q���V���q����25�N - ���a43�N�r
�����ƁB�k�C�����c�S���c���i���E�Ύ�s�j�o�g�B
�c���̔~�J�\���Y�i�ʏ̐ē��S���Y�j�́A���{������20�U�̉Ƙ\���Ă�����Ɛl�ŏ��`���ɎQ�����A���ِ푈�ɔs��ĕߗ��ƂȂ������ߕ�����A�D�y�ֈڂ�J���ɏ]�����邪���������A�D�y����10���قǗ��ꂽ�Ύ�̋����E���c�ŋ�����������B
�V���L�҂����邩�����ŁA�����b�̕����������܂Ƃ߁A���a�R�N�w�V�I�g�n���L�x���o���B���̌�A�w�V�I�g�╷�x�w�V�I�g����x�́u�V�I�g�O����v���o�ł��A���̌�̍�Ƃ�i�i�n�ɑ��Y�E�r�g�����Y�Ȃǁj�Ɉ��p�����B
�����Ԃ��Ȃ������A����m�Y�A���R�`�G�A�q���V���́A�����A�j���������ʂ��Ă�����Ƃł���B
���q��S�W
�����a36�N�P��
��������李����k���������l
���̎����Ɋւ��đ�38��Q�c�@�œ��ǂ̌x���̎藎�����w�E���ċً}���₵���̂������g�V���c���ł��B�}�W�B
�����g�V���c���́A���������Ǝ��q�̊Ԃɐ��܂ꂽ���j�E�Б��Y�̎O�j�B�܂�A�����̑��B
�E���́u������杁v�̂Ȃ��̍c�������Y����`�������`�ʂɕ��S�������ǁA�u���|�v�i�T���N�j�Ƃ�����������߂������\�L������f����悤�ɁA�[���60�N���ۂɌ���ꂽ�����^���ň��ՂɌ��ꂽ�u�v���v���p���f�B�Ƃ��Ă����ˁB
�[�Y�́w��R�ߍl�x���ǂ������ȁB
�f��w��R�ߍl�x�̘b�����ǁA���Ƃ́A�u������q�̂����ς��͈ӊO�ƒ��肪�������v�ƃC���^�r���[�œ����Ă����B
�����������Y�q�吳�X�N - ����16�N�r
�������A�ڒ��̎i�n��i
����C�̕��i
�F��O�w�i�n����Ƌ��x
���F��O�q���a�U�N - �r
�����{���܂ꂾ���A�{�Ђ͎R�`���B���͒������{�j���U�������j�w�ҖF��K�l�Y�ŁA�������������œ��������t�͊w�Z��ފw�ɂȂ�������ɐ��܂�Ă���B
���a28�N�A������w���{�w�����{�w�ȃt�����X���ȑ������Ƃ��đ��ƁA�����đ�w�@��r���w��r������C�ے��������B���c�ޓ�ɔ�r���w���w�ԁB
�����a56�N
��T�ES�E�G���I�b�g�qThomas Stearns Eliot�F1888�N - 1965�N�r
�C�M���X�̎��l�A����Ƃŕ��|��]�Ƃł���B
���a56�N�ɂ͌̐l�Ȃ��A�ӂ��������Ă��邼�A���勳���B
���g�C���r�[�qArnold Joseph Toynbee�F1889�N - 1975�N�r
�C�M���X�̗��j�w�ҁB
�g�C���r�[�����a56�N�ɂ͌̐l�Ȃ��A�ǂ���������Ȃ�A���勳���H
���P�l�X�E�N���[�N�qKenneth McKenzie Clark�F1903�N - 1983�N�r
�p���̔��p�j�ƁB
�M�҂́A���̎���̊O���̊w�҂ɂ͍����B�\����Ȃ��B
�����ۊW�_
�������l�ފw
���]���~�q���a7�N - ����11�N�r
�����{�̒����ȕ��|�]�_�ƂŁA���яG�Y�̎���͕��|��]�̑��l�҂Ƃ��]���ꂽ�B
�u�S�g�̕s���R���i�݁A�a�ꂪ������B����Z���\���A�]�[�ǂ̔���ɑ������ȗ��̍]���~�́A�`�[�ɉ߂����A���珈�����Č`�[��f���鏊�ȂȂ�B��A���N��A�����ȂƂ�����B�����\��N������\��� �]���~�v�Ƃ����⏑���c���Ď��E�����B
�����c�ޓ�q����34�N - ����5�N�r
���{�̔�r���w�ҁE�p�ĕ��w�ҁB�F��O�̉��t�B
�A�����v�ƃA���A�Y�i�̗��̓^���́A������w�̒����ȋ����ł��铇�c�ޓ����߂ďڍׂɌ������A1960�N��ɒ����Ă���B���{�Ŕނ� �u��r���w�̕��v �ƌĂ�Ă���B
���c�ޓ�� �w���V�A�ɂ�����A�����v�x �Ƃ��������_�� (���m�O���t) �������グ���B���̘J������ƂɁA�i�n�ɑ��Y���A���ҏ��� �w��̏�̉_�x �̈�߂ł�����l�̎�҂����̈��̕����N�₩�ɕ`�ʂ��Ă���B
���ۊW�_���̕����l�ފw���̑������������ȂȂǂƂ����悤���K�̂悤�ȁg�����܊w��h�̘b�͋����Ȃ��B
�呠�Ȃ������ȂƂ����悤�Ȃ�����̂ɕς��邩��A������₂Ȃǂ������B
�y�}�\�z��v�o��l���̂����Ȍo���i�������N�`�Z�N�j
�܉ӏ��̌䐾���ɉ��M�����Ƃ������R�ŁA���{�j�ł͂��Ȃ�̏d�v�l���ł��镟���F��́A���̏����ł͊��Ă��܂���B
�������F��
�����ېV�ł́A�㓡��_��Ƌ��ɒ��m�Q�^�Ƃ��ĐV���{�ɏo�d�B�z�O�˂̗R�������ƂƂ��Ɍ܉ӏ��̌䐾�����N�������B
����4�N�A�������Â̌����܂���ďܓT�\400����������B�c���َ̍撲����p�W���o�Ĕ˂̏��Q���A����Q���B���{���ł͓y�����̈�l�Ƃ��āA�i�@���ɔC����ꂽ�B
�i�@��㎞��̖���5�N�A�i�@���̍]���V���Ƌ����ŁA�@���ŏ��������Ƃ��֎~���ׂ��Ƃ̌��������o����B�������A�~���͋����̊��K�ł��������߁A�����͂��������������ƂȂ��č̗p����邱�Ƃ͂Ȃ������B
���̌�A���V�@�c���A�������A�Q�c�A�����ږ⊯�A�{���ږ⊯�Ȃǂ̗v�E���C�����B����17�N�A�q�݂���������B
�吳8�N�i1919�N�j3��7���A�I���B���N85�B
���ԂƂ��������т��Ă����悤�ł����A��x�Ɨ��j�̕\����ɂ͌����Ȃ������悤�ł��ˁB
��N��12��19���Ɂw�ĂԂ��@���x���n�߂āA2,331���X����₵�āA�����35�����I��������������B
>>263 ���������A�����]�����R���L�����������푾�ƂȂ�A���̌�͍c�����s�߂�悤�ɂȂ�B
>>328 �܉ӏ��̌䐾����̏��́A���{�j�⌛�@�j�̏�ł͏d������邯�ǁA���ۂ̉e���͂���l����A�܂����̂悤�Ȃ��̂��ˁB
�c�z�{�V�X�e���̑n��ҁE���M�҈ꗗ�\
����
�����ЂƂ���������ė���
�݂�Ȃ��E����
���R�Ȃ�ĊȒP��
�����Ɏア�ЂƂ�������������
���B�͔Ƃ���
�V�l�Ǝq���͔R�₳�ꂽ
�����ЂƂ����͂��̓y�n��
�Ƃ����ĂĎq����
�����ĊX���ł�
�����ЂƂ����̎q���͑���������
���N�i���R �֓���k�� ���{�l10���l��s�E
�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO ��21�́@��x��
���|���X
���u�|���X�����Ƃ�����v
�i�n����͐�H�q���ǁr���u�Ƃ��Ȃ��v�Ɠǂނ��ƂɌŎ�����Ă���B
�u�ǁv��l���Ƃ��ėp����ꍇ�A�u�Ȃ��v�ƓǂޗႪ�F���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
����H�̊���
�ƂĂ��ȒP�ȉ҂����Ƃ��ł���z�[���y�[�W
>>1 �C�������ܘY�X���b�h��
�Ȃ��͉̂��́H
�������i�n�ɑ��Y�������̂�
�v���̕l�����~
�y�|���쎟�Y�z
�y�ɓ��ގO�z
������ߔN�Ƃ�ƌ��Ă��Ȃ��B
�����R�N11��
���������O�őO���ꐽ�E���X�ؒj�� vs �R�p�L���E�O�Y��O
�����O�͖{���挳���i���n�c�旼���P���ځj�̋��c�쉈���ɂ������B
�w�ĂԂ��@���x�͍]�ؓ������𐔍s�ōς܂��Ă���Ƃ��낪���������Ȃ��ȁB
�����ďȂ����̂���������B
���c�����Y���_���߂��V�J���_�{�i�ʏ́F���ɐ�����j�́A�F�{��̐����T�q�̒n�_�ɂ���i�F�{�s�����c���j�B
�������N�i1444�N�j�A�ɐ��_�{��M�S�ɐM���Ă������c�������Y���A�V�Ƒ�_�̑�����A���N�Ɉɐ��_�{�n�Ɋ������n�������B
����4�N�A��㍑�ɂ͌F�{���Ɣ��㌧���ݒu���ꂽ�B
�y�瓇�E�����������z
�����Ǘ��i���N51�j
���c�����Y�i���N41�j
�i�n����́A���c�����Y�́A�����X�N�̎��_��43�Ə����Ă�����ȁB
�����Ōv�Z����K������������Ȃ��낤�ȁB
���c�����Y�́A�����̍��͑��Ƃ̗{�q�ŁA���S���q�Ə̂��Ă����B
�����nj�
�y�H���̗��z
�v�c���i���������j1850�|1876
�O���́A���N����قǎv�킵���Ȃ��B�挎�ܓ��ɖڕ����͂����Ă݂��Ƃ���A�ȑO����є��S��������Ă���̂ł���B
�y��y�����Y�̖I�N�z
���͌��V��
�Óc�\�Y
��c�����̎ʐ^�͂Ȃ��B
���̏����̎ʐ^�͂������B
��͍b�{�̐��ɂ���B
�i�n����́A�����Ǘ��@�P���ǂ̃��[�_�[���g���`�߂Ƃ��Ă��邪�A
�J�͍~��~��@�l�n�͔G���@�z���ɉz����ʓc����
�����Ǘ��@�P�������c�c�g���`�ߔ�
�_���A�����c�c�C����Z����P��
�_���A��O���c�c������13�A���P��
���쌧�̗R���́A�F�{�s���𗬂�锒�삾�ȁB
�F�{����t�]���̉p�Y
�_���A�̗��̓����ɌF�{�ɂ������ʌ����Y�B
�������������łق�킩�����C���ɂȂ��̂́A�z���W�����X�B
���F�{����i�ߒ���
�y�L�O�L�Áz
�y�H���ˁz
���t���i�����܂��j
�������c��S���t���B�L�Â̐�����10�q�Ɉʒu����B���̐���ɓc��s������B
�Ȃ��A�L�Â͕��������s�S�݂₱���L�ÁB
>>385 �����q�˂Ƃ����A�퓬�I�����˂��낤�B
����ȘA����M���������H���ˎm�������B
������\�l�A���i���q�j�A����
�����a���i1846�|1877�j
��x�k�������c�s�V�i�i�i�n����͂������c�s�V��Ƃ����j
���c�s�V�i�����x�k���ɉ��������̂͌c�����N�i1865�N�j�B
�������i�݂j
������\�l�A���i���q�j�A��������̔T�؊�T�����ցA����̋ʖؐ��b���K�˂āA�O���ꐽ�ւ̉��S�����߂Ă���B
�T�؎��g���O���ꐽ�̗��ւ̉��S���^��ꂽ�̂ŁA����炴��Ȃ����n�ɗ������ꂽ�̂��������ȁB
�������i���s�j
�R�������s�ɂ��鉩�@�@�̎��@�B�ї��Ƃ̕�B
�g�c���A�a���n�߂��̔��s�厚�֓����Ō��ɂ���A���\4�N�i1691�N�j���B��3��ˎ�ї��g�A�����������B
�F�{�̐_���A�ɂÂ��ďH�����I�N�����Ƃ̕����ƁA�O���ꐽ�͂Q�U���A�R�c�n���Y�A�����ꐴ�i���҂Ƃ��O���̒�j�A��������A���R�r�F�Ȃǎ�ȓ��u�𓌌����ɏW�߁A�u���̂�҉�͂��̎��ɂ���v�ƍ������K�N�̎�ӏ���������B
�T�؊�T�Ƌʖؐ��b���ʗ��̉��̂���Ŏ������݂��킵�����C�O�́A���݂ł������̊��B���ق�����B
��T�Ɛ��b���オ�����̂́A�V�s�ł����≮�̑Δ��O���Ǝv���B
�Δ��O�͂̂��ɒ��C�O�Ɩ��O��ς����B
�����g
�V��7�N�i1836�N�j�]�˖{���������ɖ��b�����D�̎��j�Ƃ��Đ��܂��B���Ƃ͍���ꑰ�̊����L�̎q���B
�Éi���N�i1848�N�j�֓����Y�̗����قɓ��傷��B�����̏m���͌Z��q�ƂȂ�j���ܘY�ł������B
���̂Ƃ��̌j���ܘY�Ƃ̃R�l�N�V�����ŁA�R�����߂ɔC�����ꂽ���̂Ǝv����B
�z�K�D�a���
�����M��
�F���Y
�O���ꐽ���ߔ����ꂽ�ꏊ
�����X�N12��3���ɎR���ٔ����E���Վ��ٔ����i�ٔ������E�⑺�ʏr�j�ɂĕٖ��̋@���^�����ʂ܂܊W�҂̔����������n���ꂽ�B
�l��˗�
�����R�N�S��16���ɐ����ɈڏZ���߂�����A�攭��l�����k�����̓c����(�ނs����)�ɓ��������̂͂T���Q���������Ƃ����B
������
�����q���R
�V�����������S���꒬�������p�_�ɂ��鑐�q���R�͖����ɓ����ČÉ͍z�Ƃ̑n���ҌÉ͎s���q�ɂ���Čo�c���ꂽ�B
���������ɂȂ�ƎY�o�ʂ͌������A�吳3�N�x�R�ɂȂ�Ƒ����̍z�v���������R�ւƈڂ��Ă������B
�Ő�����6,000�l�̐l�X����炵���Ƃ����B�������쑽���̐�����30�q�̒n�_�B
�،ˍF��́A���q���R�̌o�c��C���邱�Ƃ��a�ɂ��āA�i���v�����ɗU�����B
���V�x��
�����s������B�����w����݂�ƁA����ɋ�����������V�x���ƂȂ�B
�L�y�����ł͋���꒚�ڂ̎��̉w�B
�����{�����Ԓ�
���������̓����ɂ����鉮�~���������n���Ƃ��Ċт��o�ꂵ���B
����͉i���v�̏�������T�O�Y����t�����P���̂��߂̈ړ���i�Ƃ��đD�h�ɏM���`���[�^�[�����n���Ƃ��ēo�ꂷ��B
���o�ˁi�̂ԂƁj
�i���炪��t�����P���̂��߂̏㗤�\��n�Ƃ��Ă������B
��t�s������o�ˁB���݂͉��C�̖����ɂ��C�݂����P�q���ꂽ���ɂȂ��Ă���B
JR��������t�w�̂������B
�y�v�ċ������z
�ŏ��̔�Q�҂́A�x���⎛�{�`�v�i30�� / �O�d���m���j�B
�a�����͈̂���T���Y�i�i�n�͈���T�O�Y�Ƃ��Ă���j�B
�y�ɐ��\���z
�� �勴�ꑠ���ԁi�������� / 1848�|1889�j
����9�N�O���ꐽ�炪�����������̗��Ɍĉ����Ĕ��������킾�Ă������s���Ď���B
���͂̂̂�����15�N�V������F���Ɏ��w���P�Z��ݗ��B
�k�z�B���Ђ��������A�k�C���J�Ƃɂ��������B����22�N2��13�������B
�� �쑺�E��i���������j
�O��3�N�i1846�N�j�ܓc�����v�̑��q�Ƃ��ĎF�����������S�������ߍݐ��c���i�̂��̎������s��Ւ��j�ɐ��܂��B
��C�푈�̂Ƃ��́A�鉺�l�ԏ����i�����͐쑺���`�A�ČR�͉i�R���Y�j�̕������Ƃ��Ē��H�E�����̐킢�ɎQ�킵���B
�����œ��R���R����_�A�r��A�����V�h���o�Ĕ��͂ɐi������ƁA����ɑ����l�ԏ����̏������Ƃ��ėL���̌���ł��������͍U�h��Ő킢�A���͏�ח���͒I�q�ɓ]�킵���B
��Îᏼ��ɐi������ۂ́A�쑺�w���̉��ŏ\�Z���̐킢�ɗE��A��ɉ�Îᏼ���͐�ɎQ�킵�R�����������B
����4�N�A�˂���e����h�������ہA���������ɏ]���ď㋞���߉q���R��тɔC����ꂽ���A���̍q�C�����������҂Ɏa������A�@�ɓ��������B���̂��߁u�n�i�v�Ƃ����������������Ƃ����B
��Ɉɗ\��F���ɔ����Ƃ��Ĕh������邪�A����5�N�ɂ��̐E�������A�������A�������B
https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-c2-df/qqs499aqk/folder/228323/11/15321811/img_3_m?1515840196 ���{�e���r�N�����㌀�X�y�V�����w�c����x�i1987�N�j�ł́A���{���O���������B
�����ЂƂ�̎������̌x�@�����͒������V�ŁA������͉��[�����������B��\�Ȃ́u�G���X�̊C�v�B
�i�n���u�ɂ��v�ƃ��r��U���Ă����̂ŁA�����Ƃ���Ŋo���Ă����B
�� �����R����
�������������s���l�����B
���r�͕M�҂ƕҏW�̂ǂ��������ꂽ���킩���
���{����
����]�V�q��
��������h�i������j�ꓙ�x���c�c���{�x�@�ے�
�����X�N8��21�� - �{�茧�����������ɍ�������A�{�茧���͎x���֊i�������ꂽ�B
�،ˍF��
����9�N3���ɎQ�c�͎��߂����A���t�ږ�Ƃ����E�ő������ɗ��܂��Ă��邪�ȁB
�їF�K
����i����j
��������їF�K�́A��R�Ɋۂ߂��܂�Ă��܂��܂����B
���c�V���ƍ����V�g�̌��́A�̂��ɕ�����������邪�A���Ԏ��͕��u���ꂽ�܂܂��ȁB
���Ԏ��͖���10�N�̐���푈�ɍۂ��u�`�E����W������v���J���Ă��邩��A
�����G���i�����悵�j
�u�j�q�̊�F�́A�r�X�y�X�Ƃ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�i��v�ۗ��ʁj
�{����
�˖엘�H�̏o�g�n�g�쑺
�����O�̎������s�n�}
�������Y�́A����6�N�̐��ςʼn��삵���x�����g�̂ЂƂ�ŁA����̖��ɏ]�R���Ă����ȁB
�c������
�]�_�V���Ђɐ��肱�x�����̖���ƂȂ��Ă���B
�c�����Ƃɂ��ẮA���̂悤�ȏ������s�̂���Ă���B
"�������m�����������Đ���푈�ɗՂ킯�ł͂Ȃ��B
�e���A�e�Z�킪�G�����ɕ�����鎖�Ԃ�����邽�߂ɁA�����̌��N��j�~���悤�Ɠ������̂��A��������̋��m�E�c�����Ƃł������B
�c���́A��O�A��y�^�@���ւ��������A���͖����_�҂Ƃ��Č���c���߂��������̌ւ�ׂ��r�p�ł���B"
�� �����؏��
����푈�ł͐��������ɂ��������A�߂炦���Ē���1�N�B
�̂������̐^������`����Ă��邱�Ƃ�J���u���쌌�j�v�������B
����15�N�����_���Y��Ƒ嗤�o�c������N�ɂ킽�邪���@���킵�A�̂��������x�@���ɂƂ߂��B
�� ������
����17�N�ɍ������ƍ������ē������Ƃ����������������Ȃ����܂���ɕς���Ă���B
���Î������o�����Â����Ƃ̖���̖��̂́A�����̃o�J�̂������ŏ����Ă��܂����B
�F���̏������́A�H�Q������o�Ă���B
�Ȃ��A�����葺�ƌĂ�Ă����̂͏��a16�N�܂łŁA����ȍ~�͍��蒬�B
�� �Y��
�͐�t�߂̒����͍����k�E������ƂȂ��Ă���̂ɁA�n�}�Ō���Ɛ삻�̂��̂͗Y��ƂȂ��Ă���B
�Ȃ��A�i�n����͏������i�[��j�Ə�����Ă���B�{�����J�b�R���������ԈႢ�B
�[��͋э]���ɉ͌�������B
�㗬�ɂ���Y��̑�
�� ���R�M��
�� �����c�i��
>>438 ���������Y��́A�u����L���̑傫�Ȑ�v����Ȃ�����
�G�W�v�g�l��Ogawa River�ƌ�������A�u����v�̃W���[�N���Ǝv���郌�x���B
�Y��̑�́A��N��NHK��̓h���}�u�����ǂ�v�̃I�[�v�j���O�Ŏg�p����A��C�ɐl�C�ɉ��t�����������̊ό��X�|�b�g���ȁB
�� �l�C
�� �J���o��
�������Y�͍��Ðr�����h���s�V���̂͂܂���������ȁB
>>444 �J���o���́A����Ƃ͂܂��������̎������q�ׂĂ���ȁB
�������Y�͐������ÎE����ƌ������Ǝ��ʂ܂Ō����Ă����������B
���̍ٔ��ɂ����āA�J���́u�������Y�͎h���Ⴆ�Ăł��������~�߂�i��������j�ƌ������v�ƌ��������B
�J���o���͕n�R�l�ŁA�w����Ȃ��A������������Ă��Ȃ��B
�� ���鎵�V��
>>448 ���Ă����悤�ɒJ���o���̐l�i��f��I�ɋK�肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���w�Z���͑����������̐����������ĒJ���̌��t���A�������������̎撲�ׂł��邩�玄�w�Z�����̊���ŒJ���̌��t���B
����ߔM���Ă���ƁA�������t�������̈Ӗ��ɉ��߂���邱�Ƃ͂���B
���͉łƌƂ̌��܂���ɂ킽����60�N�Ԍ������Ă�������A���̂��Ƃ��悭�킩��B
���ǂ́u���H�F�G�v�̎莆�͉�Âɂ��H�삾�����I�I
�� �����c���R�Ζ��(�����ނ�)
����10�N�P���A�������{�͕���e���A���D�ւƐςݍ������Ǝ��݂����A���w�Z���k�����{����B
�P��29���̖�ɉΖ�ɂ̂P�����P���̏�j�Ēe��U���������D�B�c�����Ζ�ɂ������ɏP�������B
�h�q���(�^�U�͂��Ă����h�q�ƌ���������͑������ɗ\���\)�Ƃ����A�e��P�����Ƃ����A
�� ���z���P(����݂Ȃ�)
�����c�Ζ�ɂ��P���������w�Z�}�̃��[�_�[�B
���e���u�c����v�ł͗���X�V�B
https:// �|�\�l�̎q���܂Ƃ�.net/wp-content/uploads/2019/01/WS002463-300x283.jpg
����X�V�̉摜���Ȃ���
�����c�Ζ�ɏP���V�[���ɐΈ�x�q���o�Ă����ˁB
�Έ�x�q����̖��͑��c�O��̍ȁE���a�q�B
�Έ�x�q�͎��㌀�ɂ͌������Ȃ����e���������ȁB
���B�ɂ��p�o�u�d��������K�����W���[�v���
>>444 �u�����͎h���Ⴆ�Ăł��c�c�v�́A�������Ő�������Ƃ����Ӗ��̖����̏퓅�傾��B
���̌�����
>>450 �������悤�ɁA���w�Z������ё��������ŗ������قȂ����̂��낤�ȁB
�ĂԂ��@���Ƃ܂������W�Ȃ����A�Ђ����Ԃ�ɕ����p�q�������̂œ\���Ă����B
�����A�ی����̐搶�ɂ��������DNo.�P�ƌĂꂽ�B����Ȃ̂Ȃ����ǁB
>>459 �����ÎE�͎��w�Z�����s�������\���������B
�P��29���ɑ����c�Ζ�Ɏ������N���Ă���B
�����A���ȉ�������Ƃɉ���āA���̑�ɋꗶ����B
�������q�͐����ÎE�c�ł���Ƃ���ΐ�̑�`�������ł���B
�J���o�����������Y���烁���o�[�̎����E�~�h����o���̂́A���̌�̂��Ƃ��B
�� ����o���q
�V��13�N�i1842�j�y���˂̏����牮���ܘY�̎O�j�Ƃ��Ęa�H�i�킶���j�ɐ��܂��B
�͂��ߐ牮�ДV���̖��œo�ꂷ�邪�A�����琛�쐩�ɂȂ�̂��͕s���B
���C�M�̏Љ�ŊC�R�Ȃɓ��Ȃ��C�R�����ƂȂ�B
����푈�u�����O�ɊC�R���D�������Ƃ��Ď��������ɕ��C���A���̔��[�ƂȂ����w�e�D�����x�ɌW��������ߊC�R�̒��ł̗���͕s���ɏI���B
���̎����ł͎��w�Z�k��̏P���E���D��h�����ߒe��𐅂ɐZ���Ȃǂ̏��u�������Ԃ̎��E�ɖz�������B
�܂��Ȃ����D������A���E�𗣂ꓯ�n������A�̂�����17�N�i1884�N�j�Ɏ��E�B
�x�����A���g���ÎE�c�ł������̂��ۂ��ɋ����͂䂫�����ł����A
�����ȉ��̎��w�Z�}���ɒǂ����̂́A���{�̒����ɏ���ĉΖ�ɂ��P�����������ł��B
�����ÎE�]�X�͎��w�Z�}���������邽�߂̑�`�����ɂ����܂���B
�܂�A������̈����͟��z���P(
>>454 )�B
�Ƃ͂������̂́u�c����v�ōō��ɖ����ȃV�[���́A�Ζ�ɏP���V�[���Ȃ�ȁB
�ꍑ�ł̓�x�ڂ̎��ɂ��I�����A�[�l�X�g�E�T�g�E�́A���l�ւ͗�����炸�A
�� ���{
����̖k���ɂ��鎭���s�̎��B
�����͍��{����C�H�Ŏ������Ɍ������\��ł������A�����ɂ��C�オ�r��Ă����B
�킪�n�܂�O���ă��N���N����ˁB
�� ��F�S�R
��y�^�@�{�莛�h�̑m�B�O����~�����ւ��ꂽ�̂Ŏ������ɕz���ɗ��Ă����B
�������Y�炪�ߕ߂��ꂽ�ہA�������̖���Ɗ��Ⴂ����A�Ƃ��Ɏ��w�Z�}�ɑߕ߂��ꂽ�B
��F�S�R�͒��B�̋Ή��m�����̒�q�B
�����ߕ߂͐����̎������A���Ɠ����̂Q���R���B
>>450 �J���o���͖����̎u�m�������o�Ă��Ȃ�����A�u�h���Ⴆ�Ăł��~�߂�v���������Ő�������
�Ƃ��������ɗ��s�����퓅���m��Ȃ������Ǝv���B���F�F���̈��B�������鉺�ɏZ���̂Ȃ��c�ɎҁB
�J���������̓}�W�Ő������h������Ɗ��Ⴂ�����낤�ȁB
�� �쑺�j
�� �⌳��i�͂��߁j
����쑺�j���������鉺�ɐ������悤�Ƃ����}�z�ۂɏ�荇�킹�A�쑺���珕�������߂�ꂽ�Ƃ�����ʂœo�ꂷ��B
�쑺�j�̎�蒲�ג����ɏo�Ă���̂��������B
http://www5d.biglobe.ne.jp/ ~iamarock/iwamoto/familyhistory/album/motoi2.jpg
����o���w���z�ƁE�⌳�\�x���͏��[p34�̎ʐ^
2��17�������ɖ쑺�j�̌���������R�j�ǂɂ�萼�������ɂ����炳���B
�� �������ِl��
���{���̗m���a�эH��ł��鎭�����a�я��̋Z�p�w���ɂ��������C�M���X�l�Z�t�̏h�ɂŁA�c��3�i1867�j�N�Ɍ��Ă�ꂽ�B
���݂̓E�B���A���E�E�B���X�̌��ɂɂȂ��Ă���B
�E�B���X�͎F�p�푈�i���v�R�N�j���R�̓A�[�K�X���̍b���璭�߂��B
2��3��
�����@�F�����肩�畐�̎���ɋA��B�������Y�ߕ߁B
�T�g�E�F�����ό�
2��5��
�����͂��܂��̓��L������Ȃ����B
2��6���i�J�j
�����@�F���w�Z��u���ɂ����ĊJ��̕]��i�j���s���B
�T�g�E�F�c���ό�
�J�킪���肳�ꂽ�Ƃ���ɁA�����E�˖�E���͋ɕ`����܂��B
2��7��
�� �쑺���`
�V��7�N�i1836�N�j�쑺�^�\�Y�̒��j�Ƃ��Đ��܂��B�Ɗi�͌䏬���g�ōʼn����̔ˎm�ł������B
�Ȃ̏t�q�͒Ō������̖��ł���A�Ō������̖��͐��������̕ꎅ�q�ł������B�쑺�͐����������̂悤�ɉ�����ꂽ�Ƃ����B
�쑺�͊C�R�̎����I�w���҂Ƃ��ď��������d��A�C�R�n�n����S�����B
����푈��A�Q�c�E�C�R���ɏA�C���A�C�R�������p���������A�R�p�L���ƈقȂ萭���̐��E�Ƃ͈�����悵���B
���������̂��Ƃł͐��v�Ȓn�ʂ��߂����A���t���x�ւ̈ڍs�Ɠ����ɂ��̍���ǂ�ꂽ�B
�� ����O
�V��9�N�i1839�N�j�������鉺�ɔˎm���R�x���q��̒��q�Ƃ��Đ��܂��B������A���R�x�V�i�B
���ق̖��t���e�ł���B
��q��Ƒ�v�ۗ��ʂ��͌������Ă����ۂɌ�Ղ�]����������A���R���I�����O�̖ʑO�ő吺�Ŏ��ӂ�����A���ȂɂĖ����V�c�̌�O�Ő����Ύ����r�[���r�ʼn��ł���ȂǁA��s�����������B
���]�̍Ȃ̕��q�V�c�r���̖��́A�͂��ߒ���̍Ȃł������B
>>462 �������ٕ̈ς������m�����̂�2��3�������A�����m�点���̂�����o���q�Ƃ����͈̂ӊO�������B
2��9��
���낻��ӌ��\�Y�����E�U���Ȃ��Ă����B
>>341 ���N��NHK��͂��g�V���V�������ȁB
�ǁ��i�K�ƓǂޗႪ���ɂȂ�����ȁB
���\�҂ł��A���������オ�����C�z���炢�y���̂Ȃ�D���ɂȂ�邪�A
�q���E���ē��\���ɂ��Ă��܂�������͍D���ɂȂ��́H
�� ���R���j
����̖��̖{�����ł��s�������Ă����̂́A�n���[�E�p�[�N�X���ȁB
�p�[�N�X�����Ȃ𑗂�������ł���_�[�r�[�O���́A��15��_�[�r�[���݃G�h���[�h�E�X�^�����[�ł���B
�n���������@�n���������@
�p�[�N�X�Ɣ�r����Ə��C�M�̓ڒ����Ԃ�ɂ͕��ꂩ����B
����Ȃ��Ɓw�X�쐴�b�x�ɂ͏����ĂȂ���B
�܂��o�J�͕����Ă����������ǁA����푈�Ɋւ��鏟�̒k�b�́w�X�쐴�b�x�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��B
�T�g�E���L�̐���푈�֘A�́A���������̖�ŒP�s�{������Ă���ȁB
�� �a�J�F��
�C�V���s�̑ߕ߂́A��H���Ȃ̒��łP�s�G���ꂽ�������ȁB
>>500 ���R�O�~�Ɗ��R���j������l���Ȃ̂��ۂ����l���n�߂�ƁA�������Ȃ��Ȃ�ȁB
�،˂���͊��R�O�~�Ɗ��R���j������l���Ȃ̂��ۂ����l�������ăm�C���[�[�ɂȂ����̂��������B
�� �R�p�L��
�i�n�͂ǂ̍�i�����̂������őދ��@
�� ���c���D�i49�j
�� ���c�����i51�j
������������Z�ہi��v�ہj�ۈ�
�Ȃ��A��Z�ۂ̉ے��͏a�J�F���i
>>510 �j�B
���w�Z�}�K�N�̌R�����̒́A���Ëv���̓����ɂ����̂��낤�ȁB
�R��������ꂽ�ɂ�������炸�A��������R�ɑ��ė�W�ȑԓx�������̂́A
�y�����Ґ��z
�� ���i���V��
����10�N1��29���A�������s�����c�̉Ζ�ɂ���A���{���e����^�яo���܂��B
����A���z���P�Ɓi
>>454 �j�ŏ��i���V��Ɩx�V���Y���A�Ζ�ɂ���̕�����o���v�悵�A���s�B
���ꂪ����푈�Ɍq����܂��B
�� �x�V���Y
�� 2��14���i�����2���j
�ɕ~���ʍ]������c�c�{����
����45�����̕��ɂƗ�����
�� ���ӌQ��
�� �m��i��
�� 2��14��
�� 2��15��
�� 2��17��
�� ���̎���
���~�͖���2�N�F���˂̏d�b��K���������������̂ŁA�~�n��3600�u�A�����̌�a�Â���ŕ������������A��ɂ͑傫�ȏ��̖��������Ƃ����B
����푈�ŏĎ��������A����13�N�ɐ����]�����Č������B���܉��~�Ղ͌����ɂȂ��Ă���A�����̈�˂��c���Ă���B
�� �������q
�� �������q
���������̍ȁB
����2�N�i1865�N�j�A���������ƌ�������B������3��ځA���q�͍č��B
�����Ƃ̊ԂɓБ��Y�E�ߎ��Y�E�юO�̎q�ǂ����Y�ށB
�܂��A�����̉����哇�ɂ����铇�Ȃł��鈤���߂Ƃ̎q�ł���e���Y�E�e���������{�炵���B
�� �����Б��Y
����17�N�ɋg��F���⏟�C�M���̓����|��������t���A�����V�c�̎v��������|�c�_�����R�m���w�Z���w�𖽂����A13�N���̊ԃh�C�c�Ŋw�сA���̊ԃv���C�Z�����R���тƂȂ�B
����35�N�������̈ېV�̌��ɂ���݂�������ؑ��ɗ��A�M���@�c���ɏA�C����B
�� �s���l�Y
�� ������
2010�N�A�������njS�̊������E���ǒ��ƍ������Ĉ��ǎs�ƂȂ����B
�����Ƃ����n���́A�D�̑ǂ�u���Ă�������A��������肪�o�Ė��������Ƃ����u�Ƃ̖ؓ`���v�ɗR������B
��������u�Ɩv�u�Ə�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�A�₪�āu�����v�ɂȂ����B
�������㍠���炱�̒n����x�z���Ă����̂́A�呠���̈ꑰ�Ƃ��������؎��ł������B
�����ɖ{����u���������A�����ɖ{����u�����R���ȂǂƂƂ��ɁA�݂��ɓ���������Η������肵�Ȃ���A���Î��Ƃ̐��͑������J��L���Ă����B
�� ����h
2005�N�A�����s����ш��njS��5���ƍ������Ė����s�ƂȂ�B
�����̍����͂ނ�����B
�� ���y��
�{�茧�̒��암�ɑ��݂��Ă����{��S�̒��B2006�N�A�{��s�ɕғ�������ł����B
�]�ˎ���͓��Î��̍��y���ˎO���̏鉺���ł������B
�� ���ڊX��
�� �I�쑺
���������k�����A���njS�ɑ����Ă����B
����17�N�g�����ƍ������ėN�����������B�����I�쒬�p�~�B
�� ���v���z��
�F�{���Ƌ{�茧�̌����ɉ��v�����Ƃ����}�s�ȓ���������B�l�g���炦�т̍����ɔ������K��X���B
�� �g�c����
�{�茧���т̎s�厚�������ɂ���u�g�c���� ���̓��v��K�₵�܂����B
���̓��Ƃ������O�̒ʂ�A����������������̉���ɐZ�����ď���������Ƃ��������`�����c���Ă��܂��B
���������ƃA�[�l�X�g�E�T�g�E���H�����F�{�ւ̌o�H
�� 2��20��
�����͐ϐ�̉��v���z�����R���Ăɏ���Ĕ��։z�����B
�˖엘�H���u�F�{��́A���̐|�i���炳�ڂ��j�ň�@���ł��킷�v�ƌ������̂́A���̎��B
�� �l�g��
�ˎ�Ƃ̑��ǎ��͊��q���㏉���̌��v4�N�i1193�N�j�A���̒n�̒n���ɔC����ꂽ�B
���̌�퍑�喼�ɐ������A�]�ˎ���ɓ����Ă��̎�Ƃ��đ����������ېV���}�����ɂ߂ċH�Ȕ˂̈�ł���B
����4�N�ɔp�˒u���ɂ��l�g���ƂȂ����̂��A���㌧�A���쌧���o�ČF�{���ɕғ����ꂽ�B
�� �i����
�F�{���l�g�s�y�蒬�ɂ��鑂���@�̎��@�B���ɓ`���H��̊|��������A�H�쎛�ٖ̈��Œm����B
�n���͉��i15�N�i1408�N�j�Ƃ�17�N�i1410�N�j�Ƃ������B��a�i�A�a���������J�R�Ƃ��A���꒴�^�a�����J�R�B
���ǎ���9�㑊�ǑO���i�������j�̊J��ɂȂ�A���ǎ���X�̐��h�����B
�l�g�ɂ����鐼���̏h�ɁB
���̐�N�̕ʕ{�W����́A����A�F�y���o�āA�F�{�邩��V�q��O�̐�K�ŏh�c���Ă���B
�� �r�Ӌg�\�Y
�V�ۂX(1838) �N���܂�B�����푈�̏��q�̖�(1866)�ɐ������A���s�l���p�l�A�F�{�ˏ��Q�����C�A�A�����ċ��}�̐��N�����炵�w�Z�}�̐��͂�{�������B
����9�N�̐_���A�̗��ł͊w�Z�}�̌y����}�������A��10�N�F�������R���I�N���ČF�{�Ɏ����A�w�Z�}����͂ɓ��u700���]�̌F�{���𗦂��Đ����R�ɉ������B
���c�A���R�ɕ��킵�����틵�����炸�A�e�n����A10�����{�R�ɕߔ�����A����26������Ŏa�Y�ɏ����ꂽ�B
��������̐��_�ƒr�ӎO�R�͂��̎q���ł���B
���r�ӎO�R
��㒩���V���A���������V���̎�M���C�B�����V�������̑b��z�����ЂƂ�B
��t���l����Ėڟ�����Ђ����A���ҏ�����V���A�ڂɐs�͂����B
�r�Ӌg�\�Y���ʕ{�W��ƑΖʂ����̂́A����w�c���B
�� ���X�F�[
�Éi7�N�i1854�N�j�A���݂̌F�{�s���؈䒬�ɔ��F�{�ˎm���X�����̓�j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B
�퍑�������X�����̎q���Ƃ����B
����12�N1���ɏo������ƁA�F�{�s���c�����o���ɓ��S�w�ɂ�ݗ������B
��ɓ��S�w�Z�Ɖ��߁A����15�N2�����Z�X�s�Ɖ��̂���B���݂̌F�{�����ρX�s�����w�Z�ł���B
���l�R���ē��N�����͈�ʂɌF�{�Z�X�s�o�g�Ƃ���Ă��邪�A�݊w�����̂͋͂��R�����ł���B
�� �����쉺��
�l�g���甪��B
�����̂��̋��́A�����̂��Ă̕��F������ᔻ�̍L��Ɉ�������o���A�����̂����ނ��Ƃ���A�O�l�̊Ď��̂Ȃ��Ŏ�˂邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��������A�e�Ղɑz��������B
�ǂ����悤���Ȃ��n�ܘY���ȁB
�����̍����I�l�C�Ɣ�r����ƁA�J����̒m���x�̒Ⴓ�͋C�̓łɂȂ��Ă���B
�� �J����
�V��8�N�i1837�N�j�A��w�ҒJ�i��i�ݎ��j�̎l�j�Ƃ��ēy���������S�E��i���݂̍��m�������S�l���\���j�ɐ��܂ꂽ�B
�������͒J�畔�̖��Œm����B��C�푈���n�܂�Ɣ_�Ƌ��ɔ˕��𗦂��ďo�������B
�F�{����i�ߒ����ł���������푈�ɂ����āA�F�{��U�h����w���������ƂŒm����B
����44�N�ɖv����B
�J����̊K���́A�˖�E���Ɠ��������R�����B
�� ���R���I����
����5�N���쐴�ɏo���A��p�o���ɏ]�R�B
����푈�ł͌F�{����i�ߒ����E�J���鏭���̉��A������Q�d���Ƃ��ČF�{������炷��B
���̌�x�����Č����R�����ɏ��i���邪�A�C�R�֓]���A����16�N�ɊC�R���A��19�N�ɂ͊C�R�����ƂȂ�B
�� �^�q�m�������i
>>381 �j
������13�A���A�����B�_���A�̗�������C�B
�F���ˏo�g�B
����9�N10��24���̐_���A�̗��ł́A����𒆊_�i����8�l�̏P�����邪�A�ȥ�ߎq�̋@�]�Ŕn�����Ă��̏��E�o�����B
���̌�͑啺�c�̕�����13�A���𗦂��Ē������͂������B
�������A����10�N�̐���푈�u�i�R�i���ɂ�܁j�̐킢�v�Ŕ�e�����B�������A�ߎq�͏��q���F�{��ŏo�Y�������A�^�q�͗������������B
�� ��㑀�Z����
�F���ˎm���`���q��e���̎O�j�Ƃ��Đ��܂�A���H�E�����̐킢�E��C�푈�ɎF����10�ԑ������Ƃ��ď]�R����B
����10�N�Ɏn�܂�������푈�ł͕�����13�A�����S���Ƃ��ď]�R�����𗧂Ă�B
����28�N3���ɂ͐������{�Q�d���ɔC�������B�����푈�ł́A����܂Ő�オ�����i�߂��R�̋ߑ㉻������t�����B
���̌��ɂ��8���ɌM�ꓙ��������́E�������M�͂�����A�q�݂���������B
�� �唗���q�i�Ȃ��͂�j���
�F���ˎm�E�唗�V���̒��j�Ƃ��Đ��܂��B���m�ِ��k�Ƃ��Ċw�сA�F����5�ԑg�Ƃ��ĎF�p�푈�ɏ]�R����B
����10�N����푈�ɏo�����A�F�{��U���ɎQ���B2��27���A����w�Z�����̎w�������A��ʂ�����B
����37�N2���Ɏn�܂������I�푈�ł́A�틵���F�����Ȃ������v�ǍU���ׁ̈A8���ɑ�7�t�c�̓��������܂����B�T�؊�T�叫�̎w�������3�R�ɑg������A��Z�O���n�̍U���ɓ��������B���̌����V���ɎQ�킵����39�N3���ɋA������B
�� �x���h���i�悵�����j
��O����i�����j�ˎm�_�㎟���q�����̎��j�Ƃ��Đ��܂��B
����9�N11���ɌF�{�����߂ƂȂ�B���ߍݔC���ɐ���푈�ɑ������A�F�{��Ŏi�ߒ����J���鏭���A�Q�d�����R���I�����E���������ʌ����Y��������54���Ԃ��ď���ς��������B
�F�{����i�ߒ����J���鏭���́A1��28���ɏ��q��14�A���̘A�����T�؊�T�ɁA�������Ɉڂ��悤�������B
�J���鏭���́A2��14���i�ʕ{�W��̐�N���������o���������j�ɁA���q�ƕ����i���q�A���̕��ԏ��j�̕��͂����ׂČF�{�ď�ɂ܂킷�ׂ����u�����B
�F�{����3,000 vs �F�R12,000
�� ������
>>567 �T������ֈ������h�������̂�2��6���B
�T�̗ꉺ�̏��q14�A���́A���q�ɓ����A�����Ɉ��������Ԃ��Ă����B
�T�͕����������������������������֔h�������B
�J�́A���̎����́A�F�R������̊͑D��D�悵�ē��シ��ƍl���Ă����ȁB
�� 2��13��
�� 2��14��
�� 2��15��
�ď�̂��߂̍H���ƕĂ̔�������n�߂�B
�� 2��17��
�� 2��18��
���{�̐����߂��o��2��19���A�����͉��v���z���i
>>542 �j��O�̋g�c�������h�ɓ��h���Ă����i
>>543 �j�B
�F�{��̌��\�̌��S���́A���̓Ɠ��̐Ί_�̗͊w�\���̗�������Ă悭������邪�A�n�k�ɂ͐Ƃ������B
�� �F�{�鉊��
2��19���ߑO�A�˔@�A�F�{��̓V��t����̎肪�\�B
����́A��������������F�R���F�{�ɔ��钆�A�F�{���䂪�ď�̏�����i�߂Ă������̂��Ƃł������B
���̉ЂŁA�V��t�Ɩ{�ی�a�͏Ď�����B
�� ���ΐ�
�� ���ΐ�
�� ����
�L�^�Ɏc���Ă���Д�����̒e����o�w���������̂����ʌ����Y�����Ƃ����̂��ǂ����������B
�������Ȃ��肻�������A���ʂ����邩�H
���ΐ��͂Ȃ��ȁB
500�̕Ă��ׂĂ��Ď�������ɁA�ꗼ����600���W�߂��Ƃ����̂��������B
�� ��͕⋭
�� �{�c - �F�y�E
�� �F�R
2��19���F�ʕ{�W��̓Ɨ�����A�v��S����h�ɏh�c�i
>>550 �E
>>553 �j�B
2��20���F�ʕ{�W��̓Ɨ�����A�F�{����̋��O���S��K���Ō㔭�R�̗�����҂B
����K
�F�{�s���S���̓����8km�Ɉʒu�����K�n��B��������C�O�Ƃ̌��Ս`�Ƃ��ĊJ���A�]�ˎ���ɂ͗ΐ여��̕����̏W�U�n�Ƃ��ĉh�����B
�� ���{�R
2��19���F������
���ߎ҂͑�����b�O�������B
�������́A�L����{���m�e���B��C�푈�̓����呍�ł���B�c���a�{�̍���҂ł��������B
���悢��킪�n�܂�ȁB
�� �З͒�@
�����500�l�̖�P�����B
�w�����͑唗���q�i�Ȃ��͂�j��сi
>>565 �j�B
�������u����сB
������������с@�����{�s�ЌR��
>>594 �\�Y���A���@9����ǂ߁B
>>596 �u����т͊ԈႢ�B�������͌G��������сB
����17�N����L������̕�����12�A���̘A�����ɕ₳��Ă���B
>>596 ������т́A����������т̂��ƁB
����24�N�ɌF�{��6�t�c�̕�����24�A���i�����A���j�̘A�����ɕ₳��Ă���B
>>598 ������12�A���̕Ґ��n�͊ۋT�B
�� ��K����
�� 2��21��
�F�{����͖h��ǂ��납�A�ʉ߂ɂ������Ă͕��Ƃ�e����o���Ă��ĂȂ��Ă����͂��ł���Ƃ��������
�� �厜��
�F�{�s���ɂ��鑂���@�̎��@�BJR�������{����K�w����k��25���B
��K�ɂ�����ʕ{�W��̏h�ɂł���B
>>603 �c�ɂłS�N�ԕS�������Ă����A���Ƒ��n���̋ߑ㍑�Ƃ̎��������Ȃ��Ă����A���Ƃ̔F���̍����ȁB
�����͔���Ő�K�̐틵���B
�� 2��22��
�� �F�{��̐킢
�i�R���Y�̎O�ԑ���́A���̎��_�ł͌F�{��U���ɎQ�����Ă��Ȃ��B
�˖�͐����ƂƂ��ɐ�K�ɂ����̂ŁA�l�ԑ���𗦂��Ă����̂́A�x�V���Y���Ǝv����B
�� �\����
�� �ЎR���~�̐킢
�������̗������ԑ���̍U����������ɂ߂��B
�ЎR���~��������Ă���������13�A���̘A�����^�q�m�������́i
>>563 �j�A���̐킢�̍Œ��ɐ펀�����B
�ЎR���~�̐킢�ł͂Ȃ��A�u�i�R�i���ɂ�܁j�̐킢�v�ƌĂ����悢�悤���B
���݂̓��蔪���{�̈ʒu����ɍl����ƒn����������Ă��܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł���B
����푈�����̓���_�Ђ́A�i�R�̓���ɂ��铡���ɂ��������A���̂��߂ɂ��ׂĊD���ɋA���A�Вn�͌F�{����p�n�ƂȂ������߁A
���݂̈�쟺���Ɉړ]�B����11�N�ɉ��a�c�A�����œ�17�N�ɂ悤�₭�{�a�̑��c���݂��B
�w�ҋC���ŋC���������̂��A�l�g�E��www
>>610 �_���A�m���ł͊����̂悤�ȒE�o���Ŋ����^�q�A�����B
�������Ȃ����ȁB
�i�R�̐킢�ɂ�������̎w���́A�ʖږ��@������̂�����ȁB
�����Q���A�l�g�E��www
�� �w�Z�}�|�F�{��
�r�Ӌg�\�Y�i
>>551 �j������w�Z�}700���]���A2��22���̌F�{��̐킢�ɎQ�킵�Ă���B
�r�ӂ͎F�R��͂���K�ɒB�����Ƃ��A���鉺�̍]�Êw�Z�ɓ��u���W�߂Ă���B
�]�Êw�Z�ɂ��ẮA�M�҂ɂ��悭�킩��܂���B
�܂�����Ă�̂��i �L,_�T�M�j�߯
�� �L�n����
�� ���c�I�i������j
�Éi7�N�i1854�j��㍑�����S�t�����i���݂̌F�{���F�{�s����j�ŌF�{�ˎm�̉Ƃɐ��܂��B
����7�N�ɑ�p�o���ɏ]�R�����B�A����͖����}���������A�]�_�V���L�ҁE�ߎ��]�_�L�҂Ƃ��Ď��R�������咣�����B
����10�N�ɐ���푈���u������ƁA�{�蔪�Y��ƂƂ��ɋ�������g�D���Đ����R�ɉ�������B
�����R�̔s�k�ƂƂ��ɕ߂���ꂽ���A�₪�ďo���������ꂽ�B
����35�N�A��7��O�c�@�c�����I���ɏo�n�����I�B���I�͍��v��4��𐔂����B
��̓h���}�u�ĂԂ��@���v�̍��c�I�@
�� �ۓc�E�_��
����푈�F�{�������i���̒n�B
���O���炢�͐������Ă�ł��������ȁB
>>619 �ŁA���c�I�͂��Â����H
>>167 �k�����q�̘V��
�ȑO�͙{���ʂɂ���Ă����̂ɁA�ŋߎG�ł��ˁB
�a����I�y�̉�
�� 2��21��
�{�蔪�Y�A��K�̎F�R��N�̕ʕ{�W��Ɖ�k�B
�ۓc�E�_�Ёi
>>620 �j�ɌF�{���������W���B��40���B
�� ��������
�� ����҈�i�̂Ԃ����j
����3�N�A�˖��ɂ��L�n�������ƂƂ��ɕ����̓ԉc�i���R���m�{�����j�ɓ���A����5�N���R���тƂȂ�B
����6�N�A�w���ؘ_�x�̔j��ɂ���ɉ���A�F�{���O�c�S�S�ё��ɋA�_�����B
����7�N�A����̗��̌�A�L�n�����A�{�蔪�Y���Ƒ�p�o���Ɏu�肵�]�R���邪�A�������ċA���B
����8�N4���A�L�c���A�{�蔪�Y�A�L�n�����A���R��P�A�葺��Y��ƐA�ؒ��ɁA�ϑ��F�{��ܔԒ��w�Z�i�ʏ́F�A�؊w�Z�j��ݗ����Z�����ɊĂ߂�B
�w����_�x�𒆐S�Ƃ����l�X�Ȏ��Ƃ��s���A���R�����������e�n�ŏW����J�����H���邪�A�}�i������ƌ�����̕⏕����ł���ꓯ�N10�����ŕZ����B
����9�N���A�����}���u�̒��ŎF���̋˖엘�H��������Ƃ��˂Ėʎ��̂������L�n������ʂ��ď��Őf�B
����10�N�A���������Ő��������̎��w�Z����������ƁA�A�؊w�Z�o�g�҂𒆐S�Ƃ��������}�̓��u�ƌF�{���������������A
2��21���ɖk�サ�Ă����F�R�ɐ�K�ō����A�l�ԑ��������̋˖엘�H�̂��Ƃŋ��������w�������ɐ��{�R��ɐ�����B
�� ��Ԉ��e
�� �ԉ��R
�i�R���Y�̎O�ԑ���́A�ԉ��R��苒�����B
�O�͂̍Ō�̂Ƃ���ŏq�ׂ�ꂽ�F�{��U���̏ڍׂ��A���肩�����q�ׂ��Ă���B
�^�q�A�����펀�̏�ʂł́A���{�s�ЌR���i
>>596 �j�̊��ڊo�܂����B
2��22���ߌ�A�������͂��߂ČF�{���鉺�ɓ���B
�� ����ɉ˂��錻��̑�p��
�� �������x��������p�{
�{�����ɂ�������p�{�́A��������̖{�c�������23�A���̕��ɗp�n���ւČ��݂͉Ԕ������ƂȂ��Ă���B
���݂̑�p�{�́A�F�{�s�k�旴�c�ɂ���B
�� �t�|��
�{�����ɓ�ڂ���t�|���́A���݂̒n���ł����ƌF�{�s������Օ��ɑ�����B
�� ����猁i�����ށj
�M���������قǂ̂��Ƃ����A�F�R�͕⋋�̎蓖�Ăǂ��납�A���̓��̗[�H���ǂ����邩�������߂Ă��Ȃ������B
�u��������A�ӌ�т܂��H�v
�F�{��U���ɎQ�킵���l�ԑ���i�˖���j��800�l�ŁA�����ȏ��22���̗[���ɐ�K�ɓ������Ă���B
>>608 ���˖�͐����ƂƂ��ɐ�K�ɂ����̂ŁA�l�ԑ���𗦂��Ă����̂́A�x�V���Y���Ǝv����B
�ԈႢ�ł��B
�x�������l�ԑ���̏���������
�}�W�ŃC���T�{�[�i�|�j��{�ŌF�{��𗎂Ƃ���Ǝv���Ă����ȁB
���C�p�[�V��_���ɉ�������������点��NHK�́A�F�R�ȏ�ɐ������Ȃ߂Ƃ�B
�ŁA�F�{�邪�育�킢�̂ŁA�F�R�͕��j�ύX���܂�(*^-^*)�U���
�s���P���s�_�t�������A�ʕ{�W��A�ӌ��\�Y��
�������A�R�p�L���̕�����6,400���̐攭��c�́A2��20���ɐ_�ˍ`���A22���ɂ͔����`�ɓ������쉺�̑Ԑ����Ƃ�������B
�R�p�L���������������������z�����Ȃ��ǁ��������������������˖엘�H
���ʘ_�Ƃ��Ă͋��P���s�������������̂����A�C���Ȃ��ōU��s����Ƃ����Ƃ��낪��n���B
�F�{������ď��Ȃ̂�����A�F�{����X���[���Ėk�シ��悩�����̂ɂˁB
>>647 �������������������z�����Ȃ��ǁ���������������������������
�����I��ÁE�O�D�̒�c�ƌF�{����ɋ�������邾�낤�B
�������Ȃ�k�シ��ƌ��������āA�F�{���䂪��O�ɏo�ĎF�R��ǔ�����Ԑ����Ƃ����Ƃ��ɁA鰉��ɌF�{����}�P������B
�� ��]����i��
�� �F�{������
22���A�T�؊�T�����̗����鏬�q������14�A�����A�R���X����쉺�����B
�u��14�A���́A�S�����s���ē��邷�ׂ��v
>>571 �T�͕����������������������������֔h�������B
>>590 2��19���[���A���q��14�A����1����̂����̍������300�l�]�����邵�Ă���B
>>573 �T�͏��q�̑�������������������������v���Ăɋ}�s������B���������16���ɋv���ē����B
�܂��F�{��ɓ��邵�Ă��Ȃ��������A���q�E�����E����E�v���Ăɕ������Ă����B
�T�؎��g���A�v���Ăɂ����B
�� ���
�T�͉͌��їY�����тƂƂ���21���ߌ�S���ɋv���Ă��A21����ɌF�{����ւŋg�������̑�O����ɒǂ������B
���c�O���14�A���쉺�̏����Ƃ����̂́i
>>653 �j�A���̋g�������̑�O����̂��Ƃł���B
�T����ւɓ��������Ƃ��́A�F�R�͂��܂���K�ɂ���B
�ʖ��S��֒��i�܂��j�B�������Ƃ̌����ɂ��钬�B
�헪�I�ɂ����ΔT�؊�T�̑�14�A���͖ʔ��݂̂��鉿�l���������B
�� ����
�����́A�e�r�������͂��ӂ������k�����ォ��e�r��̐��^�𗘗p�����`���E���l�̒��Ƃ��ē�������B
�]�ˎ���ɂ́A�˂̌܃J��(�F�{�A����A��K�A�����A����)�ɐ�����ꂽ�B
�̂��炠��|���A���X���A���������ȂǁA���X���������Ԓʂ�ɗ��j�̏d�݂��c���Ă���B
���݂͋ʖ��s�����B
�� �g�����V������
�u���܂�A���͂Ȃ�H�����镐�m�̍Ȃ��B��������A�v�̒p�ɂȂ邩���H�v
�����͋g���ɑ��A�u���߂Ď��Q�������̂ŁA�Z����݂��Ăق����v�ƈ˗����܂��B
�g���͂��������A���̉�Õ��m����S���������Ɠ`����Ă��܂��B
���̏�������Ô˂̏d���E�_�ۏC���̍ȁE��q���������Ƃ����������̂́A�g���̎���̂��Ƃł����B
���J���ꂽ�_�ې�q
����4�N�A�F���y�O�˂̌����ɂ���Č�e�����n�����ꂽ�Ƃ��A���R��сA�������ƂȂ�B
��ցA�����A�ؗt�Ɛi���A2��22���̐A�̐킢�ŁA�㊯�ł���������㗝�T�؊�T�������R����r�������B
�T�͑�O����̓��������A�s�R�̔�J���c���Ă��Ȃ�60�]����I�сA���������B
>>663 ���Ȃ�O�̂Ƃ����ǂ�ł��܂��B
�l�^�o���͂��Ȃ��ł��������B
>>655 ��ւɂ͖k�����H�̐��܂ꂽ�Ɓi��e�̎��Ƃ̐Έ�Ɓj������B
���H��������̂́A�������R��S���[���i���E����s�j�B
���Ȃ���
�w�k�l�̐l�x���Ėʔ����ł����H
�y�A�̐킢�z2��22����B
��������F�{����͂��Ă����F�R�́A��@����u�A�ɐ��{�R!�v�̕���A�ߌォ��
�T�ԑ�ूQ�ԏ���(��������c�O��)�A
�S�ԑ�ूX�ԏ���(������ɓ�����)�A
�S�ԑ�ूT�ԏ���(������i�R�x��)�̂R�����������킹�Ă���B
�F�R�R�����́A�A�̎s�X�ɐi�o����ƎR���E�ؗt�̂Q�������琭�{�ɋ������ɑ������ꂪ����̂ŁA�F�{���̌���ɕz�w�����B
�� �A�ؒ�
���Ă͎��{�S�A�ؒ��B2010�N�i����22�N�j�F�{�s�ɕғ�����S��F�{�s�k��ƂȂ��Ă���B
�����ɐ���푈�̍ő�̌���n�E�c���₪����B�܂��A���{��̃X�C�J�̎Y�n�Ƃ��Ēm����B
�� ����
�F�{�s�k��A�ؒ����c����B
�u����v�o�X�◯��
>>668 ����̐e�����n�����ɕИr��˂����ނƂ���͖ʔ����ł��B
>>671 �����́A�X�ǂ��Ȃ��ƃo�X��Ƃ��Ė����c�邭�炢���ȁB
�R���r�j�̓X����A�p�[�g�E�}���V�������Ƃ��Ďc��ꍇ�����邪�A�c�ɂ��Ƃ�����Ȃ��B
�����S���̃o�X��B
�}���V�����Ɋ��҂���ȁB
�����͓��{���B�t�����X�ł͂Ȃ��B
�g�C���ƌ��킸�A�̂ƌ����Ă��炢�����B
����d��̓ޗǎ����`���������ŁA��̏�ɏ����������āA�����ł������Ă���`�ʂ��������B
�������̓����p�Ƃ����̂́A�F�����l�̃E�B�[�N�E�|�C���g�ł���u���������̂��H�v��A�Ă��邾���ȂȁB
���Ȃ݂Ɂu�A�̐킢�v�́A����o���̂Ȃ��T����̏��w�ł��B
���w�Z�̍���̋��ȏ����A�����E�R�l�̘b�Ŗ��ߐs�����������҂��������ł��B
�ΐ�����̂͂悭�Ȃ����ǂȁB
�� ���c�O��
�O��2�N�i1845�j���܂�B����6�N���R�����������A����푈�ł͏������Ƃ��Đ����R�ɂ�����B
�F�{���k���̐A�Ő��{�R����Ԃ�A�T�؊�T�Ђ������\�l�A���̌R���������B
��c�Ŗ���10�N3��11���펀�B33�B
�������Ɂu���������̂��H�v�Ɍ�����قǂ̓��]�h�B
���c�O��̃C���[�W�͗�Ò����ȓ��]�h����ȁB
���e���u�c����v�ł͑��c�O��̍ȁE���a�q���͐Έ�x�q���������A�C���[�W�ɍ���Ȃ��B
���͂����Ɵ��z���P�i����݂Ȃ݁j���̗���X�V�̍Ȃ��o���Ǝv���Ă����B
�Ȃ����c�O�������l�ԑ���̑�����r��l�Y�̐��́u�����̂����v�ƓǂށB
>>677 �g�C���itoilet�j�̂��Ƃ�́i�����j�ƌ����܂����A���̌Ăі��ɂ́A�萅�i���傤���j�A�萅��i���傤���j�A�֏��i�ׂ�j�A��B�i��������j�Ȃǂ�����A��̗���ɗ��Ƃ��쉮�i�����j����J�����̖����o���Ƃ̐����L���m���Ă��܂��B
���̑��ɂ��A�̂���A�͂���A���s��i���ӂ��傤�j�A�����i����ۂ��j�A���i�i�Ƃ����j�A��ˁi�������j�A����R�i�����₳��j�A�Տ��i����j�A���ҏ��i�悻���̂ǂ���j�ȂǁA�����̃g�C���̌Ăі�������܂��B
�֏����������炫�����t�ŁA�֗��ȏ��Ƃ����Ӗ��ł��B
�Ñ�l�̕֏��͐����������Ƃ̏؍��ƂȂ�̂��A�u���t�W�v���\�Z�ɏo�Ă���B�@
���h�i�����ʁj���@���ɂȂ�肻�삭�܂́@�����ӂȋ�i�́j�߂�@�ɂ����i�߁j�����
���̐l�͐l����H���Ă���t�i��H�ׂĂ��鉘�Ȃ炵�������Ƃ�������̏����̂̂������̂ł��B
����́A��̏�ɕ֏�������Ă����؋��ƌ����܂��B
���E�̕֏��́A�������A�̂Ă邩�A���߂�̎O�ʂ�ł����A��ɗ����͓̂���n�����A�֊��u���͖̂k���n�����ƌ����Ă��܂��B
�����������ĕւ߂Ă����̂́A�_�Ɨp�̔엿�Ɏg���Ƃ��납�炫�����{�Ǝ��̒m�b�B
���t�W�T�C�R�[�B���[���A�������������R��`���w���ȁB
>>684 ������������ł����B�����Ɓu�������݁v���Ǝv���Ă��܂����B
>>687 �킽�����͏��a40�N��܂ł̓��{������Ȃ���������{�l�ł����A
�q���̍��V��ł��Ĕ역�߂ɛƂ������J�̎v���o������܂��B
�역�߂̂��Ƃ��l����ƁA���̎���ɖ߂肽���Ƃ͎v���܂���B
>>669 �����؏���́u�F�쌌�j�v�ɂ��ƁA�i�R�x��̏������A�ɒ������̂́A�킢���I��������2��23���ł���B
�����؎��g���i�R�����̉��܁i�̂��̌ޒ����j�������̂ŊԈႢ�͂Ȃ��B
�o���Ă��܂����B�F�{���k���̎s�����B
>>659 ������͋g���G�}�i�ق��j�����B
�������A���̂悤�ɂȂ��Ă���B
���̈����l���āA����Ȃ��Ƃ��m��Ȃ��o�J���Ⴀ��܂����A�s�[�����E�U����ˁB
�܂��܂��A�݂Ȃ��ǂ����܂��傤��B
�T�؊�T������60�]���̕��ƂƂ��ɐA�ɓ��������̂́A�F�{��U�����I�����2��22���̗[���B
�� �ؗt
�ʖ��S�ʓ����ؗt(���ؗt��)�B
�T��8�q����̖ؗt�ɐ�������݂��Ă������A�A�̕��̗[�H�͏������Ă��Ȃ������B
���s�R�̏�ɔє����B�킦�܂���ȁB
���c�O��̏����́A�ߌ�7���A�T�ؘA���g������ɍU�����J�n����B
���R�͂܂��ꕺ�������Ă��Ȃ��̂ɁA�T�́u�]�͐��̎��v���ׂ��炴���m��v�ދp�����ӂ���B
�ދp��͌���̐�{���B���݂̒n���́A�F�{�s�k��A�ؒ������B
��14�A���̘A�������F�R�ɒD��ꂽ���Ɋւ��ẮA�����҂ł��鍂�c�I�i������j�A�͌��їY�����тɌR���̈����𖽂����T�؏����A�͌��я��т��E�����F�R�̊�ؐ���Y���܂̎O�҂̏،����H������Ă���B
�� �͌��їY������
�͌��я��т̏o�g�˂ł���L�O���q�ˁi���}�����E�\�ܖ��j�͌c����N�i1866�j�Z���A����B�����̍r�g�Ɉ��݂��܂�܂��B
���̌�̍u�a�̌��ʏ��q��𒆐S�Ƃ����~�S�B�˂ɒD���A�����ɂȂ��Ă��p�˒u���܂ō��̒����n�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
���}���Ƃ͔˒���L�Ái���݂̍s���s�j�Ɉڂ��L�Ô˂Ə̂��܂����A�ˑc���^���ȗ��̏��q�̒n���������ˎm�B�͍����˂̋�J�����Ƃ����قǖ��키�̂ł��B
�͌��я��т͉Éi���N�i1848�j�̐��܂�ł�����A����B�����̎��_�Ő�����19�A�����炭�͎Ⴂ�ˎm�Ƃ��ċ�J�𖡂�����ł��傤�B
>>701 �͌��я��тɘA������w�������܂܂ŁA�������킸��10���̕��ŁA400�E�̎F�R����ɓa�R�����Ƃ����T�̖��߂ɂ́A���炩�ɖ�����������ȁB
����Ȃ��ƒ������̒���ɂ����ł��Ȃ��B
�i�n���A�T�Ɖ͌��я��т̍Ō�̕ʂ�́A���c�I�������Ƃ����{�c�̖��Ƃł͂Ȃ����ƌ����Ă���ȁB
�A�̐킢�́A2���ԗ]��ŏI������B
�h���}��f��ł́A�A�̐킢�͒��ԂɎB�e����Ă��邪�A���v��̐킢�ł���B
�� ���q��
�F�{�s�k�掭�q�ؒ��B
�F�R�̑��c�����E�ɓ������̑ދp�ꏊ�B�A����3�q��B
���X�V���[�F�{���q�ؓX�̃o�C�g�E�A���o�C�g��W���ɓ\��ꂽ�A���o�C�g���̂��˂�����
�T�؏����͌ߌ�9��40���ɐA�����{���ɑދp�B
�ȉ��͕M�҂̐����ł��邪�A���c�I�͔T���{�c�Ƃ��Ă������Ƃ́u�T�S�̐Ղ͌��ꂵ�������v�Ə،����Ă���B
�� �����ˁi�Ȃ��Â��j
�F�{�s�k��A�ؒ������ˁB
�͌��їY�����т̐펀�n�B
�T�͐�{���ŋg��������Ɨ��������A�c������z���Ėؗt�܂őދp�����B
���q�ؑ��܂őދp�������c�����E�ɓ������ɁA�F�{����O�����̉��R����������B
>>701 �͌��я��т̈�̂̔w���Ɋ����ꂽ�R����������Ă����Ƃ����Ƃ��낪�A��ؐ���Y�̋U���ȁB
���c�O��펀��A��⋂̐ӔC�Ҍj�v�����A��14�A���̘A�����͑��c���̕��E�̂��邵�Ƃ��Ĉ⑰�ɑ������B
�����ő��c�̍ȁE���a�q�i
>>456 �E
>>457 �E
>>458 �j���o�ꂷ��B
���A�A�����̍s����{�����Ă����x�@�ɁA���a�q�͘A������n���Ă��܂����B
�{�������ɓ������������Ă������a�q�́A�S�������ΚM���ł��Ȃ��ƍl�������߂ł���B
�@�@�@ _ �@��
>>712 ��͂̑����́A�A�ؕ��ʂƁA����ɖk���̎R�����ʂ��ȁB
>>691 �͌��я��т̈�̂̔����҂͉����؏�����g�B
���̉����͎s���J�č��Ɏ��Ă���邪�A���R�ɂ���ؐ���Y�Ɠ��S����B
�����͊�̘b���āA�͂��߂Ď����̔���������̂��͌��я��т̈�̂ł��邱�Ƃ�m�����B
����Șb�ł��Ȃ��B
�y�ؗt�̐킢�z�i2��23���j
22���锼�A�F�R�{�c�ō���c���J���ꂽ�i
>>643 �j�B�F�{��U�������̂܂܌p�����邩�ǂ�����b�������A
�����͎��̋��s��p�������肵�����A�x��Ă����쑺�E���������A���������q��r��l�Y����������A��c�͕������Ă��܂��B
�˖�͐����Ɍ������߁A�����͋��s���~�����f�B�F�{����͂������A�c��͖k�サ�ď��q�����P���邱�Ƃ����肷��i
>>643 �̐ܒ��Ă�����j�B
23����6���������q�����ďo�������B����1800���͓��ɕ�����ĐA�ؕ��ʂɐi�o���邪�A����T�̕�����14�A���͖������͂͊��S�ɏW�����Ă��炸�A�茳�ɂ�700���قǂ����Ȃ������B
�ؗt�œW�J���������14�A����8��30�������D���ȎF�R�ƌ����J�n���ߌ�1�����܂ł͌݊p�ɐ���Ă������A�F�R�E����1������������ɉ�荞��ő�14�A���̉E���������������ŘA���͗ƂȂ�B
����ł��[���܂Ŏ�������������14�A���͖�A�ɏ悶�Ă̓P�ނ��J�n���邪�A�ؗt�R��傫���I�Ă����F�R�����ʂ��P�������Ƃŕ����͑�����ƂȂ�A��14�A���͖ؗt����z���Ď��c�R�ւƑދp����B
���̐킢�ŔT�͑�O������ł������g���G�}�����ȂǑ����̕����������Ă���B
�i�n����́A�����̐ܒ��Ă��ؗ�ɃX���[���āA�쑺�E��̏��q�苒�_����������22����̌R�c�Ō��܂������e���Ƃ����悤�ɏ�����Ă���B
���Ƃ��Ɛ����̐ܒ��ĂȂ���͎̂j���ɂȂ��̂ł͂Ȃ����H
�� �����R�`�ؗt�R
�ؗt�R�̓�ɐ��c�n�т��J���Ă���B
�� �ÐX�G�����
�� ���͉h�A���
�� ���{�i�ȂȂ��Ɓj
�F�{�s�k��A�ؒ������{
���Z�ˌ�ƚ������˂��Ö{��т�20�]���́A���{�Ƃ����W���ŁA�F�R�̏������l�Y�����E�Ό��s�Y�E�q�召���E�������ꏬ���Ƒ�������B
�Ö{�͖ؗt�܂ň����Ԃ����B�ؗt�̐퓬�́A���̂悤�ɂ��Ďn�܂����B
�����{���R��n�[�ؗt�̐킢�Ő펀�������R���m�݂̂���������Ă���킯�ł͂Ȃ��B
>>725 ���̂����ɐA�ɒ������O�����̂����̐Ό��s�Y�E�q�召���́A�ؗt�̐킢�ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��悤�ł���B
��ؗt�ɎU�����Ă����g���G�}�������ˌ��𖽂����Ƃ��ɍőO���ɂ����F�R�́A�������ɂ܂Ō�ނ����B
>>725 �ŏ������l�Y�����E�������ꏬ���Ə����Ă���̂́A�i�n�����̂悤�ɏ����Ă��邩��Ȃ̂����A
���X���̘A�ڂł́A���̓��͉ؗ�ɃX���[����āA���c���ꏬ�����E���쐳������E���������������ɑւ����Ă���B
���Ɍ�ނ����Ƃ��ɁA�������l�Y�����E�������ꏬ�����A����삯�Ēǂ��������Ƃɕς����Ă���B
�������B
�� ����
�F�{���ʖ��S�ʓ����厚��ؗt������
>>726 �Q�����Ƃ��A���فB
������x�A
>>719 �̔z�u�}�ɂ��������Đ������Ă݂�B
�A����R���ɂނ�����3�������A�_�{�i�����q�召���E��蔼���q�召���E�Ό��s�Y�E�q�召���B
�A����ؗt�ɂނ�����3�������A���c���ꏬ���E���쐳����E�������������B
�����̐A�؉I����Ƃ����̂��A�������l�Y�����E�������ꏬ����2���B
����1,600�B
�Â��āA�R��3�����̖ؗt�ւ̐i�s�o�H�ł��邪�A�����Ȃ����̂ŁA�܂������ȍ~�ɁB
>>728 ���͓c������������Ƃ���ɂ���B
�� ���䗅�R
�� �啽
�R���O�������ؗt���̔w�ʂɏo�������̂́A�ߌ�1���ł������B
�� �g���G�}�����̐펀
�A����������őO���ɓ`�߂ɑ���ȂǁA���͂�R�l�Ƃ͂����Ȃ��ȁB
�T����̉��Ő키�Ƃ������Ƃ́A���ʂƂ������Ƃ��B
���B�����Ȃ���A�T�̗��g�o���ȂǗL�肦�Ȃ������B
�����̍Ñ��Ɋ���I�ɔ������āA�őO���Ɏ��畋���B
�u�T��wwwwww �K������ wwwwww
�� �Ί�
�F�{���ʖ��s�Ί�
�T�͖ؗt����Ίтւ̑ދp�����ӂ����B
���a�Ȃ̂ō�����f�ʂ肵�ĐΊт܂őދp�B
�� �
�F�{���ʖ��S�ʓ����
�ؗt�̑O������1�q����B��14�A�����n�d�����Ԃ��Ă����ꏊ�B
�T�͂킸��40���l���n�d�ǁi�R�l�ł͂Ȃ��l�v�j�ɑ�{�������т����āA�S�R�̓a�R�Ƃ����B
�� �����x�ꂽ�T�ؘA������݂��Đ펀�����l�X
�A�����݂�����l�v40�l�ɓa�R�𖽂��邽�߂ɑO������1�q����ɗ����o�J�B
�����ȘA�����̉��A�ؗt�Ő������14�A���̋]����
�y�F�{�������z
�����͕���҈�i�̂Ԃ����j
29�ŋ{�蔪�Y���2�ΔN���ł��邵�A100�Ύ��̏�m�̉Ƃł��邩��A���m�o�g�̔��Y�������ɂȂ�킯���Ȃ��B
�ڂ�����
>>629 �ɏ������B
���ɏ����o���肳���Ă������Y�������ɂȂ��킯���Ȃ��B
�����Ƃ̏��Ȃ������̂́A���ゾ���ł͂Ȃ�������ł��ˁi�L��ͥ`�jͰ
�� ���Q
�w�c�ɐ���ł���Ⴂ�w�l�Ƃ����̂́A�{�蔪�Y���F�{�ɏo�Ă���Ə�h�Ƃ��Ă����������Ƃ����h���̖����Q�����������ł��B
�u�����L�����ɂ�����ցA���̉Ԃ��炩���������v�Ƃ����������ꂽ�L���b�`�E�t���[�Y�͊��ق��Ăق����ł��B
�����̉��������]�R�Ԉ��w�ł��B�R�̓������C�����邾���ł��B
�u�c����v�ł͌ː싞�q�B
http://nagomi-web.com/fuhou/fuhou_select/image_fuhou/78togawa_1.bmp �{�蔪�Y�̃`���|����قǗǂ������낤�ȁB
�����Ƃ͑��ɖJ�߂�Ƃ��낪�Ȃ�����ǁA�`���R�����͂������炵���ˁB
>>755 �u�c����v�̃i���[�V�������m���u�����L�����ɂ�����ցA���̉Ԃ��炩���������v�݂����Ȋ����������B
�Z�b�N�X�̍ۂ̑̉t�̏L�����A�Ԃ̍��Œ��a���悤�Ƃ���낤�ȁB
�� �]��A�T
�����҂�����ɂ�������炸�A��p�]�R�Ԉ��w�i�L��ͥ`�jͰ
���c�I�i������j�́A�}�W�ł��Q���a�낤�Ǝv���Ă����炵���ȁB
�� ��q���F�V��
�� �����F�l�Y
�� �X�F��
���Y�͈�C�ɏ����グ��������ӏ��𒆍������i
>>628 �j�ɓǂݕ��������B
�y�F�{�U���z
2��22���F12��̎l�ҎR�C�͍U���ɖ���
2��23���F�i�R���Y���苒�����ԉ��R�i
>>631 �j����C���������˒�����������Ȃ������B
���̌�A20�|���h�P�C4�������������^�ш��ȋ��ɐ����ĖC�������B
�� �]�ǐ���
�� �⌳�����Y�P��
�O��4�N�i1847�j���܂�B���Ƌ߉q�C����тŐ���푈�̂Ƃ��F���R�̖C�������Ƃ߂�B
���������ɂ��������A��R�Ŗ���10�N9��24���펀�B31�B
http://www5d.biglobe.ne.jp/ ~iamarock/iwamoto/familyhistory/album/hei1.jpg
�y�A�ւ̑ދp�z
��C�푈�ł͐i�������X�Ŗ������������B
���Ղ�̋S���A�q����ǂ������܂킵�Ă���悤�Ȃ��̂���B
�키�C���Ȃ��̂�����A�헪�������Ȃ���B
����Ȃ��Ƃ����Ă�����A���Ɂu��������邩�H�v���ɂ܂��B
�y�攭���c�z
�� ����s
�������}���S�ɂ��������B���݂̒}����s�̒��S���ɂ�����B�u�����̉����~�v�Ə̂�������s������B
���a30�N�F��}���E�}�����E�R�����E�R�Ƒ��ƍ������Ē}���쒬�������B
���a47�N�F�s���{�s�ɂ��}����s�ƂȂ�B
�� �Ίё��쏰
�T�̑�14�A���͍������o��6�q�k�̐Ίё��̎��쏰�ɒH������B
�Ίё��͌��ʖ��s�ΊсB
��̓h���}�u�����Ă�v�̋��I�l�O�̍ȁE�t��X���͐Ίё��̏o�g�B�����ł����B
���쏰�́A�ʖ��s�O�c��ɂȂ��Ă���B
�� �F�����
�n�Ӓ��т���틵������Ò��Y�����́A������D�����Ƃ����ӂ����B
��Â͕F����т̒����ɁA�l�͎Ԃō����ւ̋}�s�R�𖽂����B
>>619 �W���p�l�b�g���c���H
�u������i���A���������֏�荞�ށv�ȂǂƁA�n�����o�Ƃ��Ă��s��ł������ނ�̍\�z�́A
����ɂ́A���{�R�̓쉺�ڋ߂Ƃ����G�A�����̈ӎ����S�������B
�����A���������o��Ƃ��̎��w�Z�̐����͐����R�������ɔ��邱�Ƃɂ���Ė��V���̕s���m�������łȂ��e�n�̒���܂ł������̂��݁A
�v����ɁA�˖�E����͐����Ƃ������ԓI���l�ɁA���ԈȑO�ɂ܂������������܂䂭ῂ�ł��܂����Ƃ������Ƃł��낤�B
����푈�ׂĂ���ƁA�F�R�̌F�{��ւ̍S�D�̗��R�́A���ꂽ���̓��ł����ƂȂ��͗����ł���B
�y�R���̐킢�z
�� �R��
12���I�����A�R������̔����ɂ��A���Ƃ��Ĕ��W���n�߂�B
�����ɂ͋e�r�����n���т��x�z���邪�A�e�r���̖v����A�߂܂��邵���ϓ�����B
�]�ˎ���ɂ͎Q�Ό��̓��ƂȂ�u�L�O�X���v����������A�F�{�ˁE�l�g�ˁE�F���˂����̓������������B
�s���{�s�͏��a29�N�B�u�S�W���v����̔N�ł���B
�� �L�O�X��
���F�{���N�_�Ƃ��Ėk�サ�A�A�E�R�������ւ��o�ĖL�O���q�Ɏ��铹���F�{�ł́u�L�O�X���v�ƌĂ�ł��܂��B
�ߐ��ɂȂ��Ă��̊X���͎Q�Ό��̓��Ƃ��ĉh���A�喼�s��̏h�꒬�Ƃ��ēy�n�ŗL�̎Y�Ƃ╶��������Ă��܂����B
�̂��瓒�̂܂��ł������R���͏h�꒬�Ƃ��ĉh���A�d���Ȋј\�������݂Ɏc���Ă��܂��B
���͂����U���Ă����T�̑�14�A���̂����̓�����̕��͂́A�ؗt�ŔT������Ă���2��23���ߌ�1���ɎR���ɓ��������B
�� �o��
�F�R�͎R���̑�14�A��������ɑΉ����邽�߁A�l�ԑ������܌����i����1,000�j���A
�O�ԏ������̖쑺�E���Վ��̎w�����ɂ��ĎR���ɐi���������B
���ē��́A����҈�i
>>629 �j�̌F�{�������B
���ɏ���A�ꍞ�ϑԋ{�蔪�Y�����s�����悤�ł���B
�u�����L�����ɂ�����ցA���̉Ԃ��炩���������v
�쑺�E��̎l�ԑ�����F�{���o�������̂́A23����8���B
�s�������T���Ίё��쏰�ɂ��ǂ�����Ƃ��Ă������ł���i
>>778 �j�B
23���̖�͍��J�̂��ߐA�ňꔑ�����B
2��26���̐퓬�́A�R�����̐킢�̂����́u��ꎟ��c�̐킢�v�ƌĂ��B
��c�̐킢�̉���ŁA���{�R�̎w�������O�Y��O�����Ƃ�����̂��₯�ɖڂɕt���B
�y�����̉��z
�F�R��͐�N�͌F�{�k���ֈړ����J�n�B
�����̏�ł͑މd�I�ȎF�R�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�����̐苒�ɂ��Ă͌F�{�����ϋɓI�������悤�ɏ�����Ă���B
�F�{���̈�ԏ��������X�F�[�i
>>554 �j�������̑Ί݂̈ɑq���ɖ{�c��݂����̂́A2��24�����ł���B
�� �ɑq��
���a29�N�ɋߗג����ƍ������ċʖ��s�ƂȂ�B
�� ��؊쎟�Y
�� ���V�i�����܁j
���V����́A�F�{���ʖ��s�V�������V�Ɉʒu���鉷��ł���B
�Ėڟ��̏����w�����x�̕���u�ߌÈ䉷��v�̃��f���Ƃ��Ēm����B
����29�N����F�{�s�̑�܍����w�Z�i�F�{��w�̑O�g�j�̉p�ꋳ�t�Ƃ��ċ߂Ă������́A
���N���A�����F�{�s�X����ł��߂�����ł��������̒n�Ő����ɂ����Đ����ԕۗ{�����B
�F�R��؊쎟�Y�����A���V�ɐi�o���Ă����B
�y�F�{���z
�w�Z�}�B�ˍZ���K�ُo�g�ҁB�Ύ��̏�m�B
�����Ȕ��v���}�B�m�_�H���̐��ɖ߂��Ƃ����v�z�B
2��22���A�F�{�����ߕx���h���i�悵�����j�k
>>566 �l�ɒr�Ӌg�\�Y�i
>>551 �j���o�������N�錾���ɂ��̎v�z���Z���ɕ\��Ă���B
�� �������H
�� ���K��
�F�{�ˑ�8��ˎ�א�d�������5�N(1755)�ɐݗ������ˍZ�B
�����ĕ��6�N(1756) �d���͔˂̈�w�Z�ďt�ق����Ă��B
���Z�Ƃ�����3�N�ɔp�Z�ɂȂ����B
�F�{�ˎm���̕��������A���������̋C������Ă��Ƃ����B�������ɂ͉��䏬�킪���K�قɊw�яm�����߂����A���w�}�ɈƑւ������B
�� ���S�w��
���X�F�[�̂Ƃ���ŏq�ׂ��i
>>554 �j�B
���݂̌F�{�����ρX�s�����w�Z�ł���B
�� ��ꍂ�����w�Z
����19�N�ɁA���{�̋ߑ㍑�ƌ��݂̂��ߕK�v�Ȑl�ނ̈琬��ړI�Ƃ��đn�݂��ꂽ�B
����ȑO�͑�w�\����ƌĂꂽ�B
����27�N�ȍ~�A��ꍂ���w�Z�ɉ��̂��ꂽ�B
���݂̓�����w���{�w���̑O�g�ł���B
���{�̋������Z�̍Z���◾���́A����19�N�ɑ�ꍂ�����w�Z���n�݂��ꂽ�Ƃ��A
�Z���̌Ñ��Ö�i�ӂ邵�傤 ������j�A�����̍������H�i
>>807 �j�A�ɊĂ̎�c�Â��A
��������F�{���K�ق̏o�g���������߂ɁA���K�ق̓`���������ڐA���ꂽ���Ƃɂ��B
�i�n���E�����Ă���Ƃ���܂ŏڏq���Ȃ��Ă�����Ȃ��́H
�� ����猁i�����ށj / �����`���i�悵�����j�k
>>635 �l
2��22���̏���̌�A�F�{������̑�\�҂𐼋��̌��ֈ��A�ɑ������B
����猁i�����ށj�͕�������B�����`���i�悵�����j�͌R�Ăł���B
���ꂪ���́A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Q�Q�Q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^ �P�P �_
>>802 �F�l�̂��Ƃ������ƈӋC����Ŏ��M���n�߂����̂́A����̖��̎F�l�ɂ͐�����M���ɖ��͓I�Ȑl�������Ȃ��B
�V���ȃq�[���[�����߂Ĕ��l�ɂ��ď������Ǝv�������A�`���|���Y�ɂ͂������肵�Ă��܂��B
�����Ŗڂ�t�����̂��A���X�F�[�Ȃ낤�ȁB
�ނ��됭�{�R�̑��Ƀq�[���[�������B
������13�A���̘A�����^�q�m�������i
>>563 �j�A
������14�A����3���������g���G�}�����i
>>736 �j���X�B
>>817 �u�͂��߂Ɂv�ŕ`���ꂽ�˖엘�H���D�u�Ƃ��Ă����̂ɂȁB
���������ׂĂ��������Ƀo�J���Ƃ킩�����̂ŁA����푈���n�܂鍠�ɂ͖쑺�E��𒆐S�ɏ��������Ƃ����͍��̐Ղ��f����B
�y��ꎟ�������z(2/25)
�ߌ�S���A���V�ɂ����F�R�E��؊쎟�Y�����i
>>805 �j�����勴��n��͂��ߔT�ؑ��Ɛ킢���n�܂����B
��ؑ��́A���Ԃ̔T�ؑ������|���ēW�J�B�F�{�����ɑq�i�암�c�R�j����i��ŋe�r���n��A�ɍ��̔T�ؑ����U�߂��B
�T�ؑ��͌�ނ������A���J��D�������̂S�������삯���đR�B
�����̏o���ɌF�{���͉I�Ă�����U�߂悤�Ƃ������A�@�m���ꌂ�ނ���Ă���B
�퓬�͓��v�ƂȂ��ēԂ��܂�ŏI���B�F�R�͂͌F�{���͎��c�R�A��ؑ��͈ɑq�֓P�ނ����B
�� ��؊쎟�Y
�q���{�R�r1,200
��������̕�����1�A����3����@�������F����сi
>>779 �E
>>781 �j
�ؗt�ő�s�������q�̕�����14�A���̔s�c��
�q��F�R�r
��ؑ�600
���X��300
�� �����勴
��ؑ����n���������勴�B�摜�͂�������̋��ł͂Ȃ��B
�� ��c�̓n��
���X�����e�r��̓n�͂Ɏg������c�̓n���B
�摜�͏��a41�N�̂��̂ł��邩��A���a41�N�͂܂������������B
���̎�̓n���D�́A���a40�N��ɂ͂قڏ��ł����B
�킽�����߂肽���͓̂n���D�����������a40�N��ł����āA�역�߂̂��������a40�N��ł͂Ȃ��B
�s�c�̔T�ؘA���́A���ԂƔɍ��ɂ����悤���B
>>823 �T�ؑ��̓n�Ӓ��тƂ��琏�ʂł͒������F����т����o�ꂵ�Ȃ��������B
�����̉��ɂ́A�����㊯�ł����������J��D�����������Ă���悤���ȁB
�� ���J��D��
���B�˂̎x�ˊ⍑�˂̔ˎm�̎q�B���I�푈�ł͊��]���E�ɗz���ȂǂőP�킵���B
����37�N�ɗ��R�叫�A��45�N�ɎQ�d�����A�吳5�N�ɒ��N���ɏA�C�B
�O�E��Ɨ��^���͒��������B
���{�R�͑ދp��p���Ƃ����B���R�̒����ł���ˌ���ɓO���邽�߂ł���B
�킢�����Ȃ�̍��A����8�A���̓����400����ւ��獂���ɓ��������B
���X�F�[���������R��D�悵�悤�Ɠ������Ƃ��ɁA���̕�����8�A���ɑj�~����A��F�R�͑ދp�����B
�@ �@�@�@�Q�Q�Q_�@�@
���A���ɔs����悤�ł́A���X�F�[�ɂ��q�[���[�̎����͂Ȃ��B
>>827 �����ł́A�����̑�������̂Ƃ���ŏ��߂Ė��O���o�Ă���B
25���͂��܂���ւɂ��邩�̂悤�ȏ������Ȃ��B
>>833 ��������́A�O���̖ʎq�Ő���Ă���B
�˖�E���Ⓑ�J��D�����o�ꂷ�����́A2��27���̑�O���������B
25���E26���̐킢�͑O����B
�Ƃ������Ƃŏ����̗���Ƃ͗���Ă��܂��܂����A���26���̑�����O����ɂ��ď����܂��B
�y��������z(2/26)
26���������琭�{�R�̑�2���c�͗��c�{�c���ւ��獂���̖k�̐Ίт܂ňړ����T�ؑ��������B
����ɎF�R�̓W�J���蔖�Ƃ݂čU�������肵�A��1,600�̕��ŋe�r���n�͂���B
�F�R�͐암�c�̉z�R�x�����i
>>521 �E
>>801 �̎R���c�E�����̐암�c�͂Ƃ��ɋʖ��s�ɂ���n���j�A
���c�R�̍��X�F�[���A�ɑq�̊�؊쎟�Y�����}���������B
���Ԃ���e�r���n�����T�ؑ���500���́A�F�R�E�z�R�x�����֍U�ߍ��B
����ɑ�2���c�{�������1,000�̕����e�r���n�͂���B���ɕʂ�F�{���i���X���j�E��ؑ��e�����U�������B
�T�ؑ��͉z�R�x������nj����Ėؗt���c����܂ōU�߂��B�@
�O�D�����͎F�R��͂�����ɍT���钆�ŁA�����`�c����܂ł̍L���n��ɕ��U������ɂ͂܂��̐��s���Ɣ��f�������̂ł��낤�B
�@ �@ �@ �@ �Q�Q�Q
>>841 ���f�~�X�͌����߂��B
���{�R�����Ȃ����͂œc�����苒���Ă�����A�T�͗����펀���Ă����͂��B
�� ���ؑ�
�F�{���ʖ��S�ʓ�������
���ؑ��͓c����̐��A�ؗt�̓�Ɉʒu����B
�r�Ӌg�\�Y�̌F�{�����1,000�͋g���z�����������A���{�R�͂��łɋe�r��ȓ��ɐi�o���Ă���A���ؑ���萼�ɂ͐i�R�ł��Ȃ������B
�� ���c�R
�ʖ��s�Ɏ��c�Ƃ��������͂��邪�A���c�R�͒n�}�ɍڂ��Ă��Ȃ��B
�n�}���݂�Ə����ȋu�˂炵�����̂͂���B
�摜�Ɏʂ��Ă���R�ł͂Ȃ��B���c�̃o�X��̎ʐ^��\�肽�������������B
���c�R��26���̐퓬�O�́A�F�{���X�F�[�����w�n�ɂ��Ă������A���̓��̌ߌ�ɂ͐��{�R�ɒD��ꂽ�B
>>826 ���X�F�[�������{�R�Ɛ�����ɍ��i�͂˂��j�̒�h�̉摜���������B
���܂��͋ʖ��s���ł��m��Ȃ��悤�ȃ��[�J���ȏ����̘b�����Ă���̂��킩���Ă�̂��H
�� ���ʋ��V���i
>>521 �j
����̊�؊쎟�Y�������ɑ����Ďw��������B
���m���ł���Ɨ�������̑�����B
�Ȃ��Ɨ�������̑�����͉z�R�x���i
>>837 �j�B
>>847 �厚�͒m���Ă��ē�����O�ł��B
���ׂ����������̂́A�����ł��B
�o����C�������܂������Ȃ��̂́A��������ɍ������Ăł����s�����ł��B
�y��O���������z(2/27)
�� ��ցi
>>656 �j
��ꗷ�c�i��Ò��Y�����j�E��c�i�O�D�d�b�����j�̖{��������i
>>776 �j�B
�������䊔�����Ȃ������z�ȓ~�c�̕��i�i�摜�͓�ւ̓~�c�ł͂Ȃ��j
�� ���ЎR
�W��501m�B���ЎR�𐼂ɉz����{�蔪�Y�̌̋��r���B
�� ������
��ւɂ���^�@���B
25����A��Ò��Y�����ƎO�D�d�b�����Ƃ�����č���c���J�����ꏊ�B
�����j�́A�����E�ؗt���ĐA���̂��邱�ƁB
�����Ґ��͑�c�𒆐S�ɍs��ꂽ�B
�i�ߊ��F�O�D�d�b����
���R�F�������ؗt���A�i�o�����͌R
���R�F�ʖ����ʼnE�܁��암�c���ؗt���A��
�q���R�r
�߉q���A���̖��납��͑唗��т̖��O�������o���Ȃ������B
�F�{���ď�R�̂Ȃ��ɓ��K���̑唗���q�i�Ȃ��͂�j��т����邪�A�������Ă���̂ŕʐl�i
>>565 �j�B
�q���R�r
�w�����F���J��D�������i
>>827 �j
�߉q���A����2����
���攪�A����2����
�q�R�����ʎ�����r
��14�A���̒É��O�����́A2��26���Ɂu��ꎟ��c�̐킢�v�ŎF�R�̖쑺�E����i5�����j�ɔs��Ă���i
>>794 �E
>>798 �j�B
�T�؊�T�̑��R�O��́A�Ίтŏh�c���Ă����B
2��26���ߑO4���ɍ����ɐi�o���A����������N����i
>>837 �j�B
>>827 ���J��D�������́A��ւɂ����͂����B
���A����O����́A�F����т������Ă����B
>>789 �u�R���̐킢�v�������̉����O�ɁA�������Ɨ������퓬�Ǝ����悤�ȏ������������͎̂��s�������ȁB
�����̉��̈�Ƃ��Đ��N�����킢������ȁB
���ǂ̂Ƃ��d�ԂŒn�}�Ȃ��œǂ�ł�������A�R���ƍ����͂��̂��������ꂽ�ꏊ�ɂ���Ɗ��Ⴂ���Ă����B
��ɎF�R�̏������܂Ƃ߂ĕ`���āA��ŎF�R�̔s�k���܂Ƃ߂ĕ`������B
�y�O�ʍ����z
26���[���A�F�R������������3�������F�{��i�������B
�������������A�E�����˖엘�H�A���������c�V���̗�����I�肷���������s����2,800�B
3�����͍����̐��{�R���O�ʂ���U�����邱�Ƃ�ł����킹�A�˖���͎R���o�R�ō����k�����U�߁A�����A�،o�R�ō����̐�����A�g��������ɑq�֔����鑺�c���͍����̓���U�߂��͂��ł������B
�����̑�2���c�͓�ւ���㑱�̕������������A�߉q��1�A�������8�A���𒆊j�Ƃ��đ�����4,000�B
�D���i�����̖k�j�ɗ��c�{�c��i�߁A�F�R�̍U���ɔ����Ă����B
�� ��E
26���ߌ�6���ɌF�{�鉺�̏o�����o�������F�R3���́A�ꎞ�Ԍ�̑�E���ő�x�~�����B
��L�̍��́A�����ŗ��Ă�ꂽ���̂ł���B
���݂͌F�{�s�k���E�B
�y�R�p�L���z
�� �X�i�C�h���e
�C�M���X�̃G���t�B�[���h�������iRSAF�j���A�O�������C�t���e�ł���G���t�B�[���h�e�����������㑕�����e�ł���B
���{�ł͗���ǂ݂Łu�X�i�C�h���v�ƌĂ�邪�A�p��ǂ݂ł́u�X�i�C�_�[�v�ŁA����͋@�֕����l�Ă����W�F�C�R�u�E�X�i�C�_�[ (Jacob Snider) �̖��ɗR������B
���{���R�����n������O�\�N�������e�𐧎��Ƃ���܂Ŏg�p�����������e�Ƃ��Ă��L���ł���B
�� �~�j�G�[�e
�F�R����Ƃ��ėp�����e�B
���ǎ��̑O�������C�t���e�ł���B1849�N�Ƀt�����X���R�̃N���[�h���G�e�B�G���k�E�~�j�G�[��тɂ���ĊJ�����ꂽ�B
�]���g�p����Ă����Q�x�[���e�̏e�g�ɉ��C���{�����@�Ő������ꂽ�B
�X�i�C�h���e�Ɣ�r�����15�N�قǐ̂̏e�Ǝv���悢�B
�� �������푾����
����푈�ł͑��ɂ����ĕ⋋�╔���Ґ��Ȃǂ̌���x����S�������B
����10�N�ɂ�������{���R�̏�����́c�c32,000�B
�k����푈�̎Q�R�l
���R�� �R�p�L��
�C�R��� �쑺���`
���Ȃ݂ɖ���10�N�����̊C�R�̐�͂́A
�R��11�ǁA�^���D14�ǁA�m��2,200�B
�R�p�����R�̑��w�������邽�߂ɔ����ɏ㗤�����̂́A2��25���ł���B
�����A�O�Y��O�����������O���c�������ɏ㗤���Ă���B
�� ���c
�y2��27���z
�� �߉q�t�c
�����V���{���������ꂽ�����A���{�͓Ǝ��̌R����ۗL���Ă��炸�A�R���I�ɂ͎F���ˁA���B�ˁA�y���˂Ɉˑ�����Ǝ�ȑ̐��ł������B
���̂��ߖ���4�N�A���{�́u�V�c�̌x��v�𖼖ڂɎF���y��3�˂����1���l�̌������A���{�����̌R���ł����e����n�݂��A���̌R���͂�w�i�Ɂu�p�˒u���v��f�s�����B
���̌�e���́A����5�N�ɏ���߉q�s���������𒆐S�Ƃ����߉q���Ƃ��ĉ��g����A�u�V�c����ы{��̎��v�Ƃ����C�����ۂ���ꂽ�B
>>722 >>722 �j�B >>733 �j�A�ؗt�R�̈ʒu�W�B�オ�k�ł��B �O�D�d�b�����́A�e�r��ɉ˂��鍂���勴��j�A��h�ɉ����āA
�������A���̓����
���攪�A���̈����
���q��14�A���̈ꕔ
�߉q���A���̎l������z�u�����i
>>855 �j�B
�� ���×��i�ނ����Â�j
�F�{���ʖ��s���×�
�����ƌ��������悤�ɂ��ċe�r��̓��݂ɂ��鑺�B
���������̐�N�����c�픪�Y�����������Ƃ������e�r��Ȃɓ��������B
�� �����c�픪�Y
�� ���ԁi
>>820 �j
�O�D�d�b�́A������2�q�㗬�ɂ��锗�ԂɖC����z�����A�����ɂ����w�����ɂ����B
�O�D�͍őO���Ŏw�������鍋�_�ȏ��ł������B
���Ԃ̑Ί݂��암�c�i
>>837 �j�B
�� �⌳�L���Y�i�i�n�͐\���Y�Ƃ���j
�F�R��ԑ���l�ԏ������B
�암�c���甗�Ԃ֓n�͂��悤�Ǝ��݂邪�A�t�ɋe�r�쓌�݂ɓn�͂����߉q���A���̒m��������сi
>>838 �E
>>839 �E
>>855 �j�����钆���ɔs���B
�⌳�L���Y�͓�������������đ����B
�� �m���������
�y�˖�E�����z
�F�R�̉E������27�������A�R������e�r��ɉ����ē쉺���A�ʖ��t�߂̐����R�������U�������B
�˖�́A�R����10�������c�u����3�����i��600�j�̂ݗ����Đ�����B
����҈�i
>>629 �j�̋������͋˖���̚����ł���B
�� ���c�̓n��
�F�{���ʖ��S�e�������c�B
�R���s�ɂ�����c�E�����c�����邪�A�{���ɏ����ꂽ��������12�q�̏㗬�Ƃ����ƁA�e�����̓��c�ł���B
�˖���́A���c�ŋe�r���n�͂��A���{�R�ƌ��˂���B
http://5.travel-way.net/ ~niemon/kumamoto/kikusuimati/dotyu/arch2.jpg
�� ���c
�F�{���ʖ��s���c
�˖���͐쉈���̓������̂܂ܓ쉺���č����̐��Ɍ��������B
���c����͓����ɎR�����Ă��āA������i�߂ΐΊё��ɏo�āA�Ίё�����쉺����ΐ��{�R�̔w����Ղ����B
�˖�́A���̍����Ƃ�Ȃ������B
���o�X�⌎�c�O���H
�� �ؑ�
�F�{���ʖ��s��
���ɂȂ��Ă��锗�c�̂����k�B
�˖���͐Ő��{�R�̏������Ƒ�������B�����͋˖���̐ڋ߂�Ίё��̎Q�d����Ó��ё卲�ɕ����B
�� ��R
�x�V���Y�c�c�l�ԑ����ԏ����������@���G�̔w��։I��
�� �y�q�{�i�悤�͂������j
�ʖ���_�{�̕ʖ��B
�e�r��E�݂̋ʖ�����k���ɂ���A���ӂ́u���ʖ��v�ƌĂ��B
�V�Ƒ�_�A�i�s�V�c�A���h�̎l�_�A�ʈ˕P�Ƃ��̗��e�ł���e�r���đ����v�Ȃ��Ղ��Ă���B
���{���I�ɂ́A�i�s�V�c����B�����̎��ɋʋn���̓y�w偂������L��������A�Г`�ɂ��ƁA���̎��n�����͂̒����ʎ炪�V�c�R�ɖ������A���̌��тɂ��ʖ���_�{�̋{�i�ɂȂ����Ɠ`�����Ă���B
�y�q�{�͔T�؊�T��������Ă������A�˖�͕ʕ{��Y���Əd�v�Y�����ɗy�q�{�����������A�T��s�������߂��B
�x�V���Y���́A��R�̐��{�R�ɔs�����B
�x�V���Y���̔s�k�ɂ��A�˖�E���R�͐�p�I�@�\�������A���ɕY�������̑��݂ɑ����B
�y���c�������z
�� �g���z
���������q�����ق��O���́A�g���z��ʂ��ċe�r�여��ɐi�o�����B
�ؗt�E�c����E�A�Ƃ̈ʒu�W
�� ���������q
����푈�ɎQ�����ĎF�R�������ꏬ�����߂�B����10�N2��27���A��㍑�����͓�̐킢�ɂĊ��R�̏e�e���Đ펀�����B���N31�B
�� ��]���V�i
�� ���Njg�V��
�����3�����́A���c�̖��ɂ��A�����勴����3�q�����̑�l�Â���e�r���n�����B
�� ��l��
�ʖ��s��l��
�� ��茴�i��j
25���̍�������ŁA���{�R���ދp�����n�_���Ƃ��ēo�ꂵ���i
>>828 �j�B
�ʖ��s���
�����勴��n��Ɣɍ��i�͂˂��j�̒�������i
>>826 �j�B
���̐��ׂ���茴�ł���B
�� �ω��u
�O�D�d�b�͑���8�A���̂����̈�������茴���ʂɌ����킹�����A�����q���3�����́A�����ǂ��U�炵���B
��8�A���́A�ɍ��ؑ��Ɖi���������Ă������āA�k���̓�֊X���⊋���R�i��������j���߂����ē������B
�����R��25���̍�������ő�8�A�����ˌ����_�ɂ����ꏊ�ł���i
>>829 �j�B�ʒu��
>>864 �̒n�}���Q�Ƃ���B
�� �i����
�i�������́A�����勴�̓�𑖂鎭�����{���̓S���̓�A�e�r��̐쉈���̒��ł���B
���e���w�c����x�ł͐��������q�̐펀��ʂ��A�T�؊�T���o�ዾ�Ō��Ă����B
��肽�����Ȃ���ɋ��o����āA����E����āA�������U�X�Ȗڂɑ����Ă���ȁB
+�@ �@�@.�@..�@:.... �@�@�@..�@�@..�@.
�y���������z
�ߌ����ɂȂ�ƁA���̟���1,200�l���g�т��Ă����e�e���Ȃ��Ȃ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�ɒ[�ɖ����Ȏ��́A�v���[���l���Ɗ��Ⴂ����Ă����낤�ȁB
���c�V�����c�c���{�R�ɏ����Ă����B
�˖엘�H���c�c���c�������ދp���x�ꂽ�B
�� �]�c
�ʖ��S�a�����]�c
�˖�����e�r���n�͂����n�_
�킢�̑O�ɓn�͂����ʖ��S�e�������c�i
>>882 �j�̂���B
������x�A�F�{���̎s�����̂���
�r���s�@��֒��@�a�����i�Ȃ��݂܂��j�@�R���s
���F���@�ʖ��s�@�ʓ����@�F�{�s�k��i�A�j
���̂ȁA�˖���͂���Ƃ̂��ƂőS�ł�Ƃ�Ĕs�����Ă���B
�� ��c
�����Ŋ���������m���I�ȃo�J�ɂ͒��ӂ��悤�ˁB
�y�c����E�g���z�z
�� ��]���V�i�i
>>894 �j
�߉q���R��т�����������6�N�̐��ςŎ��E�B
�������A����́A���������x�@�̌x���ɂȂ�A�������Y�i
>>482 �j�E����e�͂��ߔ������B
�� 2��28��
�� �؈�̐킢�i2��27���j
���䑤�ɂ́A�i�ߊ��̒J���鏭���A�Q�d���̊��R���I�������͂��߁A���ʌ����Y�����A��㑀�Z�����E�����ݏ����E���얔����сE�唗���q��тȂǁA��N�̑啨�R�l���Q�����Ă����B
������O�킪�s��ꂽ2��27���ɁA�ď�R�͏��߂ď����J���A�؈���ʂֈЗ͒�@����200���o�����B
�w���͑唗���q�i�Ȃ��͂�j��сi
>>565 �j�B
���I�푈�ł́A�틵���F�����Ȃ������v�ǍU���̂��߁A�唗���q�����̑�7�t�c���T�؊�T�叫�̎w�������3�R�ɑg������A��Z�O���n�̍U���ɓ��������B
�� �؈�
�F�{��̂����k���ɂ���B
���X�F�[�̐��܂ꂽ���ł�����i
>>554 �j�B
�唗��т̕����͑���w�Z�i�ڍׂ͕s���j�̎F�R�������������A�₪�ēP�ނ����B
�����̉��ɎQ�����Ȃ������F�R�̓�̑���͉������Ă����̂ł����H
�r��l�Y�̌ܔԑ��2,000�́A�F�{��U�͐��S�����Ă��܂����B
�������{�c�Ƃ��Ă����_�剮�~�ŌR�c���n�܂����B
���̎咣����F�{�U��W���_�́A�����܂Ő��{�R���i�o���Ă��錻�݁A�Ӗ����Ȃ��Ȃ���_�ł������B
�k��W���_�����l�ł���B
���ǁA���̍U����Ƃ�����i�\���̕��j�ɖ߂����B���������Ƃ����Ă��h����͏k�܂����B
�����̉��ɂ�萼��̖��͎����I�����Ă����B
�������̐���푈�́A���Ӗ��ȎE�C�Ə��Ղɂ����܂���B
����̖��͓����ł����č��ƊԂ̐푈�ł͂Ȃ��ł����A���̒i�K�Ő푈�I���ɂ����Ă䂯�Ȃ��푈�w���҂́A
�ߑ�E����̐����Ƃ̐푈�̎~�ߕ��̉��肭�������������Ă���ƁA
��̋K�͂������Ƌߑ�ł͑傫���قȂ邾�낤�B
���E�j�̋��ȏ��ȂǂŁu�A�����J�͂��̂悤�ɍl���A�h�C�c�͂��̂悤�ɍl���Ă����v�Ƃ����ނ̕��͂�ǂނƁA
�u���{�Ƃ��Ă͂��̂悤�ɍl���Ă��܂��v�Ƃ����ނ̔��������l�B
�E�����Ă��邼�B���͂́u��̌��i�v���B
>>929 �c����E�g�����̐킢�ƕ��s���čs��ꂽ�R���̐킢�́A2��26������3��21���܂ł�24���ԁi
>>789 �j�B
>>909 ����̐�p��Ŏ��̍s�����ώ@���邩��A���̂悤�Ȏ��]���ɂȂ�B
�����̐킢�ɎQ�������F�R�̏����̒N��l�Ƃ��Ď�����Ă��Ȃ��Ƃ��납��l����ƁA
���̍s���͏��Ȃ��Ƃ��F�R�����ɂƂ��Ă͏펯�I�ȍs���������̂��낤�B
�u�������҂͎m�ɔv�Ƃ����ϗ������R�Ƃ��đ��݂��Ă����̂��B
�����ɓ������ꂽ�V�v�z�́A���a�ɂȂ�ƕ����������ȁB
>>688 �u�ߘa�v�̏o�T�����t�W�B���t�W�ŋ��B
�y�����z
�킢���n�܂�Ɛl�X�͉ƍ���w��������Ԃɐς�ŎR�֓�������A��ӂ𗊂��ĉ������֔����肵���B
�F�R�ɂ͌얯�v�z�����������A���R�ɂ͊F���������B
���R�͖��Ƃ��G�̍ԂɂȂ邱�Ƃ�h�����߂ɁA���R�Ɩ��Ƃɕ������B
�m��������сi
>>880 �j�̒������A�암�c����ދp����Ƃ��ɖ��Ƃɕ����Ă���B
�m����т̃q�[���[�w������ቺ���܂����B
���c�V�������e�r���n�萭�{�R�ɓ˓������Ƃ����A���{�R�͔ɍ��ؑ��ɕ����đދp�����B
���̉������̓쐼���̖��Ƃ����ׂďĂ������A�����̒��͊D���ɋA���Ă��܂����B
�y�F�{�z
�Ό��^���i�܂���j�̎��`�w�鉺�̐l�x�ɁA����푈�����̌F�{�鉺�̗l�q��������Ă���B
�^���͓���10�ŏ��w�Z�ɍ݊w���Ă����B
�ނ͑�_�ɂ��O���w�����֍s���A���c�V����r��l�Y�ɐ��������Ă�����Ă���B
�^���̕��̂Ԃ₫����ۂɎc��B
�u�\�l���̂��鉺������ŏI��肾�B���̃S�W�����Ō�̈�C���Ƃ͎v���Ȃ��v
�y�����z
�y�R���猬�z
�� ����
�e�r��̎x���Ŗk���痬��Ă��ĎR���ŋe�r��ƍ�������B
����ɉ�������k�̊X�����L�O�X���i�R���X���j�ł���i
>>791 �j�B���݂̍���3�����B
�Ȃ��e�r�쉈���̓����̊X���́A���֍s���Ɠ�ւɒʂ��Ă���B�����̍���443�����ł���B
�R������ɂ��Ă�
>>790 �ɏ������B
�� ���䉮
�F�{�������̖{�c���u���ꂽ���āB
�R���͑傫�ȏh��ł������̂Ŕѐ����i�V���j�����������B
���̂��ߎR���̎F�R���m�̊Ԃŗҕa�Ɣ~�ł��o�������B
�y���h�Ꝅ�z
����5�N4���̑������z���ɂ���āA�����̏����E����Ȃǂ̑���l�̌ď̂�p�~���āA�˒��E���˒��ƌĂԂ��ƂƂȂ����B
����11�N�̌S�撬���Ґ��@�ł́A�����̌S�E���E���������A�e�������Ƃɖ��I�̌˒���I�o���邱�ƂƂ��A�˒����s���������s�����߂̌˒�������ݒu����邱�ƂɂȂ����B
����17�N5���A���{�͌˒����x�̉��v���s���A�˒���m���̔C���ɂ��u���I�z�ɐ�ւ��āA����5����500�˂Ɍ˒�1����u�����x�ɕύX�����B
�i�n����͖���10�N�ȑO�ɂ����I�˒��������悤�ɏ�����Ă��邪�A�ꕔ�̒n���ɗ��܂邩�A���邢�͌��ł͂���܂����B
>>955 �ŏq�ׂ��悤�ɁA���I�˒����@�������ꂽ�̂́A�����̎�������7�N��̖���17�N�ł���B
�� ���w�Z
�� ������
�F�{�����h�s������
�a�����@�R���s�@�e�r�s�@���h�s
�� ����c��
>>926 ���������{�c�Ƃ��Ă����_�剮�~
�k���_�Ђ̐_�����i��V��B
�k���_�Ђ͓V��2�N�i979�j�ɋ��s�̋_���Ёi����_�Ёj���������đn�����ꂽ�B���Ƃ͋��s�Ɠ������_���ЂƌĂ�ԉ��R�̏�ɂ������i
>>631 �j�B
����4�N�i1647�j���ݒn�Ɉڂ���i�F�{�s����t���j�A��㍑�{�̂�������{�̖k�Ɉʒu���邱�Ƃ���k���_�ЂƉ������ꂽ�B
���������搶�{�c��
����푈�Ƃقڎ����������ČF�{�E�啪�E����̔_���͈Ꝅ���N�������B�����̔_���Ꝅ�͋���Ȑ���푈�̉e�ɉB��Ă��܂�m���ĂȂ��B
���̏W��֎~�̕z�B�ɑ��āA�_���͖T���Ə̂��āA�Ȃ����l���̏W����₽�Ȃ������B
�����}���w���������k���̌˒������́A2�����{�A����푈�J��O�ɒ��܂����B
�� �F�{���̌S
�ʖ��S�@���{�S�@�e�r�S�@���h�S
�F�y�S�@���v��S�@��v��S�@
�V���S�@����S
���k�S�@�����S
�� �s���E���Y
����10�N1��9����������ɒ[�������h�Ꝅ�́A2���������h�J�ɂ�����A���q��M���ɂ����ċC�����グ�A3��1���ɂ͍◜�n��ɒ��̔@���������B
���̐�3,000�͂�����܂��Ǝv����B�ԃ��V���Ƃ�̂����ĊO�֎R���ɓ�������e�����������炢������A���̘T�s�̒������������悤�Ƃ������́i�ÊՂ̍��q�T�G�k�j�B
���̔N�A�Ꝅ���ЂƂ܂����܂������A�������V��̎s���E���Y�́A���̌��ߕx���h���i�悵�����j���ɔ�Q������i
>>566 �j�B
�ژ^�̖����Ɂu�E�͖{�N�O������}���\���̐߁A�ł����킳���@�T���A�O���̒ʂ�Ɍ����@���̒i���͂��d��@�����\�N���N�l���O�\����\����O����◜����l�S�E��Ԓn�@�m���@�s���E���Y�v�Ƃ���B
������̔_������
�y�얞�����Y�z
�ÊՂ͌��݂̒n���ł����āA�����Y�����܂ꂽ���́A�R�����Α��Ƃ�������B
�� �얞�����Y
�얞�����Y�́A���B�ɂ��Ē_�����������B
�������̊����Ƃ��Ċe�n��]�킵�����A8��17���A�F�R�̉�̐錾���č~�������B
�������ꂽ���A��N�]�ɂ��ĕ��Ƃ���A�������}�̎w���҂Ƃ��Đ��d���ꂽ�B
�얞���e�E�x�L�Z��̂��Ƃ��i
>>630 �E
>>652 �j�B
�� �얞���e�E�x�L�Z��i�c���Ɍ뎚���������̂ł�蒼���j
�얞���e�ƕx�L�Z��́A�]�Z�풷���Y�ƂƂ��ɐA�؊w�Z�Ɋw�сA���R�����v�z�̐�g�ɐs၂����B
����10�N2���A�F�R���N��A�ꓯ�W�܂��ĎQ��̐�������c�������A�c�_�S�o���钆�A����q�����얞���e�̈ꐺ�ŎQ�킪���܂苦�������������ꂽ�B
2��22���A�F�{�鑍�U�����n�܂�ƁA�얞���e�E�x�L�̌Z��́A�܂������ɏ�ǂɎ��t������B
�u���̎��ɂ��܂�����v�Ƌ��ԂƁA�Z��݂��ɂ��̖���A�Ă��A�e�ۉJ���̒��A�s��Ȑ펀�𐋂����i
>>652 �j�B
�얞���e�@�얞�x�L�@��
����̖����n�܂�O���A�R���̒n�ł́u�˒������v�̖�肪�捹������Ă����B
�˒��͖������{�ɂ�蒥�Ŋ��I�Ȗ�����S�킳��Ă���A���W�̕s�������܂�A�˒��I�ɂ��邱�Ƃ����߂āA����10�N1��28���A�R���̌��ꎛ�ňꖜ�ȏ�̐l����W��J���ꂽ�B
���̗����͎��������w�Z���\���������ł��������i
>>522 �j�A�F�R�̐i�s�ƂƂ��ɁA�F�{���S��Ɉ��̖����{��Ԃ�����A�R���Ţ������������s���邱�ƂɂȂ����B
�� ���ꎛ
�V��6�N�i1578�j�n���B�F�{��z��̍ہA�]�����ޖō��ꂽ������\����B
���j�̕���ɓx�X�o�ꂷ�邱�̂����A����10�N�̐���̖��ł͎F�R�̖��a�@�ƂȂ����B
�F�{�����}�͑��n���̎��R�����^���Ɣ�ׂ�Ɩ{���ɋ߂��������������B
�����̑�O�킪�s��ꂽ2��27���ɂ́A���h��тő�K�͂ȈꝄ���N�����Ă���B
�������́A���̓��A�Ȃɂ����Ă����̂ł����H
�˖�E�����ɂ��ċe�r���n�萭�{�R�Ɛ���Ă��܂����i
>>881 �j�B
�얞�����Y���R���̖������ɂȂ邱�Ƃ��v�������̂́A�����̑�O�킪�I����ĎR���Ɉ����g�����ゾ�����B
�Ȃ��A�{�蔪�Y�͎F�R�{�c�i
>>961 �j���̊��ŁA�F�R�Ƃ̘A���ɓ������Ă����B�����̉��ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��B
�`���|���Y�́A�������Q�ƃZ�b�N�X�O���ł��B
�� ���ӌQ��
�V��11�N�i1840�N�j���������풬�Ő��܂��B
���c�������W�����F���ɓ`�������w���`�����ɒn�m��������w�сA�R���ɒ����Ă����B
����10�N3���A�������A��A�e�������A�V�����W���A�������̎�����ł߂�Ȃnj���ɂƂ߂��B
4���A�ʕ{�W��E�ӌ��\�Y���ƂƂ��ɐV���2���1500���𗦂��Ėk�サ���B
���ӂ͐_���ɖ{�c��u���A�l�g���o�Ĕ�����ʂ������A���{�R�̔w�ʂ��Ղ����ʕ{�E�ӌ��������������A�F�R����K��ɔs��F�{��݂̈͂������ɋy�сA�l�g�ɑދp�����B
4��21���A���ӂ͖Q����������ƂȂ�A����𗧂Ē����đ����ʂŐ�����B
5��30���A���ӂ͐l�g�̊�}���A�͖���Y�ƂƂ��ɋ~���ɕ��������A���{�R�̐����̎~�߂����������ċ�����ɉ˂��鋴���Ă����Ƃ��������Ƃ��A�e�����ďd�����A�㑗���ꂽ�g�c�ŋA��ʐl�ƂȂ����B���N38�B
�얞�����Y�́A�R���ɂ����āA���ʑI���ɂ�萔���̐l�������I�o���������s�킹���B
�� ��X�y��
�������̕����������Ă���ȁB
�ۓc�E�_�Ёi
>>620 �j�ŋ��������Ƃ���40�]�����������A�R��������������ɂ�300�`400�ɑ����Ă���B
��̒n��̌˒��E���˒��Ō����ۊǂ��Ă���҂�����ƁA�������͉��������Ă����Ĕނ���a�E���J�l��D�����B
�������ɂ͂Ȃ炸�҂��܂����Ă�������ȁB
>>974 �{���̖����h�͐l�E�������邩��|����B
���E�ɂ���������Ė����h���Ă����A���̂ق����A�܂��l�ԂƂ��Ă܂Ƃ�����B
�� ������
�u�l���v�Ƃ��������ɂ́A�l�E���̃C���[�W�����Ȃ��B
���X���̖`������c�������낤�Ǝv���Ă����̂����A�����y�[�X���x�������B
�w�����̍�x���ēǂ�ł��߂ɂȂ�܂����H
����Ȃ��Ƒ��l�ɐu���ȁB
���X��
��̓h���}�ɂȂ����Ⴕ���͂��Ăق����i�n�ɑ��Y��i�@Part14
http://2chb.net/r/nhkdrama/1554270531/ ���{�j�ɗ��Ă��Ȃ������̂ŁA��̓h���}�ɗ��Ă��B
����Q�P������e���r�����ʼnf��u�փ����v��邼
�u�����̍�v�Ő�J�萳�͌J��Ԃ��u�֓��Ǘ́v�Ƃ��������ŏ�����Ă��邯�ǁA
���̃X���b�h�͂P�O�O�O���܂����B
5�����˂�̉^�c�̓v���~�A������̊F���܂Ɏx�����Ă��܂��B
�^�c�ɂ����͂��肢�������܂��B
��������������������������������������
�s�v���~�A������̎�ȓ��T�t
�� 5�����˂��p�u���E�U����̍L������
�� 5�����˂�̉ߋ����O���擾
�� �������K���̊ɘa
��������������������������������������
����o�^�ɂ͌l���͈�ؕK�v����܂���B
��300�~���瓽���ł��w�����������܂��B
�� �v���~�A������o�^�͂����� ��
https://premium.5ch.net/ �� �Q�l���O�C���͂����� ��
https://login.5ch.net/login.php
�j���[�X �X�|�[�c �Ȃ�ł� ����
���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/history/1521275224/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��BTOP�� TOP�� �@
�S�f���ꗗ ���̌f���� �l�C�X�� |
>50
>100
>200
>300
>500
>1000��
�V���摜 ���u�i�n�ɑ��Y�@Part13 YouTube����>6�{ ->�摜>303�� �v �������l�����Ă��܂��F�E�i�n�ɑ��Y�@Part10 �i�n�ɑ��Y�@Part12 �y�i�n�ɑ��Y�z�@�փ����@�y���c���l�z Part.6 �y�����������z�i�n�ɑ��Y�A���`�X���y�����zpart2 AI���i�n�ɑ��Y���w�K�I�V�씭�\�ցI�I �y�Љ�z�i�n�ɑ��Y�̎��M���e������@�u���n���䂭�v�ŏI��Ɓu��̏�̉_�v��1��c�i�n�ɑ��Y�L�O�ق����\ �y��Ɓz�i�n�ɑ��Y�ē��������s�j�ς̓��{�l�ֈ⌾�u����Ȃ����v�����̓��{�̋���E�C���t����������p���W�̊�b��z�����Ə̎^ �����̓��䑏���l�i�A���w5�N���Ŏi�n�ɑ��Y�u���n���䂭�v��S���ǔj���A�u�����V���v����������܂œǂ�ł��遨�l�g�E�������� [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net �i�n�ɑ��Y��Q�҂̉�������� �i�n�ɑ��Y�̉ƍN�ߏ��]���ُ͈� �i�n�ɑ��Y�̍�̏�̉_���f���炵�߂��� �ē����O�M���G�g�̉ߑ�]���͎i�n�ɑ��Y�̂��� �i�n�ɑ��Y�̔��̖тƉA�шꏏ�^�����K���P�[�����R �y�ߕ�z��{���n����i�n�ɑ��Y�̝s��������👉���ȏ�����폜�� 4 �y���z�u�i�n�ɑ��Y�̋O�ՂQ�v�P�O���R�O���܂Ŏi�n�ɑ��Y�L�O�قŊJ�Ò� �y��p�z�i�n�ɑ��Y�̈ē����E�V��k���玩�s�j�ς̓��{�l�ւ̈⌾�@�u���{�l��I����Ȃ����I�v[8/04] �y�ߕ�z��{���n����A���ȏ�����폜����� �w�ҁu�̋Ƃ�95���͎i�n�ɑ��Y�̑n��A���������́h�p�V���h�ł����Ȃ��v �ɒB���@�Ƃ��������{�S���ɗ^�����e���[���̓c�ɑ喼�A������Ǝ����グ�߂�����Ȃ��H������i�n�ɑ��Y�̎d�ƁH �y�ߕ�z��{���n����A���ȏ�����폜����� �w�ҁu�̋Ƃ�95���͎i�n�ɑ��Y�̃t�B�N�V�����������j���Ɗ��Ⴂ���������v �y�g���C�A�X�����z��J�ɑ��Ypart19�y�A���`��p�z ��J�ɑ��Y Part3 [���f�]�ڋ֎~] �y�g���C�A�X�����z��J�ɑ��Ypart7�y�Z�K�T�~�[�z ���c�y��̍��O�ܘY���ĐD�c�T��̎i�n�]���Y�����ĂȂ����H�y�L�������͂܂�œ����ĂȂ��z �n�j�J�������Y�@Part1 $$$ ���������Y part11 $$$ �Q�Q�Q�̋S���Y 6�� �A���`�X�� Part1 �y���b�z�O�����G�R�[�Y Part1 �y�Έ�ȑ��Y�z �y�ԊO�ҁz �C�i�R�E ��c�_���Y Part1�y���S��\���z �y�e�����y�j23���z���������u part118�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �y�e�����y�j23���z���������u part153�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �y�e�����y�j23���z���������upart132�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �y�e�����y�j23���z���������u part166�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �y�e�����y�j23���z���������u part168�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �y�e�����y�j23���z���������u part16�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �y�e�����y�j23���z���������u part147�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �X�v�ۏˑ��Y part18 �y���\�m�z�����m�E�����Y�@�M�I���j�����_���キ����[ part18 �w�p���v�L���E�V�U�[�Y�|Pumpkin Scissors�|�x��i�����YPart83 ���ɍ�K���Y��part28 ���Q�W���Y�@Part46�y�w�ԍ�19�z �y���S�z�Q�n���ƗV�ԓ����Y�d�S�y��ԁE�ߘa�z 2022�N Part.3 �y���N���ڎw���z���Q�W���Y�@part30�y�z �y�j�R���z�R�X�������Y part2�y���n�z ���`���Q�Q�Q�̋S���Y �d���h�^�o�^��푈 part28 ���`���Q�Q�Q�̋S���Y �d���h�^�o�^��푈 part27 ���e���̍O�����Y�A�i���f�G�������I Part2 ���`���Q�Q�Q�̋S���Y �d���h�^�o�^��푈 part5 NACK5 Part60�@�y�A���n�E�S�ہE�����Y�@�_��DJ�̊y�����W�I�z �y���̂�(����&���D��)�z��{���|�\�Б���part3�y�n�z�����Y�z NACK5 Part62�@�y�A���n�E�S�ہE�����Y�E�r�Ӂ@�_��DJ�̗������W�I�z �y�e�����y�j23���z���������u part55�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �y�e�����y�j23���z���������u part71�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �y�e�����y�j23���z���������u part217�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �y�e�����y�j23���z���������u part2�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �y�e�����y�j23���z���������u part8�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �y�e�����y�j23���z���������u part67�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �y�e�����y�j23���z���������u part81�y�c���\�E�g�c�|���Y�E�ь��s�z �yTBS��10�����q��剉�z ���߂�A�����Ă� Part2�y�g�������E��������Y�E��|���̂ԁz �yTBS��10�����q��剉�z ���߂�A�����Ă� Part3�y�g�������E��������Y�E��|���̂ԁz �y�e������21�z�n�P���肢�t�A�^�� part5�y����ԁE�u�c�����E�ԋ{�ˑ��Y�E�u���~�E�ᑺ���R���z �F�J�����Y part29 �R���q���Y Part.5 �~���[�W�J���u�E���ܗ����Y�vPart29 �y�i����A�Ƃ��Ƃ��z�@�q�R��part863�y�J�����Y�z �y����G���@�m�X�͑��Y�z�@�V���E���ʃ��C�_�[�@�y�r���s���A�l�Ӕ��g�zPart 18
19:48:25 up 5:21, 0 users, load average: 13.68, 11.93, 12.04
in 0.076793193817139 sec
@0.076793193817139@0b7 on 040508