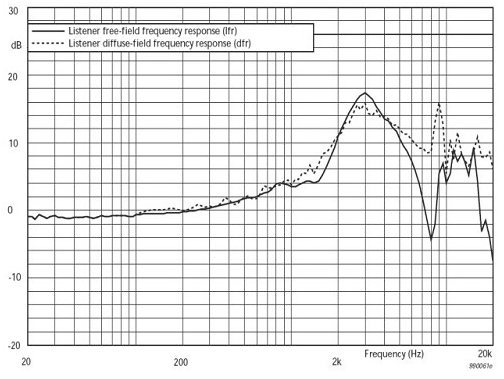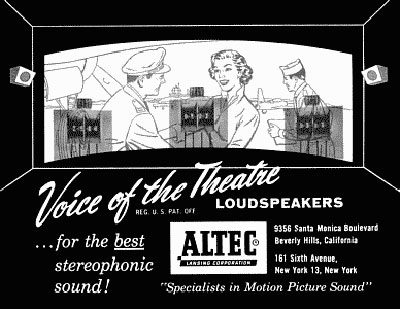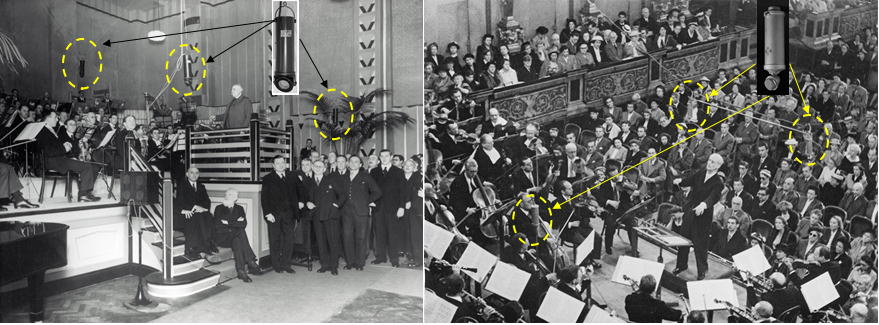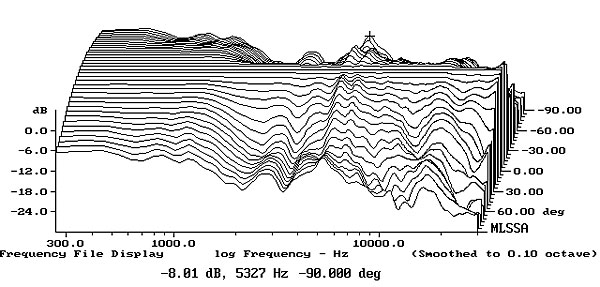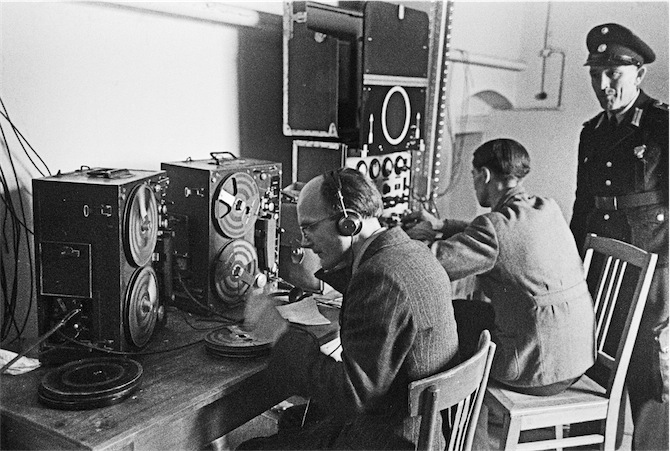�������ȗ��R�ɂ�鏑�����݂̍폜�ɂ��āF �����p�V �Ƃ݂������:�������t���g���F���O���[33������ YouTube����>7�{ ->�摜>35��
����A�摜���o �b�b
���̌f����
�ގ��X��
�f���ꗗ �l�C�X�� ����l�C��
���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/classical/1620879500/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B
�@,�i�M�R�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@ �@ �@ ,r�]'�@�@
�t���g���F���O���[�̕����L�^���܂Ƃ߂����̂��Q�Ƃ����
https://furtwaengler.org/download/RundfunkSenAuf.pdf 1947�N���A���t��Ȍ���n��RIAS�ł̕����͎w�Ő�����قǂ����Ȃ�
�������s�ł̘^�����قƂ�ǂ��߂邱�ƂɂȂ�B
���̒��S�̓n���u���NNWDR�A�E�B�[��RWR�A�����h��BBC��
NWDR�͌�RRG�̃V���i�b�v���ARWR�ABBC��EMI�̃��b�O����
�����̍L��ɂ��������n��ƂȂ�B
���̂��Ƃ͐��̃t���g���F���O���[�̉��t�̕]����
�h�C�c�����ƃE�B�[���������h���Ƃŕ������Ă��邱�ƂƊ֘A���Ă���
�x�������t�B���ƃE�B�[���t�B���̂ǂ��炪����Ղ��Ƃ�����r����
���̂ǂ�����t���g���F���O���[�̌|�p��m�邤���ŕK�v�Ƃ������ƂɂȂ�B
�ЂƂ̉��t����B�̑����̕����ǂɔz�M�����̂�
�t���g���F���O���[�̃I�y���j�ς̓h�C�c��ƃh�C�c����
>>6 �v�t�B�b�c�i�[�́u�p���X�g���[�i�v��1956�N�̃U���c�u���N�ŐU��\�肾������ˁB
����������猋�ǃP���y���U�邱�ƂɂȂ������ǁB
�P���y��1955�N�����̋L�^���c���Ă�ȁB�i�^����Ԃ͗ǂ��Ȃ��j
���J�i����V�����e�B�j�A�p���X�g���[�i�i����P���y�j��
�t���x���͏o���\�肵�Ă��悤�ł��ȁB
https://archive.salzburgerfestspiele.at/archiv/j/1955 ���J�̂ق��̓R�R�V���J�̈ߑ��ƕ���ł̐V���o�������̂�
���ڂ��̂��̂�ς���킯�ɂ͂����Ȃ������悤���B
�I�y�����s����������ςȂ悤�ŁB
����I�[�f�B�I�h�̒m�荇���̉ƂɐV���������DAC����������łƂ������Ђ����������ہA
���������Ĕ�����p�[�c�Ȃ甃������A�ڂ��イ�BDAC�̃p�[�c�� Cirrus Logic �ł����H
�^�[���Ճ��c�F�����̑��̉������ǂ������̂�
�t���x���̃��C�u�^���̗ǂ��Ƃ���́A�}�C�N����e�[�v���R�[�_�[�̊Ԃ�
�����͂����Z���^�[�̉���ǂ�ŋ������B
�܂��c�M�n�M���炯�ɂȂ�Ȃ��悤�F�ŋF��܂��傤�B
�c�M�n�M�����ƌ����Ȃ琢�ɏo����Ă��鑽���̃f�B�X�N�������Ȃ��Ȃ�̂���
�x�������t�B���̃u���b�N�i�[���āA������}�b�`������ˁB
�����̓t���g���F���O���[��㕜�A�̓�
�e�B�^�j�A�p���X�g�ł̃��C���͉����Ђǂ�����
�̂̃��C�u�ɂ��Ă͉��A��������B
���R�[�h�^�����o�J�ɂ��Č����Ă��t���g���F���O���[����
���̎����A�����������Ȃ��Ȃ��Ă�������
�U���c�u���O�̖��e�ő厸�s�����đ�p�����������
���n�ł̉̎肢���߂ŗL���ȃx�[���̐l���ɐG�ꂽ�C������
�R�[�K���ƃ}�^�`�b�`�̋����@�Ȃp��������
�Ίۂ͓��{�̂��̗��OK�K�[���̎t����������
>>27 ���̑厸�s�������e�̎ˎ�̎����^���͂Ȃ���ł����H
��̃X�e���I�^���Ƒ�R�������R�[�h��Ђ̃C���`�LLP�������������
���͂悤�������܁[��
�u�I���t�F�I�ƃG�E���f�B�[�`�F�v�̃L���O���R�[�hCD�����B
�}�C�N���ז����ƕ��匾���ĉ����������������G�s�\�[�h�͗L��
>>36 �u���[���X2�Ԃ̎��ł���
�u�ߎt ���Ă����悤�� �R����
>>39 �����ł͂Ȃ��ă��F��
��蒼���I
>>39 ���̃`�����R�͓������Ƃ�������Ȃ��L�`�K�C
���܂܂ʼn��S���R�s�y��\������낤
�悵�I
����Ȃ�A1938�N�̃����O�A�t���[�_�[���C�_�[�̂��
�J�������������Ă����͎̂��m�̎����������g�̐��i���Ђ����ĕK�v�ȏ�ɋ����Ă���������Ȏ��ɃJ�������𐬒������Ĉꗬ�ɂ����̂��ނ�
�t���x���͏��������������
�u�ߎt�@���Ă����悤�ȁ@�R����
�i�`�X���͎҂Ƃ��Ďw���Ҋ������~���ꂽ�Ƃ��̂�����
�t���x���̌�̏�C�̓`�F���r�_�b�P�ɂȂ�͂��������̂ɃJ�������ɂȂ����͉̂��ŁB�A�����J�ł̐l�C�H
�{���q�����g���v���o��������������
�v�l�̃G���U�x�[�g�ɂ�����K�́A����K�A�ƈ����������肾�����Ƃ���
�t���g�x���O���[���������������
���R�|�Ńt���x����ᔻ�����܂��Ƃ��ȕ]�_�Ƃ͈�l�����Ȃ�����
�J�������Ƃ͌|�p�̊i���Ⴄ�����
���R�|�ŃJ��������ᔻ�����܂��Ƃ��ȕ]�_�Ƃ͈�l�����Ȃ�����
�o�J���������̂͑�R�����̂ŁA���l�̂��肩�Ǝv���Ă���
>>62 >>64 ��͂茻�ꂽ�ȁ@����N�l�̓���l���Ă�肷��Ώ��Ă�Ǝv���Ă閳�\
���܂�����Ȃ��Ƃ��肵�Ă݂��Ƃ��Ȃ��Ǝv��Ȃ��̂�?
���x�����O����B
�u�h�q�K���v���p�N�������N�Ƃ������X�R�A�����N�Ƃ�������ƃ��L�ɂȂ��ėx��o���l�ƈꏏ����
>>66 �p�N�����w�E����ĉΕa���������I�E���Ԃ����邵���\�̂Ȃ����N�����[
>>69 �������t���J��Ԃ��Ă���
����N�l�̓���l���Ă�肷��Ώ��Ă�Ǝv���Ă閳�\
���܂�����Ȃ��Ƃ��肵�Ă݂��Ƃ��Ȃ��Ǝv��Ȃ��̂�?
>>70 �t�@�r����p�N����\�`���[�Z����Yw
>>70 ���̒��N�l�͂����l�̏������݂��p�N�b�Ėʔ������Ă��\
>>62 �̃p�N�����w�E����
>>66 �ʼnΕa��������
�����
>>70 �ł܂��܂��Εa���������Ă�o�J���N�l
������������ƍ��鎖�葤�Ɍ����Č떂�������ĂT�����̒�Ԃ̂��������
���悤�A�����̃p�N�����N�l
>>71 �T���N�X�I
��͒m���Ă����ǎw���p�����߂Č���
���y�̉^�т��B�R�Ƃ��Ă��Ă��Ȃ���I�[�{�G�̖点���ɂ͈��D������
���͋C������w���҂Őɂ����l��S��������
>>77 �i�����̘A���R�̌�˂Ƃ͂˂��c�c
����҂͖����Ń{���q�����g�������E�E�W�F�[���X�f�B�[�������̂̎��ނ����]���ɁB�_�l�̋C�܂��ꂩ
�A�����Ɍ�˂��ꂽ�̂̓��F�[�x��������
����̍�i���x�������t�B���ɂ�艉�t���A�t���x���Ƃ��𗬂��������M�u�N��̎���Y��Ȃ��ʼn�����
���K���R�[�h�p�^���W�听CD-BOX�ASACD�ŏo���\��͗L��̂��ȁB
�����������邩�Ǝv������T�T���őS�����܂��
Art & Son Studio ��M���Ĕ����ׂ��Ȃ̂��낤���B
���ђ��Ƃ��S�̎�ł���������̂悤�ɑ��������B
����������A���}�X�^�[�Ȃ�āB
�����͂����Ȃ�
>>82 CD-BOX�����ꂽ��A�o����
>>85 �^�[����Testament�͂�����ƕ����ǂ���e�[�v�������Ă��ĕ������邯�ǁA���̐l�͒��Â�LP��I�[�v�����[���������������̂悤�ɐ�`���邾������B
�t���x���̃x�g���t�ł̍ō��̉����͂ǂꂾ?
1954�N�̃o�C���C�g�̑��
�o�C���C�g�̑�9����1951�N�ȊO�ɂ���̂�?
�t�����X�t���g���F���O���[����Еz��
�_�ˌ����Ƀt���g���F���O���[�Ƃ����i���X�������������������Ȃ����悤���B������X���ɐF�X�ʐ^���\���Ă���
�o�C���C�g�̑�������̓C���`�L�H�삾������
�������炢���ɂ��Ƃ��Ă����悤�Ȋ�����������
���������Q�l�v�����Ĕ����Ă���
�Q�l�v�����낤�������낤�����e���ǂ���Ή�����͂Ȃ�
���������b����Ȃ���
���t�O�Ɋy���ɐ��������Ă�̂����n�[�T����������̂��̂��Ƃ���
>>93 1954�N�Ձ@�I���t�F�I����o�Ă�
�g�c�G�a���������Ƃ��̂���
�����A�^����Ԃ͂��܂�ǂ��Ȃ�
����54�N�̃t�B���n�[���j�A�ǔՂ͂������Ȃ̂�
�o�C���C�g�̑������b�O�����łɘ^�����Ƃ����Ƃ������x����������ɐ_��������鎖�ɁA�Ղ͎���Ŕ���c�����B
�t���g���G���O���[�����܈�N�Ƀo�C���C�g���y�ՍĊJ�̏����ɉ��t�������Ԃ̃��R�[�h���ƁA���ɂ͒x������悤�Ɏv����B�ނ̖��S�l�̘b�ł́A���̉��t��̗����A�ނ��Ԃɏ悹�ċA��r���Ńt���g���F���O���[�͎Ԃ��~�߂Ăق����Ɣޏ��ɗ��B�O��́u�Ђǂ����t�v����������邽�߂ɐV�N�ȋ�C���z����������ƁB���̈�b����킩��悤�ɁA�^���ȃA�[�e�B�X�g�͎����̎d���ɖ����ł��Ȃ����Ƃ��������̂��B���Ԃ̑��y�͂ɂ͒����R�[�_������B���̃e�[�}�́A���̐��ɂ������Y���B�����ăR�[�_�́A��]���������ɑ����s�i�ȂŒ��ߊ�����B�y�͂̍Ō�Ńe���|�𗎂Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�s�ӂ����悤�ɓ��˂ɁA�������I���̂��B
�����̘^���Z�p�͎��̈������̂����������
�t���g���F���O���[�͓������ۂ��Ă��������������������Љ���Ɩ��̕���I��ł��܂����B�D�_�s�f�Ȑ��i�ŐU��ꂽ�l���������낤
�ǂ��ł͂Ȃ����B�Ȃɂ��`����g�����ň�������̂ł͂Ȃ��B
�t���x�����^���ɗ������铪��������������Ɨǂ��^�����c������
�J�������ɏo�������Ƃ��t���g���F���O���[�ɂ͏o���Ȃ������B���R�[�h�Ɋւ��Ă̓J�������������Ɛi��ł����B�J��������ь�������傫�ȗv���ƂȂ����͂�
�A���Z�����̕���3�ΔN�ゾ���A�A���Z������葁���͂�đ������B
�t���g���F���O���[�̃R���T�[���Ċ��������o�[���X�e�C����
�t���g���F���O���[���a135�N�L�O�A���p�����[�X�p�ɘ^�����ꂽ�������܂Ƃ߂�CD55���g����
https://www.cdjournal.com/main/news/wilhelm-furtwangler/92104 �@20���I�ł����Ƃ��̑�Ȏw���҂̈�l�A���B���w�����E�t���g���F���O���[�̐��a135�N���L�O���āA�ނ̃X�^�W�I�^�����ׂĂƁA���p�����[�X�p�ɘ^�����ꂽ���C���������A2021�N�̐V���}�X�^�[�Ŏ��^����CD55���g�̃{�b�N�X�E�Z�b�g�wThe Complete Wilhelm Furtwangler on Record�x��9��24���i���j�ɔ�������܂��B
�@�����ɂ́A1926�N�ɘ^�����ꂽ�x�������E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�Ƃ́u�E�F�[�o�[�F�̌��w���e�̎ˎ�xOp.77�`���ȁv����A1954�N�ɘ^�����ꂽ�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�Ƃ́u�x�[�g�[���F���F�̌��w�t�B�f���I�xOp.62�i�S�ȁj�v�܂ŁAWarner Classics�J�^���O�i��HMV-EMI��Telefunken�j��Universal�J�^���O�iPolydor�ADecca�ADeutsche Grammophon�j�̉��������^����Ă���ق��A1950�N�ɃE�B�[���E�t�B�����w���������o�����i�uJ.�V���g���E�X�F�c��~���ȁv�ق��j��A1950�N10��1���ɃR�y���n�[�Q���Ńf���}�[�N���������^�������������́u�V���[�x���g�F�����������ȁv�Ƃ������M�d�ȉ��������^�B�f���}�[�N���������^�����u�V���[�x���g�F�����������ȁv�͂��Ƃ��Ə��p�����[�X�p�ł͂Ȃ��B��̃��C���^���ł����A���ʂɎ��߂��Ă��܂��B
�@�e�f�B�X�N�̓I���W�i���E�W���P�b�g�̃f�U�C���ɂ�鎆�W���P�b�g�ɕ����B���������160�y�[�W�̃u�b�N���b�g�i�p��A����A�ƌ�j�ɂ́A�t���g���F���O���[�Ɋւ���G�b�Z�C�Ƒ����̎ʐ^��A���^�����̘^���� / ��� / �^���X�^�b�t / �}�g���b�N�X�ԍ� / ���̃J�^���O�ԍ��Ƃ������ڍׂȃ��X�g�Ȃǂ��f�ڂ���Ă��܂��B
�ڍ�
Warner Music Japan
https://wmg.jp/wilhelmfurtwangler/discography/24779/ >>114 �v���Β���ނ����̎����ɉ���̂͊��
>>114 �{���ɂ��������u�����v�߂��������������l���������Ȃ�
����͋ɂ߂Ĉ����Ȍ��߂��������Ǝv����
�u�i�`�̎c�}������v�Ƃ��A���̘A�������i�`�̗v�l
�B���ǂ������Ă��������l����A���łɑR���댯����
�Ȃ������������ǂˁB
�c�}�̕������T�h������Ă����낤��
�o�[���X�e�C�������_���l�łȂ���t���x���͉���Ă����Ǝv��
�펞���x�������E�t�B���ɂ��M�S�ȃi�`�X�}����13�l����
>>121 �����B�펞���̘^�����Ȃ����A50�N�̃����O���Ȃ�
>>121 �Ƃ肠���������B
2011�N���}�X�^�[�Ɣ�ׂĂǂ�ȓ���������̂��A�b��̂��̋ȁA���̋Ȃ̏o���͂ǂ��Ȃ̂��A�����Ă݂�������ˁB
>>122 50�N�̃����O�������̂́A�}�X�^�[�e�[�v���`�F�g������̂��̂�����d���Ȃ��Ƃ��āc
53�N�̃����O�������͈̂�̂ǂ������� �R(`�D�L)�
2011�N���}�X�^�[��SACD�n�C�u���b�h�����Ղ����A�����ɂȂ�Ȃ��ƌ��ē��������H
����membra���������A107���̃{�b�N�X���o�������Ƃ��l����ƁA��͂�55�������ł͉͗ߕs���B
�풆�^���S�W
�����������爤�D�Ƃ�������Ȃ����A���D�ƂƂ������̃��^�͊��Ɏ����Ă邩��ˁB
�t���x���͂�������n�Q�o������?
�X�J�����ł̎w�A�X�e���I�^������Ă����̂ɂ͋�����
���������ɃX�e���I�^�����Ă��猾����A���̒�\��
>>128 1950�N�̃C�^���A�ŃX�e���I�^���H�H�H
�ɂ킩�ɂ͐M�����������A�ǂ��\�[�X�H
�W�O�N��ɃL���O�ŏ��o�̂Ƃ��A����Ŏg���Ă���B
�t���x���̋����X�e���I�͎w�̑��Ƀt�����N���c���Ă�
>>128-132 �X�J�����̎w�̏����Ղŕ�������킸���ȃX�e���I���́c
���m�����e�[�v���X�e���I�p�@���CD�������Ƃ��ɕ������鍶�E�̈ʑ�����������������Ă���ɉ߂��Ȃ��悤�ł��ˁB
�v�́A���E���~�b�N�X���Đ^�����m�����ɂ����Ƃ����ڂ������ʂƂ��Ă̎��R�����I�^���X�e���I�̂悤�Ȃ��̂ł��B
T���搶�̎u�̍����ɂ͖��x�Ȃ���h������B
���ŋ�YouTube�ɃA�b�v���ꂽT������̓���̒��ŏЉ���
���̐l�ǂ������o���Ȃ́H�����̃��R�[�h�}�j�A�H
�{�E�͎w���҂ŁA��p�Ŋ������Ă���B
EMI�̃X�e���I���^���̓t�����F���v���1955�N�i�j�R���C�E�}���R/�t�B���n�[���j�A�j��
�{�E�w���҂��ă}�W�H
T������̓l�[���A�p�[���H�̗��������B�Ɏt�������v���̎w���҂���ł���B
���{�͂��납���ĂŎw���������Ƃ��Ȃ���p�ł������ĂȂ��Ƃ������Ƃ̓A�}�`���A���x���̎w���҂��t���g���F���O���[�ňꔭ���ĂėL���ɂȂ��Ă�낤�Ƃ������_�Ȃ�ˁH
�ꔭ���Ă邱�Ƃ��o���Ȃ����\�ȃU�R�����i���Ă₪��
>>143 �����ł���Ȃ��ƌ�������Ȃ���A���B
���̏������݂̋L�^�͉i���Ɏc��B
����Ȗ��_�����̑ΏۂɂȂ�悤�ȏ������݂�����
���Ƃ��v��Ȃ��̂��ˁB
�{�l���H
����������
>>138 >>141��������{�l�������肵�Ă�
>>143 ���Ԃ��p�ł�����͂��ĂȂ���
�������Ă��o�Ă��Ȃ�����
���l���Ȃ߂邱�Ƃ����\���Ȃ��N�Y
�������̐l�B��������̃X���ɒ���t���Ă���́H
�u2�����˂�t�����F���X���ɕ��\���v�݂����ȓ���グ�Ă�
�u�������߂ɂ�������イ�o�邯�lj��҂��낤�v���Ďv�������
(-) �`�����l�����������߂ɕ\�����Ȃ�
����ς�{�E�ŃT�b�p���ڂ��o�Ȃ�������Ď�Ŗڗ��Ƃ��Ȃ�Ďד�����ȁB
�G�����ӂ����ăx�^�x�^�\����Ă�̂̓`�����R����
>>156 ���l�ɂȂ肷�܂��Ď���age���Ă������100�{�}�V���Ǝv����B
�������Ă�˂���A�o�J�`����
�����ԓ��ł����I�E���Ԃ����邾���̃o�J�`�����Rw
������{�E�͉��Ȃ�
���l�̐E�Ƃ̎��ł˂��A�悭����Ȃɂ˂��A�L�[�L�[�L���[�L���[�˂��i�j
>>162 ���l�̐E�Ƃ̂��ƂŃL�[�L�[�L���[�L���[�����Ă���̂�
�����̌��݂̐E�Ƃɗ������Ă���낤��
�t���x������̌����ȑ�2�Ԃ͑f�l���x���̑ʍ�
�����Ȃ̑��ɂ̓s�A�m�d�t�ƃ��@�C�I�����\�i�^���Ԃ�������
�s�A�m�Ɗnj��y�̂��߂̌����I���t��
��Ȃ����Ďw�������鉹�y�Ƃ̓x�[�g�[���F�������߂Ă�������?
����̃t�����N�͕ʉ������m���V���N�������ăX�e���I���ʂ܂�����ˁB
�Â����͕��w����
�^�R�u�͑�p�ł����d�����Ȃ��Ƃ����A�}�`���A���x���̕��w���ҁB
>>165 �ēc��Y�ɓł���Ă�̂�������Ǒf���炵�������Ȃ���B
�����͓�=�V�_�̂�肸���Ƃ悢�B���E�ň�Ԕߌ��I�Ȍ����ȂƂ��N�����J�߂Ă��������Ɣ���邩���B
������������ȑ�����Ȃ��f�l�ɏ�����킯�Ȃ�����B
������Ƃ͎u�̍������Ⴄ�B������̋Ȃ̓��[�h�I�����B
�w������Ȃ��A�}�`���A���x���B
�Ђ���Ƃ��Ď��̃��R�|�̃t���g���F���O���[���W�ŋN�p����Ēm���x�グ�ăV�e�B�Ƃ��j���[�V�e�B�݂����ȍ����ʃI�P�i�o��_���Ă�̂�������ǂƂĂ������ł���B���͂�����肪�y�o���Ă邩��͂̂Ȃ����[�g���Ȃ�Ă��ĂтłȂ���B
�V�_�͎�����
>>173 >�Ђ���Ƃ��āE�E�E
���Ȃ��ϑz�Ȃ��肻�����ˁB���������l�ɖڂ�t������Ɩ��Ȃ�ȁB
�ց[�A�s���{�l�����W�҂����m��Ȃ����ƃz���g�ɏ��Ă��😱
>>121 ���̃G���C�JLP�͌���Ղ������Ǝv������
���߂ɓ��肵���ق���������
�Œ���̑̌n�I�Ȓm�����Ȃ��̂Ƀ������B�̒�q�Ƃ������ĊC�O�̃A�}�I�P�ɖ��ʂȎ��Ԃ��߂������Ă�Ƃ������Q�҂�����ł��傤���Ȃ�
���\�̑㖼���݂����Ȑ��{�q���ł���ꉞ����o�Ă邩���
�t�����X�ɗ��w���āA�u�U���\���łQ�����܂Ői��ł�݂���������A�}�Ɣ�ׂ�͎̂��炾��
���N�قǑO�ARS3D�Ƃ����Ǝ��̕����Ńt���g���F���O���[�̃��m�����^����
>>180 ����}�W�Ȃ́H�t�����X�Ő��K�̉��y����ے��C�߂����Ă��ƁH
�}�W�Ō����Ă�Ȃ�\�[�X�o��
��������������
�Ƃ������u�������B�Ɏt���I�v�݂����Ȃ�����Ƃ����o������Ȃ���
�������������Ƃ����̂������Əo���Ăق������
>>182 �ȁ[�ɂ���������������B��Ȃ����Œ��ׂ��A���\�B
���O���w���Ƃ��y��ł���̂��܂��ؖ����Ă���搶�����B
�܂������Ő搶�f�B�X���Ă�͉̂ߋ��ɂǂ����Ř_�j���ꂽ�z���낤�ȁB
�{�l���Ǝv������{�l����Ȃ��̂�
�R���R�ƌ������Ȃ����������������
>>184 �搶�̓����S���`�F�b�N���ĂȂ��ă\�[�X�o���Ȃ�ăL���O�I�u���\���ȁB
�t�����X��Ō�������A�������B
�������{�E�̎w���҂�YouTube�Ń��R�[�h�G�k���Ă̂�����͂���Œɂ��˂�
>>187 �p�C���b�g�ɂȂ������L���w���҂����܂�����A���͂⎞��̗��ꂩ��...�B
�����������N�̃��R�|��FM�ԑg�̌���ɂ���ȉƁA�w���ҁA���y�w�҂Ȃ�
�吨�́u�{�E�v�͂�������Ⴂ�܂������ˁB
T���搶�̔ԑg���L�v�Ȃ̂́A�w���E��ȁE�I�^�N��3�ʂ��烌�R�[�h�̖��͂����
����܂�2ch�ł�������Ȃ������悤�ȃR�A�ȏ��ɂ����y���Ă���Ƃ���B
���̒��ł��t�����N�̃X�e���I�͒��W���̃N�����^�̖��̎����ł����B
�ȉ��̏��Ɍo����������Ă���B
http://www.furt-centre.com/osirase/200409_12RecordConcert.htm �v�_�������ʂ��Ă����B
�������y��w��w�@�C���A1997�N�t�����X���w�B
�}�����]���������y�@�Ŏw���E��Ȃ��t�����V�[�k�E�I�[�o���Ɏt���B
1999�N�A2001�N�u�U���\�����ێw���҃R���N�[�����I�A�Z�~�E�t�@�C�i���X�g�B
�����H�F�쒿�̌�y�����B
��w�̌�y�͐�y���̂���̂��펯�Ȃ̂��H
T�����t���g���F���O���[���n�Q�F�ł�������Ȃ���
>>189 ���̒��x�̌o��������{���ƃA�}�I�P�������Ăт���Ȃ�����B
�u�U���\���͓��{�l������10�l�D�����Ă邪�S�����₭���Ă�킯����Ȃ��B
����̂ǂ��݂����ɐ����̂������w���҂��������邩��ȁB
�v���I�P�U���Ă��S�c��h�ƃZ���^�[���݂̐l�Ԃ������ɂ��邾������H
���O�璮���ɍs���Ă��̂�w
>>191 ����I�P�Ƃ���y�ɂ͐�Ε��]����B
�j�n���Ƃ����������ȁB
����Ȃ�ĉ��t���y�ɂ����Ƌt�炦��B
��������̐l�����͌��������Ɛ����݁[��ȃR�[�z�[�ɕ��]���Ă����̂�
ID:GPKc1lw6 �̑����Ă鐢�E���ĕ|���B
�����̏������݂͏�ɓi�݁E���݁E���i�����Ȃ�����킩��₷��
>>199 �\�����ώ@���͕J�L�R���邨�O����
���l���C�ɂȂ��ċC�ɂȂ��Ďd�����Ȃ�
�A�m�l�����̒��Ԃł���
���Ƃ���ł��Ȃ��̉��y�I�Ȍo�����Ăǂ�Ȃ��̂Ȃ́H
�Ƃ������}�g���ȉ���o�Ă��̒��x�̉��t�ɂ����Ȃ�Ȃ��̂�
���Ƃ���ł��Ȃ��̉��y�I�Ȍo�����Ăǂ�Ȃ��̂Ȃ́H
>>201 >>203 ���l�ɐq�˂�̂Ȃ�܂�
�����̌o���������̂���V���낤
�����������A���̂��悤���Ȃ�
5�����˂�ʼn���ړI�ɌJ��Ԃ��Ă���̂��H
����́A�ʔ������Ă���c�t�]���N����������A�y�b�B
�R�[�^���[�������̃C���^�r���[�ɂ��������ǁA�R�[�z�[���Ă������̊w���̗L�n���琥��}���c�[�}���ŋ��������ƌ�����قǍ˔\�����������Ă��B
�t���g���F���O���[�͐��K�̒�q����Ȃǂ���������o�Ă��Ȃ��B
������o�Ă��Ȃ��̂ɁA�s������̂��Ƃ��u���y�̊�{�I�������ł��Ă��Ȃ��v
>>205 �̂��Ǝv����l�̌��t��`���ʼnL�ۂ݂��āA�y�Ȑ������ł���
>>207 �|�p�͌o���łȂ����ʂ��S�Ă��Ēm��Ȃ��̂���
�s������̂��Ƃ��u���y�̊�{�I�������ł��Ă��Ȃ��v
�y���͓ǂ߂Ȃ����A�y����ł��Ȃ��E�E�E�Ƃ������Ƃł����i�j
�t�����X���w�������ăG�R�[���m���}���Ƃ�����Ȃ��ĕ��������ƂȂ����傾���A��p�Ŋ�����Ă̂���p�̊����̖���I�P����Ȃ��O�V����݂����ȋ������Ƀ��C�V�����ċ��o���Ă������
>>196 ����I�P�Ƃ���y�ɂ͐�Ε��]����B
�j�n���Ƃ����������ȁB
...�B�I�c�����ǂ����싅�]�݂�������( �L,_�T�M)�߯
���y�̘b�ł���B��w�싅���Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��H
���Ȃ��̑�D���ȃR�[�z�[�搶��낵���A���̎w���ґŐ��ł��ϑz���ĂĂ��������B
���ς�炸�A�z�ǂ������g�̖����A�z�ȉ��V�����Ă����wwww
135�����肩��s���M�҂����̃X���łs����_�i�������悤�ƍH�삵���玸�s���ĉ��サ��������݂�����w
�܂��s���{�l�~�Ղ̉\������Ȃ��ǂˁB
T������̐����̃��x���͂ǂ�ʂȂ́H
���y�Ƃ��Ăǂ��݂Ă��̈��n����B
�w���҂��Ė_��U��Ă��邾���Ŋ���������
���y�Ƃ͑̈�n��
222�Q�b�g������������킴�Ə������ޒ�\��w
�Q�Q�Q�Q�b�g�ł��Ȃ�����������킴�Ə������ޒ�\����
�����A�X�e�C����Ȃ݂̓��]��
�y�����ǂ߂Ȃ��̂ɑ����������Ȃ���
>>224 �����I�E���Ԃ��������\��
�S�p�ŏ������݂���Ƃ���͂܂��ɒ�\���̃`�����s�I������www
���w�^�N�\�ȃA�}�I�P�ɐ��t�y���̌ږ�x���ɂ�
���y�̐�勳��Ċy����B�҂Ŏw������Ȃ����邨���ł��A���y���ۂł킩���Ă��Ȃ��Ƃ�����́A��������悤�ȋC�����܂����ǂˁB
�A�}�I�P�w���҂�[�`���[�o�[���낤�ƁA���呲�Ƃ��ĉ��y�ŐH���Ă�Ȃ�\���������Ƃ��Ǝv��
>>230 �������呲�ƁA��������w�A�{�ƕs�U�ł���炵�Ă�����͉̂Ƃ����������X�|���T�[������Ƃ����̂����ʂ̑z������
���������̂͂������
���ʂ͒p������������youtube�����Ŏ��ȘI�o�Ȃ�Ă��Ȃ�����
���ƍD���ȃ��[�`���[�u�ŁA�ʔ�����
>>232 �c�t����������Ă��݂�ȍ��邾������
>>231 ���͏���ɒp���������v���Ă����������
������ʔ����q�����Ă���
>>234 �c�t�̍����͂���������A�c�t��1000���l���Ă��A���̗͂��Ȃ��A������Ƃ������ƁA��̂��猈�܂��Ă���̂ŁB
>>235 �ׂɎ��������ɗ͂�����Ƃ��v���ĂȂ����������Ă����Ȃ�����
���������Ǝv���Ȃ疳�����Ă���Č��\
�o�C���C�g 1951�N�̑��A�ǂ��������n�b�L�������Ă��ꂽ��t���g���F���O���[�̕]�_�Ƃł����Ǝv�����ǂȁB
�R�[�z�[���Ȃ��̂͂����Ƃ��Ă��S�c�̑{�����C�V�����Ď����グ��̂����Ƃ��B
�t���g���F���O���[����
>>239 �݂�Ȓm���Ă��
����������
T���̐��z�M�̂Ƃ��K�������K�O���o�Ĉ̂�����CD�̉����R�����g���������݂����猩�Ă��Ȃ�
�^�R����͉��y�Ɓi�w���ҁA�w���ҁj�Ƃ��Ă̓S�~
>>242 >>243 �\�����ώ@���͕J�L�R���邨�O����
���l���C�ɂȂ��ċC�ɂȂ��Ďd�����Ȃ�
�A�m�l�����̒��Ԃł���
�����ώ@�A���̕�����
�܂�A���ȗD�z��f���o�����������铹�̂Ȃ��X���N�\��Y�Ƃ������Ƃ�ww
>>244 ��l�̉��y�Ƃ��S�~�Ă�肷��̂ł����
���̎w���҂̉����ĉ������ł��邩��������Ȃ���
�܂��������Ȃ��ŃS�~�Ă�肵�Ă��Ȃ�����H
�r���ő����Ă��܂����B
�W�����A�[�h����w�����Ăǂ����̃X���ɏ����Ă���������
>>246 5�����˂�ł́A���̐l�Ɍ��炸
�t���x�����J�������������^�[���g�X�J�j�[�j��
�`�F�����o���X�^���A�o�h���T�h��
�E�m���R�o�P�����A���̑���������̉��y��
�S�ăS�~�Ă��̑ΏۂȂ��
���̐l�ɂ���������肩�������ȂǂƂ���
���������͓̂�����Ȃ�(��)
>>249 �����̖��m�ƌ���S0���������Ă����܂Ńh�������Ă���Ӗ��A�܂���
>>238 ���܂��A�����������B
>>253 �ǂ������H
�����������H
�ǂ����ł��ꂽ�̂��H
����ȏ��������O�̐S���₳���������Ă����̂�����
���X�ݕ��̋�������葼���̐S�Ő��i���邪����
�ׂȐS���瑼�l���ׂ�Ă܂ł��˂������悤�Ƃ��Ă͂�����
���̉Ђ͎������g�ɍ~�肩�����Ă��邾��
�ЂƂ��ɐg����o���K
�^�R����䥑��ɂȂ��ē{���Ă�😡�̂���
>>246 ������Ђǂ��͉̂����@�A�}�I�P�Ƃ͂����ӏ܂ɑς��Ȃ�
�S�����K���ĂȂ����x�����Ǝv�����ǂǂ�Ȏw���������̂��{���ɋ^��
�u�Ƃ肠�������킹�Ēe���܂��v���x���ł����Ȃ����ǂ���Ȃ̑f�l�̎w���ł��ł����Ȃ�
���̐��́u�����ɑ��Ă̓m�[�^�b�`�v�Ȃ�
�w���p���f�l�̂���@�������悤�Ƃ���Ɨ������痐��邩�牽���ł��Ȃ�
���R���˂ɗ���Ă��I�P�͂��Ă����Ȃ�����I�P�ɍ��킹�ĐU���Č떂�����Ă�
�܂��ɑf�l�̓������̂��́@���̑O��CD�ɍ��킹�ĐU��u�w���^���ҁv���{���̃I�P�̑O�ɏo��Ƃ����Ȃ�T�^
�������g���ǂ�ȗ��K���Ă�H���i�̗��K�Łu�ǂ��U������ǂ��Ȃ邩�v�w�K�����I
>>256 �܂����A���Ȃ��̂��̈ӌ��́A�s������̂ǂ̓���̂ǂ��̕�����
���Č����Ă���̂��A��������Ă��炤�K�v�������ˁB
�����URL�ƁA���̓���̉������b�̏��Ȃ̂��A�����Ăق����B
�i���悶��Ȃ�������A�b�c�Ƃ��c�u�c�Ȃ̂��H�j
���ƁA�u�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v�Ƃ����̂�
�悭�킩��Ȃ��B�����Ƌ�̓I�ɐ������Ă���i����̉������b
�̏��Ȃ̂������āj�B
���ꂩ��A
�����̐��́u�����ɑ��Ă̓m�[�^�b�`�v
�Ƃ����̂��悭�킩��Ȃ��ȁB�s���������Ɋւ��Ă͑S�����ڒ��ŁA
�ǂ�Ȃɉ����������Ă��A�ق����炩���ɂ��Ă���Ƃ������ƂȂ́H
�u�����Ȃ��ł��������]�v�̓T�^����
>>257 ��^���Ԃ����邾�낗
�{�l�H����Ƃ��M�҂݂����Ȃ̂�����̂��H
������ł��オ���Ă����ǂ�ł������
>>256 �̂Ƃ���Ȃ͕̂����邾��
���M�Ȃ����ȃt���t���w������̃w���w�����t
�w���҂��t���t�����Ă邩��e���|���ɂ����Ă����Ȃ�낤��
���������Ęa���ȑO�ɗႦ�J�����j�R�t�̖`���Ȃ��j�]���ł��A��������ȁH
�A�}�I�P���w�^�N�\�Ȃ͎̂w���҂̐ӔC�����H�v���̎w���҂Ȃ�H
�{�l�Ȃ�ǂ�ȗ��K�������Ȃ��ƂɂȂ�̂������Ă���܂��H��
�Ƃ肠�����A�ЂƂɍi���Ă��A
>>260 ������߂��@�������瓚�����
����Ȃ�T�̃_�������ڍׂɕ��������̂��H�A���`���H
�]�_��Youtube�ɉ����āA
�����炭�s�����͎w���҂ɉ����č�ȉƂł�����̂ʼn�X�ƈ���ăt���g���F���O���[�Ɍ���Ȃ��߂��B�����Ƒ��h����ƌ��������̂ł͂Ȃ��̂��ȁB
�x�l�Y�G���̃t���g���F���O���[���Ă�����
���{�̃t���g���F���O���[��
>>266 ���ɂȂ�����
�G�h�D�A���h�E�`�o�X�Ƃ����l�̂��ƂȂ�
�J�����X�E�p�C�^�ł͂Ȃ�
�p�C�^�̓A���[���`���������
�e���Ŕh������B
��p�̃t���g���F���O���[�A���x��A�{����������グ�n�߂����ǂ�������������肽���낤�H
�Ճm��EDHC�n�̐l�����Ƃ̏������C�A�i�C�[���Ȍ𗬂�
�i�C�[����🐙🐙w
�ŋ߂̑��I���W�̓���͌ӎU�L��
����ȂƂ��܂ŏo�Ă��Đ�`����邵��
���͈������ă����^�[�@
🐙�̓Z���^�[�ōu�������Ă�̂�
����Ȃ̂ɒ��点��Z���^�[�̒m����
�Z���^�[�͉��̎g�r���s�����ʼn���������ȁB
�E���j�A����̐l�ɂ����点�ĂȂ����������H
���x�o��55���g��Art & Son Studio 192kHz/24bit���}�X�^�[������
�z�M�ŗ~����
>>280 ����������Ȃ������A��������ē������̂낤�Ɣ��낤�Ƃ���B
���܂�����
�����@��ł����܂�A32bitch�̎���Ȃ̂����A�A�A
bitch�Ƃ�
�r�b�`�͂�������20��܂ł��
T�����ɂ��ẴA���`�ӌ��́A�����炭�w���ɂ��Čo�����������A
>>289 �܂������Ă�̂��@�{�l�H�M�ҁH�A���`�H
���ł���������A�}�I�P�ł��w���I�P�ł�T�̉��t�ƒ�����ׂĂ݂��
����ŏI�����邾���̘b��
������x�������ǃA�}�I�P���w�^�N�\�Ȃ͎̂w���҂̐ӔC�����H
�v���̎w���҂Ȃ�H
�ꐶ��������Ă�t�҂����ɐ\����Ȃ��Ǝv��Ȃ��̂��H
�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���E�E�E��
>>289 �����̓t���g���F���O���[�̃X����
�����̓C�J�T�}���w����T�������X���ł͂Ȃ�
���O��T�����^�Ȃ̂Ȃ��X������Ă������Ō���������
�t���g���F���O���[�̃X����T�������Ȃǘ_�O�I
���O�̂���Ă鎖�̓t���g���F���O���[��`�����Ă���
�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���E�E�E��
T���̓t���g���F���O���[���t���b�`���C�Ɏ��Ă���B
�N�[�x���b�N��V�����e�B��������
�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���E�E�E��
T�̘b�������l������H
Youtube
Youtube
�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���E�E�E��
>>288 �����EMI�J���[(AI�����H�j�ł������������B
DG��33CD BOX�́A�ǂ��Ȃ������B
�͏㋦���90�̉��������������ŌnjR�������Ă邾��������Z���g���Ɠ������̓V���Ȃ�ˁB
15�Έʁi���S���t���āA�F�X�킩��悤�ɂȂ�����̔N��j���傫���Ȃ��Ă���t���g���F���O���[�̎��������l��80���邩��A���������l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ�ˁB
���̎w���҉����璮���ėǂ��̂��킩���
>>305 ��r�I���^�̗����{�b�N�X����r
�P�D�x�[�g�[���F�������ȑS�W�iWarner�j
�Q�D�u���[���X�����ȑS�W�iWarner�j
������
>>306 �f�����������߂��肪�Ƃ�
�u���[���X����n�߂Ă݂܂��[
���T�C�g�̃������[�����������ƁA1�ʃo�C���C�g���A2�ʎw�A3��Andromeda�̃x�[�g�[���F���펞�^���W
�u���[���X�ƃx�[�g�[���F���̌����ȑS�W(Warner) ���ׂ���A�u���[���X�̕����o�����悭������B
�v���Ԃ�ɑS�W�̃x�g�V�����Ă݂�
�v���Ԃ�ɑS�W�̃}���y�����Ă݂�
>>300 🐙���͂��̃R�����g���\���ɂ����悤���B
�����ɓs���̈����R�����g�������Ȃ��悤�ɂ���🐙���A����Ă鎖�}�W���������I
���̃R�����g�ɏ�����Ă�ʂ肾����🐙���͔��_���o������\���ɂ��ē��Sww
��������A���h���Ǝv����B�N���V�b�N�E�����ނ��Ă��錻��Ŏ������犈�H��
��l�����A���ɔS�����ē�������̂����Ȃ��Ă������邪�A������
VPO�Ƃ�EMI���K�i���C���łȂ��j�x�g�܁A������ƈႤ������Ă邯�ǁu�����v
�������Ȃ�Ă낭�ȓz����Ȃ����
��💩������t���g���F���O���[�ɂ������ăW���X�J���f�v���Ȃ�Ă�邻��������t���g���F���O���[�𗘗p���Ă�̂�🐙������肶��Ȃ��ȁB
>>322 �G�����l�������Ȃ���B
���������ᔻ���Ă�����A�����炭���������YouTube��up����n�߂����́A
���{�̃v���I�P�̒���ɌĂ�邩�ǂ����͉��y�͂ƁA��͂�R�l�B
�u�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v
>>329 ���ɓI�Ă���B
�o���҂���Ȃ��Ƃ킩��Ȃ������B
>>331 �ł͋M���Ɏ��₷��B���̂悤�Ɍ�������ɂ́A�������w������
�I�[�P�X�g���̉��t�̓�����M���͌��Ă���Ƃ������ƂɂȂ��ˁB
����ł��A�ǂ̓���̂ǂ̕����Ɂu�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v���Ƃ�
��̗Ⴊ����̂��A�����Ă����B�����url�Ɖ������b�̏��Ȃ̂��B
���͕ʂɓ�������̃t�@���ł����ł��Ȃ����A���������Ȃ��ōD�������
���ƌ�����������Ȃ�ˁB
>>326 ���ɓI�Ă���B
�o���҂���Ȃ��Ƃ킩��Ȃ������B
🐙����̊G������D����������Ɍ����������A�m��Ȃ��l�̈������J��Ԃ��悤�Ȃ疼�_�ʑ��ői����ꂽ�畉�����Ⴄ�̂ŁA�K���ȂƂ���ň����Ƃ��������B
>>332 >���͕ʂɓ�������̃t�@���ł����ł��Ȃ���
��
���l�ɂȂ肷�܂������肾�낤���{�l�o���o������w
>>336 >���������ɂ��땳�w����🐙
>���O�͐l�ԂƂ��Ă��Œ�̕�����
>���O�̉��t�ȂǕ������l�[���A�����͎̂��Ԃ̃��_
���̕��͂������YouTube�̓���̃R�����g���ɏ�������ł���B
��������Γ�������{�l�Ɋm���ɓ`����B
���ł����5ch�ȂŃl�`�l�`�ƈ����������Ă���B
��������{�l�ɒ��ڌ����������낤�B
���āA�ł��邩�Ȃ�
��p��20�N�����Ă��̒�x�����Ⴈ�b�ɂȂ�Ȃ�������
ID�ς��đ�O�҂ɐ��肷�܂������{�l�̏������ݎ~�߂�₤���[��
Youtube��T���̎w���݂Ă݂����Ǎ����ȁB
���x�o��55���g�̏ڍׂ����\����Ă邯�ǁA���̃f�[�^���z���g�Ȃ猋�\�ȋ����Ȃ��ǂȂ��B
>>345 �`���C�R�̌��Z����3�y�͂͊���EMI�`���C�R�t�X�L�[BOX�Ɏ��^����Ĕ����ς݂��B
>>345 ���܂������Ƃ́A������
>>345 Shin-p�̃T�C�g��M���Ă�̂��H
���x���Ⴂ��
Shin-p��CD�ȍ~�̎������m��Ȃ����h�f�l
�����Ă���e�����������������W�߂Ă܂Ƃ߂Ă邾��
Shin-p�͌����Ƃł����ł��Ȃ��P�Ȃ�h�f�l
>>345 ���U�����f�ԑt��3�Ԃ̖������ƌ����Ă�29�N�Ղ́A
CD�����ɉpSYMPOSIUM���畜���Ղ��o�Ă���B
>>349 �@SYMPOSIUM�Ղ͌���1930�N�ՂƓ������Ă������_����Ȃ����������H�������̃f�B�X�R�O���t�B�ł������Ȃ��Ă�B
�A���X�BSYMPOSIUM�Ղ���NAXOS���C�u�����[�ɓ����Ă�����茳�̂�iDG�Ձj�ƒ�����ׂĂ݂����ǁA�ԈႢ�Ȃ������^������B
���U�����f1929�N�^���͎c���ĂȂ��̂�����
1944�N�̃G���C�J�̓E�B�[���t�B�������A��������ƃ\�A���e�[�v��ڎ������킯����Ȃ��ȁB
>>354 �E���j�A��VOX���h�C�c�A�I�[�X�g���A�̕����ǂ���^���e�[�v������ă��R�[�h�������B
�悭�m���Ă鎖�Ȃ��ǂȁA�A�A
�E���j�A���ꂳ��́A�L���]�_�Ƃł�...
>>355 �������B�E���j�A�Ղɂ��Č�������ƃ��j�R�[�����ǂ������A�t���g���F���O���[�v�l���̂Ȃ̂�
�������Ă��܂����B
���Ȃ݂Ƀs�b�`�̖��A���R�[�h�ł̓����f�B�A�ȊO�͑S�ŁBDXM�Ƃ�����ŏC�������́H
�I�[�X�g���A���h�C�c�ɕ�������Ă����Ƃ�m��Ȃ��y�����邱�Ƃɋ���
�E���j�A��VOX���^���e�[�v����������͊��ɐ��ŁA
�x�������̃e�[�v�͐�シ���Ɏ����Ă��ꂽ�̂ł͂Ȃ�
�E���j�A�̃G���C�J�A�̂�LP�ɓ����ł���������
�E���j�A�̃s�b�`�͂���������A��������1939�N�ɍ��ۓI��440�Ɋ�����߂Ă���A
�����������e�N�j�N�X��1200�͏d��
CD�ł�CDJ�ł���
>>365 ���Ȃ݂ɃJ�[�g���b�W�͉��g���Ă�́H
���m�����J�[�g���b�W�H
�E���G���̃s�b�`���������ĉ�Hz�H���Ȃ�ŏ��̈ꉹ�ő���\����Ȃ����ȁB���ꂪ
>>368 �σz�����̂Ƃ���u�z�����v�ɂȂ��Ă���̂ŁA���������ł��B
�I���́A�s�`�R���t���^���e������A
�S�R�����ɂȂ��ĂȂ��ˁA�u�X�y�A�i�ő���킩��v�u�q���g�v���w�`�}���Ȃ��B
����̐������œ��������������ȁB�N�������̂��ƃ`�N������w
>>374 ��
�{�l�̂����ɑ��l�ɂȂ肷�܂��ĉ������Ă�H
�����炨�O�̓_���Ȃ�
<<< �������悤�Ƃ���Ɨ������痐��� >>>
�Ȃ�œ{�����́H�w���҂Ƃ��ăo�J�ɂ��ꂽ����H
����A�o�J�ɂ����A��������̂͌|�l�̊�{
�w���҂��w����œ|�����ăJ�[�l���������H
�u �������悤�Ƃ���Ɨ������痐��� �v
�s���A�A�E�t�^�N�g�����܂��U��Ȃ���ˁH
�A�E�t�^�N�g�͕\������������ƍ��킹�邽�߂ɐU����́B
����ĉ��Ɂu�A�E�t�^�N�g�̐U���������v�������Ƃ��Ă��A
����������Ă��āu�������痐���v�i�������痐��邪�n�܂�j
�Ƃ������Ԃ̔�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO ����͈ȑO�A�~�X�^�[�������f�B�X�����������w���̃J�����j�R�t
�̌����ȑ�1�Ԃ̓���B�`���Ŏ��̃A�E�t�^�N�g�̗l�q�������B
�������R�ɁA���ʂɃA�E�t�^�N�g��U���Ă���B���̃A�E�t�^�N�g
�̐U����ɑ��ăP�`��t���鉹�y�Ƃ�����Ƃ͓���v���Ȃ��B
�����������̕����A����ȊO�ɂǂ������U���������́H
�~�X�^�[������A���ɋȂ̓r���̂ǂ����Ŏ��̃A�E�t�^�N�g��
�U����ɃI�J�V�C�Ƃ��낪����̂Ȃ�A���̉ӏ��������Ă���B
�������b�̂Ƃ���Ȃ̂��B
�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO ����͈ȑO�A�~�X�^�[�������u���������������v�������Əq�ׂĂ���
�������̓���B�~�X�^�[������A�ǂ��Ɂu�������v�̏�ʂ�����́H
�u�������v�̏�ʂ�����̂Ȃ�A���̉ӏ��������Ă���B�������b��
�Ƃ���Ȃ̂��B����������Ȃ��ƌ�������Ȃ���B
�ŋ߂͂��O��N���X�����c�c���O�����f�B�X���Ă���悤�����A��������
�Ȃ�ˁB�n�������������͂ɏo������Ă邩��B
���ꂩ�炠�Ȃ����g�{���Ɂu�Ȃ肷�܂��v���悭�g����ˁB
���������Ȃ�˂�
374,375,376,378,379,380,381
�~�X�^�[�����̓g�X�J�j�[�j�X���ɂ��o�v���Ă���悤���B
�A�E�t�^�N�g�Ƃ������A�e���|��ς����Ȃ���
>�Ⴆ�t���[�Y�̏I���ŏ����e���|���ɂ߂悤�Ƃ��āH
>>390 ���ǂ��Ȃ��̌����Ă��邱�Ƃ́u�t�@���^�W�[�v�Ȃ�ˁB
�u�t�@���^�W�[�v������u��̗�́H�v�Ɠ˂����܂��ƕԓ����ł��Ȃ��B
���Ȃ�����5ch�ɏ������݂���̎~�߂�����������Ȃ��́B
���������炳�B�p������������A�~�X�^�[������
�����炾��������̗�͎����Ăق�����
��ؑ̈��̗��N����Ƃ������̂��A�h�n�b����u�����I�Ȑ�`�������ւ���ܗ��͂T�O����
�u�t���[�Y�̏I���Ńe���|���ɂ߂悤�Ƃ��ė����������v
�A�C���U�b�c����Ԕ���ɂ����w���҂̃X���Ƃ͎v���Ȃ��i�s���Ⱥج
�������̉��t�𑼂̃A�}�I�P�ƒ�����ׂĂ݂悤��YouTube�ł��낢�댩�Ă݂����ǁA���t�ȑO�ɃJ�����A���O�������������
�u �������悤�Ƃ���Ɨ������痐��� �v
������A���l�ɂȂ肷�܂��ĘA�����߂�����
�u ���Ƃ��}�E���g���悤�Ƃ��邪��̗�������Ȃ�����M�p����Ȃ� �v
���̑�p�̕ςȓ𗦂��ĊM������������������B���Ƃ��J�b�R������w
�������ǂ��̂ɂ�����肷������
�u �e���|���ɂ߂�Ƃ��ɂ͗������������Ƃ��K�v �v
��̗Ⴊ�o���Ȃ������炨�O�̕��������I�@��
>>389 �����͕�����Ȃ����lj����x��ĐU���Ă�悤�Ȉ�a���͂��Ƃ����Ƃ��邩����
���͂�����
>>406 >�����x��ĐU���Ă�悤�Ȉ�a���͂��Ƃ����Ƃ��邩����
�����t�ł͂Ȃ��A��������Ă��̂悤�Ɋ������ꍇ�ɂ́A
����́u�f���f�[�^�Ɖ����f�[�^�̃Y���v���l������K�v��
�����ˁB�������悭���ɂ߂Ȃ��ƁB
���Ǘ����͋�̗���o�����ɓ������̂�
���Ǘ�AV ayasa���͋�̗���o�����ɓ������̂�
���Ǒ��u�̓Z���^�[����Ȃ̂ɉ���ł͂Ȃ��ƉR�������ē������̂�
�u �������悤�Ƃ���Ɨ������痐��� �v
�����̃J�����j�R�t�����Ă݂�
��������J�l�B�����A
>>389 �ł̃e�[�}�ƂȂ��Ă���
>�Ⴆ�t���[�Y�̏I���ŏ����e���|���ɂ߂悤�Ƃ��āH
>�������������Ƃ�����ǂ��̑O����i���������Ӗ�
>�A�E�t�^�N�g���H�j���Ȃ�����ܘ_�����ł��Ȃ�T�͂���
>�����ƃI�P�ɍ��킹�ĐU��i�I�P�ɂ��Ă����j
���A�������b�̏��ɂ���̂��Ƃ������Ƃɑ���ɂ�
�͂Ȃ��Ă��Ȃ��ł��ˁB���ɏd�v�ȁu�������������Ƃ��Ă���v
�Ƃ�������Ɋւ��ẮA�ꌾ���G����Ă��܂���B
�������������Ƃ��遁�㔏����̐U��グ
�U��グ�ŗ������������Ƃ���w���̃e�N�j�b�N�̑��݂͔ے肵�܂��A
414�ɏ������ł���I
�u�J�b�R�����U������Ă�Ƃ���v���u�U��グ�ŗ������������Ƃ��Ď��s�����Ƃ���v
>>388 �����ł̓~�X�^�[������
>�Ⴆ�t���[�Y�̏I���ŏ����e���|���ɂ߂悤�Ƃ���
�ƌ����Ă���B���m�Ɏw���҂������̈ӎu�Ńe���|��ς��悤�Ƃ��Ă���s��
����ˁB������
>>416 �����ł�
>�e���|���ɂ߂悤�Ƃ��遁�w�^�N�\�Œx���
�Ƃ����}���ɂ��āA�w���҂̈ӎu�Ƃ͖��W�ȃe���|�̗h��Ɍ���������
���܂��Ă���B���邢��ˁA�~�X�^�[�����B
��L�̌����������s�Ȃ����̂�
���͓�������ł͂Ȃ��B�����A���̘b��ɂ��Ă����������������̂�
�G�ɕ`�����悤�ȗܖڔs���ɂ����̃X���b�h�͓����X������t���g���F���O���[�X���ɖ߂�܂�
�Ō�Ɉꌾ
���ǁA�����͑��l�ɂȂ肷�܂����܂܉R���ē������̂�
�v�����݂���ō������Ȃ��Ƀg���`���J���Ȃ��Ƃ��菑���Ă������瓖�R����
�������Ȃ��ɂȂ肷�܂��Ƃ������Ƃ������z�͎�������������Ȃ��Ƃ���Ă���낤��
���͎�������ɍ������Ȃ��g���`���J���ȍl���ł��������⑼�l�f���Ă���낤�ȁB
���̂�����̗���o���Ɩ₢�l�߂���Ƃ�������Ă邩�琫��������
T�u�̎w����youtube����Ō��Ă݂����A���t�ɍ��킹�ă^�R�x�肵�Ă���悤�Ɍ������B
���ǁu�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v��
>>438 ���̍r�炵�̃L�`�K�C�̓g�X�J�j�[�j�X���ł��������̂�\����Ă�
72 ���O�F�������̓J�̗x�� 2021/09/02(��) 20:08:40.10 ID:9yBkgsWx
���ǁu�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v��
�u�_���~�߂ĐU�蒼���ƐU��グ���x���v�Ƃ������Ƃ������̂�
�ꌾ�Ō����ƃA�E�t�^�N�g���U��Ȃ�
�Ȃ��Ȃ�
�u������v�̓���ɃR�����g��������ł݂�H
���t�����]���ꂽ�̂ɑ��ĕ����Ŕ��_���Ă��_���Ȃ̂ɂ˂��c�c
�u�������悤�Ƃ���v���āA�e���|���ɂ߂Ă������Ƃ�������Ȃ���ˁB
�Ⴆ�e���|���グ�Ă����Ƃ��̗�������̕���i���������̂���
��������ĕ�������
>>414 �݂����ɐ�������ĎS�߂ȋC�����ɂȂ��
�����܂ł��ē����̃_�������ڍׂɐ������Ăق����̂��H
���ꂱ�������̉c�ƖW�Q����
������������Ȗ{�l���Ƌ^���郈�C�V���i�v���̎w���҂���ł��悗�j�ƔS���i�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���j
������������Ȃ������Ƃ��Ă������͑���f���낤��
�����ق��@�ق�Γ����̘b�Ȃ��炭������Y����
�p��m���@�����̓t���g���F���O���[�̃X���Ȃ�
�ǂ����Ă��������Ȃ瓿���X�����ĂĂ������ł���
>�ǂ����Ă��������Ȃ瓿���X�����ĂĂ������ł���
����ς肱����
���ǂ����A�v�����Ō����Ă邾���Ȃ��
���������A�K���ɂȂ��Ăs����̓�������āu�e���|���グ�Ă��鏊�v��T����
�����Ƃ��̒��Ԃ̓X���r�炵����
�����Ⴀ�������������@��n�O
�u�e���|���ɂ߂�v�Ƃ��̋�̗�́A���Ƃ��ł����グ�Č떂���������ǁA
���낢��ƖZ�������炨���Ƃ܂����Ȃ������́H
����A�ɂɂȂ�����Ŗ߂��Ă����B�����������B
�܂��ł��ʏ�̃t���g���F���O���[�X���ɖ߂����痧��������肾���ǂˁB
�͂����߂�܂���
>>453 ���O��������L�`�K�C
�������ĒN���Ɏ��Ă�Ǝv������J�c�h���`�����l������
>>462 �J�����j�R�t�̌����ȑ�P�Ԃ̃X�R�A����肵���BWeb��ɂ���B
�u kalinnikov symphony 1 score �v�ŃO�O��Γ���ł���̂ŁA
���O�����肵��B
�`���i��P���߁j�����Q�O���߂܂ł̊Ԃɔ��q���S��ς���Ă���B
�ŏ��̔��q�͉����̉����q�Ȃ̂��A�Q�Ԗڂ̔��q�͉����̉����q�Ȃ̂�
�E�E�E�E�E�Ƃ�����ɁA�T�Ԗڂ̔��q�܂Łu�����̉����q�v�Ȃ̂���
�����Ă���i�������ǂ̏��߂̓��Ŕ��q���ς���Ă���̂��������Ă���j�B
����������ɓ�����ꂽ�Ƃ���ŁA���O�̂����������͖������B
���ꂼ��̔��q�̕ύX�̒���̗����ɗ���͑S�������Ȃ��B�������u�S���v���B
�`���̃A�E�t�^�N�g�Ɠ����悤�ɁA�����ɃP�`�����鉹�y�Ƃ�����킯���Ȃ��B
�u���q�̕ύX�v���e���|�̕ω��Ɠ��l�ɁA�w���҂��u����������v�|�C���g���B
���������Ă������͗���Ă��Ȃ����B
�t�����F���X����T���ɔS�����闝�R
�ǂ������������̎��i���
�A�}�I�P�o��������ۂ��A�F��֘A�̐l�A�A���`�Z���^�[�A���̃X���̌ÎQ
����Ńt�����F�������Ƃ������A�Ȃ��Ȃ��`���Ċ�������ˁB
�Ⴆ�A�悭�J�������̌|���Ɣ�ׂ�����̂�����
�t�����F���P���ł́u�܂��߂ȁv�x�������t�B���̕З��݂���̂�
>>464 >���{WF����ƌq���肪���邾���ʼn������̂���
T�����q���肪����͓̂��{WF�Z���^�[��
����Ƃ͌q����͖���
T������̘b���l�R�̊z�̂����������邾���Ȃ̂�
�J�[���E�t���b�V���̖��ɂ̓S�[���h�x���N�A�V�F�����O�̂悤�ȐE�l����
�t�����F���̃x�������ł̊������x���������ЂƂ̗v����
463���������҂����A�ǂݕԂ��Ă݂��炿����ƕ�����ɂ����������������̂�
�⑫����B
������������ɓ�����ꂽ�Ƃ���ŁA���O�̂����������͖������B
���������̕����́AT�����w�������J�����j�R�t�̌����ȑ�P�Ԃ̓���
�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �ɂ��Ă̂��Ƃł���BT�����y���̒ʂ�ɔ��q��ύX���Ă��āi������O�����j�A
���̕ύX�̒���̗����ɂ͗��ꂪ�܂����������Ȃ��Ƃ������Ƃ��B
�܂��~�X�^�[�����͂������_���Ă��Ȃ��Ǝv�����A�ꉞ�O�̂��߁B
��L�̓���́u�`�������Q�O���߂܂ł̊Ԃɑ������镔���v�́A�~�X�^�[������������
�o�L�ڂȒP�Ȃ��۔�]�i
>>414 �j�ł͊��S�ɃX���[����Ă���B���ǂ��̕����Ɋւ��ẮA
�~�X�^�[�������g��������܂����������Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ��ȁB
�u�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v�́A���ǂ̓~�X�^�[�������y�����`�F�b�N������
�K���ɏ������o�L�ڂɉ߂��Ȃ������E�E�E���ꂪ���_�ł��ˁB
���������������߂��̂ɔR���������₪����
�t�����F�����C���^�r���[�ɓ��Ă��钘���ł�
�t�����F���̃x�������ł̊�����1922�N���炾��
�t�����F���̉��t�ɂ����āA�y�Ȃ̘_���I�A�����h�邪�Ȃ��̂�
�ł̓i�`�X�h�C�c�̕���������قNJԈ���Ă������Ƃ�����
���E�ōŏ��̎��C�e�[�v�ɂ��X�e���I�����^����
�t�����F���̃}�O�l�g�t�H���^�����J�n���ꂽ�̂�1940�N���̂��Ƃ�
1942�N��AEG�H��ł̉f�����^����
�@�f�t�H���g�̎w���҂Ɠ����ʒu�ł�1�{�}�C�N
�A�c����^��A���r�G���g1�{
�BUFA�f���ǂ�2�{�}�C�N
�ȏ��3�ӏ��Ƀ}�C�N���ݒu����Ă���B
�悭�m���Ă���̂�UFA�̉f����Youtube�ł��ς��邪
���ꂪ�X�e���I���^���������ǂ��������Ȋ��������ĂȂ�Ȃ��B
�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO >>476 �݂��Ƃ��Ȃ�������ww
���w����T���̂Ȃ肷�܂��������~�܂�Ȃ�wwww
�f����UFA����Ԗ��i�����̂�
1936�N�̃x�������E�I�����s�b�N�̋L�^�f���
�����̃h�C�c�ł̃}�b�`���Țn�D�������яオ��B
�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �i���{�����ҏW�H�j
���̎����ɃN�����O�t�B�����̃I�[�f�B�I�Z�p���قڊ������Ă���
���W�I���牮�OPA�܂ʼn����o�͂ɉ������J�^���O�������Ă����B
ARG�̃}�O�l�g�t�H���́A�������������I�ȕ��͋C�̂Ȃ��ɕ���������
Hi-Fi�^���̈Ӌ`���咣���Ȃ���Ȃ�Ȃ�������
1941�N�̃f���ł�UFA�̉f��قŃt�����F���̘^�����܂�
�e�[�v�^���𗘗p�����l�X�Ȍ��p�ɂ��ăv���[��������
�������̒m��̂�RRG�����̏��L�������W�I�p�����ł���B
�풆�̃t�����F���̃��W�I�R���T�[�g�^����
�������̔������~�܂�Ȃ��悤�����A
�������������̉��㏤�@�͎~�߂đ��X�����ĂĂ����ł���Ă���
�ق�
���̃X���̏Z�l�Ƀt�����F���̎��|�͓ɐ^��
Youtube�ł�T������̃t�����F���]��
T��������قǂ̘J�͂��₵�ăt�����F���_�b�ɒ��ނ̂͗��R���悭����Ȃ��B
�܂�O��ƂȂ��Ă���t�����F���_�b�̓h�C�c�y�d�Ƃ��Ĉ�ʓI�Șb�ł͂Ȃ�
�Ⴆ�e�B�^�j�A�p���X�g�ƃ��B�[�X�o�[�f���̃u��4�̊J�n�̈Ⴂ��
���߂̓��ِ��Ƃ����A�t�����F���̃u���[���X�ْ͈[�I�Ƃ�����B
>>494 �R�[�z�[��ᔻ����̂�����������Ɍ��ЂɂȂ肽�������ǂȂ�ˁH
�{�Ƃ����܂��s���ĂȂ�����B
�J�y�[�Ƃ������̒������Ŕ��Ă��ǂ��ɂ��Ȃ��ł���B�傫�Ȃ����b���Ċ������ȁB
���̓Ɠ��̃u���[���X���߂̑ǂɋ�����̂̓J�������ł͂Ȃ��x�[���ł���B
>>499 ������X���[����B��]�̖{���Ƃ͑S������Ă��邩��B
70�N��̐y�Ђ݂����ȌÏL�����͂���
>>502 �t�����F���̕����I�ȑ��ʂ�
�ނ����Ȃ�����������́u�ÏL���v�N�w��|�p�_�̂ق����Y�قɌ���Ă��鑤�ʂ�����B
�Ⴆ�Ε����|�p�_�A�z���̋����́A������`�A����炪���ۓI�Ɍ���Ă��邱�Ƃ�
�t�����F���͌����Ȃ̂��\���v�f�Ƃ��ĕ���ɏ悹�Ă����Ƃ��ׂ���������Ȃ��B
�Ⴆ�Ε����|�p�_�Ƃ͔��̍s�ׂ����Ă���悤�ł��A�x�����~���̌��I�[���̑��݂�
�t�����F���̘^���ɂ����Ĉ�ԑ����݂���B���̕����i�͍��ł����l�̂�����̂��B
�z���̋����̂��A�h�C�c���L�̒n�拤���́i�Q�}�C���f�j�Ɉˑ����Ȃ���
�ނ̃R���T�[�g�ւ̓��ʂȐM�����l����ƁA���f�B�A�ɂ����鋤���̌`�����Ă�B
�t�����F���̓t���C�g���̐S���w��j�[�`�F���̐l�_�_���S���F�߂Ȃ�������
���{�ɂ�����l�C�́A�V�������A���X���̖��ӎ��̑��`�A�l�Ԃ̉\���Ƃ���
�S���ʂ̚n�D�ɖ�������Ă���B�t�����F���̎w���̓R�b�N������Ɠ��ꎋ����悤�B
����Ȃ��̂͌o�ϊw�Ɛ����w�̖��ŁA�����Ƃ͋�����u���ĕ̎�������
�t�ɂ����̖��ɉՂ܂�錋�ʂɊׂ��Ă���B�������l�ԏL���Ă悢�̂����ǁB
�u���[���X�̈�Ԃ����̓x�C�k������
>>503 �Ȃ�ق�
���̃J�y�[�̓���T���Ă݂�
>>504 50�N�O�̃J�r�L�����t����ł���
����݂����Z������ł����Č���ɐ��������������ł���
>>504 >�t���C�g���̐S���w��j�[�`�F���̐l�_�_���S���F�߂Ȃ�������
������Ē��삩�����Ō����Ă�́H
����🐙���͏ォ��ڐ��̊��ɂ͌����Ă邱�Ƃ��A���L�^���ŕ��}�B�w�����}�f�����Ȃ��B
�f�l����ɂ������������Ă���ۂǗ��̉�Ȃ�
�f�l���肾����x���x�����������Ă�ˁH
>>507 ������Ȃ�u�s�ł̐l�v�uBEASTARS�v�u���@�C�I���b�g�E�G���@�[�K�[�f���v�����肾�ȁB
�A�j�������Ă����Ƙb�ɋ̂������ςȂ��ƃ{�P���B
>>508 �t���I�ȈӖ����ȁB
�w�����Ă�Œ��͔��������݂Ă�悤�Ȋ������Ƃ������Ă�
�{�l�͓w�߂Ę_���I�Ȏv�l�ɓO���Ă����B
������_�̂��Ƃ��U�����l�Ƃ͋�����u���悤�ɓw�߂Ă���
���g�ƊϏO�Ƃ̋����̌��ʼn��y����������ƐM���Ă��B
�ǂ�ł���x�[���ɋ������������ꂽ
>>512 �u�s�ł̐l�v�uBEASTARS�v�u���@�C�I���b�g�E�G���@�[�K�[�f���v�Ȃ��ςĂ�
���̒��x��50�N�O�̃J�r�L�����t�̗��邾���Ȃ�ȂɌ��Ă��ꏏ�ł���
>>514 �l�C�̃J������
���͂̃x�[��
�x�[���͐��ɉ��y�ē̃|�X�g�Ɍb�܂�Ȃ������n���f�B�L���b�v������Ȃ���
�t���g���F���O���[�w���̃u���T���O�O���ĐF�X���Ă���������̓���ɂԂ��������Ă��܂����B
�ł����̔Ղ���ԉ����ǂ���ł���H
�Z���^�[��CD���K������������ԗǂ��킯�ł͂Ȃ�
���l�b�g�S�L�u�����쏜���鎞�ɕ֗��ȃR�s�y�p�f�ޏW
���܂ɂ������Ȃ��̂łȂ�
�w���҂ɂ��Ă͌��s�����ꂽ�̂��A�����H�Ƃ������ł���
>>523 ������ƍ��Z�����̂ŏ������߂Ȃ��̂����A
�߁X�������܂��B
>>525 �������܂���̂ł��肢���܂�
525���������҂����A�肪���̂Ő������܂��B
��Ő��K�^���R���v���[�g�̉��͂������H
�Z���^�[���̉ؗ�ȃo�g���e�N�j�b�N
>>527 ���킵�������T���N�X
�܂�~�X�^�[�������A�v�����݂ƌ��߂��Ńg���`���J���Ȃ��Ƃ����������Ă���Ƃ������Ƃł���
�E����ł͂Ȃ���������킴�킴�g��
�C���r���œ��e����Ă��܂����E�E�E
��������
�݂��Ƃ��Ȃ�🐙�̎���age ��������
�݂��Ƃ��Ȃ������̎���age ��������
>>530 �܁[���G�ɕ`�����悤�ȉ��o���Ă�
���킵�������T���N�X�ėL���Ȏ����R�s�y�����
�����̘b��
>>416 �Ō������Ă�@���߂�
�N�Y�ǂ�����邫�Ȃ牴����邵���Ȃ�
536�̓~�X�^�[�����̔����B
🐙����v���v��😡
JaneStyle�Ō��Ă���̂���
>>532 �Ƃ��́u�E����J�E�v�Ƃ����\������Ȃ���
���̃I�o�J����͐�u���ŕ\������Ȃ��G�������g���ē��ӂ����Ă�����
FireFox�ŃX�������Ă悤�₭�u����v�����^�R���Ƃ킩����(��)
�~�X�^�[�����Ƃ������̂́u�������痐���v�Ƃ��o�J�����Ă邾������Ȃ�
�u�E����J�E�v�Ƃ����X�Ə����Ă�����(��)
�����JaneStyle�Ō��Ă���l�B�͂����ƁH�H�H�������낤��
�u�������痐���v�̐����ȑO�ɁAJaneStyle�Ń^�R�̊G�������ł�̂���������
�~�X�^�[�������ƃ^�R�c�{�N�A�����^�R�̊G������f���Ă�
���҂��Ă�������Nw
�ǂ����Ă��ł��Ȃ���u�������痐���v�̏ڂ���������f���Ă�������w
>>539 ���ӂ��ɏ����Ă�C���͂킩��̂���
JaneStyle�ł�
�@>�E����v���v���E
�@>�܂�䥂ő����ȁE
�Ƃ����\������Ȃ��̂���
�c�O�������˃^�R�c�{�N
�������JaneStyle�Ō����^�R�̊G������f���Ă��ꂽ�܂�
�ł��Ȃ��̂Ȃ�u�������痐���v�̏ڂ���������f�����܂��A����Nw
���Ȃ݂�Live2ch�Ŋm�F���Ă݂��獕���^�R�̊G�������łĂ�����
�u�\������Ȃ��G�������g���ē��ӂ����Ă����v
>>537 >�N�Y�ǂ�����邫�Ȃ牴����邵���Ȃ�
����[�����������[�[�[
���������[�[�[
��p���珑�����ނ���ID���R���R���ς��̂��H
>>545 ���A�����t���g���F���O���[�X������
🐙����͑�p�̃t���g���F���O���[�������
�^�R�c�{�N�L�^�[(��)
�����ƁA��������炸JaneStyle�ł͂��������Ă�Ƌ����Ă������
545�̓��e���悭�킩��Ȃ��l�ɉ������ƁA���́����K�C�́A
�^�R�c�{�N�̂��Ɓ����K�C�ƌĂ炩�킢����
�u�N�Y�ǂ�����邫�Ȃ牴����邵���Ȃ��v�Ȃ�ĚV����Ă����Ȃ���
�ڂ��^�R�̐Ԃ����I
>>546 �}�����H�����͂��w���͂��S�~�̃_���w���҂�
�ǂ������^�R�c�{�N
�^�R�c�{�N���珑�����݂��[����
�^�R�c�{�N����Ԏ������[����
�������₻�낻��I�y���V�e�B�ŃA�W�A�̃I�[�P�X�g�����Ă�ŃR���T�[�g�����t�F�X�g������ˁB��p�̃I�P�������������^�R���̃I�P�͌Ăꂽ���ƂȂ���H�R���i�Ђœ��{�̎w���҂Ɠ��{�̃I�P���肾���ǁA�����^�R�����}�V�Ȏw���҂��������x���炢�͌Ă�Ă邾��B
�^�R�c�{�N�A���i�͂��ꂭ�炢�ɂ��Ƃ��Ȃ�
�����������̉ߒ���jane�Ń^�R����}�[�N�������Ȃ��̂��������Ă���e���V���������Ȃ�
�u�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v
���������
>>566 ��������ĉƑ��⒇�Ԃ̊��҂�w�����ė��w�����t�����X�ł͂���ȍ����ȉ��y���炪�{����Ă����̂�
���҂��ċ��o���Ă��ꂽ�l�����̓A�}�I�P�̎w�����낭�ɂł����ɓ���T�C�g��f����䥂ŏオ���Ă邨�O�����ĉ����v���낤��
�y���̓ǂݕ����Ă������A���q�Ƃ����K�������ʕ\��炢�͓��{�ł͋`�����烌�x������@���Ȃ��̎���͈�����́H
�Y�������₾�������Ă��@
>>414 �̎w�E�Ń{�������U��グ�Ă�Ƃ��낪���O�̃A�E�t�^�R�g����
>>567 ����ς肠�Ȃ���566�̂悤�Ȓ��������ɂ��������Ȃ���ˁB
���Ȃ��̕����Ō����Ȃ�u�`�����烌�x���v�̖��B
�u���̋Ȃ������q�Ȃ̂��v��c�����Ȃ��ŁA�u������_����v���Ƃ͂ł��܂���B
��p�̎w���҂����Ȃ��S���m��Ȃ��l�̂��Ƃ����X�ƕ����ă^�R�c�{�N�͉������������
>>567 �̃A���J�[����݂Ă悤�₭�킩�����̂���
�^�R�c�{�N�����X�Ɣ�排������Ă��鑊����ē����ƌ����l�H
���̐l����p�ɂ���l�H
���̐l���^�R�c�{�N�̎����̂��ƁH
�܂��������H����Ƃ��Z���^�[���H👶
�Ȃ�قǁA�^�R�c�{�N�͂��̐l�̔�排��������邽�߂ɂ��̃X���𗘗p���Ă���̂�
�^�R�c�{�N�����̐l�ɂǂ�ȍ��݂������Ĕ�排������J��Ԃ��Ă���̂��m��Ȃ���
>>575 >�^�R�c�{�N����排������������̐l�̃X���𗧂ĂĂ����ŃI�i�j�[���Ă��Ă���
���̒ʂ�B�^�R��Y�͂����t�����F���X���ɏ������ނȁB
�^�R�c�{�N�݂͂�Ȃɂ�����Ă��(��)
���⋦����Z���^�[���Ȃ��ȁc
���ƁA���Ă͑e���ȉ����̊C���Ղ����Ȃ��Ȃ��ŋ���Ղ͍������Ƃ����̂��E�����������ǁA�ŋ߂͐��K�Ղō������̂��̂���y�ɔ�����悤�ɂȂ�����������A���������Ȃ�youtube�ɂقƂ�Ǔ]�����Ă邩��Ȃ��B
�r�[�g���Y�̉������o�������悤�Ȃ��̂���
�r�[�g���Y�����}�X�^�����O�ŐH���q���Ȃ��́H
>>579 �������ɋ�����Z���^�[�������͏o�s�������Ǝv���B
���͊��o�������}�X�^�����O��ς��čĂяo���Ă����Ԃ������Ă���B
�}�X�^�����O�ς��Ă��債�ĉ��͗ǂ��Ȃ�Ȃ����A������������Ē��ቹ���y�������悤�Ȍ���I�P�̋����ɍ��킹���悤�ȍ��ς������ɂȂ��Ă��镨������B
��T�o��1942�N4��19���̑�㒮���ꂽ������A�������ǂ��������ĉ�����
�\�A�R�������čs�����鍑�����ǂ̃e�[�v�������Ȃ��́H
�Z���^�[�Ղ́uSP�̍c��v�͍D��悾�����B
�i�`�X���F�肵���h�C�c�鍑�̍���ł���u�_�˔\���X�g�v
�t���g���F���O���[�̓i�`�X�h�C�c�̊ŔX�^�[�ł�����
������C.�N���E�X�����x�[������Ȃ̂������Ȃ��B
>>590 ����ȏ�Ɏ��R��`�h�C�c�̊ŔX�^�[�ł�����
�������Ƃ����������߂Ȃ���\��
�h�C�c�Ō��͂������Ă����i�`�X�́A�����̌���ł̃N�i�p�[�g�u�b�V�����U�_����������܂����B
55���g�͂����B�����������Ă݂����lj����͌��\�������B���܂ł�CD�͂܂Ƃ߂ď����ł���Ȃ����B
�X�}���B�r���ő��M�����܂����B
�\����Ȃ��B�Ȃ���쓮�������ȁB
����͂�������Ƃ������T���N�X
���������A���ꂩ��A37�N�̃R���F���g�K�[�f���ł́u�_�X�̉����v���������ǁA���o�Ղ������^���Ԃ����炩�ɒ����B
>>600 �R���F���g�K�[�f���͉̂��̔Ղł�108���قǓ����Ă���BM&A���Z������̂���Ȃ����B
����ɉ��̔Ղł�1938�N�̃R���F���g�K�[�f���A�t���[�_�E���C�_�[�̂��������������Ă���iDante(Lys)�Ձj
1937�N�̃����O�A����ς茩����Ȃ��̂��H���Ȃ育�����������āA���������Ȃ��̂��Ⴀ��܂����H
�ց[�ʔ�����
�v�X�Ɂu�قق��v�Ɠǂ߂鏑�����݂���
>>601 �@M��A�Ղ́u�����L���[���v3���Ɖ���������2���g�Ȃ̂ŁA���^���Ԃ̊W�ŃJ�b�g�����̂��ȁB
>>910 �n�C���]�̃_�E�����[�h�ŁA�����ꂽ���A�����܂��H
e-onkyo�Ńg���X�^���S�Ȃ�2936�~�B�����n�C���]��SACD��8172�~�Ȃ̂ɉ��i�ݒ�Ԉ���ĂȂ����H
�����{���ʔ�p�̂�����p�b�P�[�W���f�B�A�̉^�����ȁB
>>596-601 55���g�A���̎茳�ɂ��͂��܂����B
�u�b�N���b�g�̂��������ꂾ���̏��ʂ��炻��Ȃɕ�����Ղ������N�����Ă��������A���ӂ��Ă���܂��B
�������A1����2�������Ɖ��肵�āA�S�������I��̂�1�����ォ�c
���͉����ȁB
> 1�����ォ�c
������͏d�v�ȏ�����Ə����Ă��Ėʔ����ˁB
>>596-601 �̒lj�������B
�E1937�N�̃R���F���g�K�[�f���̃����O�͈ꉞ�S���^���������A�v���f���[�T�[�͔��蕨�ɂȂ�̂̓����L���[��3�������Ɣ��f�������ǁA�t�����F���ɘ^�������Ă������茈��B
�EI�Ƃ̌_��1951�N�Ɉ�x�ꂽ�ہAEMI�ADG�ADecca���_���\���o�Ă����B�_�ꂽ�^�C�~���O��DG�̃O���C�g�Ƃ����쎩���̘^�����s��ꂽ�B
�EEMI�ƍČ_��ۂ̏����ŁA1953�N��DG�̃V���[�}����Decca�̃t�����N���^�����ꂽ�B
�E47�N�̃E�B�[���t�B���Ƃ́u�p�Y�v�̑�2�y�͑�O����1949�N�ɍĘ^�����Ă�̂́A���܂ł́u�I�[�g�`�F���W���[�ōĐ��ł��Ȃ��̂ő��߂̃e���|�ɂ���ƌ����Č��X�Ę^��������ꂽ�v�ƌ����Ă����ǁA���̓t�����F���{�l����u���̕����Ƃ̃e���|������Ȃ��v�ƌ����čĘ^����\���o���B
�E49�N�̃��c�F��������e�[�v���R�[�_�[���������ꂽ���ǁA51�N�܂ł�SP�̎��^���Ԃɍ��킹�ĂԂ�^���������i����͑O����w�E����Ă��j�B
�E�u�c��~���ȁv�̓e�X�g�^������10���ȏォ�����ĂāA���̂܂܂���SP1���Ɏ��܂�Ȃ��̂Ŗ{�Ԃ͑��߂̃e���|�ɂȂ��Ă�B
�E1950�N�̃x�g�V�͑S�e�C�N�̃I���W�i���e�[�v���c���Ă��āA����ēx�I���W�i���e�[�v���g���ĕҏW�����B�L���ȏI�y�͂̏����̐��͊��S�ɏ�����Ă邯�ǁA���ꂪ�A�E�g�e�C�N���玝���Ă�������Ȃ̂��A���ǐ����ǂ̎��_�ō��������̂�������͂ڂ����Ă�悤�Ɋ�����B
�E1926�N�́u���e�̎ˎ�v���Ȃ�1949�N�́u���[�G���O�����v�O�t�Ȃɂ��A�E�g�e�C�N���c���Ă���悤�ȏ������Ղ肾���A�O�҂ɂ��Ă�1935�N�̕��̊ԈႢ�H�i1935�N�̘^���̕ʃe�C�N�͓��{�����o�Ă��j
�E�g�l�u��
�܁[���r���ŏ�����������B
�ڂ������T���N�X�A���Ԃ�����a�Ă��ꂽ��ł���ˁB
HMV��30%�N�[�{���t�^�ɂȂ�����|�`��\��
�͂�����
>>612 ����̗v�_���Q�l�ɒ����܂��B
���肪�Ƃ��������܂����B
JaneStyle�g�����
>>606 �� �E �ɕ����������Ă��āA
���Ԃ�^�R�̊G�����Ȃ낤�ȂƂ͎v����
>>612 ����̊e���̖`���� �E �������_���Ƃ킩���Ă͂��邯��
�^�R�̊G������z�����ď��Ă����͓̂����̔閧(��)
�t���x���̓��R�[�h�^�����o�J�ɂ���
���g�����t���g���F���O���[�̂P�X�S�Q�^���̑�9�������]�����Ă���
���⑫
�u�{�l����v�Ƃ��u�Z���^�[������v�Ƃ������Ă鏑�����݂́A�^�R�c�{�N�̏������݁B
����A���x�͕��������Ƃ̂Ȃ����l�����C�V�����n�߂��ȁB
�S�����ڂ����͈̂�ʐl�ɂ��܂ł��S�����Ă邨�܂��̂ق��ł́H
>>621 ���Ȃ��Ƃ��t���g���F���O���[�X���݂̂�Ȃ͂��O����Ԍ������Ǝv����
���������������Ƃ������B�S�����ڂ����Ƃ������B
�^�R�c�{�N�����i�ɋ����ĒN�����Ȃ߂悤�Ə����Ă�̂͂킩�邪
�����͂��O�̕s���̋�s�������Ƃ��낶��Ȃ�
�����s���Ƃ����͓̂��R�̌��ʂ���B
T���̉��t�Ȃ�ĕ������l�i�V
�������ł��̐l��p�̃X���𗧂ĂāA�����ɏ������݂Ȃ����B
���܂��p�N�����N�l�̃R�s�[
�낭�Ɏw���������A�Œ�J�����������Ɍ����āA�A�E�t�^�R�g�̓o�b�`���I
�p�^�R�c�{�N�͎��i�̉�(��)
>>612 >>630 �@
���̃}�g���b�N�X�ԍ�����l����ƁA����1����4��30�b�Ɖ��肵�āA
���C���̉����F34����153��
�����L���[���F15����67.5��
�W�[�N�t���[�g�F10����45��
�_�X�̉����F26����117��
�ɂȂ�̂ŁA�����L���[���Ɛ_�X�̉����͍���o�Ă镪�������������Ȃ��������ۂ��ˁB���C���̉����͑S�Ȏ��^�ł��鎞�Ԃ����ǁB
���̕����͌��X���^����Ȃ������̂��A���̃}�g���b�N�X�ԍ��́u�ҏW��v�̂��̂Ȃ̂��B
�O�����h�X�����Ƃ̉�����r�]�����낻��
GS�̖��e�̎ˎ�A47/5/25�^��+�c�����A49�N�u���V�Ȃǔ����Ē����Ă݂��B
�u�U�E���K�V�[�v�͎����ĂđS����������ł����A
>>635 �قƂ�ǂ��ׂāA�Ƃ��������K�V�[�̕������|�I�ɑ���
�F�X�Ə����̂��߂ɂ��Ƃ邩��A�������悭�Ȃ����Ƃ��Ƃ�����`����Ŗ��킳���ȁB
�X�J���̃����O�̏ꍇ�A���Ƃ̃I���W�i�����A�Z�e�[�g�̂����e�[�v�ɕς�����Ƃ���
���|�I�ɉ������ς���āA����������ׂ������������A����ȊO�͂��ׂČ\���S���B���܂����ȁI
�R���v���[�g�{�b�N�X�ɓ����Ă�o�C���C�g�̑�9������������Ă����̂͑��̐l�������Ă邪�A�y�͊Ԃ̒��O�m�C�Y�������Ă�B
>>638 >�y�͊Ԃ̒��O�m�C�Y�������Ă�B
����͋����[���b���BEMI�Ղ��{�ԁi�ɋ߂��j�Ƃ������ƂȂ̂��E�E�E
�����ƁA�Ƃ�ł��Ȃ��������Ă��
>>639 �@��1�y�͂̌�Ƒ�2�y�͂̌�͂��ꂼ��uHall ambience�v�Ƃ����ʃg���b�N�ɂȂ��Ă�i0'55"��0'34"�j�B��3�y�͂Ƒ�4�y�͂̊Ԃ͕ʃg���b�N�ɂ͂Ȃ��ĂȂ����ǁA����܂ł̂悤�ɂԂ�ɂ͂Ȃ��ĂȂ��āA��͂�y�͊Ԃ̉��m�C�Y����i�قڃA�^�b�J�ő����Ă���悤�Ȋ����j�B
�Z���^�[�Ղ��y�͊Ԃ̒��O�m�C�Y���J�b�g���ꂸ�Ɏ��^����Ă�炵�����ǁA���̓Z���^�[�Ղ������ĂȂ��̂ŗ��҂��������̂Ȃ̂��ǂ���������Ȃ��B
�G���N�G���X������o��悤�ł����A�t�����N�Ȃǂ̉�����r�������[���Ƃ���B���݂ɁA�G�����Ȃ��Ȃ�����Ȃ��B
�����Ƃ��E���������S���Ȃ������Ă�
55���g�A1���ڂ��珇�ɕ����Ă����C�͂͋N����Ȃ��̂ŁA�C�ɂȂ�i��ɉ�����j�̂��畷���Ă����܂����B
�����Ƃ��������]��ŏ����Ă����˂A�ƁB�S���S13�̒��Ńt���g���F���O���[�̃G���C�J���ނɂ����������ȁB�����ƃt���g���F���O���[�̎w���p���`����Ă��悤�ȁH
�t�B���f���t�B�A�ǂɂ��I�[�}���f�B�Ǔ��R���T�[�g���`���ꂽ����������ȁ��S���S
55���g�A1���ڂ��珇��2���ڂ܂ŕ����܂����B
>>646 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q149950349 �S���S�P�R�ɁA�h�C�c�̎w���҃t���g���F���O���[���o�Ă���b�����邻���ł����A�P�s�{�̉����Ɏ��^�����
�S���S�P�R�ɁA�h�C�c�̎w���҃t���g���F���O���[���o�Ă���b�����邻���ł����A�P�s�{�̉����Ɏ��^����Ă��܂����H
���łɕ����܂����A�t���g���F���O���[�͖S���Ȃ��ĂT�O�N�ȏ�o���Ă��܂��E�E�E�B�S���S�P�R�̎���ݒ�͂�����ɂȂ��Ă���̂ł����H
�u�r�E�e�E�y�\�X�t�H���c�@���h�\�v�i��R�V�T�b�j�ł��B�u�펞���̃h�C�c�鍑�������t���g���F���O���[�̉��t���X�e���I�^�����Ă��āA
���̃e�[�v���㉟���������V�A����A�ŋ߂ɂȂ��ĉ��������ꂽ�v�Ƃ����ݒ�ŁA���o�������l���̑_�����S���S�����������Ƃ����e�ł��v
�����̌��ʂ����B�o�Ă��܂���
>>649 DG�̋������Ղ͐푈���Ɏ���ꂽ�͂������A�A
646�ł����A�����s�i�Ȃ̂Ƃ���ŏe���̂悤�Ȃ��̂���������c�䂤���e���������B�ȂA���ꂩ�Ȃ��H�킩���ȁA�Ƃ��������B
>>650 ���ׂĂ���� ���肪�Ƃ��B
���K���R�[�h�p�^���W�̔��オ㩂̗\�z����������A�������������ă��C�u�����W���o���Ă����̂��낤��
�o�C���C�g��RIAS�͉ߋ�EMI�Ɏς��������܂���Ă���̂�
RIAS��Audite�A�E�B�[���ƃU���c�u���N��Orfeo�A�X�g�b�N�z�����t�B����Weitblick����BOX���o�ĂāA��v�Ȃ�͉������łقƂ�Ǒ������Ⴄ���Ȃ��B
�t�����F���̘^����S���W�߂Ă��Ȃ�Ă���́H
JaneStyle�Ō��Ă���E�ɕ��������������o���ȁI�����킩��A���̏��^�R�c�{���I
�i�Z�オ���W�I�Ńt���g���F���O���[������Ă��������L��B�Ԓ˕s��v���g�L�����ő��̖���ƂƋ��Ƀt���g���F���O���[������ς�ǂ��ƒ����Ă��������B
55���g��CD3��4���܂����B
�̗̂��j�I���ՂȂ�Ēቹ���̃I�[�f�B�I�@��ł�
�ŋߏo���N���V�b�N�̐[���Ė{�ɂ��낢��ʔ����������Ă�����
�u�ǎ҂��N���V�b�N�̐[���ɗU���Җ]�̃K�C�h�v
>>665 �́A���ɕ���CD�����B
�u�R���F���g�K�[�f���v�̑�9�A����Ȃ��āu�N�C�[���Y�z�[���v�̑�9�ł����B
���Ȃ蓪�����Ă���ȁB
���̒��q����Ō�܂ł��ǂ蒅���̂͂��ɂȂ���B
�C�̂ނ����̐l���撣���Ē����Ƃ�悤���
�o�C���C�g�̑�X��SACD�ɂ́A
>>671 �Đ��@��ɂ���Ă͈���Ē������邩������܂��A�m�F��������f�[�^�͂܂������������̂ł���
>>673 ���X�A���肪�Ƃ��������܂��B
�n�C�u���b�h�ՂƃV���O�����C���[�ՂŁi�f�[�^�������ł��j��������������Ă���
�ꍇ�����邩�Ǝv���܂����A�o�C���C�g�̑�X�̏ꍇ�͂���ȂɈ��Ȃ��̂ł��傤�ˁB
����Ă��猋�\�b��ɂȂ��Ă���͂��ł�����ˁB
55���g��CD5�A37�N�����h�������̃x�[�g�[���F����9���܂����B
1937�N�̑��͕s���Ȏ�舵�����Ă鉉�t�����
55���g�̂���CD6�A'37�N�����h���E�R���F���g�K�[�f�������̃����L���[����3�����܂����B
�t�����F���̎w����������Ăǂ�ȋȂł����肪�������ĕ������ƌ������炻������Ȃ����
�t���g���F���O���[�J���[�O���r�A�ʐ^�W�����͂܂��ł����H
�t���g���F���O���[�̏Ռ��k�[�h�Ƃ����ꂪ������w
��ɉ��\���s�A�X���ă��q�J�����łȂ�̓p���N���b�J�[�Ȃ̂ɁA�t���g���F���O���[���w�����邨�p���v�����g���ꂽT�V���c�𒅂��j�������B
>>680 ���̐����ʐ^���J���[�Ō��Ă݂���w
�v�l�̂�w
Amazon�̃X�g���[�~���O�z�M�Œ���������
55���g�̂���CD7�E8�E9�A'37�N�����h�������̐_�X�̉��������ƁA���N��SP�^���̉^�������܂����B
�X�E�F�[�f���������������ɂ��t�����F���́w�o�C���C�g�̑�9�x
https://www.hmv.co.jp/news/article/2110131018/ >>686 �o�C���C�g���̕����lj����͂��łɁA
�I���t�F�I����o�Ă���̂ŁA�������䂭���̂ł͂Ȃ����A
�X�E�F�[�f���a�h�r����̃����[�X�Ƃ����̂��ʔ���
���̃��[�x���́A�ߋ��ɂ��O�����E�O�[���h�Ƃ��A
���C�u�^�������܂Ƀ����[�X���Ă���
���x�������Ăǂ�ȉ��t�Ȃ̂��͂悭�������Ă�̂ɒP�ɉ������ǂ��Ȃ��������m�F���邾���̂��߂ɔ��������x�������́H
55���g�̂���CD10�A�`���C�R�t�X�L�[�́u�ߜƁv���܂����B
>>687 �I���t�F�I����o�Ă�����̂Ɠ������̂Ȃ낤���A���t�I�����
�����┏������^����Ă���Ƃ����̂������[���B�I���t�F�I�̂���
�͂���炪�Ȃ��A�u���ꂪ�{���̓����̃��C���^���v�Ƃ������ɂ́A
�l�I�ɂ͈ꖕ�̋^�O�������Ă����̂����A����炪������̐���
���M�����邱�Ƃ��ł���B
���ƒ��ڂȂ̂��A�u�����̓���v�������Ă���ĂƂ����ȁB
EMI�̂�����u�����v�Ɖ��t�O�̃t���g���F���O���[�̒��肪�{���������̂��悤�₭������B�i�����͂Ƃ������A���t�O�ɃI�P�Ɏw���҂������b��������Ȃ�ĕ��ʂ͂��肦�Ȃ��ƑO����s�v�c�������j
>>686 .
�t���g���F���O���[���a135�N�̝{�������鐢�I�̑唭���I
�u�S�l�ނ̎���v�Ƃ܂Ŏ]�����Ă����A
�t���g���F���O���[�����̖������C���w�o�C���C�g�̑��x�A
���̐^�������ɖ��炩�ɂ����I
�܂���1951�N7��29���A�X�E�F�[�f�������ɂ���Ē��p�������ꂽ�ԑg�A�`����3������i�h�C�c��A�p��A�X�E�F�[�f����j�ɂ��A�i�E���X���狐���̓���A�Ӑg�̎w���A��Ⓑ�߂̃C���^�[�o�����͂��݁A�Ō��2�����ȏ�ɋy�ԑ劽���Ɨ��̂悤�Ȕ���i�Ɣԑg�I���̃A�i�E���X�j�܂ŁA85���ԁA��̃J�b�g�Ȃ��ɓ���̂��ׂẲ���SACD�n�C�u���b�h�ՂɎ��^���܂����B
���@�̂��������̓L���O�C���^�[�i�V���i���Ɖ��̐[���������^�[���E���[�x���̎�ɎҁA�̃��l�E�g���~�k�����₵�Ă������wFurtwangler / A Discography by Rene Tremine�x�i�^�[���E�v���_�N�V�����@1997�N���jA4��56�y�[�W�̍��q�B���̒��́u�o�C���C�g�̑��v�i1951�N7��29���@�o�C���C�g�A�j�Չ̌���nj��y�c�j�̍��̍Ō�̍s�Ɏ��̂悤�ȋL�q���uBavarian Radio, Munich and Swedish Radio (archive LB 14784)�v�B�o�C�G���������A�~�����w�������A�����ăX�E�F�[�f���������������Ă����Ƃ����̂ł��I
����1�s�̋L�q�𗊂�ɁA���Ђł͒��N�̕t������������X�E�F�[�f��BIS�̃��x���g�E�t�H���E�o�[����ɉ����T�����˗��B�����Ă��ɁA���������̂ł��I ���̃g���~�k���ł���������ł����ɁA70�N���̊ԃX�E�F�[�f�������ǂɖ����Ă����u�o�C���C�g�̑��v�����������B
�y�o�[��������̃��[���z
�u���̏�Ԃ͈����Ȃ��B�v�������ǍD�BSACD�n�C�u���b�h�ŏo�����ƂɌ��߂��B�}�X�^�[�e�[�v�����ꂽ�B���ꂩ�特���ƃm�C�Y���̃`�F�b�N�������Ȃ��A�N���ً}������ڎw���ăX�^�W�I��ƒ����B�}�X�^�[�e�[�v�Ɉ₳�ꂽ���͈�J�b�g�����ɁA85���Ԃ�1����CD�ɂ����^����\��ł���B���̓`���̖����̊j�S�ɐG����邱�Ƃɉ�X�X�^�b�t�ꓯ���������Ă���B�v
�o�[��������M��R�₵�č�ƒ���SACD�n�C�u���b�h�Ձu�X�E�F�[�f���������������ɂ��o�C���C�g�̑�9�v�Ɍ�����ҁI�i�A�������j
�y�o�[��������̃��[���z
���������ҏW�Ȃ��̃Q�l�v���Ƃ������I�`�͂Ȃ����Ƃ��F��
�Z���^�[�łƂ̈Ⴂ�͖������ł����c
�Q�l�v���̕����f�����m���ł���
EMI�Ղ̓��b�O�̎肪�������o�[�W����
Furtwangler Broadcasts & Broadcast Recordings 1927-1954�ł�
�Z���^�[��SACD�I�N�ō��l�݂͂����l�ܖځH
>>693 �v�l���������Ă��ˁB
�u�{�ԉ��t�O�ɘb��������Ȃ�Ă��肦�Ȃ��B
�@�o�C���C�g�̂��̓��A�����q�Ȃɂ��܂������A�������Ȃ��Ƃ�
�@���Ă܂���ł����v
��������̃��[�`���[�u�Řb��ɂȂ��Ă��
�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO >>703 ����Ƃ��Ȃ��Ȃ����L�`�K�C���܂��Ăъ�悤�Ȃ��Ƃ�����Ȃ�S�~
�L�`�K�C������l�^�t�����Ă�ˁH
�]���̐��X�E�F�[�f�������̉������������̂�
�풆�̃}�O�l�g�t�H����p�������̂��A�p�ẴA�Z�e�[�g�ՂɈƑւ�����
�قƂڂ肪��߂���e�[�v�^�����ĊJ�����Ƃ����o�܂����������炾�Ɛ��@����B
FM�����̓h�C�c��1949�N���炾���X�E�F�[�f����1955�N����炵���B
https://www.radiomuseum.org/m/agabaltic_s_en_2 ~year.html
https://www.radiomuseum.org/m/philips_s_en_1 ~year.html
1951�N�̊C�O���p������ǂ������i���̂��̂������������ƂȂ邪
�����ق���AM�����ł̎�����O��Ƃ��Ă�̂�10kHz�����̋K�i�ƂȂ�B
����Ƃď����͐풆�̃}�O�l�g�t�H����������������Ȃ̂�
�����ł̉������ێ�����Ă���A�ȑO�̃X�g�b�N�z�����֘A�̉������
�����Ƃ����Ƃ������z�ɂȂ�̂��Ǝv���B
>>697 �Z���^�[�ł̓Q�l�v���̃I�`��](��)
����̃X�E�F�[�f�������łƃZ���^�[�ł̉��t�̕����ɑ����Ȃ�Ƃ��Ⴂ������
�Ƃ�����܂��䂪�[�܂��ˁB������Ƃ����Ȃ��Ăق����C�������邗
���ƁA
>>638 �ŏq�ׂ��Ă���55���g�̒��̑�X�̊y�͊Ԃ̒��O�m�C�Y�i�̂悤��
��������m�C�Y�j�Ɠ������̂��A�X�E�F�[�f�������łɂ�����̂��ǂ�����
�C�ɂȂ�Ƃ��낾�B
HMV�̃N���b�V�b�N����̂P�A2�A�R�ʂ́A�v��V�O�N�������Ȃ��t���g���F���O���[�B
�V����50�N��̃I�P�����������蒮����ׂĂ�����
>>711 ����A���ꂪ�܂Ƃ�
�F���x�炳�ꂷ���B�t�����F�������ŋ��
�����ɒ�ʂ���M���b�Ɛc�̂��鉹��EMI�̃t���x���̖��͂��ƍ��荞�܂ꂿ����Ă��邩��ȁ[
�l�I�ɂ͎��̓u���C�g�N�����N���}�X�^�[����������
55���g�̂���CD11�A12���܂����B
>>715 ���X�ɏo�Ă��鏬�l�^�Ǝ����ɂ����u�قق��v���Ă��܂�
���肪�Ƃ��������܂�
>>612 ����̏����u49�N�̃��c�F��������e�[�v���R�[�_�[���������ꂽ���ǁA
51�N�܂ł�SP�̎��^���Ԃɍ��킹�ĂԂ�^���������v�����Ǝv�����ǁA
�`���C�R��4�Ԃ⌷�Z���A���c40�Ԃ����������͐V���̕������悪�ǂ��o�Ă��Ċ������ȁB
�W���P�ɂ�from original tapes�Ƃ��邩��A���}�X�^�[�ƌ������V�ҏW�Ղ݂����Ȃ��̂��B
>>684 ����̏����u���R������L�͈̔́A���Ղ͒m��Ȃ��������Ɗm���ɑf���炵���P���������B
���̕ӂ��āA�悤�₭�����Ă悩�����Ǝv�����B
�o�C��̑�S�y�͖`���ȂI�^�P���̔N�����ɕ����Ă��Ƃ����v����(��)
�o�C��̗��pp���炢�Ŏn�܂�I�P�ɂ�銽��̉̂͘^���̈��������̂ǂ̔Ղ��ǂ��������Ă������莊�ɂ�����
�������̃��W�I�����ł̓V�F���b�N��SP�Ղ𗬂����͂�
>>718 1941�N2���Ƀe�[�v�ɘ^�����ꂽ�u���b�N�i�[No.7�Ȃ�Ė�������B
����̓e���t���P����SP���R�[�h�̂��߂̏��Ƙ^��������f�B�X�N�ւ̃_�C���N�g�J�b�e�B���O�^�����B
Furtwangler Broadcasts & Broadcast Recordings 1927-1954
55���g�̂���CD13�A14���܂����B
https://furtwaengler.org/download/Auftakt_und_Ausklang.pdf �����ł�28���߂��������Ԃƍ��v����̂��x�[��VPO(1943)���Ƃ����ӌ��B
����������p�Ƀe�[�v�^�����ꂽ���́B
���łɋr��38��
�i������|��j
>>700 >EMI�ɘ^�����������Ă��܂����o�C���C�g�ŁA�C�O�����p��
>�ǂ��������@�ł�������H
�����m�̒ʂ�A�����̓��W�I�͐����p��������O������
���^�̑������݂Ƃ͊��o���܂�Ŕ��Ȃ̂ŁA��a���������邪�A
���W�I���e���r�����������f�t�H���g������
���w�E�̂悤�ɁA�o�C���C�g�̑��̓~�����w���A�p���A
�V���g�D�b�g�K���g�A�X�E�F�[�f���Ő��������ꂽ
���͈Ⴆ�ǁA���[���b�p�͑嗤�łȂ����Ă���
���{�ł��瓖�����A�k�C�������B�܂ŒÁX�Y�X�A��������
������O�������킯�ŁA�Z�p�I�ɂ͖��Ȃ�����
>>726 �d�b�̒��p����̉�����WE�Ȃǂ̎��؎����ł݂��邪
���̂܂���͗l�̐��͒n�}��������������
�h�C�c�암����p����X�E�F�[�f����Hi-Fi������͂���Z�p��
�ǂ��������̂Ȃ̂��ɋ������������B
�����炭�����͖����ł̑��M�ł͂Ȃ�
�d�b����ɂ��L���`����������������Ȃ��B
�X�E�F�[�f���̓f���}�[�N�o�R�iMalmo?Copenhagen�j
�p���ւ̓X�g���X�u�[���o�R�ʼn���Ԃ�ڑ�
>>694 Bavarian radio, Munich
�~�����w���̃o�C�G���������ǂ���
�~�����w�������Ȃ�ĂȂ���
�L���O���R�[�h�̍L��S��or���т�����܂������H
>>728 BIS���甭���\��̃o�C���C�g�̑��̉����͊��ҏo���Ȃ��Ǝv���B
55���g�̂���CD15�A16���܂����B
>>732 ���O����������
���x�܂��R�����g��
���O�̐l����\���Ă���悤�Ȃ܂��R�����g��
���d�b�����AM�������x���̉���
�d�b����ł�1930�N���20kHz�̓`�����\�������B
�i�����̓t�B���f���t�B�A�`���V���g���Ԃ̃X�e���I�`�������j
https://archive.org/details/bellvol18system00techniamerrich/page/294/mode/2up ���̓��X���������C�R���C�U�[�Ŏ����グ�邽��
�ʑ����c�ނ̂ƃ_�C�i�~�b�N�����W��������B
>>733 ���O�����A������
���O�����A�܂��R�����g��
���l�̂��Ƃ��A�ᔻ���Ă���
���O�̕������l���A
���̂��̂�
�܂����݂��ɂ܂�Ȃ��l���𑗂��Ă���Ƃ������Ƃ�
>>735 ���܂���������
���܂���
>>732 �ł͂Ȃ������ɗ��ނ�
�W�Ȃ����l�ɗ���ŃX���r�炵�Ă���
���O�̓]���_���l�����̂��̂ł͂Ȃ���
55���g�̂���CD17�A�����h���E�t�B���̃u���[���X�����ȑ�2�Ԃ��܂���
>>740 �ĂёO���t�Ԃ���ꂽ��\�{�P�V�l�o��w
>>741 ���O����������
���O�̕������l����\���Ă���
�܂��R�����g��
�X�e�C���ꂪ���^�C�A���ăX�g�[�J�[���ł����ɂȂ�ł��傤
�y�X�e�C����(�^�R�c�{�N)���X�`�F�b�N�\�z
�E�ǂ�ł��Ĕڗ�Ȑl�Ԑ��������邩�H
�E����ւ̓i�ݎ��ݎ��i�������邩�H
�E�S�������H
�E�u��\�v���g���Ă��邩�H
�E�݂�Ȃ��s���Ɋ����郌�X���H
>>741 �͈ȏ�̑S���ڂɂ��Ă͂܂�܂���(��)
�m���ɂ܂��^�R�c�{�L���Y���Ă��܂����ȁA���̃X��
>>718 �̌��̃u��7�����ǁA�N���g�E���[�X�̏،����Ă���E�B�[�������̘^����
�X�L�[���̗̂×{���ɂ͂��߂ă��W�I�Ŏ����̉��t�����������Ə����Ă���B
������2/2�ARRG�ł̕�����2/23�Ȃ̂ŁA����͂��̊ԂɋN�������̂��낤�B
55���g�̂���CD18���܂����B
>>748 ���O����������
���O�̕������l����\���Ă���
�܂��R�����g��
�l�I�Ɏv���̂́A�^���̉����]��������Ƃ�
�����ЂƂC�ɂȂ�̂́A�j���A�m�C�Y���_�N�V�����̖���
>>748 > �t���O�X�^�[�g���A�S�����͉߂������̂�
�S�����߂����H�ޏ��̃}�z�K�j�[���v�킹�鐺�A�\���͂̐[�݁A
���̂��̎����A�l���N�����ޏ��̑S�����B�A�����J����͂܂������ɖт���������ԂŁA
������ꂾ���ŏI����Ă��A�����O�i�[�\�v���m�P�l�������낤���A
���̂��̎������������������ŁA���̏�͕����ʂ�̍ō��̃u�������q���f�ł���ō��̃C�]���f��
���B�����B
��̏����̃A���A�Ƃ������Ă�ƁA���Ղ̃I�P�͂����ɂ��t���x������
�鍑�����A�[�J�C�����ăv���X��
�����u�����̃{�b�N�X�i107CD�j�̓A�}�]���ł��A
���Â�2���~�O��ł����Ɛ��ڂ��Ă����
�����P�����ʂ������āA���E�I�ɔ��ꂽ
�����u�����͈ӊO�ɔ���肪�����̂ŁA
�Ĕ��͌���������
>>754 �̎�̐��̏o�̗ǂ��i�ǂ��܂ō��������o�邩�A�����������j�ƁA�\���͂Ƃł͐���̔N��ɈႢ������܂��ˁB
���̂ǂ�����̂邩�A�̌���p�x�̈Ⴂ���Ǝv���܂��B
���́u�̗́A���̏o�ł͂����Ⴂ���ɂ͓G��Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��Łu�S�������߂����v�Ə����܂����B
�܂��A�̉E�q��␝�E�q��i���j���A�̂̔����������S�������A�ӔN�̉��Z�͔��Q�������������^���������S�������A
�ӌ��͕�����邱�Ƃł��傤�B
����55���g�̂����ACD19���܂����B
�E�W�[�N�t���[�g�q��
�@�{�Ղł͂��̋Ȃ����Ֆʃm�C�Y�������A����͂�����ƊϏ܂̖W���ɂȂ�܂��B�܂��A�������ʼn����r�����܂��B
�@�]���Ղ��\���ɊϏܗp�Ƃ��Ēʗp�����̂ɑ��A������͂��肬��A�E�g�Ƃ��������ł��B
�@���������t���̂��̂͑f���炵���ł��B�t���g���F���O���[�F���Z���ȃ��[�O�i�[�Ɏd�オ���Ă��܂��B
�E�u�^���z�C�U�[�v����
�@�����͗ǍD�ł��B
�@���t�������̂ł����A�^���ɂ�����Ɩ�肪����܂��B
�@�I�P�����F�[�k�X�]�̂̐�����e���Ƃ���ŁA�����ׂ���������e���܂���|�������̉����قƂ�Ǖ������܂���B
�@���������̂́u�w���҂ɕ������Ă����R�[�h�ɉ�������Ȃ���������Ƒ傫���I�v�ƃ~�L�V���O���[�����w���҂ɒ��ӂ��ׂ��ł��傤�B
�E�W�[�N�t���[�g�̃��C���ւ̗�
�@����������ǍD�ł��B
�@���t�́c ���̋Ȃ͂��܂�D���ł͂Ȃ��A���̉��t�Ƃ̕�����ׂ��ł��Ȃ��̂ŁA���f��ۗ��������Ǝv���܂��B
�@���̋ȁA�킴�킴�P�̂Ř^������SP�Ŕ���o���悤�ȉ��l�������ł����˂��H�܂����̎���������ł��傤���B
�E�u���܂悦��I�����_�l�v����
�@����������I�ɖ��Ȃ��B
�@���t�����[�O�i�[�̌��I�Ȍ��ʂ��w���҂��\���ɓ`���Ă��܂��B
�����A���͏��Ȃ̊W�߂ł����B�C����蒼���ĕ����܂��B
>>758 �����W�W�C�̋Y�����Ȃ�
�K���ň����������Ă�߂����悤�Ƃ��Ă��������ۂǃW�W�C�Ȃ̂ł́H
>>760 �݂��Ƃ��Ȃ��W�W�C�̌����H
SP�����Ղ̍Đ��͋��Ƃ݂��B
�܂��I���ˁ[�̂�w
������ł��挻�����タ���Ɠ���������
>>761 ����l���Ǝv������ł�ӂ�W�W�C���̂���(^�^)(^�^)(^�^)
���Ȃ�Ō�܂ł����Ăق���
�X�e�C������^�R�c�{�N�����쎩���̒��ԂŔ�r�I���ƂȂ������Ă�����炻���Ƃ��Ƃ��Ă���
����Ӗ��ł͂Ȃ��X�e�C���ꁁ�^�R�c�{�N���Ǝv���Ă���
�{�P�ĂȂ��t�����F���Ɋ�������Ƃ̓N�����^�����ɐs����Ƃ����悤
55���g��CD20���܂����B
�i
>>773 �̑����j
�E�u���[���X�u�n���K���[���ȁv����1�ԁA3�ԁA10��
�@����������ǍD�ł��B
�@1�Ԃ�10�Ԃ̓x�������t�B���ՂƂ̔�r���\�ł����A�ǂ������Ă��x�������Ղ��t���g���F���O���[�I�Ȋɋ}���݂̉��t�ł��B
�@�悭�u�t���g���F���O���[�͔ӔN�ɂȂ�ɂ�ċq�ϓI�Ō͂ꂽ���t�ɂȂ��Ă������v�ƌ����܂����A�@���ۂɂ͕ω��͐�㑁�X�Ɏn�܂��Ă������Ƃ�������܂��B
�E���[�O�i�[�u�j�������x���N�̃}�C�X�^�[�W���K�[�v���A��1���ւ̑O�t�ȁA��3�� �k��̗x��
�@�������̂͗ǍD�ł��B
�@�������O�t�Ȃ͂��܂�ɂ�SP�p�^�����ɂ��ƂȂ������A��X�̋L���ɂ��邱�̎w���҂̉��t�Ƃ͂܂�ŕʕ��ɕ������܂��B
�@�k��̗x��́ASP�̔Ֆʂ̗]��̖��߂��̂Ƃ��Ă͔��ɏ�o���Ŗ��͓I�Ȏd�オ��ł��B
���ĂƁA���̓u���[���X�̃��@�C�I�������t�Ȃ��ڋʂł����A�]���Ղ̈�ۂ���A�����������\���������Ȃ��E�E�E
>�����������\���������Ȃ��E�E�E
>>773 ���z���肪�Ƃ��������܂�😊
����CD1���璮���n�߂܂����B
�F��U�F�̑S���r���[�ƂƂ���
�ǂ�ł��܂�
55���g�̂����ACD21���܂����B
776���^�R�c�{�N
���̔��[�͖v��50�N�Ȍ�ɕ����^�������K���[�g�Ŏ�ɓ��������_��
�s�s�`��-1
�s�s�`��-2
�s�s�`��-3
�s�s�`��-4
>>778 �܂������̂��擜���n�Q
�����o������A�E�t�^�R�g����
�t���g���F���O���[�̓x�������E�t�B���̌�C�Ƀ~�����q���K�[�𐄂��Ă���
>>786 �ǂ��ŏE���Ă����b�����m��A�K�Z�ł��傤��
�V���g�D�b�g�K���g�Ŏ��O�̎����I�P��U���āA���B���@���f�B�A
�o�b�n�A�w���f�����A�o���b�N�𒆐S�ɉ��t�����w����
�o���b�N�ȍ~�́A�n�C�h���A���|�c�@���g�A�撣���ăx�[�g�[���F���A
�V���[�x���g������܂ł����p�[�g���[�ŁA���}���h�ȍ~�̍�i��
�����Ȃ��w���҂Ȃ̂ŁA������ƍl�����Ȃ�
�f�b�J�̐ꑮ�ŁA�E�B�[���t�B���Ƃ̘^�������������݂��邪�A
�E�B�[���t�B���̕]���͍ň��������ƁA�����̃f�b�J�̃v���f���[�T�A
�W�����E�J���V���[�̉�z�L�Ƀr�b�N������悤�ȋL�q������
���セ���������K�Z����������A�^�R�c�{�N(���X�e�C����)�F��ł��傤��
�t���g���F���O���[���~�����q���K�[��]�����Ă����Ƃ����L�q���ǂ����œǂ悤�ȋL����������
�O�O���Ă݂���wiki�̃~�����q���K�[�̍��ڂ�
>>786 �̋L�ڂ������
�~�����q���K�[�̖������͖������Ǝv��
>>776 �F�쒿�E�E�E��
���O���Ȃ�̍���҂��ȁB�F��ɑ����M���グ�Ă���Ƃ��������ƁB
�o�J�ȍ���ҁE�E�E�m���ɃX�e�C����ɋ߂����̂������邗
55���g�̂����ACD22��������x�����܂����B
>>785 �Â����͑���ɓ����Ă��ƂȂ������Ă�
���^�R�}�[�N�͓\��Ȃ��Ȃ�����ˁA������
>>792 ����ɓ����Ă��ƂȂ������ׂ��̂͂��O����A���̃o�J
�^�R�X�e��͂܂�����Ă��̂�
>>414 ��ǂݕԂ�
>>424 �̎S�߂ȋC�������v���o��
���O�͕�������
������������ߒ��œ����̉��y�̒t�ق��𖾂炩�ɂ��Ă��܂�����
�܂��s���Ȃ��p�X�����ĂĎ��̌o�܂����m���Ă�낤���H
�c�C�b�^�[���������HYouTube�ɂ��邩�H
���O����������Ȃ��Ƃ��Ă��O�����łȂ��������p���������H���O�̂����ŁI
>>756 �����T�F�t���g���F���O���[���� 2022�N�J�����_�[�i�J�[�h�T�C�Y�j������300���A��������
�^�R�X�e��͐�p�X�����ĂĎ��̌o�܂����m���邻���ł�(��)
�E���j�A�̃G���C�J�̃I���W�i���e�[�v�̂Ƃ��Ɠ�����
55���g�̂����ACD23���܂����B
�E���q�����g�E�V���g���E�X�u���ƕϗe�v
�@�V�[�b�Ɩ�Ֆʃm�C�Y�͂���Ȃ�ɂ���܂����A���̂����C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂��B
�@���t��SP�̂��߂̐������݂Ƃ͎v���Ȃ��قǂ��炵���o���ł��B
�E���n���E�V���g���E�X2���u�c��~���ȁv
�@�����͔��ɗǍD�ł��B
�@���t�ɂ��ẮA
>>612 ����SP�̕\��1���ɔ[�߂邽�߂Ƀe���|�𑬂߂��|�̂�������A�]�X����K�v���Ȃ��ł��傤�B
�@������l����ASP2����3�ʂɕ����Ď��^���A4�ʖڂɉ����̏��Ȃ����^���Ă���Ă��������L������̂ł����c
�E�x�[�g�[���F���u�����ȑ�4�ԁv
�@�����͗ǍD�ŁA�_�C�i�~�b�N�����W���悭�����Ă��܂��B
�@���t�����̎w���҂炵���D���ł����A���͕������������āA�t���g���F���O���[�̃x�[�g�[���F��4�Ԃ͂ǂ���Ă������ɕ������Ă��܂��̂ŁA
�@����ȏ�̌��y�͔����܂��B
>>801 ���́u���C�Ȃ��Ȃ����v�Ƃ܂ł͎v���܂��A�]����CD���Ձi����LP����N������CD�͏����j�ɔ�ׁA���炩�Ƀo�X�������Ă��܂���B
�����܂ł͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B
���āA���ɕ���1���͏��Ȃ̊W�߂ł��BSP���������ɖ����ɋ߂Â��Ă������̘^���ł����A�ǂ�Ȏd�オ��ł��傤���B
��L�̎ʐ^�͋��NJy��̍\������1947�N�̃u���[���X1�Ԃ��ƁB
>>798 �����i���������ǁj�Ƃ�
���������ǂ́A�v�l�A�m�o�A����A����A���Ȃ̊��o�A����эs���ɂ�����
���҂Ƃ̘c�݂ɂ���ē����t������Ǐ�����A���_��Q�̈�ł���B
��ʂɌ����⌶�o�A�ُ�s����������B���{�ł�2002�N�i����14�N�j�܂ŁA
���_�����a�ƌď̂���Ă���A2002�N����u���������ǁv�Ƃ����ď̂ɉ������ꂽ�B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%A4%B1%E8%AA%BF%E7%97%87 >>805 T�����g�̕a��J�~���O�A�E�g��
>>807 �ϑz���p�[�\�i���e�B��Q
�ϑz���p�[�\�i���e�B��Q�Ƃ́A�ȋ^���p�[�\�i���e�B��Q�Ƃ��Ă��A���疾�m�ȗ��R�⍪���Ȃ��A
���邢�͉��̊W���Ȃ��ق�̏����̏o�������珟��ɋȉ����āA�l����U�������A���p�����A
�ׂ����Ƃ������s�M����^�O��a�I�Ɍ������^���A�L���ΐl�W�Ɏx����������p�[�\�i���e�B��Q
�̈�ތ^�ł���B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%84%E6%83%B3%E6%80%A7%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E9%9A%9C%E5%AE%B3 >>808 ���̎��X��
�z�������痣��Ȃ������̂��̂���w
�^�R�c�{�N�����O�[���͈̂�����q���������Ă��Ă��邩�瑼�ɍl���邱�Ƃ��Ȃ��̂��낤
���������^�R�c�{��������A
>>798 �Ő�p�X�����c�C�b�^�[��YouTube���Ƃ������Ă����ǁA�ǂ��Ȃ�����
������ŕs���⎹�i���Ԃ��܂��Ă���A�X�������a�ɂȂ��Ă߂ł����߂ł����Ȃ��ǂ�(��)
�V�Q�͂͂�o�Ă��Ă�(�}�W)
�^�R�^�R�ƃV���X�^�R�[���B�`�X����
>>809 ���[�`���[�o�[�ɂȂ�ɂ�
YouTuber�ɂȂ�ɂ́AYouTube�Ō��J���铮����B�e���A�ҏW���Ȃ���Ȃ�܂���B
YouTube�̃A�J�E���g�́AGoogle�A�J�E���g����������ɍ쐬�ł��܂��̂ŁA�������
���Ȃ��ł��傤�BYouTuber�ɂȂ邽�߂ɂ́A�B�e�@�ނƎB�e���������ҏW����
�Œ���̃X�L�����K�v�ł��B
https://mynavi-agent.jp/dainishinsotsu/canvas/2021/06/post-489.html#: ~:text=YouTuber%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81YouTube%E3%81%A7,%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
�^�R�c�{��������ɂ͈ꍏ���͂₭�o�Ă����Ă��炢�����Ƃ݂�Ȏv���Ă���悤�ł���(��)
55���g�̂����ACD24���܂����B
�i
>>816 ��葱���j
�E�`���C�R�t�X�L�[�u���y�Z���i�[�h�v��� �����c�A�I��
�@�����͔��ɗǍD�ŁA���y��̑��������������Ă��܂��B
�@���t���ǂ��̂ł����A�~�������ΏI�Ȃł͂����ƃA�b�`�F�������h���~�����������ł��B���ASP�p�^���Ƃ����Ă͎d���Ȃ��ł��傤�B
�E���n���E�V���g���E�X2���u�s�`�J�[�g�E�|���J�v�O���b�P���V���s�[������A�Ȃ�
�@�����̓O���b�P���V���s�[�����肪��ςɗǍD�A�Ȃ��̕��͔Ֆʃm�C�Y������܂��B
�@�����t���ʁX�̃e�C�N���Ƃ������Ƃ͂����m�肵�Ē����Ȃ�܂����A���t�͂܂�őo�q�̂悤�ɂ�������ŁA��������̂��ނ��ł��B
�E���[�c�@���g�u���J�v��� ��̏����̃A���A�u�|����Ȃ��ėǂ��̂ł��A�䂪�q��v�A�u�n���̕��Q�͂킪���ɔR���v
�@�����́A�m�C�Y�͖����̂ł����A�̎胊�b�v�̉̂̃t�H���e�B�b�V�����}�C�N��������ꂸ�A�������̉����ꂪ����܂��B
�@���t�́A���̐������̂��o�����Ƃ��������A���b�v�̍ō����̓W����A�Ƃ��������ł��B
�@���J�̃A���A�A�p�p�Q�[�m�́u���͒��h���v���A�����ł͈����̐����ŁA�P�Ƙ^���ł͑P�ʂ̐����ʼn̂���̂͂悭���邱�Ƃł��B
�@�������A���b�v�́u�n���̕��Q�v�ŁA���炩�ɖ�̏����̈����̐������̂��o���Ă��܂���B
�@�u���͒��h���v�Ȃ�Ƃ������A���̃A���A�ň����̐������o���̂������A�Ƃ����̂͂������Ȃ��̂ł��傤���H
���āA����CD�̖ڋʂ̓`���C�R�t�X�L�[�̌����ȑ�4�Ԃł��B���[�i�[�͑O�}�X�^�[���特���ɍא�e�[�v���g���n�߂܂������c
>�`���A�i�E���X��
806�A807�A809 �͑S�ē���l���i�^�R�c�{�N�j�̏������݁B
������
���ƁA815���^�R�c�{�N�̏������݂����A812���������B
>>818 �����������I�ȏ؋��ł��ꏏ�ɉ����Ȃ����
���t�̐^�U������ɂ��������Ȗ�肾�Ƃ������ƁB
��{�I�ȉ��t�̗ǂ������͕ʂ̖��B
�o�C���C�g�̑��̖���
1.EMI���t�����F���̑����X�^�W�I�^������`�����X����
�@�����ߌ��Ƃ��ă��b�O���Ȃ̏o�������o�C���C�g�ƃ��c�F������2�ɍi��
�@�Ȃ̃V���o���c�R�b�v�̋����ӌ��Ńo�C���C�g���̗p
2.�t�����F���̃��C���^���̃����[�X�̓o�C���C�g�̑�オ��
�@����ɂ�胉�C���������_�i�����ꔭ�@��������ʂɏo��
3.EMI���o�C���C�g�̘^������Ɛ肵�Ă���
�@���C���Ŗ��Ɗ����������̓��n�[�T�������ŏC��
�@����͓����̘^�����@�Ƃ��ĕ��ʂ̎�@��
�@1960�N��ɉ����O���u�����K�̎����^���v�ƌ��y���Ă���
4.���C�����_�Ƃ����}�����Ƃ�������ĕҏW�s�ׂ͂���ɏ�h��
�@���C�����t�ł��邱�Ǝ��̂������̊j�S�Ƃ����F�����ł܂�
���x�o��SACD�̃o�C�X���A���̂��߂���������Ȃ�
SACD�ŏo������ɂ́A�Œ�I���t�F�I�ȏ�̉����łȂ��Ƌ�����
>>819-851 ��ϗD�G�ȃ^�R�c�{�`�F�b�J�[���������̗l��(��)
�^�R�^�R�p�j�b�N���o�Ń^�R�c�{����o�Ă�����Ԃ��������Ċy�����
�u��\�v���X���o�Ă�����哖����ƌ������Ƃ�(��)
55���g�̂����ACD25���܂����B
>>823 �X�E�F�[�f���֒��p���ꂽ���̘̂^��������������o�C�G�������������̉���������ꂽ�I���t�F�I�Ղ�艹�������Ȃ�͔̂������Ȃ����낤�B
SACD�Ŕ�������̂͒P��SACD�̕������^���Ԃ��o���邽�߂��Ǝv����B
�S��85��������SACD�łȂ���P���Ɏ��^�o���Ȃ����߂��Ǝv����B
����BIS���甭�������SACD�͉����͊��ҏo���Ȃ��̂ŁA���̂��߂̎����Ǝv�������������Ǝv���B
�ǂ���55���g�̈Ӑ}���A�ŐV�̃��}�X�^�[�Ƃ����G�ꍞ�݂���
>>826 �u�܂��s���Ȃ��p�X�����ĂĎ��̌o�܂����m���Ă�낤���H
�c�C�b�^�[���������HYouTube�ɂ��邩�H�v
��
>>828 �@���ہA�����55���g�ŏ��߂Ė��炩�ɂȂ����������������ˁB�f�B�X�R�O���t�B�̍������������ꂽ�̂͑傫���Ǝv���B
�����ł̓A�}�`���A�ɂ��瑊��ɂ���Ȃ��đ�p�̃A�}�`���A���܂��炩���Ďw���҃J�����u���Ď��Ȏ������Ă�v���̎w���҂���
�������̏Ǐ����Ɍ���Ă��镶�͂ł��ˁB
���˂����݂ǂ���͂�����ł����邪�A�܂�
>>826 ���������肾�ƁA�{�l����̏������݂��ƌ��ߕt����A�^�I�J�����܂Ɍ������邪
�܂����^�R�c�{�������������ȃA�^�I�J���Ƃ�(��)
>>831 ��p�X�����c�C�b�^�[��YouTube�ŕs���⎹�i���Ԃ��܂����
�ǂ���������^�R�c�{�̒��ł������Ă邾���Ȃ�A������A�^�I�J�ɂȂ��
>>827 >�S��85��������SACD�łȂ���P���Ɏ��^�o���Ȃ�
�m���ɂ����ł����A���̓_��Y��Ă��܂���
��H
>>835 CD�w��85���l�ߍ��ނ炵����B
�ǂ����Ō����B
>>827 ����̂̓Z���^�[��(�I���t�F�I)�Ɠ����̔��H
�ł����ꂪ�{�ԁH
12���܂ł܂��܂�����(��)
>>827 ����A�����ƁAEMI�ՂƂقړ��ꉉ�t���Ǝv���B
�o�C�G���������̃e�[�v�̓��n�[�T�����Ǝv���B
�o�C�G���������̉����ō��ꂽ�Z���^�[�Ղɂ͓r���Ńe�[�v���q�����悤�ȉӏ��������ȁB
>>839 �e�[�v�̎��^���Ԃ̖�肶��Ȃ��H
1955�N�̎��_�ŋU���i���n�[�T���j���o������A�o�����Ȃ��H
55���g�̂����ACD26���܂����B
�t���g���F���O���[���ăh�C�c���y�̌����̂悤�Ɏv���Ă��邯�ǁA���͓����Ƃ��Ă͑������p�[�g���[�L����
�ł��^�R���̃X���������ƊĎ����Ă��H
�����ƁA�^�R�c�{�N�̈����͂����܂ł�(��)
>>841 �o�����
EMI��1955�N�Ƀo�C���C�g�̑�X���������ɂ��̉��t�Œ��������O����������h�C�c�ł��٘_���o�Ȃ������̂�����AEMI �Ղ��{�Ԃ̘^�����낤�Ǝv���B
�w���҃t���g���F���O���[�������̂����V�x���E�X���낭�ɏЉ�Ȃ������̂�
>>841 �o�����B
�����O��1968�N�̒����ňȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u�t���g���F���O���[�ɂ��x�[�g�[���F���́w�������ȁx�̃��R�[�h�i�G���W�F���j�́A
�����K�̎����^���A�Ƃ�������̂ŁA���O�̊P�Ȃǂ������Ă���v
�����Ƃ����t���̂��̂͑�ϕ]�����Ă���
�u���́i�o�C���C�g�́j���t�̓��_�I�Ȕ��M���́A
�����ł��A�����������R�[�h�ŏ��L�ł���ō������́w���x���v�킹��v
�Ƃ��L���Ă���B���C���ł��邱�Ǝ��̂͂ǂ��ł������̂��B
�ǂ������`��ő����K�̎����Ƃ����������͍��ł͕�����Ȃ���
�uLP�Đ����u�̓t���g���F���O���[�ƃ��R�[�h�ʼn�b����}�́v
�Ƃ܂Ō������l�Ȃ̂ŁA����Ȃ�̏��\�[�X�������Ă̂��Ƃ��Ǝv���B
�ނ����C���̃t�����F�������R�[�h�Ƃ��ĔF�m���ꂽ�̂�
�����1970�`90�N��̃t�����F�����@�����̃��b�V����
21���I�ɓ����ĕ��������̃I���W�i���e�[�v�����J����
>>848 �Ȃ�قǁB����͗L�͂ȏ��ł��ˁB
����σZ���^�[�Ղ��A�{���̃��C�u���B
�{������Y�̃��W�I�ԑg�ŁA���s�s���̍L�㎁���x�[�g�[���F����5�Ԃ��o�[���X�^�C���A�J�������A�t���g���F���O���[�ł̈Ⴂ��������A�{������Y�̓t���g���F���O���[�̃^������ō��ɗǂ��Ɛ�^�������B
>>850 �ł��^�R�c�{�N(�X�e�C����)���̃X���������ƊĎ����Ă��H
�{���Ă邵�������������Ă邩�m���ĂĔ������邩��w
>>849 �u���[���X2�Ԃ̃��C����EMI���烊���[�X���ꂽ�̂�1974�N����
55���g�̂����ACD27���܂����B
>>857 >�]���ՂɂȂ������y�͊Ԃ̃C���^�[�o�������^����Ă��܂�
���A�����Ȃ�ł����@�m��Ȃ������ł�
�莝���̂b�c�Ŋm�F����ƁA������CDC�K�i�iCDC-7470812�j�́A
�y�͂̃C���^�[�o���́A���ׂăJ�b�g����Ă��܂����A
2010�N���}�X�^�[���ƁA�P�y�͂ƂQ�y�͂̃C���^�[�o���̂݁A
���킴��Ɖ��m�C�Y�����^����Ă��܂���
�ŐV���}�X�^�ɂ�����A�y�͊Ԃ̃m�C�Y���C�ɂȂ�܂�
BIS�ՂƂ̔�r���҂��������ł�
>�i���������Ă���55���g��LP�����S�����������S�Œቹ�������Ă��Ȃ������猙���Ȃ��B���ȗ\��������c�j
>>859 �}�W�ł���
����������A���܂ЂƂ����ɂ��Ď��ꂪ���������̂ŁA
�C�ɂ��Ă܂����@�g���X�^���ƃC�]���f�S�Ȃɂ��ẮA
�͂�����Ɓu�O�̃��}�X�^���D�݁v�Ƌ��Ă����̂ŁE�E�E
����ς肻���ł�����
���̂�������₷�����Ăȁi�����j
>>860 �q���g�F
>>711 �@
>>717 �@
���������������ɂ͌l��������܂�
���I�y����@���Ȃ͒�������̂Ŗ���
�uLP����ȍ~�̃��m�v��
����SACD�ŃX�s�[�J�[�O4�`5m�̈ʒu�ł���Ȃ�̉��ʂŒ����̂��l�I�Ƀx�X�g
�V�Ղ��ƒ��̏o�����̑���Ȃ�������ƁA�C���z�������肾�Ƃ����̂�������Ȃ����C���z��������
54�N�̉^���������傢������ׂ��Ă݂���
�F�삪�ǂ��v�����͊W�Ȃ�
>>845 ���O�̐��͕̂������Ă���(��)
�ϑԂƂ����V�F���w���A�N�����y���[�A���ƒN�������H
��������Let It Be �X�y�V�����E�G�f�B�V����2021���Ă邯��
���T�C�Y�̃R���|��C���z�����Ɓu�y���|�b�v�Ŗ��邭�N���v�ȉ��̕��������f������̂���
���܂��ɉF��Ƃ������Ă�o�J�o��w
>>873 �����X�����A�o�J�͂��܂�����
�ނ��Ă邱�ƂɋC�Â���
�o�C���C�g�̑��
�o�C�G�����Ղ̓t�����F���D�݂̎w���ғ���̒��Â�1�{���^�̂悤�ȉ�
>>859 ���傦���I
���x�̃��}�X�^�[�Z�t�͉�������Ă���H���ꂩ�����̂��J�T�Ŏd���Ȃ��ł��B
����͂��Ă����A55���g�̂����ACD28���܂����B�u�o�C���C�g�̑�9�v�ł��B
�����́A���̔ՂɌ����Č����A�ǍD�ł��B�����ƒቹ����������������ł��傤������ŏ\���ʗp���܂��B
�Ղɂ���Ă͑��y�͍Č����̃e�B���p�j���ł̉��ʂ��i���Ă�����u����̉́v�̃��t���C���̍������ォ�����肵�܂����A
���Ղł͂���Ȃ��Ƃ͂���܂���ł����B
���t�́A���y���̂��̂Ɍ����Č����A���������]�X���邱�ƂȂǎc���Ă��܂���B
�������̘^���ɂ́A�����A���t�̑��Ɂu�ҏW�v�Ƃ�����肪���݂��܂��B
�ҏW�ɂ��ē��Ղɂ��Ȃ�̋^����������̂ŁA�w�b�h�z���ł�����x���������A���̒��g��������Ɛ������Ă݂܂��B
����͎���i�����H�j���e�ɂāA�Ƃ������ƂŁB
����A�ӊO�ƍD�]���ł���
�����Ɛh���ł���Ǝv�����̂�
>>875 �����ɋC�Â��Ȃ��̂��^�R�c�{�N�̂������Ⴓ(��)
�������g�̊���}������Ȃ��q��������������Ȃ�ȂƎv��w
�ق��B�����n�Q�A�^�R�W�W�C�A�Z���^�[���͂�����ւǂ����B
���������y�t���g���F���O���[�Z���^�[�z
http://2chb.net/r/classical/1635510807/ �A�^�I�J�����n�Q�̃^�R�c�{�W�W�C��A�悩��������Ȃ���
���ꂩ���
>>880 �̃����N��̑���œ�������ւ̌l�I�Ȏ��i�ƕs���s�����Ԃ��܂��邪����(��)
�킩�����ȁI
�^�R�c�{��A�������̃X���ɍs���Ă������
>>802 �x�[�g�[���F��4�ԑ�1�y�͂̕ҏW�~�X��?
https://furtwaengler.org/download/RundfunkSenAuf.pdf ���A���t��̓��t������Ă�����A�ǂꂪ�{�����B
1947.05.24�@BPO�@NWDR�@
Beethoven: Egmont Ouv., Symphony #6, Symphony #5
1947.05.25�@BPO�@RIAS
Beethoven: Symphony #6, Symphony #5
1947.05.26�@BPO�@Germany&NWDR
Beethoven: Egmont Ouv., Sym #6, Symphony #5
�����Ă�̂�5/25��RIAS�����Ƃ����Ƃ��낾��
>>885 ���������Ă��ꂱ�꒲�ׂĕҏW�~�X�̉ӏ���˂��~�߁A�ǂ߂����Ȃ��y�����ɂ݂Ȃ���A���߂�CD23���܂����B
���_�́u�����Ă��Ȃ��v�ł����B�����E�x�����������āA��̂߂�悤�ɉ��y���i�s���܂��B
���}�X�^�[�Z�t���A���̉ӏ��i��1�y��141���߁A143���߁j�Ɍ���������A�Ƃ����������̂�m��Ȃ������̂ł��傤���H
�������Ղ���N�����̂����ڂ��ď]����LP�p�e�[�v���g�����̂ł��傤���H����Ƃ��������Ղ͔p���ς݂ł�ނȂ��̂ł��傤���H
�Ȃ��A�^�[������o���E�B�[���t�B���Z�b�g�̒���FURT1085�Ɏ��^�̂��̉��t�́A���̉ӏ��������Ă��܂��B
����͂��Ă����ACD28�i�o�C���C�g�̑�9�j���w�b�h�z���ŕ��������܂����B�ҏW�ɋ^������������߂ł��B
�^��_�́A�܂����̉��t���{�ԂłȂ��Q�l�v�����Ɖ��肵���ꍇ�A
�E�����̊W�҈ȊO�������Ȃ������͂��̃Q�l�v���ŁA�`���ɂ���قǐ���Ȕ��肪�����Ă���̂͂Ȃ����H
�@�����̉����F�`���̐���Ȕ���͌ォ��\������B�r���Ŕ���̎����ς���Ă��鏊������B
�E�I����̐���Ȕ���͏��l���ł͏o���Ȃ��̂ł͂Ȃ����H
�@�����̉����F�I����̔�����\��t���ł���B�w�b�h�z�����Ɩ��炩�ɐ�p���̍��Ղ��������邵�A����ȏI�������ꂽ�璮�O�͈�u�������ɂƂ��A�����ނ�ɔ��肪�N����͂��ł���B
�E����������\���������Ƃ����Ȃ�A����u���Ă������ׂ��Ō�̈ꉹ�̃Y���������Ă��Ȃ��̂͂Ȃ����H
�@���̉����F�����̐�\��Z�p�ł́A�Ȃ̓r���Ő�\�������͎̂���̋Ƃ������̂ŁA���y���t���̂͐�\�肵�Ă��Ȃ��B
�i�����X�ɑ����j
�i�O���X��葱���j
�����̎w���҂Ƃ��Ă̎�����ے肷�鏑�����݂ɁA�Ȃ����������邩�������o���Ɣ��_���܂��B
�Ȃ��A���̂ւ�Ŋ��Ɂu�ʃX�����Ă�v�ƌ����Ă��ł��ˁB
������l����A���̂ւ�ŗ��Ă�ׂ��������̂ł��傤�ˁB
244 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/07/27(��) 06:56:23.30 ID:kXiadRJS
�^�R����͉��y�Ɓi�w���ҁA�w���ҁj�Ƃ��Ă̓S�~
���R�[�h�}�j�AYouTuber�Ƃ��Ă͗L�\
���Ă��Ƃ�FA�H
246 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/07/27(��) 08:34:45.83 ID:dG3sX6g8
>>244 ��l�̉��y�Ƃ��S�~�Ă�肷��̂ł����
���̎w���҂̉����ĉ������ł��邩��������Ȃ���
�܂��������Ȃ��ŃS�~�Ă�肵�Ă��Ȃ�����H
249 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/07/27(��) 08:54:49.28 ID:i33Q8EM+ [3/4]
�W�����A�[�h����w�����Ăǂ����̃X���ɏ����Ă���������
�Ă�����Ȃɂs������̖{�Ƃɂ��Č�肽���Ȃ�ʂɃX�����Ă����������Ǝv������
�����덪���������ė�����������ł���l�͂��Ȃ��̂ł��B
331 ���O�F�������̓J�̗x��[] ���e���F2021/08/19(��) 17:48:46.96 ID:GneMfZ9F [4/4]
>>329 ���ɓI�Ă���B
�o���҂���Ȃ��Ƃ킩��Ȃ������B
332 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/08/19(��) 18:20:03.67 ID:mcbhKgcZ [2/2]
>>331 �ł͋M���Ɏ��₷��B���̂悤�Ɍ�������ɂ́A�������w������
�I�[�P�X�g���̉��t�̓�����M���͌��Ă���Ƃ������ƂɂȂ��ˁB
����ł��A�ǂ̓���̂ǂ̕����Ɂu�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v���Ƃ�
��̗Ⴊ����̂��A�����Ă����B�����url�Ɖ������b�̏��Ȃ̂��B
���͕ʂɓ�������̃t�@���ł����ł��Ȃ����A���������Ȃ��ōD�������
���ƌ�����������Ȃ�ˁB
338 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/08/19(��) 23:18:28.12 ID:/kePqBnL
>>332 >���͕ʂɓ�������̃t�@���ł����ł��Ȃ���
��
���l�ɂȂ肷�܂������肾�낤���{�l�o���o������w
340 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/08/20(��) 00:11:36.07 ID:kiM33CqM
��p��20�N�����Ă��̒�x�����Ⴈ�b�ɂȂ�Ȃ�������
341 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/08/20(��) 01:27:19.50 ID:ocXj6GjH [1/2]
T�͎����ɂƂ��ēs���̈���youtube�R�����g���������ƍ폜���ďL�����ɊW�����Ēm���Ղ肷�锖�����N�Y
344 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/08/20(��) 11:19:48.30 ID:+ppjeLsN
Youtube��T���̎w���݂Ă݂����Ǎ����ȁB
���M�Ȃ����ȃt���t���Ȏw���A���t�̓w���w���B
�_���_�����B
���x���딚���Ă��݂܂���B
420 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/09/01(��) 19:57:36.04 ID:Orlk6ajM [5/7]
�u�J�b�R�����U������Ă�Ƃ���v���u�U��グ�ŗ������������Ƃ��Ď��s�����Ƃ���v
�����ł��B
421 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/09/01(��) 20:29:40.58 ID:Orlk6ajM [6/7]
>>388 �����ł̓~�X�^�[������
>�Ⴆ�t���[�Y�̏I���ŏ����e���|���ɂ߂悤�Ƃ���
�ƌ����Ă���B���m�Ɏw���҂������̈ӎu�Ńe���|��ς��悤�Ƃ��Ă���s��
����ˁB������
>>416 �����ł�
>�e���|���ɂ߂悤�Ƃ��遁�w�^�N�\�Œx���
�Ƃ����}���ɂ��āA�w���҂̈ӎu�Ƃ͖��W�ȃe���|�̗h��Ɍ���������
���܂��Ă���B���邢��ˁA�~�X�^�[�����B
422 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/09/01(��) 20:54:25.99 ID:Orlk6ajM [7/7]
��L�̌����������s�Ȃ����̂�
�u�w���҂������̈ӎu�Ńe���|��ς��悤�Ƃ���Ƃ��ɁA�Ȃ�����������
�K�v������̂��v�Ƃ����A�v���I�Ȏ����������邽�߂���ˁB
���邢��ˁA�~�X�^�[�����B
423 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/09/01(��) 21:43:13.39 ID:ogWC6Ylm
�������������ɂ���I
�E�E�E��H
���x���딚���Ă��݂܂���ł����B
����A�����ƃZ���^�[�̘b��͂�����ň����܂��B
�^�R�c�{���ǂ��Ƃ��Z���^�[�̐�`����悤�Ȃ̂������炱����ɗU�����������B
���������y�t���g���F���O���[�Z���^�[�z
http://2chb.net/r/classical/1635510807/ NGWord�F
�S�~���딚����ȁI
55���g�̂����ACD29��30���܂����B
>>903 ���q�l�����`�����H��Ȃ����т��q���A
�~�V�������́A�L�҂ɂȂ���������I�ȓ��e�ł���
>>904 =
>>905 �����Ă��邱�Ƃ����ȕ��Ă��܂���BID�̕ς��Y��ł����H
����͂��Ă����A55���g�̂����ACD31���܂����B
�E���[�O�i�[�u�_�X�̉����v��� �u�������q���f�̎��ȋ]��
�@������LP����̃��[�i�[���Љ����A������w���҂������h���ɏo�����Ă̘^���e�[�v�R���Ƃ����āA�ǍD�ł��B
�@���t���A�t���O�X�^�[�g�͐��̗͂ŕ�����������▭�ȋZ�̗͂ŕ������銴���ŁASP�Ղ����[�݂̂��錀�I�\���ł��B
�E�}�[���[�u�����炤��l�̉́v
�@���̋ȁA�����炤��l�̉̂Ƃ����̂͌��ŁA�u��E�l�̉́v�ł��B���Ɏw�E����Ă��܂����A���̂��Ȃ��h�C�c��͂ł�������܂��B
�@�܂���E�l�Ȃ�Ⴂ���A��������Ă����邩��A100%�̌��ł͂Ȃ���������܂��A�Ⴂ�������̉ɂȗ��l�Ǝv����ƍ���܂��B
�@�����͏�L���l�A�ǍD�ł��B
�@���t���t�B�[�b�V���[=�f�B�[�X�J�E�����ɐ▭�̋Z�����A�}�[���[����肾�����w���҂��t�B���n�[���j�A�ǂ𗦂��čD�����Ă��܂��B
���̈ꖇ�̓x�[�g���F����1�ԁA6�Ԃł��B�ቹ�������Ă�������̂ł����A��̕��̏������݂ł́A�ʖڂ����Ă��c
�t���g���F���O���[�̉��t��������ĉ��ł��_��������̂͗ǂ��Ȃ�
���啨���Ă��A���҂͏���
�v���̕]�_����Ȃ��A�ꉹ�y�t�@���̊��z�Ȃ���ʂɏ�肭�Ȃ������Ă�������Ȃ�
�q���Ƒ�l�ł͖��o���ω����邱�Ƃ��Ȋw�I�ɏؖ�����Ă���̂ŗ������ɏo���͓̂K�ł͂Ȃ�����
�����Z���̂̓t�����F���̂ق�����
�ł̓V�����G�b�Z���X�����킩����ō����h�C�c�����X�ɃC�L���ē���u�U���[�N���E�g���s�����v�ƃS�l�Ă�q��������������E�E�E�Ƃł����Ƃ��܂����H
�}�X�^�[�������Ȃ特�����ʂ��Ă���
>�ӏ܋L�̃��}�X�^�[�]�������Ă݂Ȃ��ƕ��͂���z�����Ă����̂ƈ������
55���g�̂����ACD32���܂����B
�c���͋��Ղ�(������)���܂�ǂ��Ƃ͎v��Ȃ������Ȃ�
>>915 ����͋M�����t�����F���ɓ��������ǂ��I�[�f�B�I�������Ă��邩
�����t�����F���ɓ����ł��邩�炾�B
55���g�̂����ACD33�A�x�[�g�[���F���́u�����ȑ�3�ԁw�p�Y�x�v���܂����B
>>920 �����炭���̉������ꂩ��̃X�^���_�[�h�ɂȂ��ł���
�u�t���x�����Đ������v�Ƃ����̂̕]�_��ǂ��̎�҂�������������ł���
�h�C�c�̃Q���}���Ȃ����\���鉹������ɂȂ��ł���
���낵���˂�
�F����Ȃ�Ȃ�ƕ]��������(��)
>>921 >�����炭���̉������ꂩ��̃X�^���_�[�h�ɂȂ��ł���
�ǂ����낤
�����55���g�́A�r�M�i�[�͂܂�����o���Ȃ����낤���A
����ŁA�}�j�A�ɂ��]�����A�������܂߁A���܂ЂƂA
����Ă�Ƃ����b�����܂蕷���Ȃ�
�d�l�h�̓x�g�S��A�u���S�Ȃǂ́A���łɐ��K�Ղ�
�����Ń����[�X���Ă���̂ŁA����͂����炪
�f�t�H���g�ɂȂ�Ǝv��
����1�����ł�CD(��`����u2021�ŐV���}�X�^�[�g�p�v)�ŏo�Ă������ꍇ��
> ���Ƃ��]���������Ă�����o�����Ⴄ�̂�
�����SP������܂߂�4�Ђ��������݂��Đ��K�^�����m�肵���_��
���̃��[�J�[�̑_���̓��C�u�W�����}�X�^�[���ł���(��)
��͂胊�}�X�^�[�̉����ȏ�ɌX�l�̃I�[�f�B�I���̍��̂ق����i�ȉ����j
���̓m�[���}�X�^�[����
�I�[�f�B�I��������
10��㔼�`20��ɂ��t���x���V���]�����҂����Ă��܂�(��)
�^���[����̃��[���ɏ��
>>933 �J��オ��܂����ˁB
�ǂ�ȉ�����яo�����(��)
55���g�̂����ACD34���܂����B
�l�I�ɂ͉��B�̒��p����̉������ǂ̒��x�Ȃ̂����m�肽���Ē�������
�t���g���F���O���[ �̌����ȑ��Ԃ́A����S�W���̐��E�ρB
55���g�̂����ACD35���܂����B
>>938 >�Ƃ̂������o�C�I���������
>�e���l������A��Ă��Ēe������
���傗
>>921 �{�����[���グ���犴�����܂����A�Ƃ����b���Ǝv����
>>938 �����j���[�C��
�ȁc���Œ�������翂т��������t�Ȃ悫��t�i�k����
1947�N�̂����炭���b�O������w�������ō����d�~
https://www.radiomuseum.org/r/hismasters_3000.html BBC���|�[�g��蔲��
EMI���ȉ~�t�������W2�{�{�f�b�J�E�P���[�����{���c�C�[�^�[��
KT66�v�b�V���v���ŋ쓮���Ă���B
100Hz�ȉ�����Ă���̂�SP����̊�{����
�w�ʂ���d�ቹ����ݍ��ނ悤�ɏo�Ă���B
����̃��{���c�C�[�^�[�͑�l���ڂɕt�����Ă���
15kHz�܂ŐL�тĂ���Hi-Fi�K�i�ł��������B
BBC�̈�ۂł͉A�T�ȉ��Ń��W�I�����ł͂Ȃ��Ƃ̂��Ƃŋp���B
���̌�̓c�C�[�^�[�����͂ȓ� Lorenz��PVC�R�[���^�ɑウ�Đ��삳�ꂽ�B
http://ukhhsoc.torrens.org/makers/EMI_Sound/index.html �����t�����F������Ȃ�l�I�ɂ̓h�C�c�����W�I�p�X�s�[�J�[���ǂ��Ǝv���B
������ȉ~�{Tw��2way�d�l���B
���R�͈�ԉ��́u�I�[�P�X�g���v��������FM�ǃ��j�^�[����������
�h�C�c�����ł̃��C�u�����͂�͂�2way�X�s�[�J�[�̃��W�I�Œ����Ă����B
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_3040gw.html ������炢�܂ŁA�J�L�R�ł��Ȃ�������B
�I�[�f�B�I�����ӂ珑���Ă�l�͂������������u�Œ����Ă���̂�
�ǂ�Ȃɗ��h�ȃe���t���P����O85a���j�^�[�����āA���̃N���X�Ŏ��܂��Ă�B
���͓��������Jensen�̃G�N�X�e���f�b�h�����W�i���v���J�j�ő�p���Ă�B
https://www.jensentone.com/vintage-ceramic/c12r �ŏI�I�Ƀg�[�L�[����̎��g���o�����X�Ɏ��߂Ă��邪
�X�e�b�v�������t�������W�Ȃ݂ɑf���Ȃ̂Ń��Y�����̓L���L���B
���Ȃ݂�1950�N��ɐv���ꂽ�X�s�[�J�[�͒�����ɋ����A�N�Z���g��������
���g���o�����X�ȏ�ɁA�X�e�b�v�����ł�����ȃs�[�N��������B
��Ȍ����̓{�C�X�R�C���ƃR�[�����̐ڑ����̋��U��
�ǂ����������h�C�c���t�������W�̓����Ƃ��Ȃ��Ă���B
�i�ȉ���SABA�O���[���R�[���̃X�e�b�v�����j
Jensen�����l�̌X���������āA�f�̂܂܂��ƃs�[�L�[�ȉ����ڗ��B
�i��i�j
����3.5kHz�Ő��Ă邪�A��������5kHz���ӂ̃s�[�L�[�ȕ�����������
�f���ȗ����オ����݂��ăj���[�g�����ȏ�ԂɂȂ����B�i���i�j
����Ɍq����悤�Ƀc�C�[�^�[�̃��x�������킹���̂�
>>949 �̓����ɂȂ�B
�f���ȃX�e�b�v�����Ƃ����̂́A�ቹ�܂ŃX���[�Y�ɔg�`���q����
�t�Ɍ����A���y�̃��Y����e���|���ቹ����x�����邱�Ƃ��Ӗ�����B
�I�P����ۂƂȂ����A�C���U�b�c�����͂������Č��܂邱�ƂɂȂ�B
�����̈�ʓI�ȃX�s�[�J�[�͑S���t�ŁA����̃p���X�������ۗ�����
�ቹ�̓^�C�~���O���x��ĕ�ݍ��ނ悤�ɍĐ������B
���̂ق�����Ԑ��Ƃ���ʊ����ቹ�ɂ���܂��ꂸ�ɏo���邽��
�悭�𑜓x�������čׂ������܂ŕ�������Ƃ����]���ɂȂ�̂���
���炩�ɒቹ��̃A�C���U�b�c������Ȃ��B���肷��̂��B
55���g�̃��c�F�����̃u���[���XVn�R���`�F���g��Audite�̃��c�F�����̉p�Y�V���[�}����Tahra�̃p�������Ȃŕ�����鐶�������Ƃ����J���t�����������{���̃t���g���F���O���[�ł���Ƃ����悤
55���g�̂����ACD36���܂����B
>>949 �̃J�}�{�R�^�̓_�������͌Â��g�[�L�[�̃A�J�f�~�[�Ȑ���
�L���f��قł̍��挸������������PA�@��̎����o�͂������Ă���B
���̓����͌��݂ł�X�J�[���Ƃ��Ĉ����p����ċK�i������Ă���
�Ⴆ��THX�K�i�ł̓t���b�g�ȉƒ�p�X�s�[�J�[��
�f�批�������̂܂܍Đ�����ƃs�[�L�[�ȉ����邽��
�Ǝ��̃C�R���C�U�[���������Ă���B
����̗��_�́A�t�����F�����D�V�݂�}�C�N�ŏW����������
�Ăу}�C�N�ʒu������˂��ăz�[���ɋ������鉹�̃V�~�����[�V�����ƂȂ邱�Ƃ��B
�@�i�t���N�n�E�X�j
�i�e�B�^�j�A�p���X�g�V���j
�i���g��j
�@�i�U���c�u���N�j
������C�R���C�U�[���g��Ȃ��ŃX�s�[�J�[���Ő�����Ӌ`��
�C�R���C�U�[�͈ʑ��ω����Ă��܂����߁A�����������ɂȂ�₷���̂ɑ�
�X�s�[�J�[���̃��x�������݂̂Ő�����ƍ���̗����オ�肪�݂�Ȃ��B
�C�R���C�U�[�ō�������������邱�ƂŋN��������ЂƂ̖���
>>952 �Ŏ����悤�ȃc�C�[�^�[�̃p���X���������������v�̃X�s�[�J�[����
�����オ�肪�݂��Ă��܂��A�ǂ��肵���E�[�n�[�̉��ɃV�t�g���Ă��܂����Ƃ��B
��ʂɃA���v�ɂ̓C�R���C�U�[��H�̖����ق����N�x���ǂ��Ƃ����̂�
�����������Ƃ������ŋN���Ă��܂��B����̓��}�X�^�[�i�K�ł����l���B
�X�s�[�J�[�̐v�Ńc�C�[�^�[�̃p���X��������������悤�ɂȂ����̂�
�ʂ̎��_�ł̓w�b�h�z����C���z���ł��ቹ�u�[�X�g���ĂȂ��@���
�X�e�b�v�������Y��ɑ����Ă��邽�߁A���܂Ō��ʂ��̂�������������B
1990�N��㔼����Diffuse Field�̕�Ńt���b�g�ȓ�����������悤�ɂȂ����B
����ł���̓�_�́A�X�l�̊O���`�炭�鋤�U�̕Ȃڎ₷��
���O���̉����Ւf���Ē������Ƃ��������߁A����ɋC�t���Ȃ��Œ������Ƃ��B
���̊O���̋��U�͒�����ɂ���A�̃��E�h�l�X�Ȑ��Ƃ��ĕ\���ꂽ���̂�
���߂ă_�~�[�w�b�h�Ōv������ƁA���̕ǂ�8kHz�ߖT��20dB�߂��̈Ⴂ���o��B
�����ЂƂ̖��́A�t�����F���̍D�V�݂�}�C�N�̉���
�w���҂������Ă鉹�Ƃ��Ă͐��������A���Œ����o�����X�Ƃ͒������B
�܂��̊��I�ɂȂ钆�ቹ200Hz�ȉ��̑ш悪���ł���������ꂸ
�t�����F���Ȃ�ł͂̃t�B�W�J���Ȗ��������������邱�ƂɂȂ�B
�ŋ߂̃f�W�^���Z�p�̉��b��
�Ⴆ��KEF�̃A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�̓X�e�b�v�������Y��ɑ����Ă���B
https://www.stereophile.com/content/kef-lsx-wireless-loudspeaker-system-measurements Stereophile���ŃX�e�b�v�������d������̂͒�ʊ��̐��m���ɂ���
����ȏ�̈Ӗ��͂��܂莝���Ă��Ȃ����߁A�����͖������Đv���Ă���B
���l�́A1�{�}�C�N�̒��^��͎��ԓI�Ȑ��������Ȃ���
�{���̃o�����X�Ŗ�Ȃ��Ǝv���Ă���B
����ŁA���^�X�s�[�J�[�ł̂����ЂƂ̖���
�R�[�����Œ��ڐU���ł���ш悪800Hz�ȏ�ł���
����ȉ��̑ш�͔��̋��ŕ���Ă���_���B
����͔�r�I�傫�ȉ��łȂ��Ǝ��g���o�����X�����Ȃ����Ƃ��Ӗ���
�d�ቹ�����t�ʂ�̏d�����\���ł�����Ȃ����Ƃ������B
�̂̃t�B�b�N�X�h�G�b�W�̃E�[�n�[�́A�@�B�I�ȃo�l�𗘗p����
�y���ăX���[�Y�Ȓቹ��f���o���Ă��������
�t���[�G�b�W�̂悤�ɒቹ���L�тȂ����ߐ�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�{�C�X�R�C�����X�p�C������̔o�l�Ŏx�����E�[�n�[�͂����Ɛ�����
�K���ȂƂ���Ő܂荇����t���Ȃ���L�����Ȃ����낤�B
Jensen��PA�X�s�[�J�[�i���݂̓M�^�[�A���v�p�j��
�N�ł����p�ł���1950�N��̃r���e�[�W�e�N�m���W�[�Ƃ���
�ǂ����Ƃ��ǂ���Ȃ̂��B
���m�����^����1�{�̃X�s�[�J�[�Œ������Ƃ́A���݂ł͂��܂�s���Ă��Ȃ��B
�Ⴆ�A�Nj������̃��r���[�ł������͕K��2�{�ōs���B
���R�Ƃ��ẮA���m��������̉f��قł������{�ݒu����
�X�N���[���̉�ʂ��璆�������ĉ��������オ��Ȃ��H�v�����ꂽ���炾�B
�����ЂƂ͘^���������X�e���I�A���m�����ŋ�ʂ�����
�j���[�g�����ɕ]������K�v�����邾�낤�B
����ł́A�I�[�P�X�g���^���̍Đ�������ɓ��ꂽ�ꍇ
2�{�ȏ�̂ق������ꊴ�����₷���Ƃ������Ƃ�����B
�Ⴆ��EMI�̘^�������݂�ƁA1930�N�ォ��3�{�}�C�N�Ŏ��^��
�I�[�P�X�g���S�̂̋������Č�����悤�Ɏ��^����Ă����B
��ʂɂ�LP�����EMI�^��������傷�邱�Ƃ̑�������
�����{�̃X�s�[�J�[�Ŗ炷���Ƃ̍������͊m���ɂ���B
�Ƃ��낪�A���ꂪ�V�݂�1�{�ł̎��^�ƂȂ��
�l�I�ɂ͖��R�Ɩ��Ă���悤�ɕ�������B
��͂�1�{���畔�����Ɋg�U�����ق����X�g���[�g�ɖ�̂��B
���m�����^����1�{�̃X�s�[�J�[�Ŗ炷���Ƃ̖���
���݂̃X�e���I�X�s�[�J�[�̑���������̎w�������i����
�`�����l���Z�p���[�V�������҂��悤�ɐv����Ă���_�ł���B
�X�s�[�J�[�𐳖ʂŒ����ē������t���b�g�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�
���ʂ���30��������Ɖ��ꊴ�������ш悪�������ɂ����Ȃ邩�炾�B
���̂��߃X�e���I�p�ɐv���ꂽ�X�s�[�J�[1�{������
���m�����^�������ꍇ�́A�����I�ɑ��������ŔE�ς��邱�ƂɂȂ�B
���Ȃ݂�
>>949 �Ōv�����������́A��45������̂��̂�
����̓X�e���I�p�Ƃ��Ă͎w�������L�����Ďg���Ȃ��B
�ȏ�A�t�����F���̈������V�݂�1�{�}�C�N�̘^������������ɂ́c
�@���g�������W��100�`8,000�g���̋��K�i�ŏ\���ł���
�@�Â��g�[�L�[����̉����K�i�i�A�J�f�~�[�Ȑ��j���D�܂���
�@�X�s�[�J�[1�{�Œ������������������X�g���[�g�ɏo��
�@�X�e�b�v���������悩����܂ŃX���[�Y�ł��邱�Ƃ��]�܂���
�@�E�[�n�[�͑���a�̃t�B�b�N�X�h�G�b�W���]�܂���
�@����̎w������90���ȏ�L���ق����]�܂���
�]����LP�^������A�[�J�C����H��ꍇ�́c
�@���g�������W�͑�͏������˂�Ӗ��ōL���ق�������
�@Hi-Fi�K�i�ɉ����Ď��g�������̓t���b�g�Ȃق�������
�@���̘^���Ƃ̃j���[�g�����ȊW�����Ԃ̂ɃX�e���I�z�u�͑Ó�
�@�E�[�n�[�͏������Ă��d�ቹ���L�тĂ����ق�������
�@���ꊴ���o�����߂Ƀc�C�[�^�[�̔����̓E�[�n�[���番������
�@�`�����l���Z�p���[�V�������ێ����邽�ߍ���̎w�����͍i��
���̑Ó��ȑI���̌������A���}�X�^�[�Ղ̖O���Ȃ��^�ۗ��_�ɂȂ����Ă���B
LP�K�i���m�肷��O��ŋN�������h�C�c�����^���Ƃ̘^���i���̘�����
���ƌl�I�ɂ́u�t�����F�����U��I�P�����ׂ���v�Ƃ������G��������
>>960 ���m�����^�����X�s�[�J�[1�{�Œ����Ă�2�{�Œ����Ă����͔���������ˁB
���܂ɁA�X�s�[�J�[1�{�ɂ��Ē����Ă݂���A2�{��_�����ɋ߂��z�u�Œ����Ă݂�̂́A������Ƃ����Ӗ�������Ǝv���B
�X�s�[�J�[�̋@��ɂ���Ă��Ⴂ���l�X����
�ł�1950�N��̃h�C�c�����W�I�͂ǂ����Ƃ�����
FM�����Ή���2�`3way
AM�����Ƃ̃R���p�`�Ȃ̂Ő��ʂɃt�������W
����͕������Ɋg�U���邽�ߗ����ɔz�u���Ă����B
https://www.radiomuseum.org/r/telefunken_opus_55ts.html �܂�Grundig��3D-Klang�Ə̂���^���X�e���I�@�\�������Ă���
�����̍��搬�����R���g���[�����邱�Ƃ��ł����B
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_3045w3d.html �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO ��L�̃��W�I�̃f�����Ĕ���̂�
> ���̋����̔��@�����������Ă���悤�Ɏv���B
�u���̉��t�Ɓv�ƌ����������ǂ��������H
BIS���������o�C���C�g�̑��͂܂��������t��ꂩ�痣�ꂽ�C�O�������B
���������������t�Ɋւ���l�X�ȃo�[�W�����̉�����ڂ̓�����ɂ����
�����������������A�A���L�`�K�C
55���g�̂����ACD37�A�o���g�[�N�u���@�C�I�������t�ȑ�2�ԁv���܂����B
�t���g���F���O���[�Ƃ������̏ꍇ�͒����A�A���ł����܂��B���̂��߂̃X���Ȃ���B
���̍r�炵�u���X���A�����͊W�҂�3���X���炢�����Ȃ����������Ă��Ă���
�I�[�f�B�I���u�̑����͉p�Ă𒆐S�Ƀ��R�[�h�Đ��ɓ������Ĕ��W�����̂�
�v��50�N���o�ĕ����Ǐ����̃I���W�i���e�[�v�̗������t���[�ɂȂ�
�̂̕��@����
>���m�����̃��C�u�^�����Ȃ�CD�̂ق����������^�C�g�������D��Ă���
BIS�o�C���C�g���
�h�{���U�[�N�̐V���E���o�����A�]�������܂��Ă��甃���������ȁA�Ǝv���Ă�����U���Ƃ킩���ē��荢��ɂȂ����̂ŁABIS�݂����ȃC�����m�͏o����m�ۂ��邵���Ȃ��B
55���g�̂����ACD38�A�x�[�g�[���F���u�����ȑ�5�ԁv���܂����B
>>980 CD�͒P�Ȃ�L���}�̂Ȃ̂ŁACD�炵�����Ƃ����̂͂��������Ȃ��B
1990�N���CD�炵�����Ƃ����̂͂��Ȃ���ꂽ�T�E���h��
�l�C�������قƂ�ǂ̍����X�s�[�J�[��20kHz�ߖT�ɋ��������M���O���o���Ă��B
���͂������ɂ��������@��͌����Ă��邪�A�f�W�^�����ۂ����Ƃ��ĕ��]�͐₦�Ȃ��B
�^��ǃA���v�ł���`�g�ŃI�[�o�[�V���[�g���N�����^�C�v��
�ڕ@�����̂������肵�����ɂȂ�̂Ə������Ă���B
�܂��A���݂̃X�s�[�J�[�̂قƂ�ǂ�
>>952 �̂悤�ȕ��G�Ȉʑ��̂˂��ꂪ����
�c�C�[�^�[�̃p���X�����ቹ�ƕ������Đ蔲���ꂽ�悤�ɏo��悤�ɐv�����B
�o�����X�I�ɂ͒������ɂԂ牺�������s���~�b�h�^�Ƃ��������ɂȂ�B
����ɃX�e���I��ʂ̂���
>>962 �̂悤�ɍ���̎w�������i���Ă���̂�
�p���X���̍������܂�ł��Ȃ��Â��^���͓ݏd�ȃE�[�n�[�ň�C�ɐF������B
�t�����F���̃��C���^����AM����FM�Ɉڍs���������
100�`8,000Hz�̗��e1�I�N�^�[���͂܂��ɂ������ŗ��܂��Ă���̂�
�f�W�^�����X�e���I�Ŗ�������p�͂قƂ�ǖ��ɗ����Ȃ��B
>CD�炵�����Ƃ����̂͂��������Ȃ�
>>984 ���X�A���肪�Ƃ��������܂����B
>>985 �X�^�W�I�ł̓w�b�h�z���Ń`�F�b�N���Ă���\���������B
���܂ǂ��N���V�b�N�̘^���̓w�b�h�z���Ńo�����X�`�F�b�N����
BIS�̓[���n�C�U�[ HD600�������B
���Ȃ݂Ƀh�C�c�����^���̓��j�^�[���[���̂Ȃ��z�[���ł̎���������
�`���I�Ƀw�b�h�z���ʼn����`�F�b�N�ƃo�����X��������B
�x�C���[�_�C�i�~�b�N DT48��1937�N���瑶�݂���Hi-Fi�w�b�h�z���������B
1940�N�ɍ����g�o�C�A�X�������}�O�l�g�t�H���̃p�C���b�g�^����
�t�����F�����v���C�o�b�N�Ŏ��������̂������炭DT48���B
�����������̃w�b�h�z���̓m�C�Y���m�Ƃ����������傫��
Nagra�̃|�[�^�u���E�e�[�v���R�[�_�[�ɕW���������ꂽ�^�C�v��
�������h�ڂɐݒ肵�Ă������B
�����w�b�h�z�������������ɋ߂����Ƃ����ƁA�l�I�ɂ͔���
�V�݂�}�C�N�̈ʒu����z�[���Ɋg�U���鉹�����������̂��Ǝv���B
���̂��ߍ��悪��������f��ًK�i��X�J�[�u�̂悤�ȃo�����X�ɂȂ�B
����
>>958 �ɂ���������
�X�l�̊O���̋��ɂ͕Ȃ������ăt���b�g�ɂ͂܂��Ȃ�Ȃ��B
�O���̉����Ւf���Ē������ƒ����Ǝ��R�ȃo�����X��������B
���Ȃ݂Ƀt�����F���̕����^���Ɏg��ꂽ�̂̓m�C�}���ЃR���f���T�[�}�C�N��
CMV3��1930�N�ɂ��łɊJ�����ꂽ���̂����A�_�C���t������U47�Ɠ������̂��g���Ă����B
https://dg.ishibashi.co.jp/?p=27417 http://www.coutant.org/u47/index.html �}�O�l�g�t�H�����܂ߘ^�����̂��̂̓t���b�g�ɘ^���Ă����ƍl���Ă����B
55���g�̂����ACD39���܂����B
���m�����ł��邱�Ƃ��䖝���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ͉��Ƃ��������Ȃ���
�n�R�l�̂Ђ��݂���
>>965 >>995 �^���X�e���I�̍�����������Ă���Ă���y�[�W���݂ăt�@�C����������Ƃ����B
���ǁA������Ȃ������m�����ŏ\���������B
foobar2000�̃v���O�C����Stereo to Mono�AMono to Stereo ��DSP�ł������Ă��݂����ǁA���lj����t���Ȃ����܂Ƃ��Ɗ������ŁB
���m�����ɂ̓��m�����̉��ꊴ��������
���X��
�������t���g���F���O���[34������
http://2chb.net/r/classical/1636491451/ 55���g�̂����ACD40���܂����B�t���g���F���O���[�ŔӔN�̘^���ɂȂ�܂��B
(
>>999 ��葱���j
�E�O���b�N�u�A���`�F�X�e�v����
�@�����CD11�ɂ���̃e���t���P���ւ�SP�^����LP�p�Ę^���ł��BCD11���蕨�����Ƃ������Ƃ�����A�����ł͏����ɂȂ�܂���B
�@���t�́A�{�Ղ͋Ȃ̔ߌ����������Ղ�ƕ������閼���ł���A�����Ƃ����܂��Ė{�Ԃ�����Ղł��傤�B
�@�����A�e���t���P���^�����Ⴋ�t���g���F���O���[�Ȃ�ł͂̎�����������A�Ǝ��̗ǂ��������Ă��܂��B
�E�O���b�N�u�A�E���X�̃C�t�B�Q�j�G�v����
�@�����̓t���g���F���O���[�Č���̘^���Ƃ����āA������ǍD�ł��B
�@���t���A�����͂Ȃ��ǂ��납�ߌ��I�Ȗ����ɑ�����Ǝv���܂����A��͂���������e���|�𑬂��ł��Ȃ��������A�Ƃ����v�����c��܂��B
�E�x�[�g�[���F���u���I�m�[���v���ȑ�2��
�@55���g�̃��}�X�^�[������A�܂��ቹ���������ɔ������x�[�g�[���F���ɂȂ�̂��ȁA�Ǝv���̊O�A�ቹ�̌�������X�̃��}�X�^�[�ł��B
�@���̊��̋Z�p�w�����ł���A�Ƃ������ƂȂ̂��A�t���g���F���O���[�ŔӔN�ł̓}�C�N�̓������ς�����̂��A�����s���ł��B
�@���t�́A���ꂾ�������グ��Ζ����ɑ����܂����A���C�u�Ɣ�ׂĂ��܂��Ɣ��͕s���Ȃ͎̂d���Ȃ��ł��傤�B
�����A���́u�}�^�C���ȁv3���g���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��c�@������Ǝ��Ԃ���������܂���B
���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/classical/1620879500/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��BTOP�� TOP�� �@
�S�f���ꗗ ���̌f���� �l�C�X�� |
>50
>100
>200
>300
>500
>1000��
�V���摜 ���u�������t���g���F���O���[33������ YouTube����>7�{ ->�摜>35�� �v �������l�����Ă��܂��F�E�� �A���W������ ���@�t�W�e���r�n �wLove music�y�`���R���[�g�v���l�b�g�ƐX���痢��TT�Z��z�x�@�� 24:30�`25:25 �� �y�S�ĉf�惉���L���O�z�u���F�m���vV2�@�f�C�~�A���E�`���[���ēu�t�@�[�X�g�E�}���v��3�ʃf�r���[ �� �R�ؗ����E���֕� ���@���W�I���{ �w�J���g���[�E�K�[���Y�̑������W�I�������I�I�x�y��Q�R�V��z�@�� 24:30�`25:00 �� �� �R�ؗ����E���֕� ���@���W�I���{ �w�J���g���[�E�K�[���Y�̑������W�I�������I�I�x �y��114��z�@�� 24:30�`25:00 �� �� �R�ؗ����E���֕� ���@���W�I���{ �w�J���g���[�E�K�[���Y�̑������W�I�������I�I�x�y��217��z�@�� 24:30�`25:00 �� �� �R�E�X�ˁE���ցE����E�D�� ���@���W�I���{ �w�J���g���[�E�K�[���Y�̑������W�I�������I�I�x�y��152��z�@�� 24:30�`25:00 �� �y�|�\�z���n��ӂ݂����s���N�w�A���f����u���b�N�R�[�f�@�������f�R���e���I [�t�H�[�G�o�[��] �y�G�k�z���L�v���W�F�N�g��1346�C���Q���Q�yF9���|.����ID���������Ȃ����̓X�o���V�C���a���@�N�������G�X���r�炵�����啟���A�t�B��遁���σA�X�y���C���t�H�K�[���J���n�M���������m�z �yFF�V���[�Y3�勃�����ʁz(�R�L��`)�uFF8ED�̃��O�i�ƃ��C�������������Ƃ��v�u�Z���t�B���g���r�A�K�[�f���Œ��Ԃ̕�Q�肷��Ƃ��v �y�o�[�X�f�[�C�x���g2022�y���������������z ���d����݃I�t�B�V�����u���O����part951 �y�����Ė����̓��C�u❣�y���݁z ���̕���~���I�t�����X�̑�x��3�l���m�[�g���_�����@�̍Č���381���~����t�@�f�B�I�[��CEO�A�O�b�`�E�T�����[����CEO�� �yW�h�b�J���t�F�X�J�����O�z�h���S���{�[��Z �h�b�J���o�g����630 ���y�G�k�z�g���C�������j���O�X���C�y�������z�� �y�e���r�z���ːM��u�s�A�m�̐������́w�N�����B�`�F���o���E�R���E�s�A�m�E�G�E�t�H���e�x�ł��v ���m����Áw�T�����C�E�j���W���t�F�X�e�B�o��2018�x��SKE����g�Ԃƃh���t�g3���̕��c���ނ��o���I �� �������E���c����E���X��仉��q ���@���W�I���{ �wAS1422 ���A���W�������X�e�[�V�������x �y��232��z�@�� 24:00�`24:30 �� ������Lancers�����T�[�Y- �l�[�~���O�E�R�s�[������ �� ���[�j���O���B'16 �� �wThe Girls Live�x �y��147��z ���{�����ٌ����ɐ����I12���ɖ��� �� ���t�@�N�g���[�V��� ���A ���h���S���N�G�X�g �����X�^�[�p���[�h 1287�i6��24���T�[�r�X�I���j �� ���[�j���O���B����&OG����25�l ���@�e���r���� �w���[�j���O���B�Q�O���N�L�O�X�y�V�����x�@�� 12:00�`13:55 �� �D �� �㚠���G�߁E�}�����ށE�쑺���T ���@���W�I���{�w�A���W�������X�e�[�V����1422�x�y��304��z�@�� 24:00�`24:30 �� �� �{��䝖��E���{���� �� �Ђ���TV�`�����l�� �w�قړ��̉��k�B�掵�b�v���o������ �攪�b�����ȃs���N�̃m�[�g�x �� 19:00�`19:30 �� �I���t�F�[�����A�I�O���L���b�v�A�O���X�����_�[�݂����Ȋ����̋����K���̔n���M����܂Ɍ����Ă� �����\�t�\�t�o�������f�W�^���t�H�gvs���y�[�W���B�W���A���ʐ^���b�N�n���y�i�ǂ�����I�j�z �y�g���^�z�A���t�@�[�h���t�����f���`�F���W�Ɍ����ăO���[�h�����y���F���t�@�C�A�ŏI�z �y�T�b�J�[�z���\�t�g�o���N�̑����`�� ���Ȃ镕����́uJ�v�i�o�I �u�A�W�A�ł͖싅���T�b�J�[���l�C�v�_���͓���FC�Ɠ������F���f�B �y���y�zV�n�o���h�u#FEST VAINQUEUR (�t�F�X�g ���@���N�[���j�v�����O���߂��@����������Ɨ��A���������ٔ��Ɂ@#yamato_lawye [���l����] �p�f�I�u���C�G���t�f�B�[�v�Y��X�m�[�t�H�[�������F�����C���܂� �y�T�b�J�[�z�����C�A���E�M�O�X����������̏h�G�A�[�Z�i�������������I�u���B�G���A�v�e�B�A�x���J���v�A�s���X�������������v �y���y�z�W�~�E�w���h���b�N�X�E�G�N�X�y���G���X�@69�N4��26��LA�t�H�[�������������߂Ċ��S�Ȍ`�Ŏ��߂����C���A���o������ [�X�R��] �y�|�\�z�L�������A���C�E���B�g���̃A���o�T�_�[�A�C���u�Ⴗ����v�u�u�����h�̈�����v�Ɣ����̐� �T�^�[���̌���RPG�u�O�����f�B�A�v�̃������A���T�E���h�g���b�N���t�����X�Ŕ����B�W���P�b�g�͖{�J�������`�����낵 ���{�ւ̔������� F1���b�h�u�������N�@�P���C�X �Q�o���e�� �R�}�b�N�X �S�A���N�T �T�����h �U�`�F�R �V�����X �W�_�j�G�� 15�s�G�[�� ����,��ސڐG �y�T�b�J�[�z��FOX SPORT�������A���g���[�Y�ƍL�B�P���ACL�Ό��́u���A��vs�o�C�G�����v�@����MF���������t�]�˔j�̃|�C���g�́H �y�\�t�g�o���N�z�f�X�p�C�l���O���V�A���͂U�D�P�X�J���A�E�g�c�X�w�b�h�u�L���[�o�͏o�����ł��Ȃ��v [�����̃}�X�J���[�h��] �גJ�����剉�A�j���Ƀn�Y�������̖@���B�X�g�u���A�Ζ����w���A�I���t�F���Y�A�A���X���[���A�O�����A�������b�N�A�c���A�������F�� ��l�ōs���������M�A�l�Y�ʔT(���Ԃ��t�@�N�g���[)�o���u�F�J���I�[�K�j�b�N�t�F�X�A���O�r�[���[���h�J�b�v2019�J��1�N�O�C�x���g�v �C�X���G���A��S���o���ɂ���w�G�W�v�g�A�g���R�A�����_���A�V���A�A���o�m���A�N�E�F�[�g�A�C���N�A�T�E�W�A�C�����ɐ��z�� �L���{�f�B�Ɠ��_�̃R���g���X�g���������G�b�`�c�c��I�����`���o�j�[�K�[���̃t�B�M���A���Z�N�V�[�ȃp�[��Ver.�ōĂѓo��I ©bbspink.com �y�}��z�n���V���H�t���Ń��[�j���O���B'18�u�t�@���I�̕�`�։��E�X�l�t�F���`�v�����L�O�g�[�N�V���[��邩��F��ȗ��Ă����I�I�I �y�T�b�J�[�zUEFA-CL��6�߁@�C���e���~�o���Z���i�A�h���g�����g�~�v���n�A�`�F���V�[�~���[���A�A���b�N�X�~�o�����V�A�� �y�T�b�J�[�zJ1�E���É��O�����p�X���I�[�X�g�����A��\GK�~�`�F���E�����Q���b�N(29)�̊l���\ �ySAOFB�z�\�[�h�A�[�g�E�I�����C���@�t�F�C�^���E�o���b�g �ypart20�z �yBenz�z �x���c�E�|���V�F�R�[�f�B���O�֘A�y���C�g�Z���T�[�j��z ����2 �g�{���ƁA�E��ڎ�X�^�[�g�@�y�i���e�B�E�q�f�A�T�o���i�����珉���ɐڎ�@��2500�l��\�� [���S������] �y�g���^�z�A�N�A�̃t�����f���`�F���W2021�N7���ATNGA�����ƃo�C�|�[���j�b�P�����f�d�r�̗p �u���b�N�t���C�f�[�Z�[���ŃE���g�����C�h�Q�[�~���O���j�^�[(2560x1080)��21,480�~�Ŕ����� �G���f�������O�Ń��_�[���O�̍��l�ɐԃT�C�������Ă�̂ɑS���}�b�`���O���Ȃ� ���Y�ƃE�H�[�����E�o�t�F�b�g�u�R�[�����̂Ɉ����H�����̍K�����l�����B�g�[�^���Ō��N�ɂ����v ���Ԃ��t�@�N�g���[2nd�A���o���I���R���f�C���[�t���Q�S�ʁI�I�I�I�I �y�|�\�z���u�E�n���t�H�[�h�A�Q�C�ł��邱�Ƃ��J�~���O�A�E�g�����o�܂�Q�C�N���u�ł̃t���f�B�E�}�[�L�����[�Ƃ̏o�������� [���̉E��] �y6/25~6/29�z�h���S���{�[�g�t�F�X�e�B�o���C�x���g �y�T�b�J�[�z�C���O�����h�̃T�E�X�Q�[�g�ēA�x���M�[�s��͈Ӑ}�I�H�@�p���f�B�A�wBBC�x�����\ �ySAOFB�z�\�[�h�A�[�g�E�I�����C���@�t�F�C�^���E�o���b�g �ypart44�z ��l�ōs���n���v�����C�����j�b�g'22�o���uFunpal�t�F�Xvol.1�v�y�i��U�E�O�����h�z�[�� 10��10���z �z���_�y�t���[�h�z�t�����f���`�F���W�\�z2022�N�H�ȍ~�A�t�@�~���[�w���^�[�Q�b�g�Ƀ~�j�o���������� �y���y�z�G���b�N�E�N���v�g���A�t�@�[�X�g�E�\���E�A���o����50���N�L�O�f���b�N�X�Ղ̔��������� [�X�R��] �L�����}���̐l�C�K�E�Z�u�t�F�C�X�t���b�V���v���Č������X�}�z���C�g�J�o�[�������B�\���W���[�ƃt�F�j�b�N�X�̑S2�� �y�h�C�c�z���t�H���N�X���[�Q���iVW�j���u�G�[�v�����t�[���v�t���C���O�I���f�B�A�e�Ќ��{�̍L���헪���Ӎ�.. [Egg��] �y�����m�C���~�i�e�B�z�u�����E���[���h�v�R���T�[�g�A�~�V�F���E�I�o�}�O�哝�̕v�l�ƃ��[���E�u�b�V�����哝�̕v�l���o�� �y�����ܗցz{{ �H������ }} �V���[�g�v���O�����P�ʁA�Q�ʂ̓t�F���i���f�X�A�F�쏹���́c���t�B�M���A�X�P�[�g�j�q ��11 �o�Y�ȁu���^�o�[�X�Љ�Ɍ����ăQ�[�~�t�B�P�[�V�������R�A�i���b�W�ɂ����f�W�^���g�����X�t�H�[���[�V�����l�ނ��琬�����I�v �̑�ȃ��^���M�^���X�g�Ƃ����H�f�l�u�}�[�e�B�E�t���[�h�}���v�W�W�C�u�����f�B�E���[�Y�v�ڂ��u�o�[�j�[�E�g�[���v �y�̋Ɓz�������̓V�ˁE���X�؋Վq�A�����ő勉���������j���[�X�T�C�g�ŁA�U���������f�������L���O�P�ʁy#���f���v���X #�T�؍�z B87W58H91�A�傫�Ȃ��K���`���[���|�C���g�̃n�[�t�������O���h���f�r���[ �� �H���y���� �� BS�X�J�p�[�I���S�����p�w���[�j���O���B'17�R���T�[�g�c�A�[�t�`THE INSPIRATION�I�`�x �� 18:00�`21:00 �� [���f�]�ڋ֎~]
18:21:43 up 22 days, 19:25, 0 users, load average: 11.40, 10.23, 10.26
in 0.067982912063599 sec
@0.067982912063599@0b7 on 020508


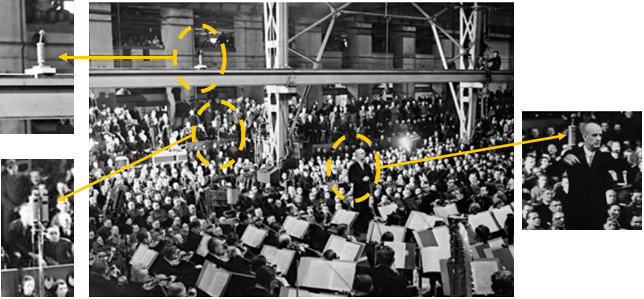
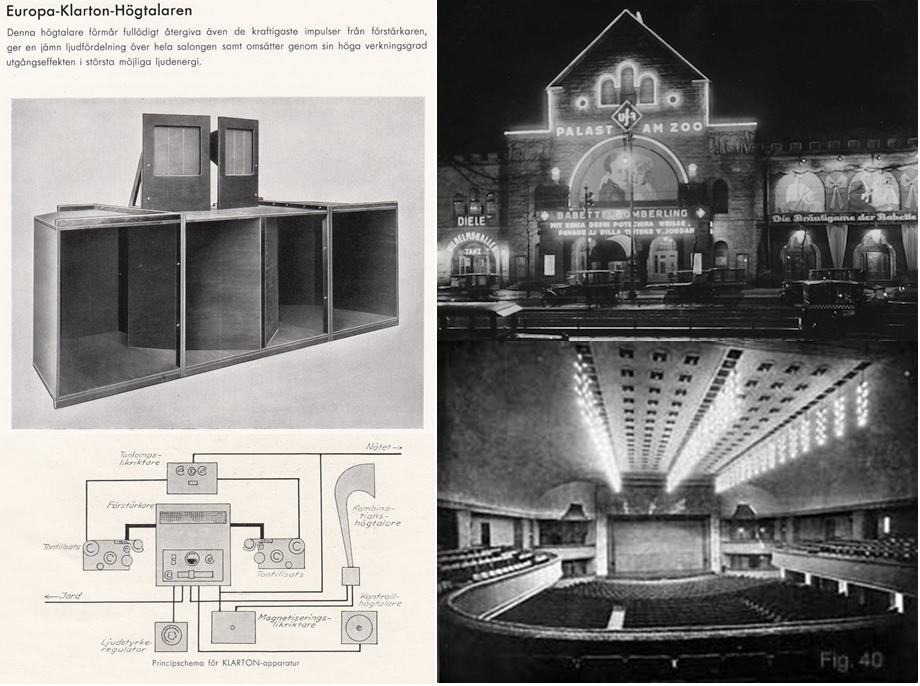







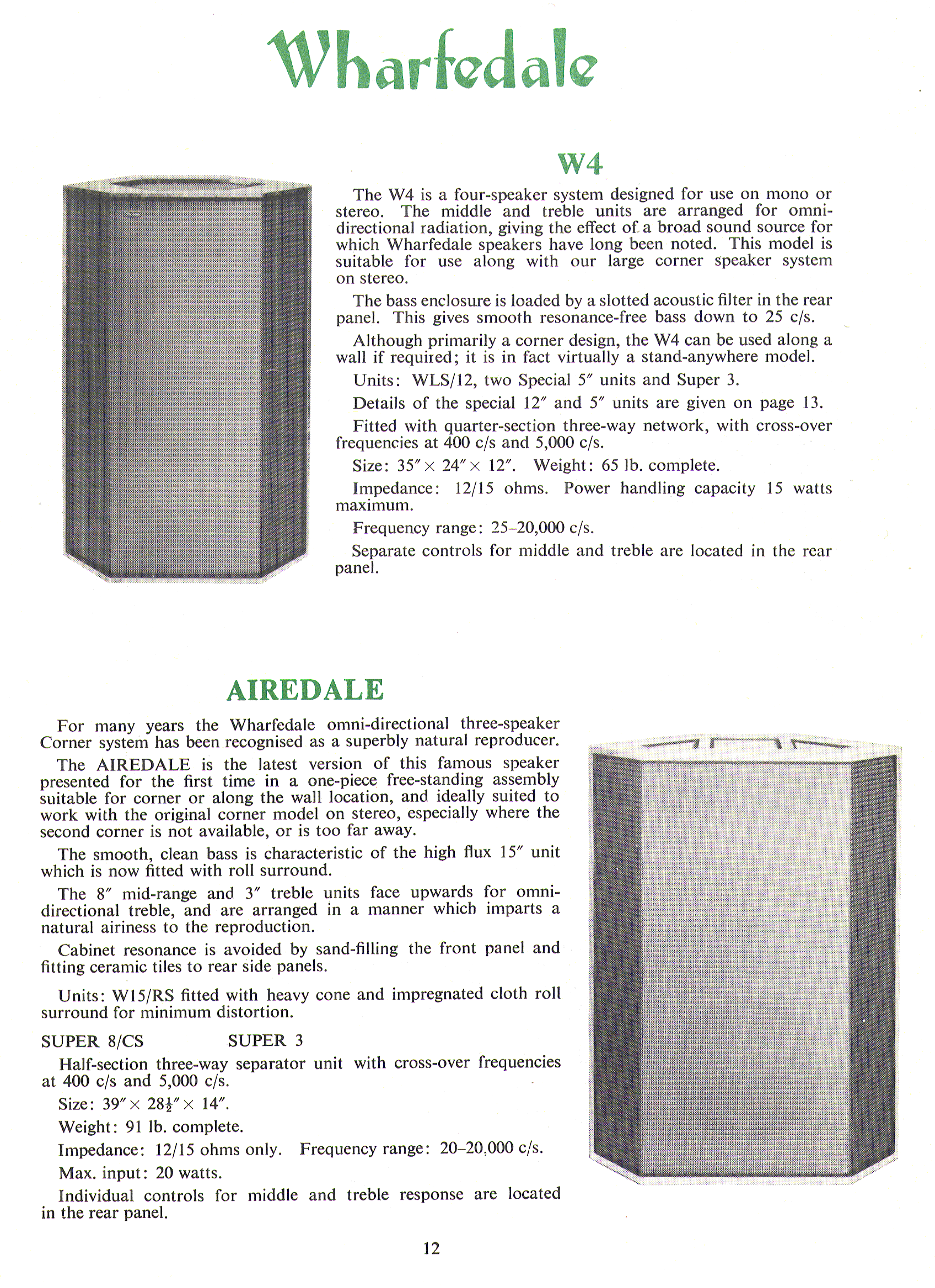

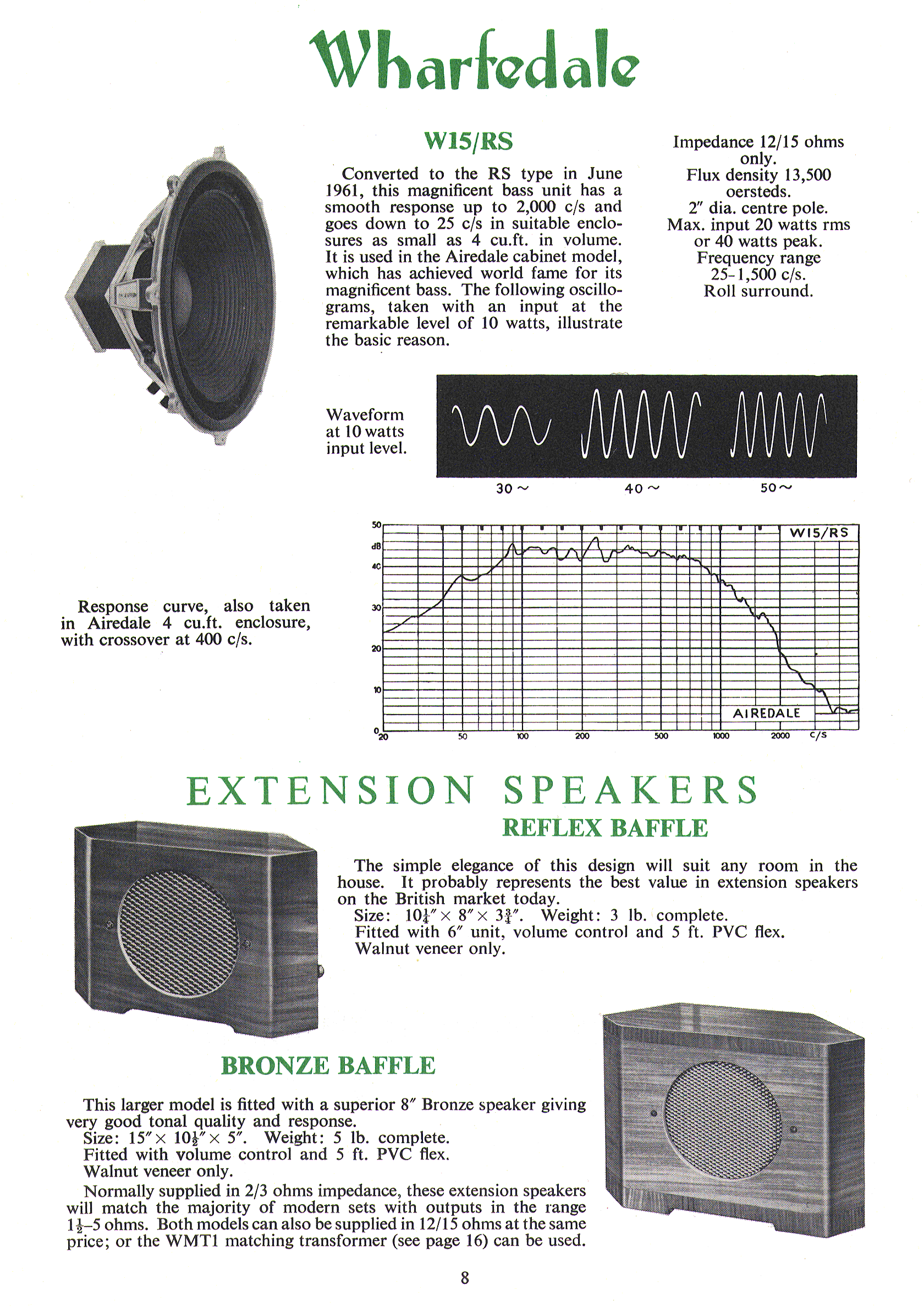

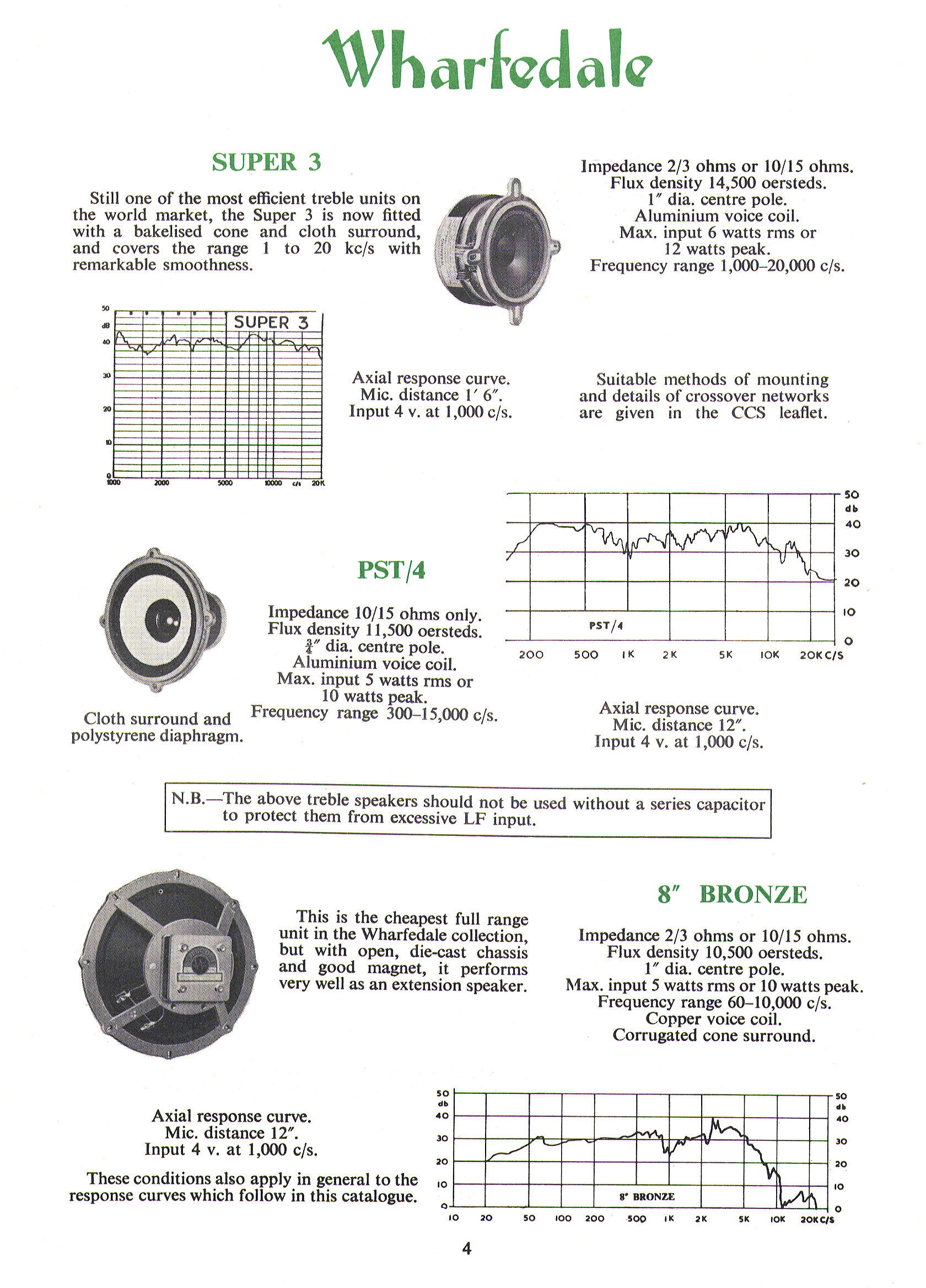
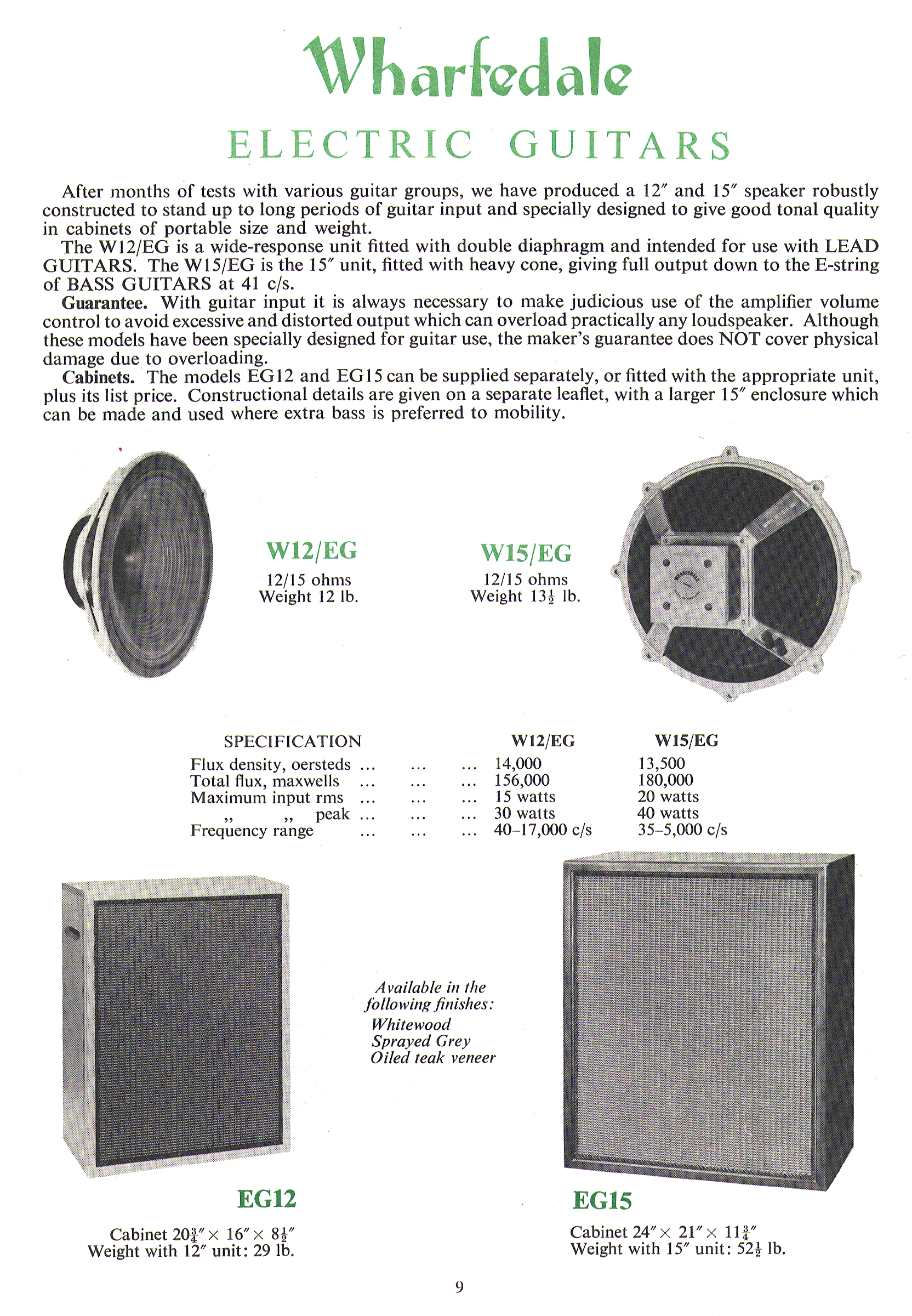
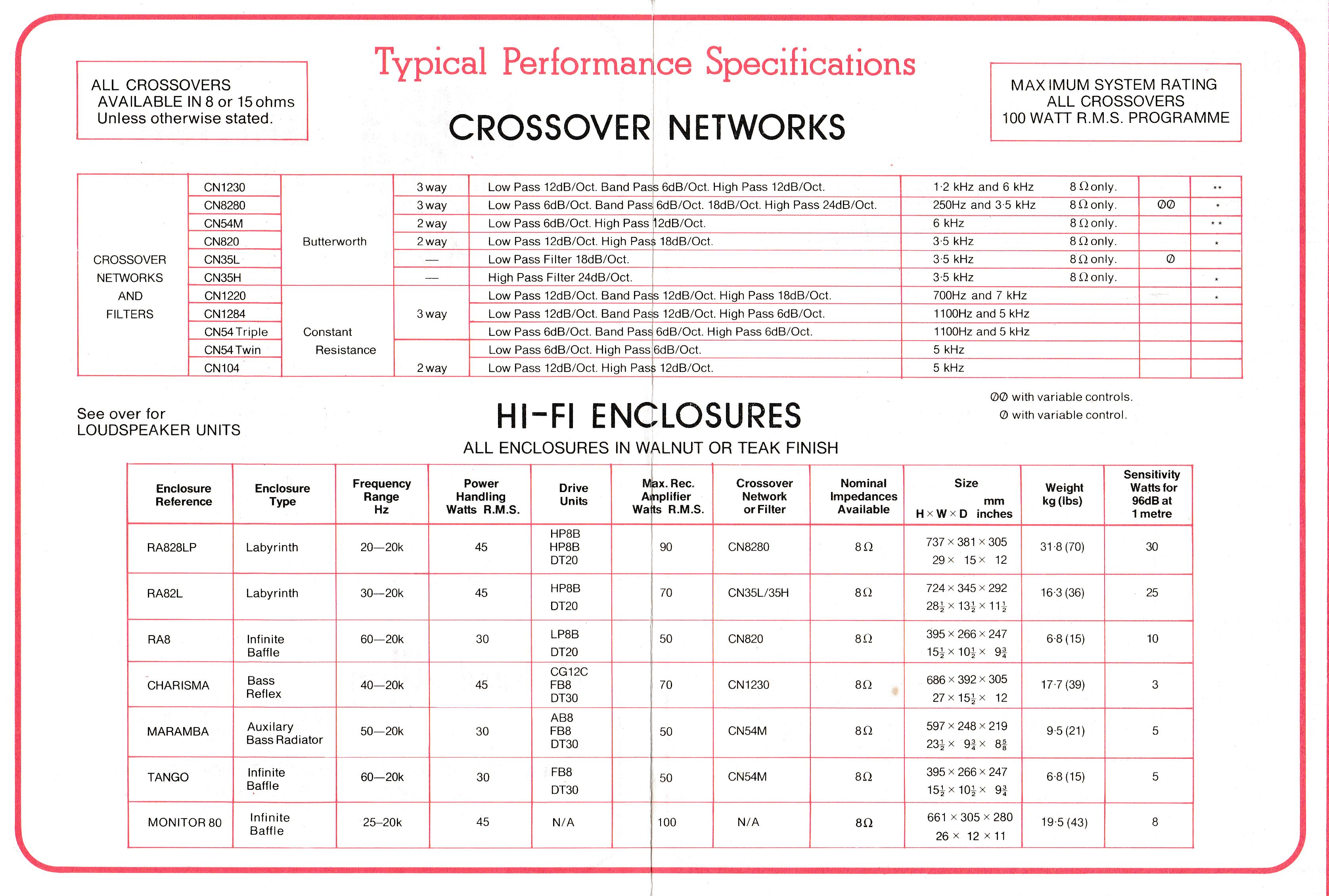
 �i���ꂪN/W�̌��āj
�i���ꂪN/W�̌��āj 


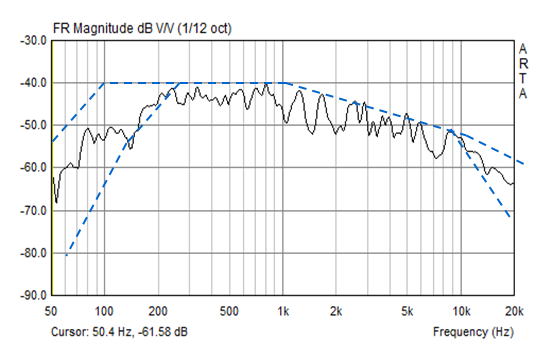


 �i��i�j
�i��i�j 
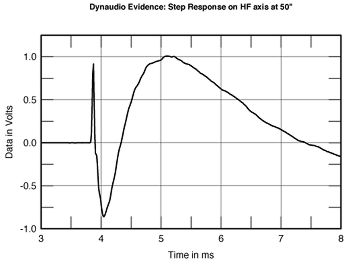
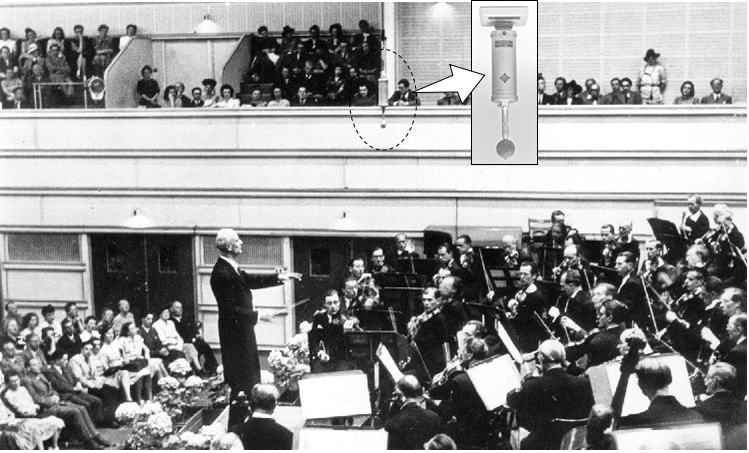 �@�i�t���N�n�E�X�j
�@�i�t���N�n�E�X�j  �i�e�B�^�j�A�p���X�g�V���j
�i�e�B�^�j�A�p���X�g�V���j  �i���g��j
�i���g��j  �@�i�U���c�u���N�j
�@�i�U���c�u���N�j